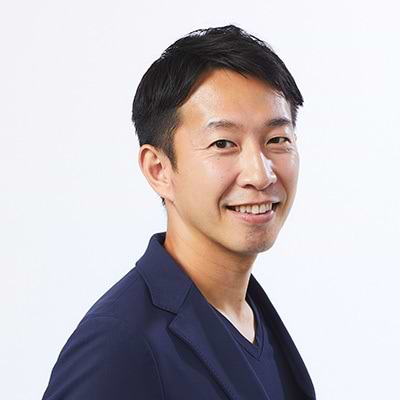2024年5月29日、慶應義塾大学は信濃町キャンパス(東京都新宿区)に、独自インキュベーション施設「慶應義塾大学信濃町リサーチ&インキュベーションセンター(CRIK信濃町 )」をオープンしました。
株式会社 電通 では、この施設の企画構想からローンチまでを一気通貫でサポート。慶應義塾大学の掲げる思想の実現に向け、空間デザイン×ビジネスデザインの両輪アプローチとして新たに提供を開始した「KU-KAN TSU-KAN(クウカン ツウカン)」サービスでプロジェクトを推進しました。
本記事では、電通 スタートアップグロースパートナーズに所属する統括プロデューサーの高井嘉朗氏をファシリテーターに、本プロジェクトについてのインタビューを実施。前編では、慶應義塾大学医学部 副医学部長(イノベーション担当)兼 慶應義塾大学医学部整形外科学 教授 中村雅也氏・慶應義塾大学 イノベーション推進本部 本部長 兼 スタートアップ部門長 新堂信昭氏、電通のクリエーティブディレクター鈴木契氏・空間設計を担当した電通の南木隆助氏に、空間デザインについて聞きました。
東京の“真ん中”で、医療・ヘルスケアの“真ん中”を目指す 高井: 今回、病院の中にインキュベーション施設をつくるという、新しい取り組みですが、どういった場所・空間となることを目指していますか?
新堂: まず、本施設を開設した背景として、イノベーション推進本部スタートアップ部門では、学内の起業環境整備のためのさまざまな取り組みを進めており、その1つにインキュベーションの場づくりがありました。
中村: 医学部では、医学の成果をスタートアップという形で患者さんらに届けることを目指して、多くの起業がなされています。そのため、信濃町キャンパスの中に起業のためのインキュベーション施設をつくりたいという思いがあり、今回、医学部と大学本部のイノベーション推進本部スタートアップ部門とで協働して本施設をつくることになりました。
新堂: 施設には、施設を運営しながら入居者とのコミュニケーションを促進するインキュベーションマネージャーや、大学教員・研究者とのディスカッションやコンサルテーションを促すサイエンスリエゾンが複数名常駐しており、入居者や訪問者からのさまざまな相談も受けています。この施設を訪れれば、ワクワクする未来が感じられる、新しい事業の一歩を踏み出すきっかけや新たな出会いが得られるといった、そのような魅力的な場となることを目指しています。
高井: あまり知られていないかもしれませんが、電通は広告だけでなく、空間デザインにも力を入れています。今回、電通が慶應義塾大学信濃町キャンパスでのインキュベーション施設開発プロジェクトに携わることになり、どんな空間にしようと考えたのか教えてください。
南木: 電通は一級建築士事務所登録をしており、万博のパビリオンなど仮設建築物の建築に携わってきました。広告は見る人の感情を動かすものですが、空間デザインも同じ。ロジックだけでは人の心は動きません。訪れた人がどんな気持ちになるのかイメージし、クライアントさまの言葉にならない期待感や興奮を設計プランに落とし込めるのが、長く広告領域でクリエイティビティを発揮してきた電通の強みです。
株式会社 電通 南木 隆助 氏 高井: 今回の構想を聞き、鈴木さんが最初に考えたコンセプトをお聞かせください。
鈴木: 実際に来てもらうと分かるのですが、この施設からは東京の要所が一望でき、まさに東京の“真ん中”。また、大学病院は誰もが気軽に入れる場所ではないため閉鎖的なイメージを持たれがちかもしれませんが、インキュベーション施設は開かれたものです。病院を強調すると閉鎖的な印象を抱く人がいるかもしれない、しかしインキュベーションを強調すると、この場のオーラが失われてしまうため、両者の特徴が失われない、イメージの“真ん中”を目指す必要があるとも感じました。さらに、この施設では医療データを活用(※)し、人を“真ん中”にした医療・ヘルスケアの発展を目指しています。そこで、“真ん中”というコンセプトを最初に考えました。
高井: ステークホルダーが多いからこそ、最初に“真ん中”という言葉で施設の価値を規定したことに大きな意味がありましたよね。慶應義塾大学側の方々も大いに喜んでくださいました。
新堂: そうですね。最初にコンセプトを両者でディスカッションしていくことで一体感が生まれました。そして、コンセプトが決まったことで、参画メンバー同士の共通認識化が図れ、その後の意思疎通もスムーズに進んだと思います。
鈴木: コンセプトが言葉になると、関係者の間に共通認識が生まれますよね。広告はこの最初の目線合わせが非常に大事で、スピード感を持ってまず目線合わせをしていきます。このような広告ではなく関係者が多岐にわたるプロジェクトにおいても、最初に目線合わせを行うことができたのは電通ならではだと思いました。
医療における使命を達成しつつ、ホスピタリティを表現 高井: コンセプトを踏まえて、どのように空間デザインを考えたのか教えてください。
南木: コンセプトを重視しつつ、「ホスピタリティをどう表現するか」を考えていきました。「病院(ホスピタル)」は、「ホスピタリティ」から派生した言葉と言われています。とはいえ、医療現場は命が関わる場でもあり、こうしたシビアな空間ではイノベーションが育ちにくいのではないかと思いました。
高井: 今のお話のように、空間デザインとビジネスデザインの両輪でアプローチできるのが電通の強みでもあります。皆さんは、このチームの強さはどこにあると思いますか?
南木: それぞれの専門領域はありつつ、いい意味で役割が固定されていないオープンな関係性を築けることですね。ビジネスデザインと空間デザインを同時並行させアジャイルで進行したのですが、空間デザインについて話すときにも、ビジネスデザイン側からも意見を出し、いい形で影響し合いました。こうした電通チームの空気が慶應義塾大学の皆さんにも伝播し、面白い議論が生まれたと思います。
中村: そうですよね。今回、電通ならではのプロジェクト進行における空気感が慶應義塾大学メンバーにも伝播し、普段の担当領域を飛び越えて、活発に議論ができたと思います。
鈴木: 何かを決める際にも「今すぐ決めましょう」ではなく、「まだこういう議論ができそうですね」という余地をいかに残しておけるかが重要ですね。空間デザインも「こういうレイアウトが定石です」と一方的に提案することもできましたが、それでは「未来のコモンセンスをつくる研究大学」や「人を中心にした医療」など、型にはまらない大きな理念を構想することから乖離してしまいます。何を決めるにしても、一度理念に立ち返ることができるバッファーを持てるのが、私たち電通の強みだと思いました。
株式会社 電通 鈴木 契氏 ソフトとハードの両面から、可逆的プロセスで施設を開発 高井: では、「CRIK信濃町」の空間デザインにおける特徴をお聞かせください。
中村: 病院である特徴を最大限生かしたインキュベーション施設をつくりたいという思いがあり、電通へは機能面はもちろん、デザインについても、その思いを反映した空間設計にしてほしい旨を相談しました。
南木: 中村さんからのリクエストを受け、オフィスの効率的なフロア構成ではなく、病院の部屋割りを生かすことにしたのですが、小さい部屋が並ぶだけでは、入居者同士の交流は生まれません。そこで、フロアをぐるっと回るといつの間にかオープンスペースにたどりつき、交流が生まれるよう設計しました。その設計プロセスでは、ビジネスデザインの志村さんと奥田さんが考えたビジネスモデルに合わせて、部屋割りを変えたり、オープンスペースの在り方を変えたりといったことも可逆的に行っていましたね。
高井: 今回のプロジェクトで得たものや、今後の展望についてお聞かせください。
株式会社 電通 高井 嘉朗氏 鈴木: 毎週金曜日に行われた定例会議では、それぞれ職能を持つメンバーがお互い自由に意見を交わしていました。最初は「おのおのの業務に直接関連のない話までする必要があるのか」という思いもありましたが、さまざまなメンバーの考えを理解し取り入れ、それをクリエイティブに反映することもできました。ずっと関わり続け、チームの関係性を育んでいくことが重要なんだと感じましたね。
新堂: 慶應義塾大学だと「K」を頭文字にしがちだと思うんですが、「C」から始まる案は印象的に感じました。しかし、深い議論を通じて「C」に込められた意味と私たちの思いやコンセプトを反映した名称であることを理解でき、学内でも話し合った結果、電通からの提案を受け取ることにしました。
南木: 今回のプロジェクトでは、コンセプト、ブランディング、事業開発、空間設計が同時多発的に起こり、相互作用しながら可逆的なプロセスで開発を進めました。それが良い施設の完成に寄与したので、こうしたプロセスを今後、オフィスビルや商業施設の開発、都市設計などにも横展開してみたいです。
イノベーションを起こすには、時には効率性にとらわれず、ワクワク感を追い求めることも必要です。鈴木氏いわく、効率性よりも好奇心が勝るのが電通の空間デザインチームの特徴。病院という施設の独自性を生かした設計プランを提案するたびに、中村さんを含め慶應義塾大学の方々も積極的に意見を出し議論に参加したそうです。その結果、大学側の課題意識に応えるインキュベーション施設が誕生しました。
※医療データの活用は研究ごとに審議の上、患者さんの同意を得て行います。