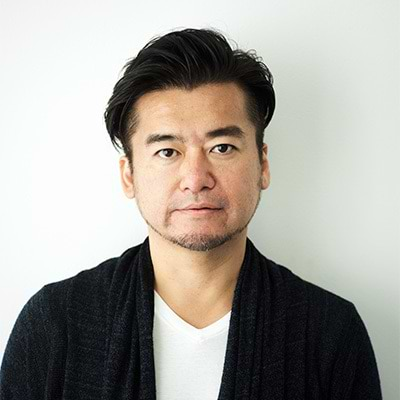雑誌や書籍作りで培った出版社のクリエイティブ力やブランド力が、いま注目されています。本連載では、世の中のマーケターに向けて、さまざまなテーマでいまの時代における出版社のアセットやコンテンツ作りを紹介しながら、出版業界を活用するためのヒントをお届けします。
前回は、「動画」をテーマに、雑誌「BRUTUS」の取り組みを紹介しました(記事はこちら)。今回は、多様な雑誌ブランドの名のもと、個性的な動画を世に出し、業界をリードするマガジンハウスの動画戦略について事例を交えながらお伝えします。
ゲストは、雑誌「BRUTUS」編集長の田島朗(たじま・ろう)氏と、マガジンハウスのビジネスプロデュース部部長の長勲(ちょう・いさお)氏。聞き手は、動画をはじめとしたデジタルソリューション開発を進めている、電通出版ビジネス・プロデュース局(以下、出版BP局)の中村一喜(なかむら・かずき)氏です。
マガジンハウス
anan、POPEYE、クロワッサン、BRUTUS、Tarzan、Hanako、GINZA、CasaBRUTUS、ku:nel、&Premiumの定期刊行雑誌をはじめ、書籍、ムック、ウェブマガジンなどを幅広く手掛ける、日本を代表する出版社。

マガジンハウスの雑誌ブランドは、「メディアも持っているクリエイティブ・ブティック」
中村:いま動画に力を入れるメディアが増えていますが、マガジンハウスは雑誌ブランドにおいて、どのような動画戦略を描いているのか、お話を伺わせてください。
長:当社では、2年前にBRUTUSが先陣を切って動画制作に取り組み、「BRUTUS ORIGINAL MOVIE」をスタートしました。これが成功したことで、anan、POPEYEなど動画に力を入れる雑誌ブランドが増えてきました。
マガジンハウスは、定期刊行している10の雑誌ブランドを有しており、さまざまなライフスタイルに合わせて多彩な動画を作れることが強みです。僕たちは、広告主に向けて、マガジンハウスの雑誌ブランドは、「メディアも持っているクリエイティブ・ブティック」だと考えてほしいというお話をしています。
長:通常、企業がCMを打つ場合、制作と、流す媒体の両方を考えなければなりません。そこをマガジンハウスは一括で引き受けられる。さらに、広告を出すプラットフォームも、すでにある程度のファンがいるのでリーチも望めます。
中村:広告において、いまでも主要な動画広告コンテンツというとテレビCMですが、多くのファンがいるマガジンハウスのメディアに広告を出すということは、テレビCMとはまた違った価値がありますよね。
長:そうですね。広告という点で雑誌の価値を突き詰めて考えると、世界観と影響力の2つがあると考えています。世界観とは、雑誌で紹介されると、商品やサービスがよく見えて、すてきだな、欲しいなと思ってもらいやすい。影響力とは、雑誌に載ると商品やサービスのサイトのページビューが得られるといった、数字的な価値です。
動画に力を入れることで、マガジンハウスの雑誌ブランドは、SNSのフォロワーも大幅に増えています。InstagramなどMeta系のプラットフォームは、これまでの運用方法ではフォロワー数が伸びにくい環境なのですが、BRUTUSのInstagramは、平均して毎月約5000〜6000人のフォロワーが増え続けていて、この1年では、前年比で約130%増加しました。他の雑誌でも、ananは約150%、POPEYEは約120%と、いずれも如実に成長スピードが上がっています。YouTubeチャンネルについては、BRUTUSのフォロワーは、以前は2000人程度だったのが、2年間で10万人を狙えるところまで成長しています。
中村:動画施策の効果が、マガジンハウスのさまざまなメディアに好影響を与えているわけですね。広告主目線で見ると、自社商品を自社メディアで紹介するのは「自己紹介」で、出版社とのタイアップは「他己紹介」です。自己紹介はどの企業も行いますが、それだけだと限界がある。そのときに他己紹介を加えることで、商品やサービスへの興味喚起が図れることは、データでも表れています。ですから、私たちも広告主に対して、出版社とのタイアップコンテンツがいかに重要かをどんどん伝えていきたい。そのとき、マガジンハウスは広告主にとって頼りになるパートナーの一社であると考えています。
田島:他にも、BRUTUSはBtoB事業として、2022年にクリエイティブ・ブティック「PB」を始動しました。これは、BRUTUS編集部が持つクリエイティブ力を、企業のさまざまな課題解決に生かしていこうという取り組みです。BRUTUSと外部クリエイターが共創しながら、広告プロモーションやイベントの企画、商品開発、メディアの企画・運営を手掛けています。
中村:こちらは、BRUTUSを全面的にアピールしていくわけではなく、BRUTUSがこれまで培った経験や人脈を生かしていくわけですね。
田島:おっしゃる通りです。「PB」は、すでに大きな売り上げを上げていて、現在は新規受注ができないほどです。また、BRUTUS発の新しいメディアとして「BRUTUS mapzine」もスタートしました。「地図連動型アプリメディア」と呼んでいるのですが、BRUTUSが過去に取材したスポットが地図で検索できるものです。
なぜ「メディア」なのかというと、編集部からアプリに向けて定期的にスポットがマッピングされたマイクロコンテンツが届く仕組みになっている。雑誌ができるいままでになかった取り組みとして、力を入れているプロジェクトの1つです。
人間のいろいろな欲望に根ざしている雑誌であることを、動画で端的に表現
中村:動画について、マガジンハウスは、社内でオリジナルコンテンツを制作するだけでなく、企業との共創にも力を入れていらっしゃいますね。例えば、KDDIが運営する「ヒルミルマガジン」。これは、いろいろな雑誌の企画を動画形式で配信するもので、BRUTUSは、2024年4月から参加されています。
田島:2023年5月に「BRUTUS ORIGINAL MOVIE」をスタートして、1年が経過しようとしているころに、「ヒルミルマガジン」のお話をいただきました。ちょうど特集連動のオリジナル動画制作が一周したタイミングで、いままでとは違った表現のコンテンツを作りたいと思ったのですが、予算とリソースの課題があったのです。
「ヒルミルマガジン」はKDDIと複数の媒体が参画しているコラボレーションですが、「ちょっとしたひとやすみに すきなものに出会えたら それは特別な時間になる」をコンセプトに、スマホでの新たな体験価値の創出を目指して、その雑誌ならではのコンテンツを「動く雑誌」として発信しています。商品を直接的に動画内で訴求するのではなく、番組提供のような形でスポンサードしていただいています。おかげさまで、BRUTUSらしい動画を自由に企画制作できています。
中村:珍しいケースですよね。どのようなコンテンツを作っていますか?
田島:すでに50本ほど制作したのですが、「観るBRUTUS」をテーマに、同誌の人気特集である「居住空間学」や、連載「自分史上最多ごはん」を動画にしました。さらに、これまで雑誌では行っていない新たな企画として「一問即答!」を配信しています。
田島:特に、「一問即答!」は、大きな反響がありました。このコンテンツは、シェフ、スタイリスト、作家など、いろいろなジャンルの人が登場し、さまざまな質問に答えていくものです。人選のバリエーションや動画のトーンがBRUTUSらしく、人間のいろいろな欲望に根ざしている雑誌であることがとても端的に表現できていると思います。再生回数も非常に伸びて、KDDIさんからも高い評価をいただきました。
マガジンハウスの一番の武器は、ブランドポートフォリオが多様であること
中村:他の動画事例としては、サントリーの「ジャスミン焼酎〈茉莉花(まつりか)〉」(以下、茉莉花)のキャンペーン「あたらしい心地いいに会いにいく。」に、マガジンハウスはクリエイティブパートナーとして参加していますよね。
長:茉莉花はいろいろなライフスタイルの人に積極的に楽しんでほしいという狙いがありました。積極的に心地いい生活を体現している人たちを介して茉莉花を表現するという方針の元、電通のクリエイティブチームの方々に声をかけていただき、サントリーさんが単独で施策をやるよりも、多様な雑誌があるマガジンハウスと共にコンテンツ施策を実施した方が良いのではないかということから実現しました。本キャンペーンには、マガジンハウスが刊行する8つの雑誌が参加しています。
マガジンハウスの一番の武器は、ブランドポートフォリオが多様であることです。ラグジュアリーもあれば、日常的なものもあれば、男性向け、女性向け、ウェルビーイングのメディアもある。マガジンハウスの雑誌ブランドそのものが、さまざまな切り口で積極的に心地いい生活を体現しているという考えの下、普段各雑誌ブランドに出演してくれている方々を起用しました。それぞれの雑誌のキャラクターが横並びであり、全体で1つの世界観が表現される。この案件を通してマガジンハウスがどういう会社なのかよく分かったと言われることがとても多いです。われわれとしても、マガジンハウスの各雑誌のブランド力を改めて確認できました。
中村:ライフスタイルの多様化がより進む中で、マガジンハウスのいくつかの雑誌を組み合わせて表現する企画が増えていると感じます。アサヒ飲料の新「Wonda」とマガジンハウスの3雑誌(anan・POPEYE・BRUTUS)がコラボレーションしたショートドラマも、その1つですよね。
長:これは、「Wonda」のブランド刷新のタイミングでいただいた案件です。クライアント案件のドラマ仕立ての動画は初めての試みでした。動画では、架空の「マガジンハウス編集部」を舞台に、若手、ベテラン編集者、インフルエンサーが「Wonda」をきっかけに新しい生活に一歩踏み出していく様子を描いています。
ドラマのタイトルは、「マガジンハウス、Wondaはじめる。」です。普通、広告企画のタイトルに社名を入れないですよね。ユニークな企画で、マガジンハウスだからできた企画なのかなと思います。
動画を通して、グローバルにマガジンハウスのクリエイティブを伝えたい
中村:マガジンハウスは今年80周年を迎えるわけですが、どのような企画を考えていますか?
田島:これまでマガジンハウスがどのように世の中のカルチャーをリードしてきたかを伝えることはもちろん、今後未来に向けて私たちがどのようなコンテンツを作って、どのように届けていくのかが感じられるイベントにしたいと考えています。その手段の1つとして動画制作もあると考えています。
長:アワードなどのイベント配信を予定しています。各ブランドから80周年関連の動画をどんどん配信していく予定です。
田島:動画の良いところはわれわれのクリエイティブを海外の読者にもすぐに届けられることです。紙を作るのと同じ感覚で編集部が動画を作れるようになり、国内外にマガジンハウスのクリエイティブを届けるのが次に目指すステップです。そういう意味では、80周年の企画としてグローバルを見据えた施策も実施できればと考えています。
中村:今後ますます、マガジンハウスの各雑誌のカラーが、より明確に打ち出された動画が広く配信されていきそうで楽しみですね。本日はありがとうございました。