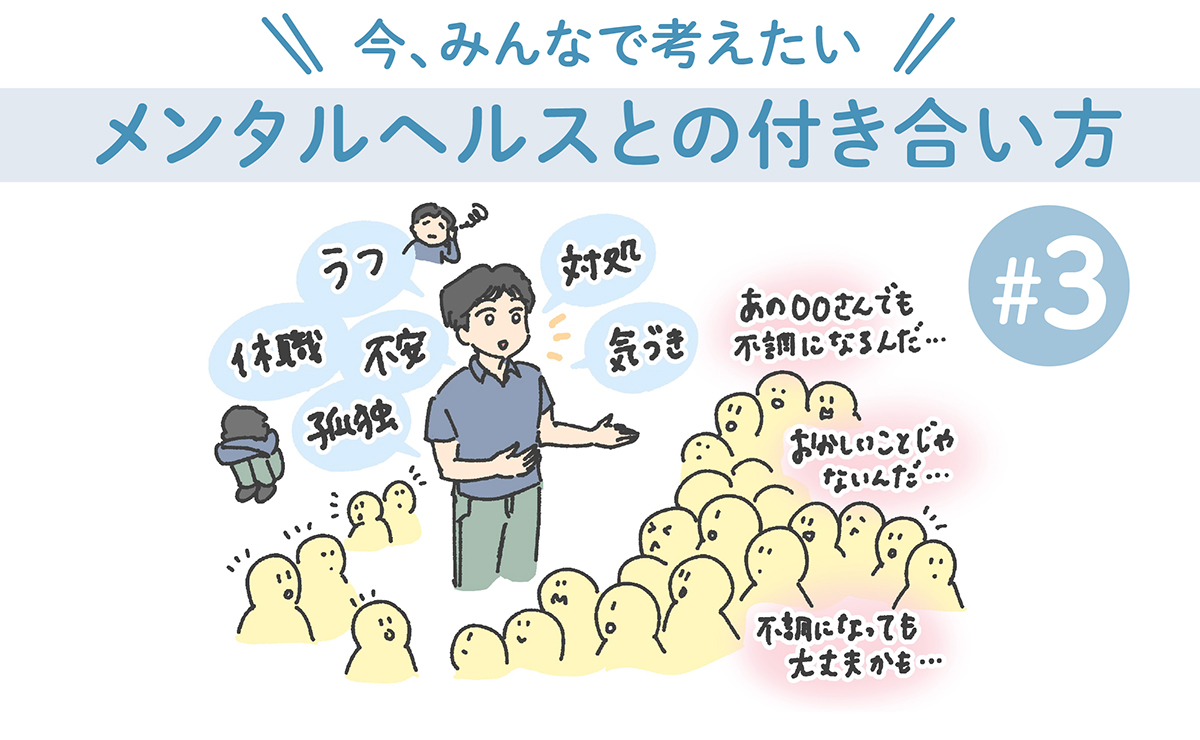dentsu Japan(国内電通グループ)は、重点領域を切り開く事例創出を担う役職として、グロースオフィサー(GO)を設置しており、2025年度には、各領域から7人が選出されています。本連載では、電通が掲げる「真の Integrated Growth Partner(インテグレーテッド・グロース・パートナー)」を体現するGOたちの、未来に向けての視点と思考に迫ります。
今回登場するのは、AI/クリエイティブ領域を担当する並河進GO。国内電通グループのAI戦略を主導するキーパーソンは、AIの現在地をどう捉えているのか。未来に向けてどのようなAI変革を構想しているのか。
並河進(なみかわ すすむ) dentsu Japanグロースオフィサー。電通入社後、コピーライター、クリエイティブディレクター、プログラマーを経て、2017年に電通デジタルに出向し、AI・データとクリエイティビティの融合を目指す「アドバンストクリエイティブセンターを立ち上げる。21年に電通カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センターの発足とともにセンター長に就任。生成AIを活用した体験を開発。22年に電通クリエイティブインテリジェンスを発足させ、東京大学AIセンターとの共同研究をスタート。Augmented Creativity Unitのユニットリーダーを務める。25年から現職。国内電通グループの「AI戦略」「AI開発」「AIによる創造力拡大の研究」「AIによるマーケティング・クリエイティブの高度化」「企業向けAIトランスフォーメーション支援」をリードする。近著に「AIネイティブマーケティング ⼈、企業、AIの幸せな関係をつくる」(宣伝会議)AIにより事業成長やイノベーションを生み出す ──最初に、グロースオフィサー(GO)としての現在の仕事の内容について教えてください。
並河: dentsu Japan、すなわち国内電通グループ全体におけるAI推進の旗振り役とクリエイティブを担っています。「AI for Growth 2.0 」を今年5月に発表しました。さらに7月には、dentsu Japanを横断する1000人規模の組織「dentsu Japan AIセンター 」を立ち上げました。
──AI For Growthについて、戦略の骨子や特徴を教えてください。
並河:AI For Growthのビジョンとしてのユニークさは、効率化の文脈で語られることが多いAIを、事業成⻑やイノベーションを⽣み出すことにも活⽤していくと宣言しているところにあります。その底流には、「人とAIが共に成長していく」という思想があります。
──具体的にはAIをどう活用して、「想像力」や「創造力」を強化・拡張していくのでしょうか。
並河:「想像力」については、生活者に関する膨大なデータを基にして、1億人規模の高解像度なペルソナを仮想再現するAIモデル「People Model」を発表しました。
──AICO2やAIアートディレクターといったAIツールの開発意図や特徴について教えてください。
並河:コピーライティングにしても、ビジュアルアイデアにしても、汎用LLM(大規模言語モデル)に「コピーを書いてください」「広告のビジュアルを考えてください」とお願いすれば一応は出てくるのですが、どうしても平均的であったり優等生的であったりという問題がありました。それを解決したくて、LLMをファインチューニングすることで生まれたのがAICO2やAIアートディレクターです。
──dentsu Japan AIセンター発足の狙いと活動内容について教えてください。
並河:ある領域を一気に進化させることを目的に、その領域に強い人財や技術、ノウハウを集約した組織や拠点のことを「センター・オブ・エクセレンス」と言いますが、まさにAI領域におけるセンター・オブ・エクセレンスとして立ち上げたのが dentsu Japan AIセンターです。
──AIについては、企業に恩恵をもたらす一方で、 誤った情報を生成する現象(ハルシネーション)や著作権にまつわる懸念も指摘されています。
並河:そうしたAIに関する課題に対応するため、dentsu Japanは「AIガバナンスコミッティ」を設置し、複数の視点でチェックする体制を整えています。
──AI人財の育成については、どのような取り組みをしていますか。
並河:dentsu Japanの中に設置された「データ&テクノロジー委員会」が、グループ全体のAI人財育成に取り組んでいます。社員はAIの習熟レベルによって、「AIベーシック」「AIファシリテーター」「AIマスター」のランクに分けられています。
──ヒトがAIと共存する未来をどう見ていますか。
並河:電通が実施した調査 (※)では、「対話型AI」に感情を共有できる人(「非常に共有できる」「共有できる」「やや共有できる」の合計)は64.9%。「親友」「母」に並ぶ“第3の仲間"になっていると言えるでしょう。中には、友人よりAIの方が「相談しやすい」「自分を理解してくれる」と感じている人もいるかもしれません。
※対象者条件:対話型AIを週1回以上使用する12~69歳
他方、これまでの話の中でも触れてきたように、企業においてはマーケティング領域をはじめ、あらゆる活動領域でAIの活用が進んでいます。
──最後に、AI/クリエイティブ領域担当のグロースオフィサーとして、今後どのように仕事をしていきたいですか。
並河:やはり面白がることが大事かなと思っています。
「AIネイティブマーケティング 人、企業、AIの幸せな関係をつくる」 並河進・著