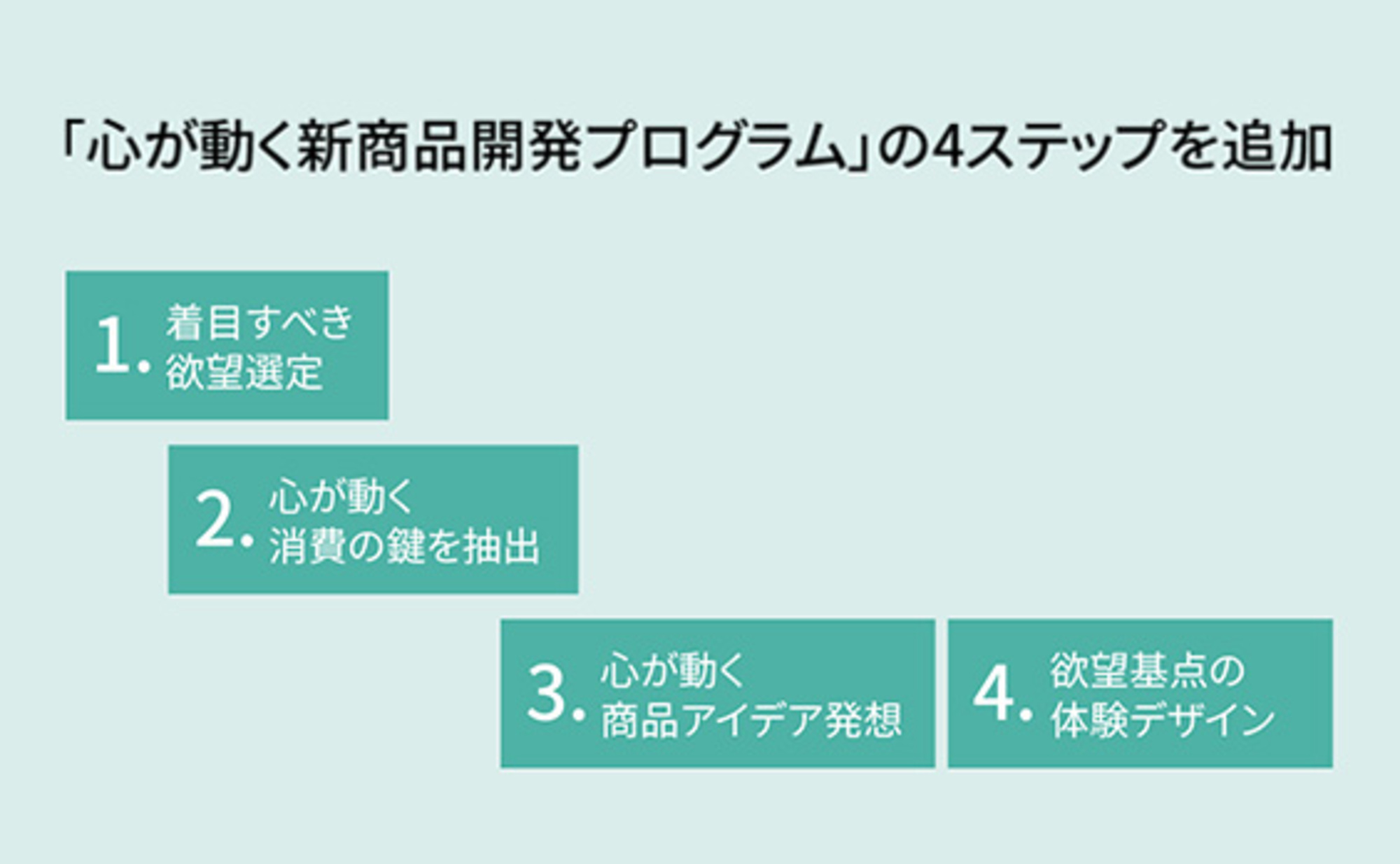あなたの得た情報は「偏っている」?データで読み解く情報偏向への向き合い方
電通デザイアデザイン(DDD)は消費と欲望の関係から、さまざまなソリューション開発や情報発信を行う組織です。
第21回からは、DDDが実施している「心が動く消費調査」を分析。調査結果から得られたインサイトやファインディングスをお伝えしています。
今回は、2025年5月に実施した第10回の調査結果に基づき、DDDの千葉貴志が情報取得における認識と行動をテーマに調査の結果を考察します。
「情報の偏り」への意識と行動で、令和の消費者意識をひもとく
情報爆発といわれて久しい昨今において、われわれが日常生活において接している情報は、スマートフォンを中心に一人一人に向けてパーソナライズされています。自分がその日接した情報が隣の人と全然違うのは当たり前になっており、「みんなが知っていること」というものは昔と比べて少なくなっています。
しかし、「自分が普段得ている情報は、偏っている」と思うかを聞いたところ、「そう思う」「ややそう思う」と答えたのは52.1%、「そう思わない」「あまりそう思わない」が47.9%となり、半数近くの人が「偏っていない」と思っていることが明らかになりました。

では、情報取得に向けた行動についてはどうでしょうか。「自分とは異なる立場の人の意見や考え、情報を知るための行動をとっている」かどうかを聞いた結果が以下のグラフです。
「そう思う」「ややそう思う」が46.0%、「そう思わない」「あまりそう思わない」が54.0%と、こちらは「そう思わない」「あまりそう思わない」がやや多いという結果になりました。

そこで今回は、この「情報の偏り」について、「偏っているという意識」と「異なる意見や情報を知るための行動」という2つの軸を組み合わせることで、令和の消費者の情報に対する向き合い方を見ていきます。
情報への向き合い方は、年代によって顕著な差
はじめに、4象限で分類した時の割合を見てみます。一番多いのが「情報の偏り認識なし×自分と異なる意見や考えに対する積極的な情報の取得行動なし(以降、積極的な情報の取得行動なし)」で29.0%、次に多いのが「情報の偏り認識あり×積極的な情報の取得行動あり」27.1%となっています。
一番少なかったのは「情報の偏り認識なし×積極的な情報の取得行動あり」でしたが、それでも18.9%のボリュームがあります。多少の差はあるものの世の中全体として、4象限それぞれに一定のボリュームの消費者がいることが分かります。

一方で、象限別の年代構成を見てみると、大きな違いが見られます。

例えば、情報の偏りの認識があり、そのうえで積極的な情報取得のための行動をとっている「情報の偏り認識あり×積極的な情報の取得行動あり」層は、30代以下で47.0%と半数近くを占めますが、50代以上では31.2%にとどまります。
対して、「情報の偏り認識なし×積極的な情報の取得行動なし」層は、30代以下で25.8%とおよそ4分の1しかいない一方、50代以上では54.8%と過半数以上を占めています。
こうした状況から、情報の偏りと積極的な情報取得のための行動については明らかに年代による違いがあると言えます。
現代の消費者が抱える「欲望」は、情報偏向意識と行動に影響するか
次に、同じ4象限に対して、DDDが定義する「11の欲望」※を基に、各欲望を最も強く持つ人々ごとの違いを見てみましょう。


※「11の欲望」について詳しくは、こちらをご覧ください。
・「新しい欲望に、名前をつけてやる。」( ウェブ電通報)
・DENTSU DESIRE DESIGN、人間の消費行動に影響を与える「11の欲望」2024年版を発表
レーダーチャートを見てみると、ほぼすべての欲望因子において、各象限の傾向が同じような形となっています。その中で、「情報の偏り認識あり×積極的な情報の取得行動あり」層(水色)は、他の象限よりもすべての欲望が強く、逆に「情報の偏り認識なし×積極的な情報の取得行動なし」層(薄いオレンジ)は全項目弱い様子が見てとれます。
つまり、情報の偏りに対する自己認識と積極的な情報の取得行動の有無は、各自が持つ「全体的な欲望の強さ」と相関があると言えそうです。
また、概ね同じような形のチャート図を示す中でも「承認&優越」「興奮&享楽」「収集&没頭」といった、比較的消費行動につながりやすい3欲望には各象限における、数値の差が比較的顕著にみられます。その点を踏まえると、各象限は全体的な欲望の強さに差があることに加えて、価値観や消費行動にもある程度の偏りや違いがあると考えられます。
幸せを感じやすいのはどのタイプ?情報への向き合い方と「価値観」の関連性
ここからは、象限ごとの価値観について見ていきます。「自分は幸せだと思う」かどうかを聞いた結果が以下のグラフです。

「自分とは異なる立場の人の意見や考え、情報を知るための行動をとっている」と答えた「情報の偏り認識あり×積極的な情報の取得行動あり」層、さらに「情報の偏り認識なし×積極的な情報の取得行動あり」層のほうが、行動をとっていない2つの層よりも「幸せだ」と考えている人の割合が高い結果となりました。
情報があふれる社会においては、情報に対する向き合い方と幸福感は無関係ではないと言えるのかもしれません。
他の価値観項目についても見ていきます。

いくつか特徴的なところを詳しく見てみましょう。
「インターネット上の情報よりもテレビ局や新聞社などの大手メディアの情報を信頼している」と答えた人の割合が、全体平均では56.7%でしたが、「情報の偏り認識なし×積極的な情報の取得行動なし」層が60.3%と他の層と比べて大手メディアへの信頼度が高いことが分かります。これは図表4で示した年代構成の影響も大きいと考えられます。
「YouTubeなどの動画共有サービスでレコメンドされた動画コンテンツを見ていると、自分の興味関心が広がっている気がする」という項目については、「情報の偏り認識なし×積極的な情報の取得行動あり」層が63.3%と他の層より高くなっています。
レコメンドは多くの場合、ユーザーの検索内容や再生状況から、興味関心に近いものを深掘りしていく機能です。しかし、自分の得ている情報を偏っていないと捉えているこの層の人たちは、「興味関心の深掘り」ではなく「興味関心の広がり」の契機と捉えているのではないでしょうか。
「日常の裏に潜む誰かの苦労や不幸せを知る機会を得たい」という項目と「自分さえ幸せであればいいと思う方だ」という項目を組み合わせてみると、どちらも「情報の偏り認識あり×積極的な情報の取得行動あり」層が一番高い結果となっています。「誰かの苦労や不幸せを知りたい」と思いながらも、「自分さえ幸せであればいい」と答える人が多い点からは、「誰かの苦労や不幸せ」を見ることで、相対的に自分の幸せを確かめている可能性もあるのかもしれません。
情報の偏りは、単に世の中から「みんなが知っていること」が減っているというだけでなく、幸福感やさまざまな価値観の違いとも関連があることが分かりました。個人としても社会としても、どういった状態が「情報空間や情報摂取においてあるべき未来」なのかを考えながら、周囲を取り巻く情報と向き合っていく必要があるのではないでしょうか。
【調査概要】
第10回「心が動く消費調査」
・対象エリア:日本全国
・対象者条件:15~74歳男女
・サンプル数:計3000サンプル(15~19歳、20代~60代、70~74歳の7区分、男女2区分の人口構成比に応じて割り付け)
・調 査 手 法:インターネット調査
・調 査 時 期:2025年5月13日(火)~ 5月16日(金)
・調 査 主 体:株式会社電通 DENTSU DESIRE DESIGN
・調 査 機 関:株式会社電通マクロミルインサイト
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

千葉 貴志
株式会社 電通
未来予測支援ラボ
プロデューサー
営業、デジタル、テレビなどの部署を経験した後、電通総研に出向。社会調査全般を担当し、スポーツやメディアに関わる過去の業務経験をもとに「地域とスポーツ」「メディアの未来」をテーマに活動。2022年より電通に帰任し、クライアントの未来の企業価値を創発する未来予測支援ラボ/未来事業創研/消費者研究プロジェクトDENTSU DESIRE DESIGNに所属。2023年より、SPORTS TECH TOKYOにも参画。