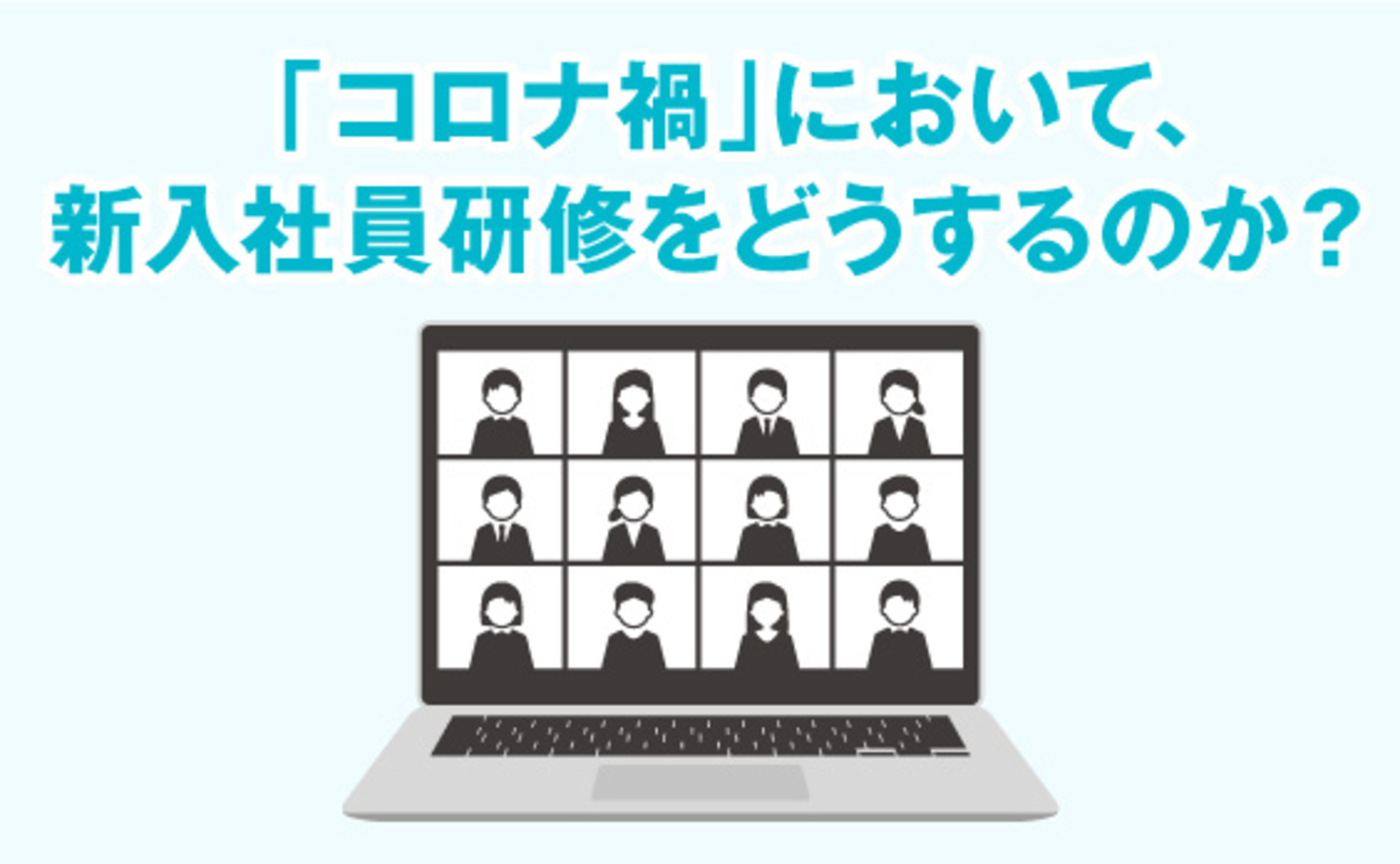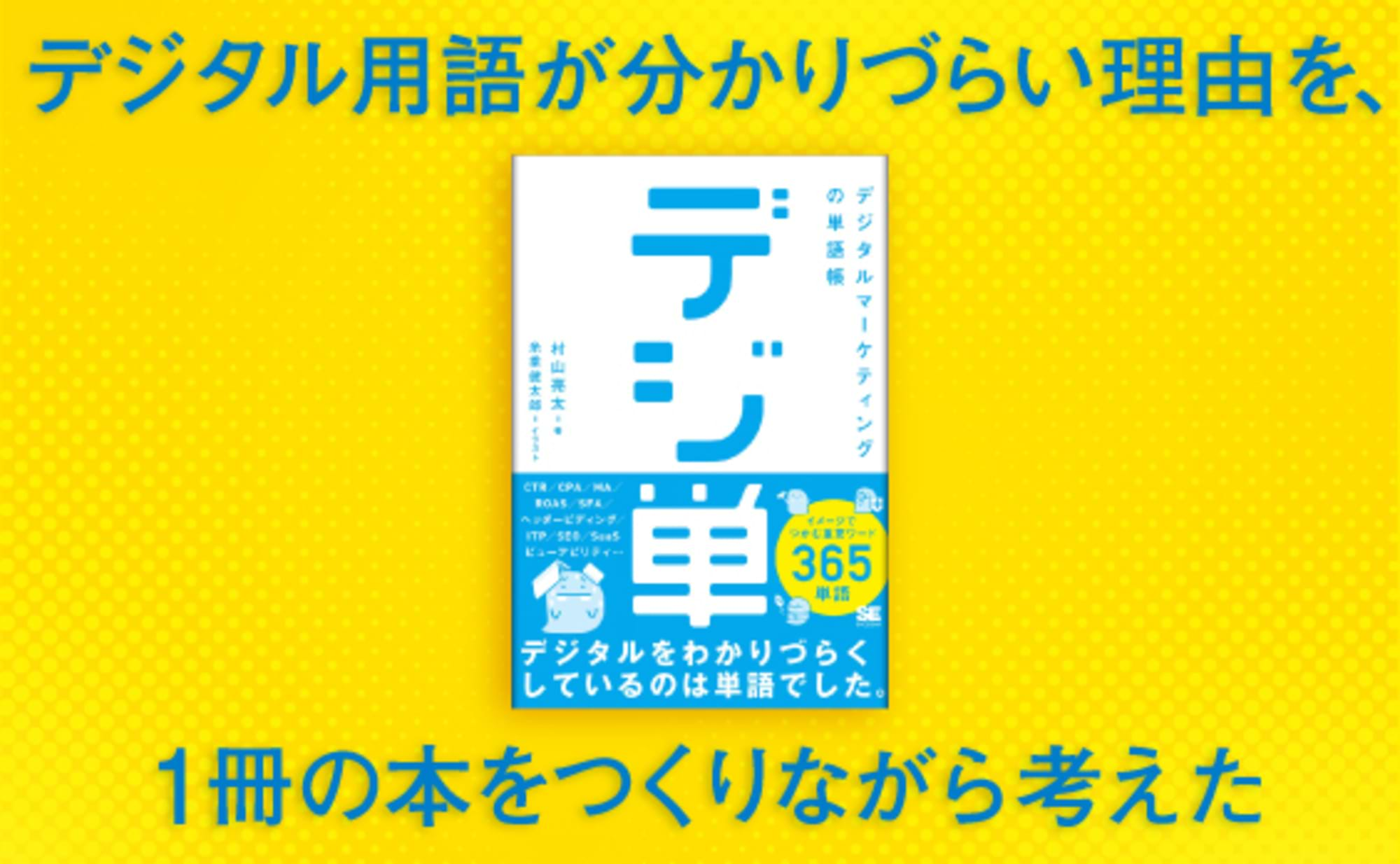これからはデジタルでやっていく。全社員に「デジ単」を配布したNTTタウンページの挑戦

井原 知宏
NTTタウンページ株式会社
※電通の村山亮太による書籍「『デジ単』デジタルマーケティングの単語帳 イメージでつかむ重要ワード365」」(発行:翔泳社)。その重版出来を記念して、本書を2000冊一括購入(!)して 全国の社員に配布したという、NTTタウンページ企画部の井原知宏さんにお話を聞きました 。
<目次>
▼社長の思い「強い者が生き残るのではない、変化に対応できる者が生き残るのだ」
▼紙の事業で蓄積した“資産”をデジタルビジネスで生かす
▼「これからはデジタルでやっていく」社員の意識もデジタルシフト!
社長の思い「強い者が生き残るのではない、変化に対応できる者が生き残るのだ」
──長年「ハローページ」(50音順電話帳、2021年で発行終了)、「タウンページ」(職業別電話帳)という電話帳の事業を続けてきたNTTタウンページが、自社のユニークな資産を生かしたデジタルビジネスを推進するため、「マーケティング部門」を新設しました。井原さんは準備段階から携ったとのことですが、これまでのご経歴は?

井原:1998年、新卒でNTTタウンページに入社し、今年で24年目になります。広告の訪問営業を7年、そこから営業企画、経営企画などを経て2020年の2月からマーケティング部門の立ち上げ準備を始め、以降はマーケティングを担当しています。
──この20年は、まさにアナログからデジタルへのシフトと共に歩まれたと思います。会社の事業領域はどのような変遷をたどったのでしょうか?
井原:今も昔も紙の電話帳の広告事業を主としていますが、私の入社した頃にインターネット版の電話帳「iタウンページ」が始まり、大きく成長して、2本柱になりました。
その後2012年に、タウンページの掲載情報をデータベース化した「タウンページデータベース」を販売するNTT情報開発と経営統合して、データベースビジネスという柱を加えました。さらに2019年からはホームページを基盤とした「NTTタウンページ Digital Lead(以下、デジタルリード)」という、デジタルマーケティング商品の販売を始めました。

──電話帳の広告事業からデジタルマーケティング事業に舵を切り始めたのは、広告収入に変化があったからでしょうか?
井原:それもあります。紙の電話帳の広告収入が1千億円を超えていた時代もありましたが、徐々に減少し続けています。今でも紙の電話帳による広告収入が売り上げの約7割を占めてはいますが、企業にDX(デジタルトランスフォーメーション)推進という変化が求められる時代を迎え、会社としての軸足をデジタルに移そうとしているところです。
──会社のビジネスをデジタル化していくためには、マーケティング部門が必要だと考えたのですね。
井原:はい。今後デジタル商材を本格的に販売していくに当たり、業務効率を最大限上げるには、各組織や全国の営業所の連携が大きなポイント。マーケティング部門はそうした社内の協力体制をつくる役割を担います。また、これまで着手できていなかった、お客さまからの問い合わせを増やすデジタルマーケティング戦略にも取り組み始めています。
特に、当社の社長(酒井紀雄氏)は
強い者が生き残るのではない、変化に対応出来る者が生き残るのだ
というダーウィンの言葉を社員向けメッセージに盛り込んだり、時代の変化に呼応するマーケティング部門の設置には強い意志があったと思います。
紙の事業で蓄積した“資産”をデジタルビジネスで生かす
──「営業により広告枠を販売する」ことを長く続けてきたNTTタウンページが、今マーケティング部門を立ち上げたのは、「時代に合わせた事業を行っていく」という会社の意思表示でもあるわけですね。ここからは、デジタル分野での事業について聞きます。まず、「タウンページデータベース」はどんなビジネスでしょうか?
井原:タウンページに掲載された約640万件の情報を業種別にデータベース化し、どこにどんな施設や店舗があるのか、全国の大企業から個人事業主まで幅広い情報を網羅しています。
──データベースはどんな顧客に、どのように活用されるのですか?
井原:企業や事業所では、DM送付、テレマーケティングや商圏分析に、カーナビ会社では電話番号から目的地を設定して経路が案内される機能に活用されています。新しい使われ方としては、人の動きをリアルタイムで見ることができるNTTドコモのデータと組み合わせ、行政や自治体向けに販売したりもしています。つまり、「観光客がどのお店にどう流れているのか」「有事の際にどのような避難経路が使われるのか」といった情報が可視化できるのです。
また、過去20年超、18億件に及ぶデータが蓄積されているので、例えばA町は10年間でどういった業種の店舗が増えたのか、あるいは減ったのかといった、全国各地域の“栄枯盛衰”を見ることもできます。それを基に、相関関係分析や未来予測もできるということで、大学など研究機関からも注目いただいています。

毎月更新される「タウンページ」掲載情報633万件(2020年6月末時点)をデータベース化したもの。1900業種に分類された全国の登録情報を特定の業種、地域といった絞り込みをかけて顧客に提供する。NTTタウンページが紙の電話帳を始めた時から長年蓄積してきた“資産”をデジタルサービスに活用している商品の一つ。
──もう一つのデジタル商品「デジタルリード」は、中小企業や個人商店を主なターゲットにしたサービスですよね。
井原:デジタルリードは、小規模な店舗でも運用できる、コンパクトなデジタルマーケティング支援のサービスです。タウンページのお客さまは中小企業から個人商店くらいの規模の方が多く、そうした方々に向けて「ホームページを起点に集客から成約までをワンストップで支援」と掲げています。海外の電話帳事業会社の動向を調査したところ、デジタルマーケティングビジネスを展開していることが分かり、それを参考にしました。
以前、全国のタウンページのお客さま、つまり広告主にアンケートを実施したところ、回答約7000件のうち6割近くが従業員5人以下で、その6割がホームページを持っていませんでした。
お話を聞くと、世の中の動きを感じて「何かした方がいい」とは思っているけれど、「デジタルには詳しくないから、何をしたらよいかが分からない……」という方が多い。それに、少人数で回している事業主は、新たなことに手間も大きな費用もかけられない。そんな、古くから付き合いのあるお客さまのビジネスを、デジタル化でより良いものにするために立ち上げたサービスが、デジタルリードです。
具体的にはホームページの制作とスタートアップフォローを請け負います。ご希望や業態に応じて、SEMと言われるウェブ広告やブログ、SNS連携による集客、Eコマースの決済、予約や資料ダウンロードなど、必要な機能を選択いただけます。基本パッケージは月額1万2100円(税込み)からと、始めやすい価格に設定しました。
ホームページの掲載内容、必要な要素については、各地の営業スタッフが得意のヒアリング力を、デザインはこれまでの電話帳編集でつちかったデザイン力を生かして、理想のページづくりをお手伝いしています。導入から3カ月間は、担当のスタッフが連絡を取りフォローするので、デジタルツールが初めてのお客さまにも安心して利用いただけます。
──お客さまに寄り添ったサービスですね。評判はいかがですか?
井原:2019年の9月から販売を始めたのですが、おかげさまで約9000件の売れ行きです(2021年1月現在)。おそらく2月には1万件に達するでしょう。しかし、販売のペースが良過ぎて、お客さまをお待たせしてしまっている状況もあります……。
われわれマーケティング部門の業務は本来、「デジタルマーケティングの戦略を立てて、売れる仕組みをつくる」ことですが、今はたくさんのデジタルリード受注に対して、販売からホームページ公開までをスムーズに進められるよう、社内連携の最適化に注力しています。

ホームページ制作と運営サポートを請け負うサービス。顧客の業態や要望に応じてSNSやメールマーケティングなどによる集客、Eコマースの決済や予約機能といった付帯サービスも提供する。今までホームページを持っていなかった事業主がイチから勉強せずともデジタルマーケティングを始められるよう、iタウンページで約20年のウェブ運営実績のあるNTTタウンページがサポートする。
──お客さまのDXを支援するために、NTTタウンページ自体も本格的にDXに取り組み始めているそうですね。
井原:当社では社内の単純業務へのRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入や、リモートワークの推進など、「従来業務をデジタルで効率化する」という意味での一般的なデジタル化も進めていますが、並行して、「事業領域のデジタル化と、それに伴う最適化」も進めている状況です。
マーケティング部門を立ち上げた際、社長から「デジタル化を機会に、社内の各部門が連携し、組織横断で全社最適を目指そう」というメッセージがありました。当社はこれまで、全国の営業所や各組織で完結する業務が多かったのですが、デジタルビジネスを推進するためには、全社が連携することが必要です。今マーケティング部門が取り組んでいるのも、まさにそこです。
「これからはデジタルでやっていく」社員の意識もデジタルシフト!
──営業の方たちはずっと「電話帳の広告枠を売る」ことに取り組んでこられたのですが、データベースやデジタルリードをお客さまに勧めるには、商品知識を熟知する必要があります。営業スタッフの商品理解を深めるため、どんな取り組みをしていますか?
井原:商品主管部門と営業部門が連携し、説明会や社外講師による研修を実施しています。また、商品に関連する資格取得も全社的に推奨しています。説明会や研修以外にも各地の営業所に本社から人を出して同行訪問するなど、知識の定着を支援しました。
コロナ禍以降には、人を派遣する同行訪問を減らし、全国から社員約30人を選抜して本社に集め、データベース販売の選抜チームを立ち上げました。徹底したOJTで知識とスキルを上げてもらい、いずれは全国の核要員となる人材です。
そして全社員に最新のデジタルマーケティング用語について知ってもらうため、レクチャーに加えて「デジ単」を配布することで、知識習得の相乗効果も図りました。
──「デジ単」はどのような経緯で導入することになったのですか?
井原:私が個人的に本屋さんでデジタルマーケティングの本を探していたんです。「デジ単」はイラストと解説の組み合わせで、専門的な用語もコミカルな表現でわかりやすいなと思いました。そこで、購入して周囲の社員や社長に見せたところ、これが好評だったので、一括購入して全社員に1冊ずつ配布しました。
──全社員に!?
井原:はい。まとめて2000冊ほど購入し、全国の社員に配りました(笑)。もちろん会社全体のデジタルリテラシーを上げたいという狙いもありますが、もう一つの理由として、私たちは何十年と紙の電話帳をやってきた会社です。「急にデジタル商品を売れと言われても……」と、戸惑う社員もいると思うんですよね。そういう社員に対しても、「これからNTTタウンページは、デジタルでやっていくんだよ」という意識を浸透させたい思いがありました。
──確かに、全員に1冊配布というのは会社の“本気度”が伝わるし、意識改革につながりますね。社員からの反応はどうでしたか?
井原:営業現場から、お客さまとのコミュニケーションに実際に役立ったという声をもらいました。ずっと紙の電話帳の広告営業をしてきたので、数年前までは、デジタル導入支援をやることになるとは思いもよらなかった人が大半でしょう。でも、急激に変化していく環境下でも手元に「デジ単」があることで、「何かあれば頼れる本がある」という安心感を持ってほしいです。
──社員のデジタルリテラシーの底上げを図りつつ、新たな事業領域への挑戦に「デジ単」が一役買っているのですね。最後に、NTTタウンページの今後の目標をお聞かせください。
井原:目標というか課題ですが、喫緊では、先ほどお話ししたデジタルリードの販売のための社内各部門の連携と最適化です。2021年度以降は、デジタルリードとタウンページデータベースというデジタル商材の販売を、どう軌道に乗せていくかに注力します。数年で電話帳の売り上げを、これらデジタル商材の売り上げが上回ることが目標ですね。
──地方の個人商店や中小企業にデジタルツール導入を勧める競合企業もいると思います。そんな中、「NTTタウンページの強み」というと、やはり古くからお付き合いのある広告主との信頼関係になるのでしょうか?
井原:そこは強みです。当社には約20万件のお客様がいらっしゃいますが、長年の営業活動の成果で、当社の営業スタッフはお客さま各社の責任者との信頼関係がしっかりと築けています。
お客さまご自身が、この時代にどう動けばよいかに迷われているとき、あるいは自社や自店舗の課題にお気づきでないとき、私たちが課題を発掘して最適なアイデアを提供する。これまで電話帳事業でつちかった営業力を、長年お付き合いしてくださっているお客さまへ、そんな形で還元できればと思っています。
「Your Marketing Partner」というのが、当社の企業理念です。既存の20万件のお客さまと、これから提案していく新規のお客さまに、最適な価値を提供し続けるマーケティングパートナーを目指し、お客様と一緒に事業環境の変化に対応していきたいです。
【本書のポイント】
・デジタルマーケティングの頻出単語をシンプルに解説
・イラストを見るだけでもイメージがつかめる
・似た単語の意味の違いや、使い分け方もフォロー
・索引つきで単語や同義語を探しやすい
・英語表記もあるので、海外サイトを読むときや出張にも便利
この記事は参考になりましたか?
バックナンバー
著者

井原 知宏
NTTタウンページ株式会社
企画部
マーケティング戦略担当
1998年にNTTタウンページ入社。関西でフィールドセールスを経験後、関西や北海道での営業企画や本社営業統括・経営企画などを経て、2020年2月からマーケティング部門の立ち上げに携わる。現在はマーケティング戦略担当として、デジタルマーケティングや組織横断的な業務に従事。