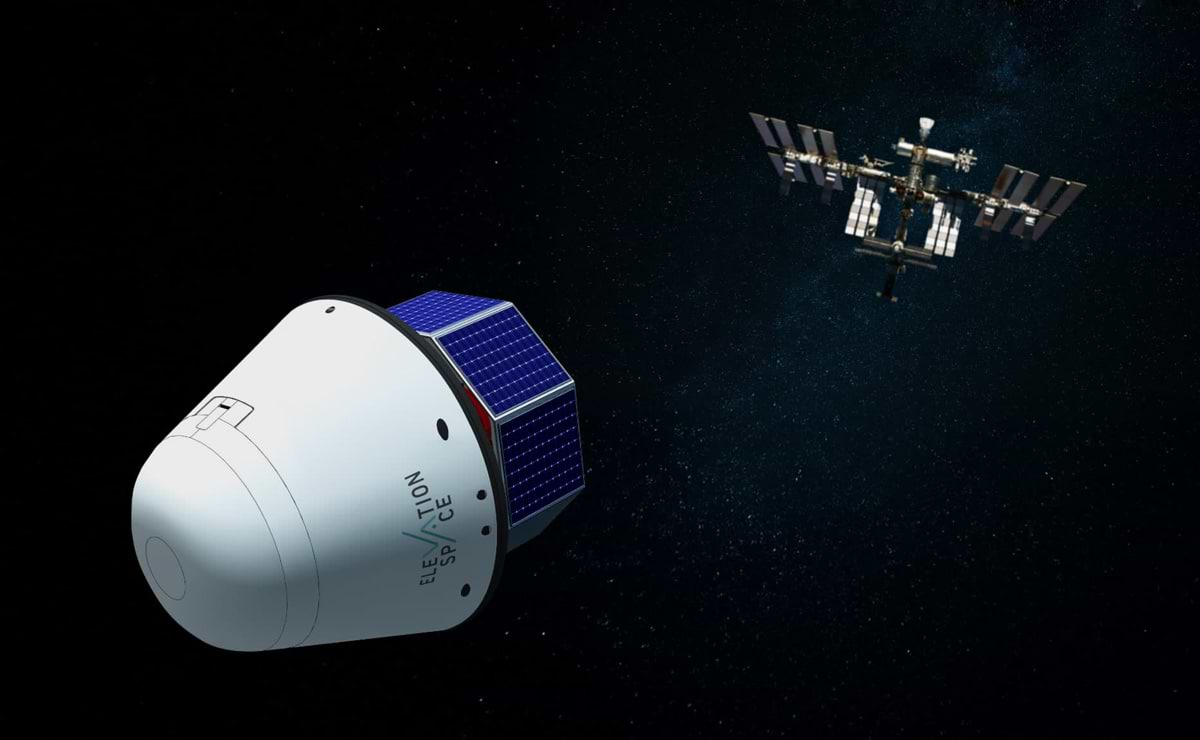グローバルなビジネス誌 Forbes JAPANと電通がともに始めた、全国各地の規模は小さくても世界に羽ばたく企業を発掘するプロジェクト「スモール・ジャイアンツ」。
6回目のスモール・ジャイアンツアワード2022-2023では、北海道北見市の「環境大善」が「ローカルヒーロー」賞を受賞しました。牛の尿を原料に消臭液や土壌改良材を手がけ、前人未到のアップサイクル事業を行う企業ですが、窪之内誠社長はある悩みを抱えています。
それは、「事業が拡大していくにつれて、スケールアップと設備投資のタイミングをどうするか?」という問題です。
多くのスモール・ジャイアンツたちが抱える悩みを解決すべく、Forbes JAPANは「オンライン師弟相談会」を実施。相談相手は、窪之内社長が“師匠”として尊敬してやまない「COEDOビール」を手がける協同商事(埼玉県川越市)の朝霧重治社長です。
牛の尿とビール──。危険な香りのする並びですが、「農業」や「発酵」という事業の共通点を持つ2人の社長の話題は、意外な方向性へと進んでいきました。
【環境大善】
北海道の主要産業である酪農が引き起こす水質汚染や悪臭被害の改善を目指し、発酵処理による牛尿の無害化と発酵液に含まれる機能性を活用した「善玉活性水」の製造販売を行う。2019年より「発酵経営」を掲げ、持続可能なアップサイクル型循環システムによる地球環境の改善に取り組む。
【協同商事】
埼玉県川越市周辺を拠点に、「COEDOビール」ブランドのビールを造るクラフトビール醸造所や、農作物の商社として事業を展開。農産物の栽培から、物流、販売、食品への加工を含め、農産物がお客さまに消費されるまでの全ての過程を農業の一環と考え、有機栽培青果物栽培指導・加工・販売、物流、ビール製造、食品輸入、廃棄物リサイクル技術研究開発など、農業を出発点とする食のサイクルすべてに関与する、総合食品企業として活動する。
「発酵」が生産拡大のボトルネックに
環境大善・窪之内社長(以下、窪之内):朝霧さんに実際にお会いしたのは2022年12月、Forbes JAPAN主催のGALAパーティーでしたね。ですが、僕自身が会社のブランディングを始めた頃に中川政七商店十三代の中川淳さんと「COEDO」ビールなどのデザインを手がける西澤明洋さんの共著『ブランドのはじめかた』を読んで感銘を受けたので、自分にとって朝霧さんは“師匠”といっていいほど、かなり大きな存在なんです。
協同商事・朝霧社長(以下、朝霧):師弟関係だなんて大袈裟な立場であるとは思いませんが、クラフトブルワリーの根っこも「農業」です。御社では肥料や土壌改良材などを手がけられていますし、畜産も私たちのビジネスとそんなに遠い話じゃないんですね。GALAパーティーの二次会では隣の席で、いろんなお話をさせてもらいました。
窪之内:『ブランドのはじめかた』で、COEDOをブランディングし、売り上げが3倍になったと拝読しました。弊社も3年半かけてリブランディングを実行し、2021年、2022年と商品リニューアルをしておかげさまで好調に推移しているのですが、1点悩んでいることがあります。
それは、事業のスケールアップや設備投資のタイミングです。牛はたくさんいて液量もたくさんある。ですが、ビールのように発酵に時間がかかるんです。COEDOビールでは倍増計画があったそうですが、生産体制はどんなタイミングで整えられたんでしょうか。
朝霧:私たちの共通点は「発酵」なんですね。おっしゃる通り、時間がかかるじゃないですか。そこがボトルネックになっていて、どんなに売れても発酵槽など設備のキャパシティが生産能力の上限を決めることになる。
実は先代が経営していた頃、地ビールブームが起こって生産が追いつかなくなった時に、ビジネスチャンスに賭けて20倍の設備投資をしているんですね。結局その判断が、ビール事業が苦境に陥った一番の理由となった。
そんなことやらなければ良かったと、気づきまして。でもあの拡張性があったからこそ、今のCOEDOがあります。この苦い経験から、私は「拡張性」を大切にしています。一気に2倍、3倍も設備を整える必要はなく、例えば20%の増強投資を継続していく。そうすれば無理をせずに事業規模に合わせて拡張し続けることができるんです。おそらく御社の場合は原料の調達は問題なくできますし、出来上がったものをパッケージ化する工程も、連続で稼働させるなどの効率化を図れば、特に問題なく拡張できますよね?
窪之内:そうですね。今のところ手作業が非常に多いので、ライン充填機などを導入したり、人海戦術で人員を増やすなど、状況に応じて対応できると思います。ご指摘の通り、うちも発酵槽がありまして、そこの容量が売上の総量を握っています。先代の時から思い切った設備投資になかなか踏み出せずにいるんですよね……。
「拡張性」を担保することで、スケールアップに対応する
朝霧:発酵業はそれでよろしいと思います。まず、設備に建屋が必要なのか、屋外の発酵タンクでも大丈夫なのかを見極める必要があります。もし屋内で発酵の管理が必要ならば、建屋はある程度経済性のある簡易なつくりで、しばらくは伽藍堂のままでも構いません。そして、事業のスケールアップに合わせて徐々に建屋を発酵タンクで埋めていくなどして「拡張性」を担保できると良いですね。
窪之内:これまでは酪農家併設のプラントがメインだったんですけど、ちょうど2022年に補助金をいただいた関係もあり、自社プラントの敷地に400トンのプラントを4つ作ったんです。ただ雪が積もって冬はなかなか稼働しないので、新しく建屋を作るか氷を割ってでも稼働させるかという議論になりました。
積雪のある冬季は北海道では土壌改良材のニーズはほぼなく、売り上げもすごく下がる時期だったんです。ですが、おかげさまで本州以西のホームセンターでの需要がほぼ下がらなかったので、新しく作ったプラントを仮稼働させて対応することができました。
朝霧:良かったですね。私たちは2016年、次のフェーズに移行するために先代の工場から現在の醸造所に移転したんです。敷地が大きい用地の確保から手がけました。20〜30%の増産計画でも手一杯になると、ジャンプしなくてはいけないタイミングがやってきます。そんな時も次の世代にとって負の遺産とならないようなレベルでやっておくことが大事だと思っています。
設備投資にも「ビジョン」を

窪之内:醸造所を新しく移転する計画は、どのようなタイミングで出たんでしょうか。
朝霧:移転まで、5年くらいかけていますね。不動産って欲しくてもすぐに良いものが出てくるか分からないし、理想的な物件が見つかればラッキー。嗜好品みたいなものじゃないですか。うちの場合は、立地も含めてブランディングに通じるので、工業団地ではなくて雑木林や田畑などがある自然豊かな環境に工場があることを理想として物件探しをしていました。
一方、立地や周辺環境にこだわらなければ、自治体からの誘致を受けて工業用地などを活用する方法もあると思います。
窪之内:うちは本社が住宅街のど真ん中にありますが、視察に来られた方は必ず「建物の中のにおいがしない」と驚かれます。酪農家から仕入れた牛の尿100トンが常時あるのに、です。確かに場所は大事だなと思いました。
今春、新たなプラントが本格稼働し、さらに需要も伸びていくことが予想される一方で、今後は資材庫をどうするかという問題もあります。市場に求められていくにつれて、設備投資の規模もビビってしまうステージになっていき、葛藤があります。
朝霧:資金の投下の仕方がポイントだと思います。なんでもかんでも自前主義でいくのではなく、外部倉庫をお借りして賃貸契約でキャッシュアウトを抑えていくなど、意識して使い分けていくことが必要です。腹を据えて100年先に向けて投資するのであれば、自社物件にすることもあり得る。うまくいかなかった時に急ブレーキをかけられる要素を持たせておくことが必要ですよね。
窪之内:設備投資にも、ビジョンが大切ですね。
朝霧:やはりこの部分はすぐに利益など結果が出るものではありません。ですが、設備は自分たちの存在意義に関わることだと思います。
やるべきこと、やらなくて良いこと、やりたいことを取捨選択する。特に私たちのようなスモールカンパニーにとってはやらない選択が結構大事だと思っています。いわゆる「選択と集中」ですね。
あえてやらないことが、ビジネスチャンスを呼び寄せる
窪之内:ちなみに御社であえてやらないことは、どんなことでしょうか。
朝霧:私たちはクラフトビールを醸造していますが、近年はあらゆる食品がクラフト化する流れがあります。例えばチョコレートやコーヒー。アルコール業界で言えば、ジン、ウイスキーにもクラフト化の潮流があります。
正直、私たちにとってウイスキーは参入しやすい事業なんです。蒸留機はそこまで高価なものではないですし、蒸留する樽も準備できる。ですが、「何屋なんですか?」と聞かれた時に私たちが全てのポートフォリオを埋める必要はない。あえてやらない選択もあるんです。
朝霧:その代わりに、クラフトウイスキーを手がけている方たちを応援しています。実際にアイルランドのウイスキーの会社ともグローバルにつながり、コラボレーションが進行中です。もし自社でウイスキーも手がけていたら、競合になってしまうのでコラボ案件は出てきませんよね。やらないことは犠牲になることばかりではないと思います。
窪之内:私たちも牛の尿を原料にしていると「牛の糞」はやらないの?と言われることもあります。ですが、こちらの分野はすでにうまく利用されていて肥料化する研究も進んでいます。一方、尿の研究事例はまだ少なく、もし有効利用ができれば地球に還元できるので社会的なインパクトも大きいです。なので、「牛の糞」はあっさり切り捨てたんです。
すると堆肥メーカーから、当社で製造している「液体たい肥 土いきかえる」を添加した堆肥を作りたいとお声がかかり、「土いきかえる堆肥」という商品が生まれ、40リットル1万体売れたんですよね。もし「牛の糞」に手を伸ばしていたら堆肥メーカーと競合するのでコラボレーションは難しかったでしょう。「牛の尿」にロマンを感じて思い切って事業の舵を切ることで、新しいビジネスチャンスも呼び寄せることができるのだと改めて思いました。
これまでのお付き合いでOEMもやっていますが、これからはきっちりとブランディングを進めて、私たちの名前を使ったり、協業する企業とダブルネームで新商品を出したり、より私たちの世界観が伝わるような手段を選べるようにしていきたいですね。

環境大善の「液体たい肥 土いきかえる」などの商品は、「ブランディング・CI/VI」部門で2022年度グッドデザイン賞を受賞した
【オンライン師弟相談を終えて】
師からの言葉(朝霧社長)
これまで廃棄物の業界は、静脈産業として見なされてきましたが、環境大善にとって「牛の尿」は動脈産業。それが全面に出されても、商品からクリーンな正統派という印象を受けるのはブランディングの効果が出ていると感じます。
「牛の尿」という大きなところからスタートされ、新しい分野を切り開いていくため、既存のニーズに対応するのではなく新しい価値を提示していくことになると思います。私たちもクラフトビールという誰も期待していなかったことを楽しめるように、サービス単体を磨いていくだけでなく、大元にあるビールが素晴らしいという概念を広める「Beer Beautiful」をコンセプトにしています。今後スケールしていく中で、ボーダーは意識して作らなくても海外展開のタネは自然と広がっていくでしょう。ぜひ世界で活動していきましょう。
弟分社長の学び(窪之内社長)
朝霧社長の言葉は明快でとても分かりやすかったです。酪農は本当に大変で、牛乳を大量に廃棄し続けている現状があります。身近なところでも、生産調整のために何軒も酪農を辞めていて日本の食の未来は大丈夫なのか心配になります。そのような苦境に直面する酪農家さんの売り上げの足しになるように、私たちは牛の尿を買うビジネスを展開しています。今回改めて、ビジョンを信じて愚直に続けていくことで世界の市場も必然と開いていくんだろうなと思えました。今後も、朝霧社長と農業について一緒に深堀りできる機会があれば嬉しいですね。
文=督あかり 企画=笹川真(電通)
Forbes JAPAN 2月25日発売号は、世界に誇る日本の「スモール・ジャイアンツ」特集!世界を制した中小企業「スモール・ジャイアンツ」の7社を紹介します。中小企業というと苦労話になりがちですが、とがった技術やビジネスモデルで世界で人気の日本企業にぜひ注目してください!
https://forbesjapan.com/magazines/detail/155