
この連載は、2023年にウェブ電通報が「10周年」を迎えたことにちなみ、「10」人「10」色というテーマのもとで、すてきなコンテンツを提供したい、という編集者の思いつきからスタートしたものだ。「10」つながりの企画ではあるものの、大きく出るのであれば「ダイバーシティ(多様性)」をテーマとした連載、ということになる。
思考に耽(ふけ)りたいとき、アイデアをひねり出そうとするとき、ひとには、そのひとならではの「お伴」(=なくてはならないアイテム)が必要だ。名探偵シャーロック・ホームズの場合でいうなら、愛用の「パイプ」と「バイオリン」ということになるだろう。
この連載は、そうした「私だけの、思考のお伴」をさまざまな方にご紹介いただくものだ。あのひとの“意外な素顔”を楽しみつつ、「思考することへの思考」を巡らせていただけたら、と願っている。
(ウェブ電通報 編集部)
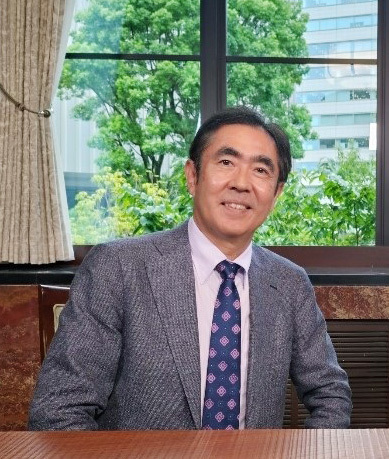
通信社とは、どういうお仕事なのですか?
──ウェブ電通報の連載「PR資産としての企業ミュージアムのこれから」を書籍にしていただいたご縁で、今回、無理をいって取材をお願いしました。よろしくお願いいたします。
小林:よろしくお願いします。
──いきなり初歩中の初歩の質問なのですが、通信社という会社はなにをしている会社なのでしょうか?同じ「記者」でも、新聞社やテレビ局の記者とは違いますよね?「ロイター発共同」みたいなことは、毎日、目にしているような気がするのですが……。
小林:ものすごく端的に言うなら通信社とは、自社サイトはありますが、基本的に紙の媒体は持っておらず、新聞社などにニュースを提供することを仕事にしている会社です。
──なるほど。情報を紙面にして、それを売り上げる。情報を電波に乗せることで、広告費を稼ぐということではなく、価値のある情報そのものをつかんでくる、というお仕事ですね。例えが適切かどうか分からないのですが、一次産業に近いというか。魚そのものを釣ってくる、コメそのものを育てて収穫する、というような。
小林:イメージとしては、間違っていないと思います。
──それだけに、取ってくる情報についてはシビアですよね。素材そのもので、真っ向勝負!といいますか。演出を加えることでエンターテインメントに仕立てる、ということはできないわけですから。
小林:そうですね。私たちの仕事の本質は、「本当にそう言えるのか?」に自分なりの決着を付けることではないかと思っています。だから、決して自分の思い込みで記事にするのではなく、自信を持って書くための前提としてさまざまな人に取材をします。

──「決着」ですか。
小林:そういう意味で、私は「他流試合」(初対面の人と話したり、飲んだりすること)と「道場破り」(相手のいる所に出向くこと)が何よりの好物です。
──「頼もう!」という感じですね。宮本武蔵みたいな。
小林:私は、大げさに言えば、世論をつくるのは解説委員(=論説委員)だと考えています。特定のだれか一人ということでなく、全国紙や地方紙(どんなに小さくても)、テレビなどにいる多くの解説委員のことです。解説の世界は「良貨は悪貨を駆逐する」ものだと思います。だれかが目を引く解説を書くと、それに触発されて別の解説委員が切り口を変えて書く。そうやってさまざまな論点が出て、あるテーマをめぐる考え方が研ぎ澄まされていく。
──小林というヤツ、なかなか鋭いことを言うな。ならば、この私も。みたいな「知性の連鎖」が起きていく、ということですね。
小林:現場の記者は抜きつ抜かれつの情報合戦できゅうきゅうとしていますが、一歩引いて俯瞰(ふかん)したモノの見方を期待される解説委員の面白さ、醍醐味(だいごみ)はそうしたところにあります。

小林:「来た、見た、書いた」程度の記事なら4、5年もすればほとんどの記者は書けるようになります。報道の面白さはその後、自分の問題意識を世の中に発信できるようになってからです。また、私は日本記者クラブの企画委員の一人として、テーマを決めて識者を招請し記者会見を開くことで、「書く」のとは別の形で問題意識を世に問うことができる喜びを感じています。

そんな小林さんの「思考のお伴」に迫ってみたい
──通信社の解説委員というお仕事が、徐々に分かってきました。
小林:解説は単なる思い込みで書くわけにはいかないので、自分の考えていること、感じていることが的外れではないことを確認したいのです。これは、いわゆるファクトチェックというものとは異なります。
──「来た、見た、書いた」程度の記事なら4、5年もすれば書ける、というのはそういうことなんですね。
小林:その分野で見識があって信頼できる人を訪ねてお話をうかがう。初めて気づくモノの見方を知ってインスパイアされることで、ヒントや相場観が得られるのです。
──「相場観」かあ。これまた、新たなキーワードが出てきましたね。
小林:「世の中はいま、どちらへ向かっているのか?」ということと「(未来は)どうあるべきなのか?」という方向と、その振れ幅を見極めることが大切です。極端な話をしますと、「犯罪者」だろうが「とんでもなく偉いひと」だろうが、私にとっては大切な取材相手なんです。「人の話に、誠実に耳を傾ける」ということが、私たちの正義ですから。
──うわっ。そういう話が聞きたかったんです。働いていると、これを言ったら怒られるのではないか?とついついナーバスになってしまうものですから。いわゆる「空気を読む」というヤツです。
小林:それが、「ペンを執る者」としての責任というか矜持(きょうじ)というか、そういうことなのだろうと思います。新聞やテレビといったマスコミが社会から得ている信頼。その信頼に対して、決して裏切らない。忖度(そんたく)はしません。嫌な質問も普通にします。社会的地位の高い人に対しては特にそうです。そうしたことが、通信社で働く私のような人間にとって、最も基本的で、なおかつ「最後の生命線」だと思います。

小林伸年さんの「思考のお伴」とは?
──さて、そんな小林さんにとっての「思考のお伴」とは一体、なんなのでしょうか?
小林:ずばり「歩くこと」です。時として「問わず語り」でしょうか。
──「問わず語り」?気になりますね。「独り言」の意味ですか?それとも「頼まれてもいないのにしゃべり始める」みたいなことでしょうか?僕もしょっちゅう、仲良しの仲間のLINEで「頼まれてもいないのに」しゃべり始めて、疎まれているのですが。
小林:後者ですね。はじめましてー、の後に本題へ入る前のやりとりと、取材を終えて帰るとき。見送ってもらってエレベーターが来るのを待つ間とかね。そのときに、おもむろに相手が語りだしたら、そこにヒントがあります。メモなんて取りません。録音も一切しない。それでは、生の人間の言葉は引き出せませんから。もちろん、相手を見送った直後に、大事なキーワードを必死で思い出してメモに取ったりするのですが。
──「歩くこと」については、いかがですか?
小林:支局(静岡、横浜、長野)にいたときもシドニー時代も、まとまった原稿を書くときは、街中を歩いて考えを巡らせていました。方法論として確立していたのではなく、パソコンの前にじっと座っていることができなかったからというのが実態ですが。今も定期的に解説記事を書いている中、テーマ設定をするとき、構成を考えるとき、執筆段階で銀座周辺を歩いています。そぞろ歩きといったのんびりしたものではありません。表面的にはそう見えると思いますが、締め切り数日前などは、内心ではのたうち回っています。
──銀座、ですか。いいですね。僕のような若輩者が言うのもナンですが、あの街には何とも言えない「気」が満ちているような気がするんです。僕は、いわゆるニュータウン育ちで、とにかく薄っぺらい土地の記憶しかないんです。確かに便利で清潔、みたいなことはあるんですが、うわあ、銀座の泰明小学校の路地の柳を揺らす風、いいなー、とか。その風には、かすかに潮の香りが感じられるなー、とか。人間くさいなー、とか。
小林:よく分かります。街の「喧噪(けんそう)」というものが私は好きなのですが、私が好きなのは「安全な混沌(こんとん)」とか「安心できる混沌」とかいうものではないか、と思うんです。歴史とか伝統とか、街を行く人の息づかいとか、建物の香りとか。それにはもう、時代を経て、雑多なものが入り混じっているわけですよ。

──オシャレで、高級で、品格のあるオトナの街。でも、雑多。まさに銀座ですね。「時代を経て」というあたりがポイントなのでしょうか?
小林:友人の息子さんが進路に悩んでいて、小林、息子に読ませるなんかいい本はないか?とアドバイスを求められたときに「古典を読ませろ」と答えたことがあります。「レ・ミゼラブル」を薦めました。進路に悩むということは、未来に悩んでいるということですよね?でも、そのヒントは遠い昔の、それも海の向こうの国の人がすでに提示してくれている、ということがたくさんあるんです。
──昔を懐かしむといった、単純なノスタルジーではないということですね。
小林:日本に多くの外国人が観光にやって来るというのも、そういうことなんじゃないでしょうか?コロナ禍を経て、安心安全の価値が世界的に高まっていますが、日本はとにかく安心安全ですからね。その上で、なんだこれは?という新鮮な体験や食事を、歴史とともに味わえる。
──食文化が、時代を経た街や暮らしに根付いている、というあたりは、日本が世界に誇るべきものの一つですよね。
小林:芸能人が一般人の食卓にあがりこんで、手料理を前に、家族の歴史やその土地の風土についてあれこれ教えてもらうという長寿番組がありますが、あのような番組が成立するなんてこと、他の国ではそうそうないことですからね。
──あれこれ楽しいお話、ありがとうございました。最後の最後に「くいしん坊」にたどり着くとは、想像もしていませんでした。
小林:そのあたりが「問わず語り」の楽しさ、かもしれませんね。

この記事は参考になりましたか?
著者

小林 伸年
時事通信社
解説委員/日本記者クラブ企画委員
1962年生まれ、東京都出身。86年、早稲田大学卒業、時事通信社入社。静岡総局、横浜総局、本社内政部、シドニー特派員、内政部長、長野支局長を経て、2014年から編集局編集委員兼海外速報部長、17年、解説委員兼官庁部長、19年より現職。


