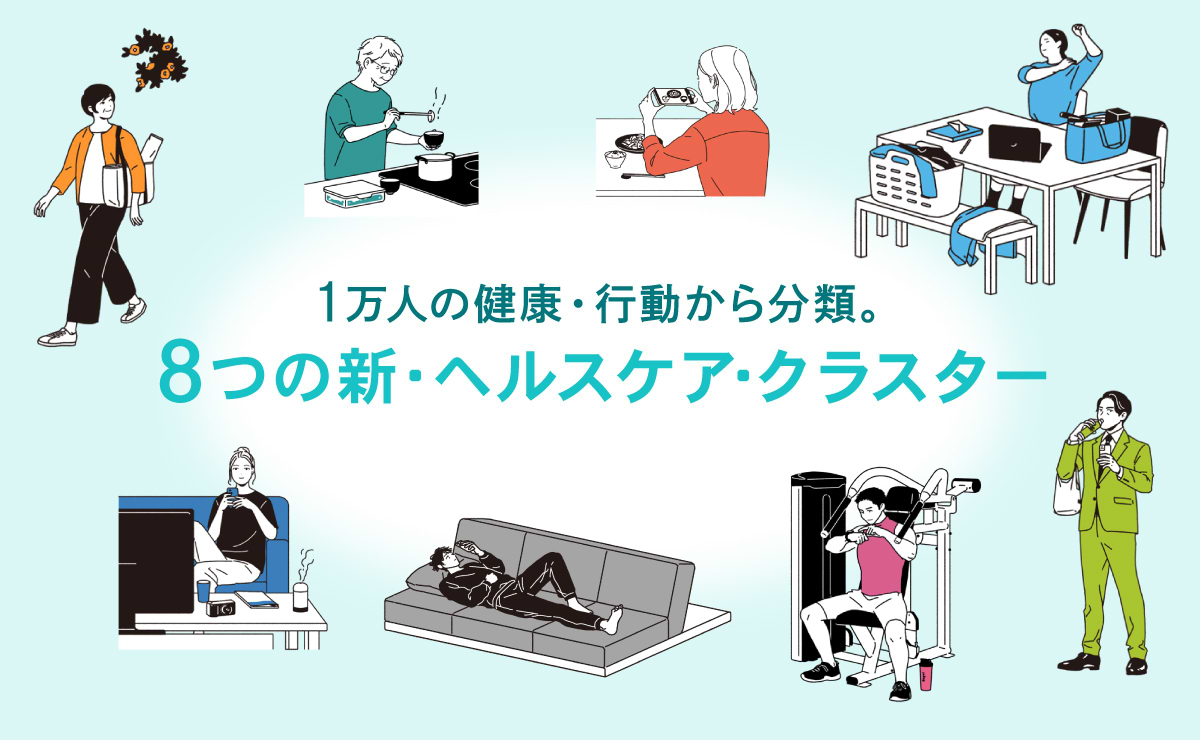電通では、中期的視点でヘルスケア市場において着目するべき50のトレンド(未来)を予測し、新規事業のアイディエーションや商品・サービスに活用できる情報ツール「ヘルスケアトレンド予測50」の提供を開始しました。
このツールでは、一般に起こると予測されるメガトレンドの中で、特にヘルスケア市場で影響が大きいと推察できる5つのトレンドを抽出。それぞれのメガトレンドの影響を受け、ヘルスケア市場ではどのような潮流が起きうるかを予測しています。

本連載では、この50個のヘルスケアトレンドの中から、特に着目したいテーマをピックアップ。その分野における第一人者をゲストスピーカーにお招きし、より深く未来を考察していきます。
第2回で取り上げるテーマは、「産後ウェルネス」の未来予測です。出産後の女性に現れる心身のケアや、育児へのサポートはどのように発展し、ヘルスケア市場に影響を与えていくのでしょうか。日本におけるフェムテック領域の第一人者・中村寛子氏と、電通ヘルスケアチームの姜婉清氏が探ります。
<目次>
▼WHOもガイドラインを策定! 今、産後ウェルネスに注目すべき理由とは?
▼腰や肩の痛み、尿もれ……出産後の女性の半数以上が、産前にはない症状を抱えている!
▼今まで人に言えなかった悩みを、カジュアルかつ専門的に相談できるサービスが増加
▼出産経験者と周囲が一緒にリテラシーを上げて、ワクワクする未来を!
WHOもガイドラインを策定! 今、産後ウェルネスに注目すべき理由とは?
姜:産後ケアとは、心身ともに不安定な状態である産後の女性の心身のケアや慣れない育児のサポートをすること。2022年3月にWHOが産後6週間の女性と新生児を支援するための世界初のガイドライン※を発表しました。
「出産に伴う身体的・精神的な影響は、適切に管理されないと増悪してしまうが、適切な時期に適切なケアを行えば、多くの場合、回復可能である。出産後の最初の数週間は、当面の健康上の懸念に対処するだけでなく、人間関係を築き、長期的な乳幼児の発達と健康に影響を与える行動を確立するために極めて重要」と指摘しています。
※「WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience(出産後のポジティブな経験のための母親と新生児のケアに関するWHOの推奨事項)」
日本においては、2019年に母子保健法の一部が改正され、産後1年以内の母子に対する産後ケア事業が法制化。日本でも今後、理解が深まるとともに、制度や商品・サービスが進化し、専門的で実用的なソリューションを充実させて適切な産後ウェルネスを確立することが求められています。
中村:私自身は出産を経験していないのですが、産後ケアについては、女性でも知らないことが多くあると感じています。一般的に、「健康な子どもを安全に出産することが当たり前」だと考えている人も多くいらっしゃるかなと思いますが、決してそうではないと感じています。
例えば、「産後うつ」は出産後に発症する気分障害の一種で、今では当たり前のように耳にする言葉です。しかし、日本で「産後うつ」という言葉が広く使われるようになったのは比較的最近のことで、1990年代から2000年代にかけて「産後うつ」に対する認識が高まったと言われています。特に2000年代以降、産後うつ対策は母子保健政策の重要な柱の一つとして位置づけられるようになり、社会問題としての認知度が急速に高まったと言われています。
こういった状況は日本だけでなく、きっと海外でも同じ状況にあるため世界中の母子の健康と福祉を改善する具体的な指針をWHOがガイドラインとして発表したのだと思われます。それだけ、産後ウェルネスはまだまだ発展途上の分野だということですが、同時に、この分野は発展させていく意義もあります。
今後、研究の発展はもちろん、社会全体で「産後ウェルネス」「産後ケア」のリテラシーを上げて、思いやりを持ちつつ支え合っていくことが絶対に必要となっていくでしょう。
腰や肩の痛み、尿もれ……出産後の女性の半数以上が、産前にはない症状を抱えている!
姜:では、出産後の女性がどのような症状を抱えているのでしょうか。ここで、興味深いデータを紹介したいと思います。

これは、出産後の女性が経験する身体的な症状を調査したものです。最も多い症状が腰痛で、実に63.6%の方が経験しています。続いて、尿もれが53.2%、肩の痛みが44.4%となっています。しかし一方で、こういった症状がありながら実際に医師の診察を受けた人は、15%にとどまっている現実もあります。
中村:「自分は尿もれがある」と他人に言うのは恥ずかしい気持ちもあり、医者であってもなかなか相談しづらいのかもしれません。前職(フェムテック事業を展開しているfermata)でも、非常に印象的な出来事がありました。
会社が運営するフェムテック専門店にテレビ取材が入ったときに、出産を経験された女性アナウンサーがカメラの前で「出産した後に、尿もれが止まらないんです」「その対処法は、骨盤底筋を鍛えることです」と発言されたんです。
すると放送後、「自分だけの悩みだと思っていた」「私だけではないのだと初めて知った」というお客さまが店舗に続々と来店。出産後の体の変化については、ママ友同士でも相談できない方が本当に多いのだと実感し、こういう情報を発信することは、非常に意義のあることだと改めて思いました。
姜:出産後の身体的・精神的な症状は、生理の話題と同じように、女性同士でも話しづらいところはありますよね。ママは妊娠中や出産までの情報収集や理解に集中していて、出産後に新たな課題に直面し、自分で判断することが難しい場面もあるでしょう。出産を経験した人にしか分からないですし、話すのも恥ずかしい。我慢して当然という思いがあるなど、悩みをオープンにできない理由がさまざまあるように思います。
中村:それらに加えて、出産後、多くのママは子ども優先で「自分のことは二の次」にしがちです。このような傾向は、私の周囲の友人にも見られるため、ママ自身の産後の症状が見過ごされやすい原因にもなっていると思います。
今まで人に言えなかった悩みを、カジュアルかつ専門的に相談できるサービスが増加
姜:それでは、未来に向けて産後ウェルネスは、どのように進化していくのでしょうか。
私の出身国である中国では、産婦の出産後1カ月間を指す「月子(ユエズ)」という言葉があり、産後1カ月は「月子中心(ユエズ・ジョンシン)という産後ケアセンターで養生に努めるのが一般的です。
日本においても、家族も滞在できる宿泊型産後ケアリゾート「HOTEL CAFUNE」が話題になっています。それ以外に、POLAが提供する産後ケアアプリ「mamaniere」のように、産後ママが気軽に相談できるアプリサービスも登場しています。国内外のフェムテック関連の企業やサービスの中で、中村さんはどのようなものに注目していますか。
中村:フェムテック市場はその時々によってトレンドがあり、常にさまざまなプロダクトやサービスが生まれています。さらに、グローバルウェルネスサミット(GWS)が2024年に発表した「今年注目する10のウェルネストレンド」の一つに産後ケアが含まれていました。この発表を裏付けるように、産後ケア関連のプロダクトやサービスはたくさん生まれています。今後もこの傾向は加速していくとみられています。
そんな中、私が常に注視しているのが、「elvie」というイギリスの企業です。エビデンスをもとに製品開発を行っているのが特徴で、スマホと連動して骨盤底筋を鍛えるトレーニングアイテムや、ウェアラブルな自動搾乳機など既成概念にとらわれない革新的な製品が注目を集めています。また積極的に独自のレポートを発表しており、そういった情報も女性のニーズや顕在化されていない課題を知る上で、参考になると思います。
それから、主にイギリス、アメリカ、カナダでサービスを展開しているママ友のマッチングアプリ「Peanut」。産後のみならず、不妊治療、妊娠、母性、更年期障害など、あらゆる女性のライフステージにおいて、さまざまなコミュニティで悩みを相談することが可能です。リアルな友だちには聞きにくいことも気軽に相談でき、何よりもカジュアルに使える。とても有用なアプリです。

さらに、産褥期(出産後の体が元の状態に戻るまでの期間)にフォーカスを当てたコーチングやアドバイスなど包括的なサポートを受けられるのが、「Ovia Health」。サイトに「女性は出産中よりも出産後の12カ月で死亡する可能性が高く、3分の1以上が出産後に生涯にわたる健康上の合併症を経験しています」という衝撃的なメッセージを掲載するなど、産後ケアの重要性も発信しています。
出産経験者と周囲が一緒にリテラシーを上げて、ワクワクする未来を!
姜:では最後に、産後ウェルネスが進化することで、世の中はどう変化していくのかを予測していきたいと思います。
中村:世界的に人口減少が続いている中で、産後ウェルネスを考えることは非常に意義のあることだと思っています。また、これから出産する人たちのことを見据えた未来を、しっかりと考えていくことも重要です。出産を経験された人たちの力を借りて、それらを集約して次代に引き継いでいく。こういった活動も考えていくべきだと感じています。
姜:同感です。まずは、産後ウェルネス事業を行っている企業と産後当事者をつなぐ「新しい仕掛け」があるといいのかもしれませんね。
中村:そうですね。現状、産後ウェルネスに関する情報が圧倒的に足りません。産後の悩みは生理痛と同じく、多くの女性が「当たり前だ」「苦痛だと感じない」と思い込む傾向があります。そのため、なかなか表に出てこず、顕在化しにくいのも大きな課題です。今後はそれらを掘り起こす作業は絶対に必要です。
さらに、単に当事者の健康面を考えるだけでは不十分だといえます。例えば、パートナーや家族がメンタル不調に陥る可能性もありますし、職場では復帰した際の業務的なサポートが必要です。ですから、未来の理想の姿は、当事者も周囲の人も巻き込んで、全員が一緒に産後ウェルネスのリテラシーを上げていくこと。産後ウェルネスが向上した未来を想像して、ワクワクしながら理解を深めていくのがベストだと考えています。
姜:そうですね。産後に関する情報の量や正確さ、情報を得るタイミングなどの課題を解決することが、母親たちの不安を軽減するカギとなります。また、これからの産後ウェルネスにおいては、赤ちゃんのケアだけでなく、母親自身のニーズに応える商品やサービスの重要性が高まっています。さらに、産褥期と呼ばれる短い期間にとどまらず、継続的な産後ケアが必要であることも明らかです。
今後の産後ウェルネスは、当事者も周囲も楽しみながら、リテラシーを上げるための空間、プラットフォーム、商品など、多様なサービスに期待できますね。

この記事は参考になりましたか?
著者

中村 寛子
多くの国内外のビジネスカンファレンス事業の立ち上げ、企画、運営を経験。2019年には日本、アジアにフェムテック市場を創出することを掲げ、fermata株式会社を共同創業(2023年12月退任・退社)。

姜 婉清
株式会社 電通
第6マーケティング局 CXコンサルティング1部
プランナー
中国出身。ソリューションプランナーとして、食品・医薬品・テーマパークを中心に、マーケティング戦略の立案に従事。OSAKA未来プレゼン大賞にて金賞受賞。