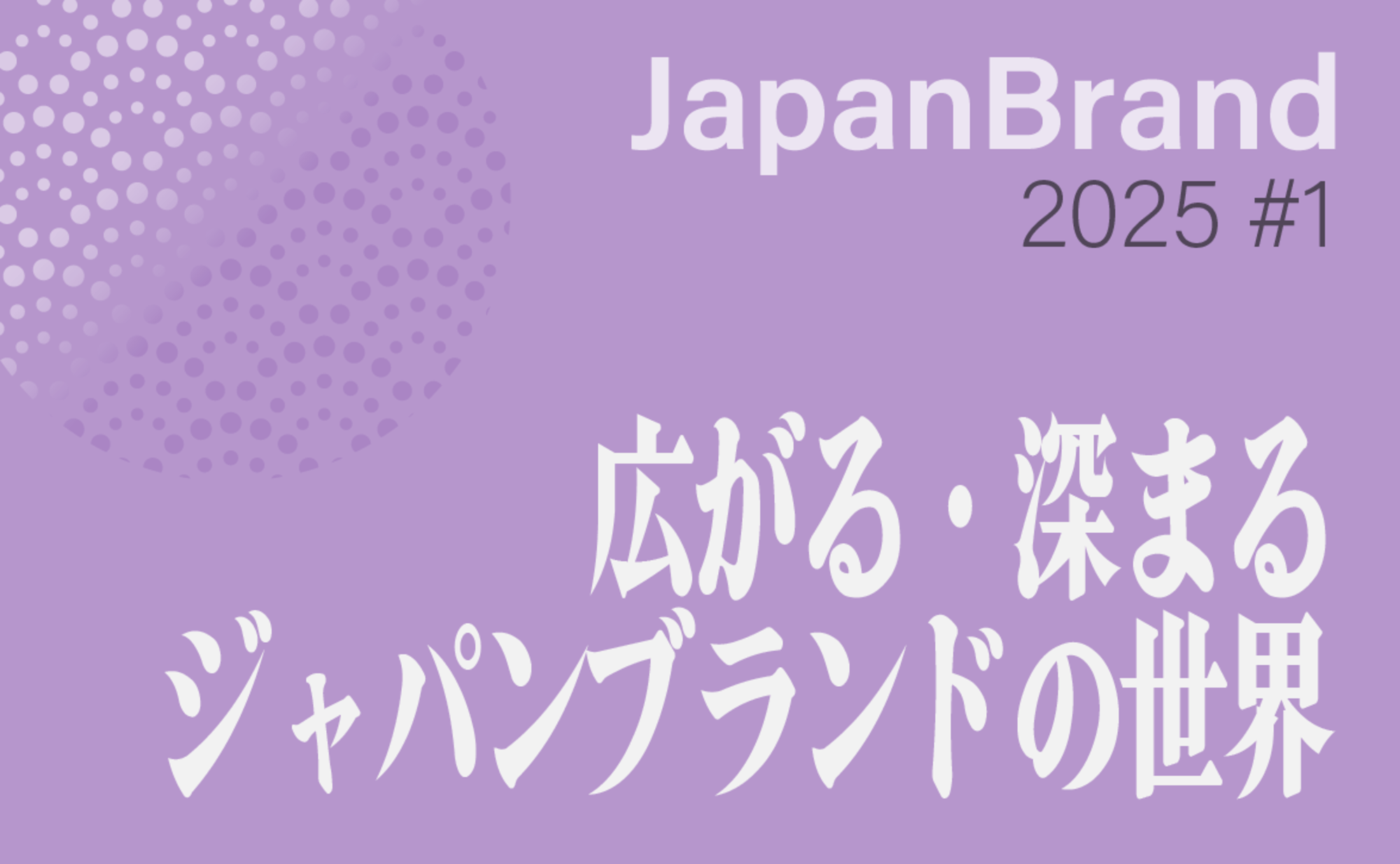広がる・深まるジャパンブランドの世界

ジャパンブランド調査は2011年にスタートし、訪日観光や地方創生、食分野、日本産品、コンテンツ、価値観、ライフスタイル、社会潮流など、ジャパンブランド全般に関する海外生活者の意識と実態を定期的に把握する、電通独自のナレッジ基盤事業です。
調査開始から15周年という節目を迎える2025年は、本調査史上最大規模となる定量調査を実施しました。調査は、20の国・地域(調査概要)、20を超える産業分野、10を超えるテーマを網羅し、これまで以上に多角的かつ実践的なインサイトの獲得が可能です。
先が読めず、予測困難な状況が常態化した現代において、本調査が未来に向けて歩みを進めるためのヒントや、認知バイアスにとらわれないための相対化視点を継続的に提供し、微力ながら持続可能な社会づくりに貢献できることを願っています。
<目次>
▼国際観光における日本の競争力
▼訪日体験と消費傾向
▼地方創生における観光の論点
▼持続可能な未来に向けて
国際観光における日本の競争力
世界の海外旅行経験者から、観光目的で再び訪れたい国として日本が最も多く挙げられ、その割合は半数を超えました。2位の韓国や3位の米国とは大きな差をつけており、日本が他国と比較して突出した人気を誇っていることが見てとれます。(図表01)

さらに国・地域別で見ると、20の調査対象のうち、13の国・地域で日本が再訪希望先として首位を獲得しており、その差は市場ごとに異なるものの、いずれも2位以下を大きく引き離す結果となりました。これは、アジアパシフィックにおいて、日本が広範囲にわたり有力な旅行先候補として定着していることを示しています。(図表02)

外国人観光客の増加が続く中、観光目的による再訪意向も年々着実に上昇しています。たしかに、歴史的な円安が訪日旅行のハードルを下げ、裾野を広げた面は否定できません。しかし、本研究の結果からは、香港と台湾を除き、円安が訪日の主な動機となっているわけではないことが明らかになりました。
多くの旅行者にとって日本を訪れる理由は、為替の有利さ以上に、体験価値や文化的魅力といった本質的な要素に根ざしていると考えられます。このような傾向は、日本への観光が一過性のブームではなく、大きな魅力として持続的に受け入れられていることを裏付けるものと見ています。
訪日体験の満足度が蓄積されることで、自然と再訪意向が高まっていると考えられる一方で、国内の人手不足が顕在化している中、今後の課題は「訪日観光の満足度をいかに保つか」にあります。(図表03)

また、日本とその他の海外旅行先を比較した際、旅行者が求める基本的な要素には大きな差は見られませんでした。多くの人が「自然景観」「食文化」「伝統文化」などを旅の主目的とする一方で、「安全性・安心感」「癒し・リラックス」「異国情緒」「清潔感」といった環境面の充実も重視されているようです。
これは、全般的にコト消費への関心が高まっていることを示すと同時に、観光体験が単なる観光資源の消費にとどまらず、心身の回復や非日常性の享受といった多面的な価値を求める行動であること、そして、旅の本質を見失ってはならないことを示唆しています。(図表04)

国・地域別に見ると、期待値の傾向には若干の差異が見られます。オーストラリアの旅行者は「独自の食文化」や「癒し・リラックス」に強く引かれ、イギリスでは「独自の伝統文化」や「清潔感」への期待が高く評価されました。一方で、アメリカでは特定項目に対する著しい偏りはない様子がうかがえます。(図表05)

8兆円規模にまで成長を遂げたインバウンド市場は、すでに国内アパレル産業と肩を並べ、自動車輸出額の約半分(※1)に匹敵する外需けん引力を持ちます。インバウンドが持つ意味合いを観光という枠組みだけでは決して捉えきれません。世界を見渡すと、訪問者数や外貨獲得額の上位国はほぼすべてが強固なソフトパワーを基盤とし、国境や言語といった物理的制約を超えて生活者を引きつける本源的な魅力を有しています。
観光依存に対する懸念や不安の声が時折聞かれますが、日本におけるインバウンド消費のGDPへの寄与は、2024年時点で約1%にとどまっており、G7諸国やOECD加盟国と比較しても依然として低水準にあります。オーバーツーリズムへの対応は必要ですが、過度な観光依存を危惧する議論とは切り離し、現実的な産業波及力や経済貢献のポテンシャルを踏まえた上で、冷静に論点を整理し、理解促進を図る必要があります。
われわれが注目している再訪意向はインバウンドの定量的評価指標としての機能にとどまらず、「再び訪れたい」という人間の根源的欲求をシンプルかつ明瞭に可視化する感度の高い指標として位置づけられます。そして、再訪の気持ちを喚起する「国際観光における持続的競争力」の強さは観光資源のみならず、日本食文化への関心や日本製品に対する信頼感といった、より広範囲にわたる文化的・社会的要素によって支えられていることが本研究で改めて確認できました。
※1 出典:財務省「貿易統計」(2024)
訪日体験と消費傾向
訪日旅行において関心が高い体験としては、日本文化の象徴ともいえる「和食」や「自然景勝地」、さらには「四季の体験」や「繁華街の街歩き」、「伝統文化の体験」などが挙げられます。なかでも「コンビニでの買い物」は一見日常的な行為ながら高い関心を集めており、特にアジア圏での支持の高さが目立ちます。
これらの結果から、訪日体験の魅力は非日常性に限らず、磨かれた日本の日常文化もしくは生活インフラそのものにも強い訴求力があることがうかがえます。当然ながら、体験に対する志向は文化圏ごとに異なる傾向も見られ、インバウンドマーケットの拡大および近隣地域からのリピーターの増加に伴い、今後の事業拡張や商品・サービス開発、マーケティング施策立案においてはターゲット地域別の対応を考慮する必要があります。(図表06)

ここから訪日体験をさらに細分化してみます。
自然体験の中では「桜の花見」が群を抜いて人気であり、日本観光を象徴する体験として確固たる地位を築いています。他にも「温泉入浴」や「自然散策」「紅葉狩り」など、日本の自然資源の多様性と魅力が幅広く認知されていることが分かります。(図表07)

文化体験においては、「季節ごとの伝統行事」や「茶道」「祭りの見物」といった日本特有の行事や精神文化への関心が高い傾向にあります。海外生活者にとってシンボリックな日本として比較的理解しやすく、かつ非日常的な価値を感じやすい領域が上位を占めました。(図表08)

さらに、「日本らしさ」の象徴に関する問いでは、「寿司」や「桜」「富士山」が代表的な存在として挙げられました。これらのイメージは、日本への訪問動機や訪問先の選定、来日時期の選好など、旅全体の設計に影響を与えていると考えられます。ただし、こうした象徴も一様ではなく、例えばベトナムでは「茶道」「うどん」「自動車」、フランスでは「柔道」「盆栽」「醤油」といった要素が日本らしさとして挙げられます。市場ごとに異なる文化的受容のあり方は、訪日観光にとどまらず、日本発の製品やサービスの海外輸出においても重要な示唆を与えています。(図表09)

世代間での違いも注目されます。Z世代では「マンガ・アニメ」への関心が、「富士山」や「寿司」を上回る場面も見受けられました。また、訪日経験が増すにつれて、「紅葉」「温泉」「祭り」など、日本文化に対する感度が高まる一方で、「桜」に対する関心は相対的に減少傾向を示しています。このことは、体験の深化と興味関心の進化が連動していることを示唆します。(図表10)

商業施設における購買意向については、コンビニが比較的高い選択率を示し、「寿司」や「アイスクリーム」「おにぎり・スイーツ」など、外国人に馴染みのある日本の軽食文化が注目されています。ドラッグストアでは「スキンケア」や「メイクアップ」、「ボディケア・サプリメント」といった商品カテゴリに関心が集まりました。また、選択率と個数選択といった指標から、アジア市場での消費意欲が顕著であり、消費行動の活発さとポテンシャルがうかがえます。(図表11、12)


お土産の購入意向については、「和菓子」や「工芸品」など、伝統と現代の融合を感じさせるアイテムが人気を集めています。国・地域によっては、「日本ブランドの衣料品」「お茶(日本茶、抹茶)」「化粧品」などに対する嗜好(しこう)の違いも明確に表れており、商品訴求においては国別のマーケティング戦略という基礎中の基礎が求められます。(図表13)
地方創生における観光の論点
一方で、マタイ効果(※2)が働き、「強さゆえの集中」という構造的な課題がもたらされています。地方部の認知度格差、訪問時期の偏在、日本らしさに対する理解の偏り、商業施設の認知・訪問意向の地域間格差など、複数の側面からこの課題の多面性が明らかになりました。
※2 累積的優位性。優れた人物や組織への好意的な評価が、さらなる成功につながりやすくなる現象。
訪日旅行者における都道府県単位の認知度や訪問経験、今後の訪問意向を総合的に見ると、「東京都」が他を圧倒して高く、次いで北海道、大阪府、京都府といった広く知られた観光地が続いています。特筆すべきは、過去10年にわたってこの上位層に大きな変動が見られない点であり、都道府県レベルでのブランド力が、ある程度固定化されている現状が示唆されます。(図表14)

より詳細に都市単位で分析すると、札幌市、大阪市、京都市の3都市が突出した認知度を有しており、他の政令指定都市や中核市とは一線を画しています。その他の都市でも一定の認知はあるものの、訪問経験においては上位とは明確な差が開いており、同一グループにおいては大差が見られません。単なる認知だけでは訪問には直結しない一方で、そもそも認知されていなければ訪問の選択肢にすら入らないという、認知と行動の間にあるジレンマが浮き彫りになっています。(図表15)

いわゆる「ゴールデンルート」とされる大都市(東京・名古屋・大阪・京都)以外の地方部を単独で訪問した旅行者の割合は、依然として低水準にとどまっています。また、その割合には国・地域間で顕著なばらつきが見られます。
一方で、地方を訪問した旅行者の満足度は非常に高く、9割を超える人が再訪を希望するなど、体験価値の高さが際立っています。これは、地方観光のポテンシャルが依然として高いことを示す好例と言えるでしょう。(図表16)

地方観光の象徴的資源である温泉地については、国・地域ごとの認知度に大きな差が存在します。
特に英語圏や欧米文化圏においては、提示された温泉地のいずれも認知していない回答者の割合が高く、カナダでは約75%が該当しました。オーストラリアやスペインでも、半数前後が知らないという結果となっており、情報の浸透に課題があると推察されます。(図表17)

地方部を実際に訪問した旅行者からは、通信環境やWi-Fiの整備状況、多言語対応の不足、アクセスの利便性といった課題が多方面から挙げられました。加えて、国や地域によって感じる課題の内容には明確な違いがあります。(図表18)

地方を訪れる総量(外国人延べ宿泊者数ベース)には限り(全体の約3割)と偏り(東アジアが約5割を占める※3)がある中で、地方観光の商機を広げるには戦略的な市場選択が必要です。文化的受容力や訪日成熟度を相対比較した上で、中長期的に育成すべき市場と短期的に地域経済へ寄与する市場を的確に見極め、着地消費の拡大に向けた施策を含め、能動的にビジョンを策定・実行する胆力と行動力が求められます。
※3 出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」(2024)
持続可能な未来に向けて
本研究では、経済的価値と社会的価値の両立を目指し、持続可能な未来に向けた価値創造は集合知によってこそ実現できると考えています。今年度は「オーバーツーリズム」「リユースバリュー」「ウェルビーイング」という三つの重要な要素を軸に、海外生活者のインサイトを多面的に可視化しました。
これらはいずれも短兵急に結論の出せる単純なテーマではありません。レポート作成における制約がある中、調査主体として生活者データに焦点をあてた知見の一部を紹介し、社会生活の基盤を共に支えるさまざまな業界や立場のみなさまの思考や行動のヒントとしてお役に立てればと願っています。
検討要素1:オーバーツーリズム
観光需要の集中を回避し、持続可能な訪日観光を実現するためには、旅行時期および訪問地域の分散が欠かせません。しかし現状では、訪日希望時期が「桜の季節」に大きく偏っており、その理由として多くの旅行者が「その季節ならではの景色を楽しみたい」と回答しています。これは日本の四季がもつ象徴的な魅力の高さを物語っていますが、同時にオーバーツーリズムの課題にもつながっています。(図表19)

一方で、桜シーズンに次ぐ訪日時期については、国・地域によって関心が分散する傾向がみられます。特に訪日経験が豊富な層、いわゆる“日本ファン層”にとっては、「紅葉シーズン」が次なる需要の核となる可能性があります。また、アメリカ市場においては「夏休みシーズン」の訪日意向が相対的に高く、中国市場とは異なる需要パターンが見て取れます。(図表20)

こうした訪日観光における需要集中(局所集中・時期集中)は日本固有の問題ではなく、世界的な観光先進国の共通課題としていまだ解決の途上にあるというのが一般的な認識です。(図表21)

需要の平準化を考えるにあたって、筆者は虫・魚・鳥の3つの目が不可欠と考えます。
- 「虫の目」による観察整理:生活者の深層心理の解読、既存アセットの棚卸し、課題の抽出といった現状認識の精緻化。
- 「魚の目」による相互理解:他国や先進事例の研究、地域住民とのすり合わせを重ねた未来像の協創。
- 「鳥の目」による指南支援:課題の早期発見と建設的解決策を支える行政のモニタリングおよび戦略的政策立案。
さらに、経済的合理性の追求だけでは限界があることを認識し、社会学や心理学的アプローチとの掛け算もさまざまな局面において求められることになるでしょう。
検討要素2:リユースバリュー
サーキュラーエコノミー(循環型経済)の観点から、中古品の再利用は重要な要素の一つです。本調査では、日本の中古品に対する関心が全体として非常に高く、国・地域を問わず注目されていることが分かりました。
特に、日本製品の「使用状態の良さ」や「高い耐久性」は生活者に強く評価されており、こうした特徴が日本独自の信頼性や価値観に裏打ちされた商品競争力につながっています。このような評価は、循環型産業の創出拡大や、模倣困難な差別化戦略の基盤ともなり得ます。(図表22)

日本の中古品市場には、元来日本製品が持つ高品質や耐久性といった商品価値が強く反映されています。新品に比べて手頃な価格で信頼性の高い日本製品を入手できる点は、世界的に注目される大きな利点です。さらに、東南アジア諸国を中心に、着物・骨董品・伝統工芸品といった文化財的価値や、原宿系・ストリート系などの独自のファッションスタイル、ヴィンテージ衣料品のファッション性、さらにはアニメ・漫画・ゲーム関連グッズといったポップカルチャーに至るまで、日本ならではの文化的要素が中古品への関心を高める契機となっています。
このように中古品のリユースバリューを考えるとき、商品価値が市場の幹を成すことは論をまちません。しかし、中長期的に顧客基盤を拡張していくためには、商品価値に加えて次のような広がりを戦略的に捉えることが不可欠です。
- 体験価値:日本文化を融合したユーザー体験の提供、コラボレーションやアップサイクルを通じた新たな意味づけの創出。
- 社会的価値:サステナビリティの視点による価値転換や、循環経済に関する教育・啓発活動を通じた社会的共感の獲得。
ここには、「環境配慮に基づく再利用」という守りの戦略と、「ブランド価値や事業価値を一段高めるための文化的・市場的展開」という攻めの戦略の両面があります。両者を組み合わせることで、日本発の中古品市場は単なる「モノの取引の場」を超え、「文化・社会・経済を結ぶ持続的なエコシステム」へと進化していくと考えられます。
検討要素3:ウェルビーイング
日常生活において重視されている価値観としては、「ワークライフバランスの確保」「希望する生活水準の維持」「快適かつストレスの少ない住環境」といった生活の質を重視する姿勢が顕著に見られました。
これらの項目は、特にZ世代において高く評価される傾向にあり、若年層の価値観に変化が生じていることがうかがえます。(図表23)

また、社会的関心のあるテーマとしては、「生成AIの利活用」「再生可能エネルギー」「ヘルステック」「メンタルヘルス」など、テクノロジーや健康、持続可能性に関する話題が上位に挙げられました。なかでもZ世代の女性は「メンタルヘルス」への関心が特に高く、世代や性別によって関心領域に違いがある点も注目に値します。(図表24)

地政学的変動やテクノロジーの指数関数的進化といった急激な環境変化に揺さぶられる世界情勢が、生活者の意識構造に色濃く影響を与えていることが本調査の随所に現れています。日常的な情報獲得ツールとしての生成AIの活用はすでに不可逆的な潮流となり、ウェルビーイングを構成する諸要素の中でも、特にキャリア意識、経済的安定性、生活環境の質、そして精神的充足が重視されている傾向が明らかとなったのです。
往々にして予測が当たらない中、ブラジルの蝶の羽ばたきがジャパンブランドの未来にどのような波紋を広げるのか、その手かがりとなるものを生活者のインサイトを起点に継続的に探索していきます。
データビジュアライゼーション・チャート・ビジュアル:リ シュンシ
電通公式データ・ナレッジ:ジャパンブランド調査ハブページ

WEB電通報特別コンテンツ:ジャパンブランドウイークリーチャート
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社電通 ジャパンブランドプロジェクトチーム
japanbrand@dentsu.co.jp
【電通ジャパンブランド調査 実施目的】
2011年、東日本大震災で日本の農水産物や訪日旅行に風評被害が発生した際に、ジャパンブランドが世界でどのように評価されたかを把握するために始まった電通の独自調査。2022年、調査設計・分析アプローチおよびアウトプットを抜本的再構築し、専門性を高める全社横断プロジェクト活動へと進化。2025年、一般向けナレッジポートフォリオを新たに企画・構築し、生活者インサイトに立脚した社会的価値の創出を目指す。
ジャパンブランド調査では、訪日観光や地方創生、食分野、日本産品、コンテンツ、価値観、ライフスタイル、社会潮流などジャパンブランド全般に関する海外生活者の意識と実態を定期的に把握。変わりゆく生活者の気持ちとジャパンブランドの課題・可能性を可視化し、複雑化が進む企業活動に寄与するとともに、日本社会における異文化理解の促進にも貢献する。
【電通ジャパンブランド調査2025 調査概要】
・対象エリア:20カ国・地域※1(アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、サウジアラビア、インド、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、中国本土、香港、台湾、韓国)
・対象者条件:20~59歳の男女(中間所得層以上)※2
・サンプル数:12,400(内訳:アメリカ・中国本土 各1,600、インド1,200、韓国・台湾・イギリス 各800、その他の国・地域 各400)※3
・調査手法:インターネット調査
・調査期間:2025年5月20日~6月22日
・調査機関:株式会社電通(調査主体)、株式会社ビデオリサーチ(実施協力)
【注記・免責事項】
※1:中国本土の対象エリアは上海・蘇州・北京・天津・広州・深セン・成都・重慶、インドの対象エリアはデリー・ムンバイ・ベンガルール、オーストラリアはシドニー都市圏、東南アジアは主にメトロポリタンエリアに限定。
※2:中間所得層の定義:OECD統計などによる各国平均所得額、および社会階層区分(SEC)をもとに各国ごとに条件を設定。
※3:各国・地域とも性年代別に均等割付で標本収集し、人口構成比に合わせてウエイトバック集計を実施。
※4:本調査における構成比は小数点以下第2位(一部整数表示の場合は小数点以下第1位)を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。
※5:本調査レポートおよびウェブサイトからの情報発信における対象国・地域の名称表記は、従来からの日本政府の見解、日本の社会通念やビジネス慣習に沿ったものです。
※6:本調査の図表作成において、分析対象となる国・地域名は一部例外を除き、国際基準ISOカントリーコード(ISO 3166-1 alpha-2)を使用しています。
アメリカ/US、カナダ/CA、オーストラリア/AU、イギリス/UK、ドイツ/DE、フランス/FR、イタリア/IT、スペイン/ES、サウジアラビア/SA、インド/IN、インドネシア/ID、シンガポール/SG、マレーシア/MY、フィリピン/PH、タイ/TH、ベトナム/VN、中国本土/CN、香港/HK、台湾/TW、韓国/KR
※7:本調査における国・地域の名称表記は、統計上または分析上の便宜を目的としており、いかなる政治的立場や見解を示すものではありません。
※8:本調査で使用した地図(世界地図および日本地図)は分析内容やページのレイアウトに合わせて一部加工・トリミングを行っており、必ずしも国境線および国土範囲を正確に反映したものとは限りません。
この記事は参考になりましたか?
著者

リ シュンシ
株式会社 電通
第1ビジネス・トランスフォーメーション局
プランナー、プロデューサー
「万物流転」と「塞翁が馬」をモットーに、マーケティング、リサーチ、メディア、グローバル、プロジェクトマネジメントなど専門性を越境させながら幅広い案件に従事。