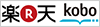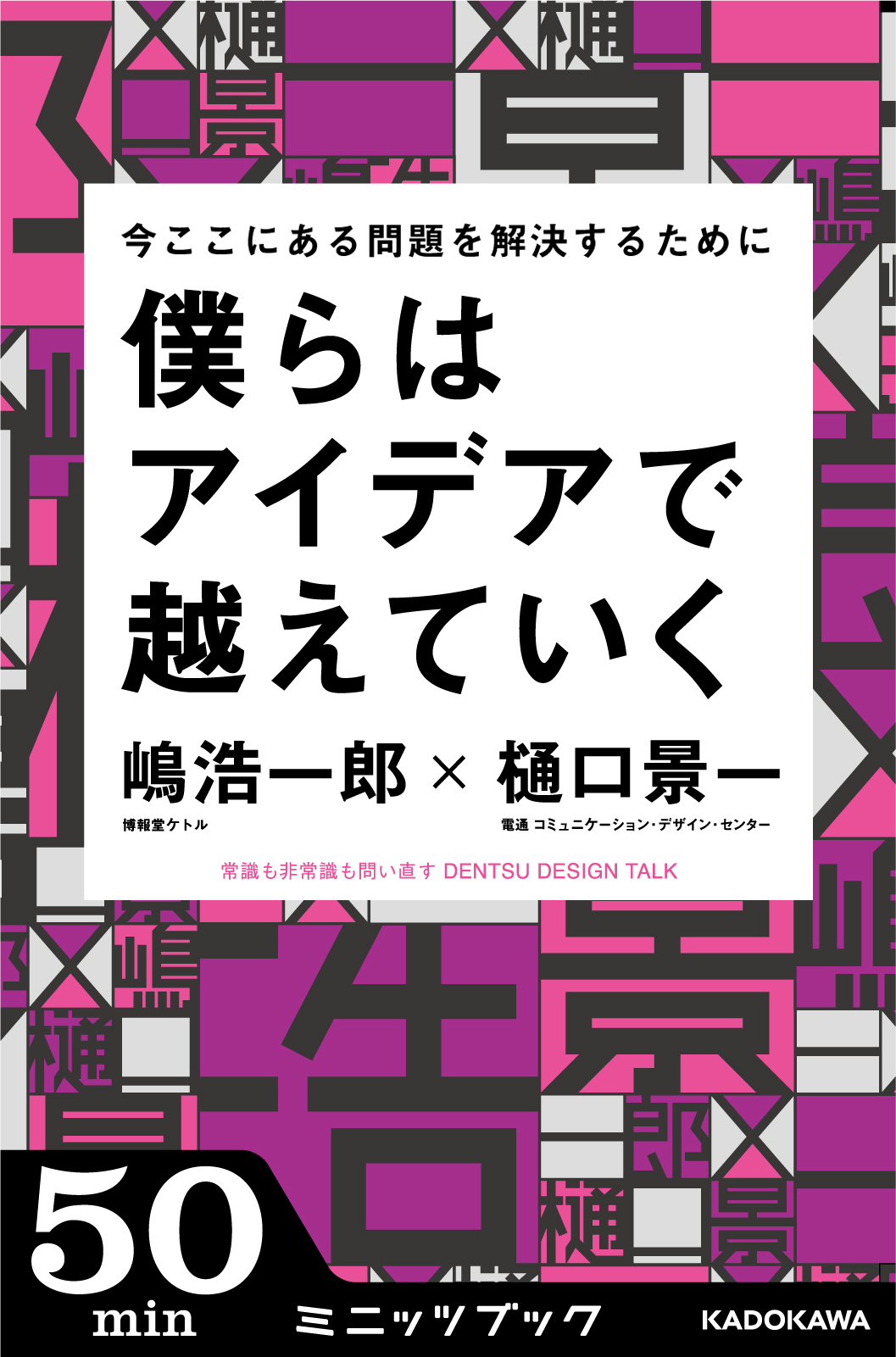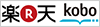株式会社ブックウォーカーの電子書籍レーベル【カドカワ・ミニッツブック】から「DENTSU DESIGN TALK」シリーズの第四弾、『今ここにある問題を解決するために 僕らはアイデアで越えていく』が好評配信中です。「本屋大賞」を設立した博報堂ケトルの嶋浩一郎氏と、地域や国家ブランディングまで携わる電通・コミュニケーション・デザイン・センターの樋口景一氏が「越える力」をテーマに語り合った本作の中身を、少しご紹介致します。
「越える力」について話そう
樋口:今日は嶋さんと「越える力」について一緒にお話し出来たらと思っています。前提として、広告と非広告の境界線とはどんなものなのか、もっと言えば「マス/非マス」といったところにある様々な境界線に本当に意味があるのかという問題があると思います。そして、その境界線があるとしたらいったいどこにあるのかということですね。
僕はそういった境界線を軽やかに「越える」仕事をしていきたいですし、嶋さんの仕事への姿勢や、生き方にも共鳴する部分がたくさんあります。おそらく「越える力」にもいくつかあるはずで、お互いにどんな力を使っているのかという話をしたいと思っています。その前に、嶋さんのケトルという会社について少しお話しいただけますか。
嶋:ケトルという社名は英語で「やかん」でしょ。超ベタですが、“世の中沸かす”とか“アイデアが沸く”といった意味ですね。博報堂ってコンセプチュアルな名前の子会社が多いんですが、一番アホな名前で僕は気に入っています。
2006年4月3日に会社を設立した当初のメンバーは5名。今は社員数25人に拡大しました。クライアントの数は30社ほどでしょうか。僕と共同CEOの木村健太郎は博報堂出身で、木村は1992年にマーケティング局に初任配属され、自分は93年にコーポレート・コミュニケーション局、つまりPRをする部署に配属されました。20代のころはお互い直接仕事をしたことはなかったのですが、30代になってプレゼンでチームを組むことが多くなりました。当時、クリエーティブの人間が一人もいないチームはまだ珍しかったわけです。なのでCチーム扱いでよくプレゼンに参加したんですけど、競合プレゼンとかに強かったわけですね、僕らは。それを見た当時の博報堂の役員の安藤輝彦さんが「嶋は木村と一緒に会社をつくれ」と。
博報堂自体も既存の広告ビジネス以外の収益拡大を狙っていたっていう背景もあったと思います。「とりあえず、こいつらを野に放って実験してみよう」ということでモルモット的に別会社を作ったわけです。それまでは、博報堂の営業がコミッションを取ってビジネスをしてきたわけですが、その日から僕らは自分のアイデアをフィーで売らなければならなくなった。最初はホントにドナドナ状態だったわけですよ。いきなり、市場で値段をつけられる訳ですからね。今はそのフィービジネスがケトルのビジネスの基本になっていますが。
樋口:ケトルでは広告だけでなく雑誌も作ったりしていますよね。
嶋:はい、『ケトル』というカルチャー誌を太田出版から発行していて、僕が編集長をやっています。02年に博報堂刊の『広告』の編集長をして以来、ポプラ社から刊行された食材誌『「旬」がまるごと』など雑誌媒体の編集・発行にはずっと関わっています。
ケトルのアウトプットは、はたから見ると節操がないと思いますよ。CMもつくるし、イベントも制作するし、デジタルもやる。僕らはクライアントの課題に対して最もいいアウトプットをつくろうと思うので、必然的にアウトプットはバラバラになる。
また、ケトルのアウトプットは多岐にわたりますが、その中でも得意技はいくつかあると思います。一つは僕がPR出身ということもあるけれど、戦略PRをベースにしたキャンペーン構築ですね。統合キャンペーンを実施するエージェンシーは多いですが、高度な広報テクノロジーを融合できるのはケトルの強みだと思っています。それからクライアントさん同士のコラボレーションの場を作るものも得意です。たとえば、少年サンデーと少年マガジンの50周年プロジェクトを合同で実施するなど、両社がウィンウィンになる場をプロデュースする仕事は多いですね。
あと、ソーシャルなキャンペーンも得意かな。自分がお手伝いさせてもらっている「本屋大賞」もそうだし、木村は震災で失われた写真などの思い出を回復させる、プラットフォームを作る仕事をIT企業と共に手がけています。
それからコンテンツの開発も得意技のひとつです。雑誌の発行や本屋の運営もケトルのビジネスととらえていて、一つ一つ収益をチェックし、それぞれビジネスとして成立していますよ。
書店員さんたちの不満から生まれた「本屋大賞」
樋口:そもそも本屋大賞は、どういう経緯ではじまったんですか?
嶋:本屋大賞は書店員有志のメンバーでつくるNPO本屋大賞実行委員会が運営していて、僕もNPOの理事の一人として賞の運営を手伝っています。僕は授賞式の運営やPR。また、フリーペーパーを編集・配布する活動を中心に行っています。フリーペーパー『LOVE書店!』は本屋大賞実行委員会の活動を伝えると同時に、広告を集め、活動資金をファンドレイジングする役目も担っています。
本屋大賞は2004年から始まるのですが、それ以前も僕は出版社の得意先が多く、出版不況に関して問題意識を持っていました。2003年から05年の3年間、博報堂が出版する雑誌『広告』の編集長をやっていました。そのころ『広告』のポスターを持って都内の書店をまわることも多かったのですが、その中で感じていたのは書店の店員さんたちも出版不況に関して問題意識を持っていたこと。でも、一書店員の力ではどうにもならない状況。そして、自分の売りたい本がなかなか売れない状況。
自分も本屋を経営してよくわかるのですが、再販価格と委託販売の問題は大きい。本屋さんは自分で売価も仕入れ値もコントロール出来ない。今週は『BRUTUS』がすごく売れるから値上げしよう、なんてもちろん出来ないわけです。一方で、再販価格があるおかげで実際は輸送費がかかる離島でも本が安く買えるというメリットもあるんですけどね。
また、一般論として、委託販売のために卸である取次や出版社はベストセラー以外の本を積極的に配本したがらない傾向がある。なぜなら本屋に本を届けたとしても、売れなかったら再び回収しなければならないからです。そのコストを怖れ、売れ筋だけが配本されることになる。青森の書店が地元の高校生に太宰治全集を読ませたいと思って配本を依頼しても、断られるケースもある。つまり、本屋さんが自分の売りたい本をなかなか仕入れられない状況になっているのです。まあ、そんな本屋は楽しくないですよね。それがなんとかならないかなあという問題意識は前からありました。
90年代から書評誌の『本の雑誌』のホームページ制作も手伝ってきました。そのホームページのコンテンツに書店員に登場してもらうコーナーも作りました。その書店員たちも同じような問題意識を持っていました。そんな有志の書店員と「本の雑誌」編集部が直木賞にかわる賞をつくろうと動き出したんです。
「直木賞、自分だったらそれ選ばないのに」って言う書店員が結構いたんですよね。で、じゃあどんな本が面白いと思うの?って聞いてみると自分の知らない面白い小説がいろいろ出てくる。書店員たちが投票で賞を決めれば面白い本が選ばれるはずだと始まったのが本屋大賞ですね。
この話は企画という作業の本質を含んでますね。企画って誰かのインサイト、つまり欲望を捉えないとワークしない。でも、人って不器用だから、こうしたいとか、ああしたいとか具体的な欲望をなかなか言えないんですよね。でも、文句は言える。文句って欲望の裏返しですよね。「直木賞、なんでこの作品を選ぶんだ」って文句は「自分はもっと売りたい本がある」って欲望の裏返しですからね。だから本屋大賞は10年たった今でもワークしていると思うんですよ。ターゲットのインサイトをしっかり突いたから。
人の欲望は文句として発露することが多い。だから僕は違う場所で同じ文句を3回聞いたら世の中に結構そういう欲望が潜在的に存在するんじゃないかと考えるようにしている。そういうわけで、おかしな趣味ですが文句言っている人を見るのも好き。スーパーのレジや、駅で駅員に文句言っている人がよくいるけど、なんの文句言っているのかすぐ聞きにいってしまう。
樋口:運営母体は最初からNPOとして考えていたんですか?
嶋:最初は収益構造が精緻に考えられていたとは言いがたいです。まずは出版不況に風穴をあけるというプロジェクトの成果が大前提だった。2年目くらいに、本屋大賞の世の中の評価を獲得することが出来、自走出来るようにNPO化を考えたんです。NPOを設立して、ファンドレイジングのためにフリーペーパー『LOVE書店!』を制作し広告収入を獲得しはじめた。NPO法人にしたのは、法人格がないと寄付などを受けられないし、さまざまな活動も制約を受けるからです。
目的達成のために有効な「肩書き」を持てばいい
樋口:僕から見ると、嶋さんは仕事に対して「編集」という観点で捉えられている、根っからの編集者だと思います。だからまずは広告から発展したビジネスとしての「編集力」をテーマにしましょう。境界線を「越える」ということにおいて、編集力は不可欠ですから。さっきの編集長フィーはどんな感じなのですか?
嶋:雑誌『ケトル』の発行に関して言えば、僕は太田出版から編集長のフィーをもらって仕事をしています。そのかわり、広告や売り上げの数字に対して目標数値が設定されています。もちろん、収益性の高い仕事ではありません。カルチャー誌が次々と休刊し、雑誌ビジネスはなかなか難しいと言われています。でも、工夫すれば雑誌を出す方法は考えられるわけです。出版社が出す雑誌とは違うオールタナティブな作り方を提示したいんです。
雑誌って一号編集することで100人以上の作家・アーティスト・文化人・写真家と関わることになる。広告マンとしての付き合いではなく、編集者として彼らと付き合えて関係が作れるのはとてもいい。
樋口:もちろんこれは編集コンテンツをやっているんだと思うのですが、僕としては、文化人ネットワークの装置を持っているということをメインにしていると感じたんですよね。
嶋:そんな、人をあざとく見ちゃ駄目ですよ(笑)。
樋口:本屋大賞にしてもそうなんだけれど、嶋さんは、編集長だからこそ出来る関係性やネットワークを構築出来ていますよね。『広告』の時から僕はそれをすごく思っていて、『ケトル』に関しても、相変わらずその状況を作っている。もしくはオーナーである下北沢の書店B&Bのイベントでも引き続きやっているということでしょう?
嶋:そういう側面も確かにあります。自分でコンテンツをつくって載っけられるメディアを持っていると強いですよね。クライアントさんがカルチャー系のイベントをやろうとすると、ケトルはブッキングとかで普通のキャスティング会社より強いわけですから。カルチャーサイドの人にとっても自分たちのことを理解する人に仕事をコーディネートしてもらえるのは助かる。より関係性が深められる有機的でいい状況だと思っています。
樋口:広告会社の人間としての声掛けになると、費用の桁が一つ変わるという現象があるじゃないですか。
昔、僕もIDÉEの方々と組んで仕事をしていて、イベントとか広告作ったりする時に建築家やデザイナーさんたちとのネットワークを作る母体として活動していたわけなのですが、最初に彼らは僕のことを電通の人間だと知らなくて、「電通の人だったんだ」と知ったとたんに、何ていうか距離が生まれるというか(苦笑)。なので、普通に文化人とのネットワークを広告会社という枠を越えながら作っておくということは意味のあることだと思うんですよね。
嶋:そういうことはあるんですよね。僕のスタイルは多分入社したときPRパーソンだったことが影響していると思うんですよ。たとえば雑誌の編集部に一広告会社の人が「こんな情報があるんですよ」とか「面白いと思うので載せてくれませんか?」と売り込みに行くともちろん話を聞いてはもらえるけど引かれる。そういう距離感ありますよね。広告会社の名前を名乗るとろくなことにならないと思って、一ライターとしていろんな編集部を訪ねた。だから自分が持ち込みたいネタ以外の企画もどんどん出さなきゃいけない。でも、この人は面白いネタを出せる人だと気づかれると話もどんどん聞いてくれる。90年代に多くの雑誌の編集会議に普通に出席していました。後から自分のことを博報堂の人だって知る人も多かったと思います。
樋口:僕も最初に嶋さんのことを知ったのは、それこそ東京デザイナーズブロックの何かの会議の時だったと思うんだよね。「確か広告会社に一応所属しているけど、嶋っていう面白い人間がいるんだよ」って聞いたことがあって。
嶋:自分が何ものかつて規定する必要ってほとんどないと思っています。誰かにとってもっとも使いやすいエージェントになればいいわけで、「博報堂」って肩書きが使えるなら使い倒すし、使えないならとっちゃえみたいな感じでしかる。
木村と嶋はキャラが違うわけですが、よく一緒に会社が出来てるねえって言われるんですが、目指すものは一緒でそのやり方が違うだけ。目的達成のためにどういう武器を使うかはそれぞれで、その違いはあまり重要ではないのと同じかな。