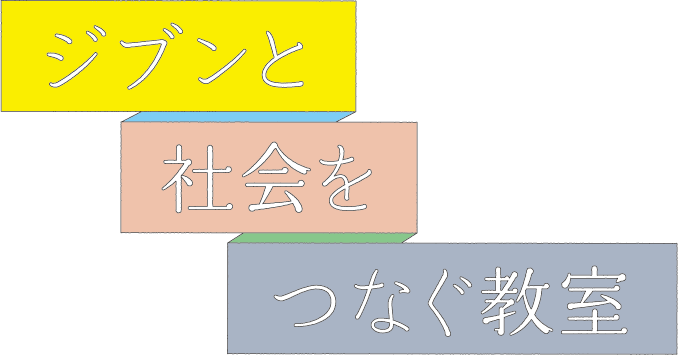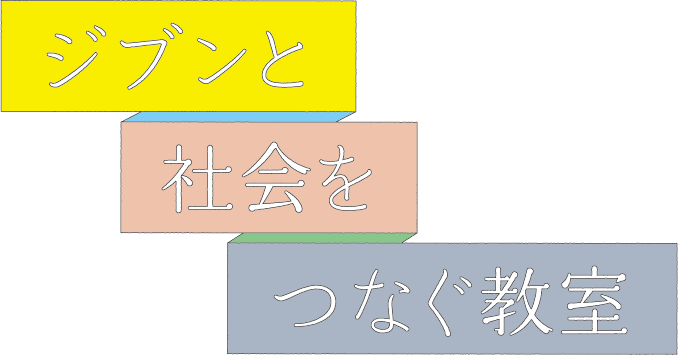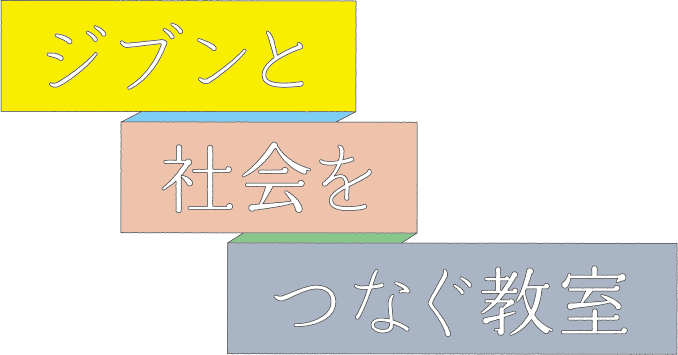「ジブンと社会をつなぐ教室」を書籍化した「なぜ君たちは就活になるとみんな同じようなことばかりしゃべりだすのか。」の特別対談の一部を紹介。今回はスクーの森さんを迎えた対談の後編。森さんは、自社のサービスを展開する中でコミュニケーションに「流派」があると考えるようになりました。自分がどの流派なのかを知ることは、面接への恐怖心を取り除くことにもつながります。
(前編はこちら)

面接で面接官の趣味を知って帰れるか
「伝える」に王道はない
保持:現在展開なさっているschoo(スクー)WEB-campusというサービスは、本当にいろいろな先生が、その場でたくさんの人に伝えて、受け取った人がレスポンスしてというのが、手に取るように分かるプラットフォームですよね。それを横で見ていると、この人の伝え方って上手だなとか、伝えるコツみたいなものが見えてくると思うのですが。
森:コミュニケーションとか教え方って「流派」があると思います。例えば劇場型。ウチにはエクセルの田中先生という教えるのが上手い先生がいるんですけど、この人はもうワンマンショー。「いいんです、エクセルはこれでいいんです」みたいに見ているだけで面白い。
保持:エクセルでそれができるってすごいですよね。
一同:(笑)
森:そういう流派もあれば、相手と徹底的にコミュニケーションをとる人も、いくつかのパターンを準備しておいて相手に合わせて出し分ける人もいる。王道のやり方っていうのは多分なくて、いずれも正解だと思うんですよね。だから新しい先生に対してアドバイスするときも、まずは、その人の流派を見極めるところから始まる。その上で、多分あなたの教え方だったら、この先生とこの先生の授業参考になりますよと言っていく。
保持:学生の場合は、どうすれば自分に合ったコミュニケーションの流派が見つかるんでしょうね。
森:前提として、コミュニケーション上手・下手っていう二元論で人を捉えないというのが重要だと思っています。自分の友達でも、プレゼンテーションさせたら負けないっていうヤツもいれば、飲み会になったら話の中心になるっていうヤツもいるし、聞き上手で恋愛相談するならこいつだなっていうやつもいると思うんですけど、どのコミュニケーションが自分の形にしっくりくるか、ちゃんと考えて分析するっていうのは大事だと思います。
面接官は「壁」じゃない
森:結局、情報をアウトプットすること自体は簡単なんです。それを相手が最後まで何パーセントキャッチしてくれるかというのが非常に重要です。インターネットの学習サービスは、飽きたらブラウザー閉じられて終了なので、そこで集中力を切らさないためにコミュニケーションの設計をしてあげるっていうところが重要なんです。それをやるかやらないかで最終滞在率が40%くらい変わったりするんですよ。
保持:教えるに限らず、伝えるっていうときには、一方的に言うより、キャッチボールが発生する抜き差しみたいなものが大事ということですね。就職活動も同じかもしれません。例えば面接とかって、数少ない双方向のやりとりができるチャンスだったりしますよね。
森:今、思い出したんですけど、就職活動のとき、グループ面接で、僕の隣の男の子が、面接のはじまる前に天気の話をしたことがありました。面接官は低いテンションだったのでうまくいかなかったんですけど、トライとしてはいいんだろうなと。結局はコミュニケーションをしに来ているので。
大来:「コミュニケーションしに来ている」っていうのは、学生にとっては素晴らしい言葉なんじゃないかと思いました。面接って、自分が自分のことだけをしゃべりに行くんだ、みたいなことじゃなく、面接官とコミュニケーションするんだっていう意識があるとちょっと違う気がする。
保持:確かに新しい視点かもしれないですね。面接に行って、面接官のことをよく分かって帰って来る人はあんまりいないじゃないですか。今日面接してくれた人に娘さんがいて、犬飼ってて、趣味が○○で、みたいに。もし、そういうことができたら、結構よい面接ですよね。
大来:みんな面接官を「壁」みたいに思ってるけど、向こうにも人格があって、その人が自分の話を聞くんだと思えるとだいぶ違うと思う。
森:僕自身も選考していてやっぱりワクワクしていますよ。やっぱり書類上で通しているわけじゃないですか、面接までは。よい仲間を探していて、いいヤツだったらいいなとか思っている。なので学生としては、向こうもドライに切り捨ててやろうと思っているわけじゃないっていう前提の中でコミュニケーションできると、ちょっとは気持ちが楽になるんじゃないかな。
<完>
こちらアドタイでも読めます!