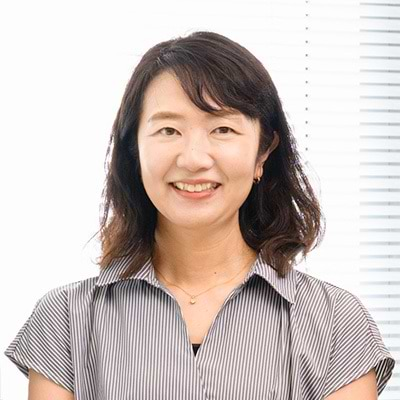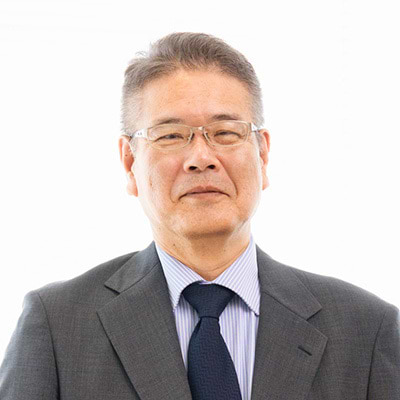お話を伺ったのは、総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報活用支援室 課長補佐の輿石美和氏(写真中央右)、日本財団電話リレーサービス広報チームディレクター上村麻子氏(写真右)、日本財団電話リレーサービス文字表示電話チームディレクター西川賢氏(写真中央左)。聞き手は電通 野村朗子氏(写真左)。
電通は国内電通グループ8社と共同で、“誰一人取り残されない”コミュニケーションの実現を目指す「みんなのコミュニケーションデザインガイド」を制作し、2025年1月28日より一般公開をしています。
本連載では、みんコミュ事務局のメンバーが、コミュニケーションにおける多様性やインクルージョンの貢献に寄与する事例を紹介しながら、その社会的意義を深掘りします。
今回取り上げるのは、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人へのサービスとしてスタートした相手の声が読める電話「ヨメテル」です。なぜ通話相手の声を文字にするアプリを開発するに至ったのか――。その経緯や社会的背景をひもとくと、聞こえにくいなどの理由によって電話でのコミュニケーションが難しい約1430万人(※1)の存在が浮き彫りになりました。
多様な“みんな”を知り、誰もが当たり前にコミュニケーションを享受できる社会のために必要なこととは?
※1厚生労働省によると、難聴患者数は全国で約1430万人(国民全体の約10%)いるといわれている。
電話リレーサービスは、国民の生活に欠かせない公共インフラの一つ
野村:2025年1月23日から、相手の声が読める電話「ヨメテル」 の提供がスタートしました。まずはヨメテルのサービスについて簡単にご紹介をお願いします。
上村:ヨメテルは、難聴者や中途失聴者など電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人へのサービスとして、通話相手の声を文字にする電話アプリです。24時間、365日、双方向で利用ができるのも特徴です。通話相手の声を文字にすることで、電話でのコミュニケーションをスムーズにする、法律に基づいた公共インフラの一つとなっています。

ヨメテルは、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人へのサービスとして、自身の声で通話相手に伝え、通話相手の声を文字で読むことができる電話アプリです。
野村:法律に基づいてサービスが提供されているということですが、このヨメテルのサービスの提供にいたった社会的背景を教えてください。
輿石:ではまず電話リレーサービスについてお話しさせてください。そもそも電話は、遠くにいる相手とリアルタイムで意思疎通ができる基礎的なコミュニケーション手段で、とくに緊急時や災害時に重要な役割を担っています。しかし、音声でのやりとりをする電話の特性上、聴覚や発話に困難のある人が利用することが難しく、緊急時に自身で電話ができないというのは、命にかかわる大きな問題でした。

こうしたさまざまな課題を解決するために海外などで運用されていたのが電話リレーサービスです。これは電話の利用が困難な人に対し、通訳オペレータを介し、手話や文字などを使って電話が利用できるサービスです。
日本では、2013年9月より日本財団がモデルプロジェクトとしてサービスの提供を開始し、聴覚や発話に困難がある人と聞こえる人との会話を通訳オペレータが手話や文字と音声で通訳することで双方向なコミュニケーションを実現してきました。
その後、日本財団でのモデルプロジェクトとしてのサービス提供が2020年度に終了するということもあり、デジタル活用共生社会実現会議の電話リレーサービスワーキンググループなどで議論を行い、総務省で制度整備について検討を行いました。そして2020年6月に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が可決成立。電話リレーサービスが制度化(※2)され、2021年度から公共インフラとしてのサービス提供が始まったのです。
野村:なるほど。電話リレーサービスを誰もがいつでも使えるように 制度化し、公共インフラとして整備されたという経緯があったのですね。
※2 法律に基づき、総務大臣が全国で1者指定する電話リレーサービス提供機関として(一財)日本財団電話リレーサービスが指定され、サービスの提供や啓発活動などを行っている。
抱える課題やニーズは人それぞれ。まずは多様な「みんな」を知ることから
野村:ではヨメテルのサービスはどのような課題がきっかけで、アプリの開発やサービス提供に至ったのでしょうか?
西川:先に提供を開始していた電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難がある人と聞こえる人との会話を通訳オペレータが手話や文字と音声で通訳するサービスです。厚生労働省の調査によると、現在日本においては聴覚・言語障害者(障害者手帳保持者)は約37万9000人(※3)います。 その中で、手話を使う人は約8万人弱いるといわれています。 この電話リレーサービスは 手話を使う人が利用できるサービスです。
ただ、自己申告による難聴者率は、日本の人口の約10%(※4)いるといわれています。
※3 厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」
※4 日本補聴器工業会の調査「JapanTrack 2022」

上村:中途失聴者の場合は、失聴するまでは音声によるコミュニケーションを活用していたため、自分の声を使いたいと思っている人が多くいらっしゃいます。しかし相手の声は聞こえない、もしくは聞こえにくいため電話を使うのが困難という状況がありました。
電話リレーサービスは、手話や文字を使って電話をするサービスのため、自分の声で何かを伝えることができません。そのため、自分の声を使いながら、相手の声を補完してくれるサービスが欲しいというニーズが以前からありました。
野村:海外ではすでにそういったサービスは展開されていたのでしょうか?
上村:海外でも同様のニーズがあり、アメリカなどではCaptioned Telephone Service(以下、CTS)という字幕付き電話サービスがあります。そのため、日本でもCTSのようなサービスを求める声が多くあり、「ヨメテル」の開発がスタートしました。
輿石:これまで限られた人しか利用できなかった電話リレーサービスでしたが、ヨメテルの登場により選択肢が増えました。
野村:みんコミュガイドでも、障害のある人の中には多様なニーズの受け手がいることをお伝えしています。ヨメテルはそういった多様なニーズに応えるサービスの一つとなっているのですね。
また、「自己申告による難聴者率は日本の人口の約10%」というデータもみんコミュガイドに掲載していますが、私たちが思っている以上に聞こえない、聞こえにくいといった悩みを抱える人は多いのですね。
上村:おっしゃる通りです。聴覚障害といっても一くくりにはできず、それぞれに抱える悩みやニーズは違うということは多くの人に知ってほしい事実です。
聴力の低下が気になる人にも!ヨメテルの利用がQOL向上の一助に
野村:ヨメテルのアプリ開発や運用にあたって意識したことはありますでしょうか?
上村:先ほど輿石さんがおっしゃったように、電話は遠隔にいる人とコミュニケーションを図る基礎的なツールです。その理念をきちんとヨメテルのアプリに反映させ、iPhoneやAndroidのOSに入っている電話機能と使用感のギャップを作らないようにシンプルな使い心地を意識して開発しました。

※イメージ
西川:昨夏に試験運用を実施して、多くの人にご意見をいただきながら使いやすさを追求してきました。特に相手の声が文字になる速度や見やすさ、ほかに発信や着信などは、当事者のご意見を反映させ、議論して作り上げていった部分でもあります。
また、相手の声を文字にする方法は、AI(自動音声認識)と文字入力オペレータ を選べるようになっており、よりスピードを重視してリアルな通話感を求める場合はAI(自動音声認識)、精度の高さを求める場合は文字入力オペレータと使い分けることも可能です。

実際の通話画面。このように通話相手の声が文字で表示される。
上村:人によっては普段生活をする上ではそこまで不便は感じないけれど、電話の機械音が聞こえにくいといった人もいます。そういった人は、ヨメテルを利用して、聞こえにくかった場所のみ文字を確認するといったこともできます。
野村:年齢を重ねるうちに聞こえづらくなる加齢性難聴の人や突発性難聴、また女性に多いとされるメニエール病で聴力の低下が気になる人などにも利用してほしいですね。実際にサービスが開始されてまだ日は浅いですが、普及率などはいかがでしょうか?
西川:登録者を見ると、現在はこのサービスを前々から待ち望んでいた人々が登録をして利用している状況です。しかし先ほどのデータでもあった通り、日本の人口の約10%が難聴者ということを考えると、10人に1人はヨメテルの利用対象者となり得るわけです。そう考えると、潜在的な対象者はまだまだ多く、その人たちにヨメテルの情報が届いていないという課題を感じています。
この辺りは、登録方法の見直しや説明会、講習会の実施などを行いながら、引き続き普及啓発を行っていきたいと思います。
誰にでも平等に情報が届く社会へ。総務省が取り組む情報アクセシビリティの配慮とは?
野村:総務省は地域の自治や社会基盤など国民の生活基盤に関わる行政機能を担っている省であり、情報通信に関する整備なども担当されているかと思います。インターネットの普及によって社会の在り方も大きく変化している今、力を入れていくべきことや課題意識を感じていることなどはありますか?

輿石:誰もがスマホやPC、タブレットなどさまざまな端末でインターネットに接続でき、多くの情報に触れることができる今、情報アクセシビリティの確保はとても重要です。情報アクセシビリティとは、年齢や障害の有無にかかわらず、誰でも必要な情報に簡単にたどり着くことができ、利用できることを指します。
わかりやすいところで言うと、UDフォントのように読みやすいフォントが使用されているか、一文が長すぎてわかりにくい文章になっていないか、難しい漢字にはルビがふられているか、色弱者や高齢者などに配慮した色彩が使われているか……など、意識すべき点はたくさんあります。ですが、意外と情報を伝える側のちょっとした心がけで解決できる部分も多くあると感じています。
野村:「みんコミュガイド」でも、ジェンダー、年齢、障害といった多様なニーズのある受け手がいることを前提に、必要な配慮や参考となる事例などを紹介しています。
■印刷

行や文字間隔を調整し、読みやすい情報量にしたり、読みやすいフォントを使ったりすることで、必要な人に正しい情報を伝えやすくなります。
■動画コンテンツ・CM

動画コンテンツやCMにおいては、配色やフォントなどの調整で視認性を上げたり、字幕を付けたりするなど、見えにくさや聞こえにくさをサポートする工夫も重要です。
輿石:こういったガイドがあるとわかりやすいですよね。
総務省ではウェブサイトのアクセシビリティに関しても「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を公開しています。国および地方公共団体など公的機関のホームページなどでは、国民にとって重要な情報を多く発信しています。そのため高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように、ウェブアクセシビリティに関する規格や手順を示し、ウェブアクセシビリティの向上を呼び掛けています。
野村:インターネットでさまざまな情報を取得できる今、ウェブアクセシビリティの向上は公的機関だけでなく、多くの企業でも意識すべき重要課題ですね。
輿石:そうですね。情報取得者の中には、視覚に障害のある方、ディスレクシア(読み書きに困難がある学習障害)の方、外国の方などさまざまな特性の人がいることも配慮する必要があります。
情報を伝えたい人たちの中にどんな人たちがいるのかをまずは想像し、文字の大きさ、動画の遷移の仕方、音声の出るタイミングなど、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を参考にして整備していただけたらと思います。
ウェブアクセシビリティの向上を多くの企業や団体が実践していくことで、誰もが不自由なく情報を取得でき、やがて誰一人取り残されないコミュニケーションの実現につながると感じています。
野村:また世の中が便利になった一方で、偽・誤情報、闇バイト、オンラインカジノなど、インターネットにまつわるさまざまな問題が発生しています。総務省で取り組まれている対策などあれば教えてください。
輿石:2025年1月から総務省の情報活用支援室では、「DIGITAL POSITIVE ACTION」という取り組みを始めています。フェイク情報にだまされたり、拡散させたりすることのないよう、国民一人ひとりが情報リテラシーを高めていく必要があります。
誰もが簡単にインターネットにアクセスできる時代だからこそ、情報アクセシビリティや情報リテラシーについて、一人ひとりが理解を深め、実践していくことが、インクルーシブな社会をつくる第一歩だと考えています。
野村:今回のお話を聞いて、コミュニケーションを取る相手の特性やニーズを想像することの必要性をあらためて強く感じました。情報アクセシビリティの配慮や情報リテラシーの向上など、できることから実践していけたらと思います。本日は貴重なお話ありがとうございました。
◎みんなのコミュニケーションデザインとは?

コミュニケーションの対象には、年齢、障害の有無、ジェンダー、国籍など多様な特性やニーズのある受け手がいることを前提に、“誰一人取り残されない”みんなにとって理想的なコミュニケーションの実現を目指す考え方。「みんコミュガイド」では、多様な「みんな」を知ることと、送り手と受け手の間に介在する多岐にわたるコミュニケーションメディアを取り上げ、必要な配慮や参考となる事例などを紹介しています。