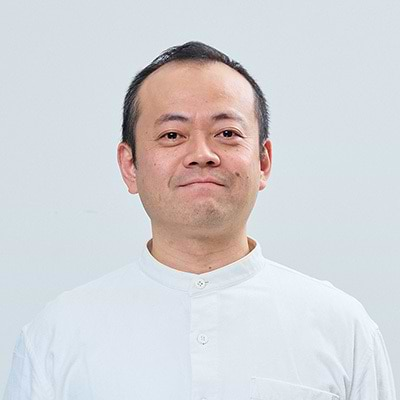写真左から、みんコミュ事務局の林孝裕氏、野村朗子氏、丸橋佳寿子氏
電通は国内電通グループ8社と共同で、“誰一人取り残されない”コミュニケーションの実現を目指す「みんなのコミュニケーションデザインガイド」を制作し、2025年1月28日より一般公開をしています。
本記事では、みんコミュ事務局のメンバーである野村朗子氏、林孝裕氏、丸橋佳寿子氏にインタビュー。ガイドの開発に至ったきっかけを深掘りしながら、みんなのコミュニケーションデザイン(以下、みんコミュデザイン)が、誰もが持つべきビジネスリテラシーの一つである理由やdentsu Japanが取り組む意義を語っていただきました。3人が考える、みんコミュガイドを賢く活用するヒントにも注目です。
◎みんなのコミュニケーションデザインとは?

コミュニケーションの対象には、年齢、障害の有無、ジェンダー、国籍など多様な特性やニーズのある受け手がいることを前提に、“誰一人取り残されない”みんなにとって理想的なコミュニケーションの実現を目指す考え方です。「みんコミュガイド」では、多様な「みんな」を知ることと、送り手と受け手の間に介在する多岐にわたるコミュニケーションメディアを取り上げ、必要な配慮や参考となる事例などを紹介しています。
「みんコミュデザイン」が、ビジネスパーソンの必須科目である理由とは?
──まずは、国内電通グループ各社が集結し、「みんコミュガイド」の制作に至ったきっかけを教えてください。
野村:2024年4月に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業による障害のある方への合理的配慮が努力義務から「法的義務」になりました。こうした社会的な背景もあり、近年では事業を通じた顧客の多様性課題への対応を推進する企業も増えています。これまでは企業がDEI※というテーマを議論する際、どうしても人事や雇用、社内領域に関する取り組み、リスク対応などに終始しがちで、なかなか広がっていかないという課題がありました。
私自身、組織内のDEI推進に携わる業務を担当しており、この状況は非常にもったいないと感じていました。
林:DEIというと、人事などの専門部署の領域だと思われ、それ以外の人たちが意識する機会があまりないんですよね、自分には関係ないことと捉えがちというか……。
野村:そうなんです。あとは、2022年に誰一人取り残されないイベントの実現を目指す「みんなのイベント・ガイドライン」を制作して一般公開をしました。しかし、作って終わりというか、ガイドを活用して企業や業界の実装事例が次々と生まれるような広がりや浸透といった部分では、いまだ物足りなさを残す結果となっています。
この反省もあり、「改正障害者差別解消法」の施行を注視していく中で、“誰も取り残されない”という意識を多くの人に持ってもらうためには、イベントだけでなく、電通グループの強みを生かしてコミュニケーション全体で考えていく必要があるのではないかと思い至ったんです。
この考えを、dentsu DEI innovations(旧電通ダイバーシティ・ラボ)の代表を務める林さんにまずは相談し、そこからアートディレクターの丸橋さんにも入ってもらって、事務局が立ち上がりました。
※「ダイバーシティ(多様性)」「エクイティ(公平性)」「インクルージョン(包摂性)」の頭文字からなる略称。
──電通以外にグループ8社が参画していることも特徴の一つですね。
丸橋:私たち以外に、電通デジタルや電通ライブなど国内グループ各社からDEIにアプローチのできる社員が派遣され30人の制作チームを組成し、さらに有識者6人による監修のもと制作が進められました。ただ、今回のガイドでは、DEIやマイノリティなどの言葉はあえて強く押し出していないのも特徴です。
野村:入り口はDEIなんですが、すべての事業活動におけるコミュニケーションにおいて必要な考え方であり、誰もが持っておくべきビジネスリテラシーの一つだということを理解してほしいという思いもあります。そのため、まずは電通グループで働く2万3000人の社員に、「みんコミュデザイン」がこれからのスタンダードになり、ビジネスパーソンにとっての必須科目になっていくということを伝えていけたらと考えています。
──「みんコミュデザイン」は、DEIに限った話でなく、ビジネスにも直結しているということなんですね。
林:今回私は、監修協力的な立場でこのプロジェクトに携わっています。私が代表を務めている社内タスクフォースのdentsu DEI innovationsでは、ビジネスを通して多様性やインクルージョンに貢献していくという考えがベースにあります。
この考え方は、ガイドを制作する上でも大きな核になっており、「『みんコミュデザイン』は社会貢献ではなく、私たちのビジネスの話です」と強調してお話をしているのも、これが理由です。
私たちのコミュニケーションが、すべての人に届くためにはどうすればいいのか――。電通グループの社員をはじめ、さまざまなメディアに関わる一人ひとりがこの考え方や知識を持って、コミュニケーションデザインをしていくことがまず重要です。「みんコミュデザイン」は、誰一人取り残されないコミュニケーションを実現するための、誰一人他人事にしてはならない必須のビジネススキルでもあると考えています。
「みんコミュデザイン」の実践が、事業成長や企業価値の向上につながる
──「みんコミュデザイン」をより身近なものとして、社会実装させていくために必要なことはどんなことでしょうか?
林:「みんコミュデザイン」の実践が、企業の事業成長にも直結するという認知を広げていく必要があると考えています。
従来のマーケティングでは、想定したターゲットに届くことを目的としており、特定の人に集約的にコミュニケーションを取る手法が主流となっています。もちろん、これは有効な手段なのですが、昨今は、デジタルシフトによって精度の高いターゲティングが可能となったことで、無駄なコミュニケーションを過度に省いていく傾向にあるとも感じています。ともすると、自分たちにとって有効な顧客とだけコミュニケーションを取り、それ以外を排除してしまうということです。
しかし、少子高齢化で人口減少が進み、インバウンド需要が増加し続ける中で、顧客ボリュームを継続的に維持していくためには、今まで届いていなかった人たちにも幅広くアプローチしていく必要があります。
「みんコミュデザイン」を実践することで、これまでリーチできていなかった人たちとの間に接点が生まれれば、企業にとっても大きなメリットになります。さらに社会貢献ではなく、事業成長としっかりリンクさせることができれば、多様なコミュニケーションの創出に企業側もしっかり投資をしていく必然性も出てきます。

野村:実際に、字幕付きCM普及推進協議会が2022年に発表した調査によると、字幕付きCMは、字幕なしに比べて、内容理解度や商品、企業への興味関心度、好感度が増加したという結果が出たそうです。さらに、聴覚障害者のほか、聞こえにくい高齢者、健聴者においても、企業イメージが良くなったと回答する人が増えたというのも興味深い結果です。
林:「広告」って広く告げると書きます。その原点に立ち返り、今まで届いていなかった人たちにも向けて、コミュニケーションを設計することは、事業の成長や将来リスクを考える上でも必要なことだと思っています。
これまで当たり前だと思っていたマーケティングの考え方を大きく方向転換することが、これからは求められていくのかもしれません。
野村:今回のガイドでも、みんコミュデザインの実践で生まれる効果のレベルを3つ星で紹介しています。1つ星は「当事者のアクセシビリティの担保」、2つ星だと「すべての人のユーザビリティ向上・ベネフィット創出」、3つ星であれば、「すべての人とブランドとのエンゲージメント強化・ロイヤルティ醸成」としており、3つ星を目指すことで、企業やブランドへの満足度や好意度が上がり、イノベーションや新たな価値が生まれると考えています。

そして、誰も取り残されないコミュニケーションを社会全体で実現していくためには、多様×多様という考え方が大事だと思っています。
つまり、私たちがコミュニケーションの対象とする人たちは多様であり、その人たちとコミュニケーションを取る手法もさまざまあって、それらを掛け合わせていくことで、どの側面から見ても誰一人取り残されないコミュニケーション体験を構築していくという考え方です。これが、イベントだけ、動画コンテンツだけ、ウェブだけと単独メディアになってしまうと、限定的なコミュニケーションで終わってしまいます。そうならないためにも、制作体制もインクルーシブ(多様な専門性の集結)であることが必要なのです。
林:今回、電通だけでなくグループ各社にも参画してもらいdentsu Japanとして、このガイドを作った意義はそこにあります。さまざまなコミュニケーションメディアにおいて専門的な技術を持っている電通グループだからこそ、みんなで手を組み、それぞれの得意分野や強みを生かしあうことが必要です。そして、クライアントや業界を巻き込みながら、“みんなに届く”コミュニケーションを“みんな”で実現していく、重要なのはまさに事業共創です。
「みんコミュガイド」は、教科書ではなくポイント集。上手に活用するコツは?
──今回のガイドでは、年齢、障害の有無、ジェンダー、国籍といった多様な特性やニーズのある受け手を細かく想定し、コミュニケーションを設計する際のヒントや実践例がわかりやすく紹介されていますね。
丸橋:ガイドには、さまざまな人たちが登場します。障害者、性的マイノリティ、外国人などとそれぞれを一くくりにしてしまいがちですが、その中にも全盲の人、弱視の人、ろう者、難聴者、男性、女性、LGBTQ+……といったように多様な人々が存在します。今回は、アルファベットをモチーフにしたキャラクターを使って、それぞれのニーズや事例、課題などを解説したポイント集となっているのも特徴です。

林:そうですね。今回の「みんコミュガイド」は、1から10までをレクチャーする教科書ではなく、ポイント集だと思って活用してほしい。最初から全部を理解しようとせずに、気になるページから読んでもらうのがいいのかなと思っています。
丸橋:パラパラとこのガイドを見るだけでもこれまでとは違った視点が生まれて、新たなアイデアがひらめく可能性だってありますよね。
林:何なら、感想や思いついたアイデアを書き込んでしまってもいいと思います。例えば、街で見つけたサインや海外の事例などをメモしたりして、ブラッシュアップしながら、企業や業界、またコミュニケーションデザインを行う担当者それぞれがオリジナルの「みんコミュガイド」を更新していくイメージです。ここに書かれていることすべてが正解とは限らないですし、今回をスタートにして、みんなで多様なコミュニケーションとはどういうことなのかを一緒に考えていけたらうれしいですね。
「みんコミュデザイン」を社会の当たり前にしていくために必要なことは?
──2025年1月に「みんコミュガイド」が一般公開されてから、どのような反響がありましたか?
丸橋:社内でいうと、営業を担当する部署からは「勉強会をしてほしい」などの問い合わせはけっこう来ています。やはり、クライアント企業と直接やりとりをする機会が多い営業担当は「知っておかなきゃ」という意識を持つ方が多いのかもしれません。なので、まずは電通のクライアント対応の窓口である営業の担当者がそういった意識を持って、クライアント企業の皆さまと一緒に勉強をしていくことは、すごくいい流れだと感じています。
こうした広がりや循環が、今後たくさんいろんなところで生まれることに期待します。

──最後に、みんコミュに関する今後の展望などあればお聞かせください。
野村:今回、電通と国内グループ各社の知見やノウハウを結集し、「みんコミュガイド」が完成したわけですが、これをゴールとせずに、ここから一つでも多くのファクト(実装事例)をつくっていくことが重要になっていきます。「みんコミュデザインの考えを取り入れたコミュニケーションを実践したら、自社の好感度やファン獲得につながった」といった事例ができれば、どんどん続く企業も出てくると思うので、次のステップは、そこを目指せたらと思っています。
丸橋:そうですね、まずはクライアントのニーズのもと、「みんコミュデザイン」を実践したクリエイティブをつくって、世の中にアウトプットすることを実現したいです。それを手にしたユーザーの反響を知ることで、次のアプローチ方法も見えてくるのではないかなと思います。
林:「みんコミュデザイン」はビジネスに直結していると何度もお伝えしていますが、「みんコミュデザイン」を実践することで見えてくる成果というのは、売り上げや利益だけではないと思っています。それがリクルーティングにつながったり、新たな協業パートナーがみつかったりと数字には表れないポジティブな動きにつながっていく可能性だってある。今後は、この「みんコミュデザイン」が企業にどのような成果をもたらすのかを分析し、フィードバックするなどして、クライアント企業のコミュニケーションデザインをしっかりとサポートする仕組みを整えていきたいですね。
また、「みんコミュデザイン」を電通グループだけのスキルや共有資産にするのではなく、業界や企業、エンドユーザーみんなを巻き込んで、私たちの“当たり前”にしていけたらと思っています。
「みんなのためのコミュニケーションデザインは、みんなでつくるコミュニケーションである」ということを忘れずに、事務局としてもさまざまな取り組みに挑戦していきます。
■「みんなのコミュニケーションデザインガイド」
〈制作・編集〉
dentsu Japan みんなのコミュニケーションデザインプロジェクト
(株式会社電通、株式会社電通デジタル、株式会社電通ライブ、株式会社電通プロモーションプラス、株式会社電通PRコンサルティング、株式会社電通クリエイティブフォース、株式会社電通クリエイティブピクチャーズ、株式会社電通総研、株式会社電通プロモーションエグゼ)