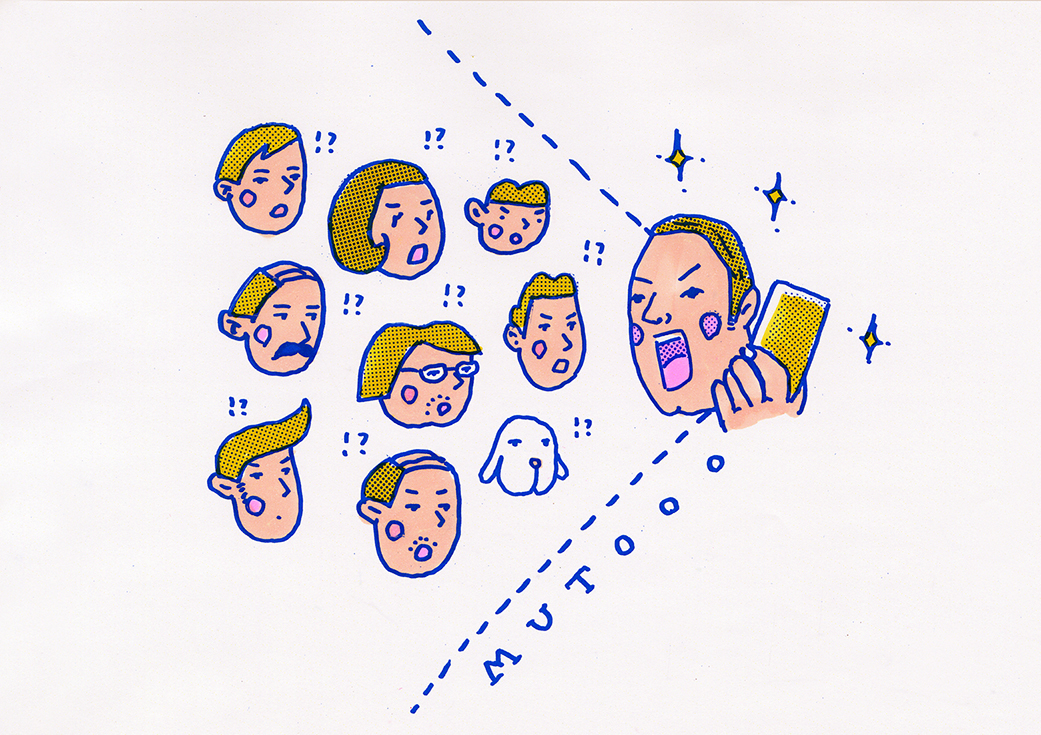1920年代、女性が社会進出していく先駆けをつくった人物がいます。
政治家でもなければ、発明家でもありません。その名はココ・シャネル。ファッションブランド「シャネル」の創始者です。
彼女は衣料品というモノを世に送り出すだけではなく、これからの女性の生き方や価値観、スタイルをファッションという「コト」で表現しました。それは単なる流行ではなく、「古い価値観にとらわれない女性像」を表現したものであり、女性解放を実現するものでした。
身軽で動きやすいことを追求し、下着に使われていたジャージ素材や、紳士もののツイード素材を採用して女性用のスーツをつくったのは、働く女性のためでした。それまでスカートしかはいていなかった女性に、パンツスタイルを提案したのも彼女です。
洋服だけではありません。ハンドバッグが主流だった時代に、両手を自由に使えるようにと、ショルダーバッグを発想。デザインが華美で大きな容量の香水瓶を、シンプルで小さな形状にすることで、バッグに入れて持ち運べるようにもしました。
どれもいまの時代では当たり前の「コト」ですが、当時は先入観や常識を覆す画期的な「コト」で、未来のスタンダードを創ったアイデアです。まさに、モノ発想に留まることなく、「コト発想」でイノベーションを起こしたと言えるのではないでしょうか。イノベーションはけっして技術の進化だけから起こるものではないことを物語っています。
僕も、こんな発想で仕事に向き合いたいと考えています。広告キャンペーンの企画や商品開発のサポートをする場合も、自主的なプロジェクトの場合も、それらを通して、世の中にどんなコトが起こせるか、コトのデザインをどうするかが、僕にとっての大命題です。
その結果、革新的なスタンダードが生まれれば、そんなハッピーなことはない。なかなかその道のりは長く険しいのですが、僕が社内の仲間と進めている「アイデアをカタチにする」プロジェクトから生まれた、ダンスメソッド「カズフミくん」はその一例でもあります。
それは振付師のパパイヤ鈴木さんと一緒に考えた、誰でも簡単にダンスが踊れるようになるメソッド(方法)です。いわば、音楽の譜面や武道の形のようなもの。1・2・3・4の数字(カズ)が書かれたマットをリズムに合わせて順に踏む(フミ)だけで、ダンスの基本的なステップができるようになることから、「カズフミくん」と名づけました。
同名のタイトルで、本(朝日新聞出版)やiPhone向けのアプリにもなっています。

アプリ画面

書籍
最終的に目指すのは、子どもの身体教育において、イノベーションを起こす存在になること。マットというツール(モノ)を使い、学校の授業(コト)を通して、ダンスの楽しさや創造性を伝える取り組みを、まさしくいま一歩一歩進めています。
前回の連載でも触れましたが、ある教育事業者と一緒に「ダンス教室」を開講し、授業カリキュラムや教材の開発からインストラクターの教育といったところまで、広範な仕事にかかわっています。実際、全国の幼稚園や保育園で「カズフミくん」を使った授業が行われています。
■モノ発想に留まらず、コト発想へ行ったり来たり
また、「コト発想からモノ発想へ」をテーマに、多摩美術大学情報デザイン学科の授業に参加したことがあります。僕らは講師兼アドバイザーとして、約半年間にわたってキャンパスに通い、宮崎光弘教授と20名ほどの学生たちと一緒にワークショップをしました。
具体的なお題は「父親と子どものコミュニケーションツールをつくろう」というもの。
ハタチを超えたばかりの未婚の若者たちに、あえてそんなお題を課しました。経験のない状況を想像し、コトからモノへのデザインを学んでもらうことが狙いです。
僕らにとっては、「アイデアをカタチにする」プロジェクトの一環として、学生の柔軟な頭からどんなものを引き出せるかにチャレンジする産学連携の取り組みでした。結果、学生に気づきを与える立場でありながら、彼らから刺激をもらい、僕ら自身が改めて大切なことに気づかされる場となったのです。
このワークショップは、
①リサーチ ②アイデア発想 ③プロトタイプ制作 ④プレゼンテーション
というステージで構成。それぞれ、①でコト発想のデザイン、②でコトからモノへ変換するデザイン、③でモノ発想のデザインをすることになります。
①のリサーチは、父親へのヒアリング、子どもの頃に父親に何をしてほしかったかを思い起こす、公園で遊ぶ父親と子どもの観察など、どんなコトがヒントになるかを発見するステージです。
「父親は仕事で帰宅が遅くなることが多いため、子どもとすれ違いになり、お互いが欲求不満となっている。それを埋められるものはないだろうか」
「子どもとの時間をできるだけつくりたいけれど、何をしてあげればいいか迷っている父親。仕事で疲れている父親に何かしてあげたい気もちはあるけれど、何をしたら喜ばれるかわからない子ども。それらをつなげるものを考えたい」
学生たちはリサーチを通して、こんなことを見つけ出しました。
中には、「本当に父親と血がつながっているのか、と子どもは密かに思っているのでは? 私は子どもの頃そうだった。それを証明してあげるものがつくれないだろうか」というぶっ飛んだところに目をつける学生もいて、授業は大いに盛りあがりました。
②のアイデア発想では、自分たちの発見や仮説を具現化するためのコトを考え、さらにモノへと変換していきます。
①で例に出した順に、
「1冊の本を親子で同時に読むしおりがあるといい。学校から帰宅して日中読む子どもと、会社から帰宅して夜寝る前に読む父親が1冊の本としおりを通して、物理的には一緒にいられなくても気もちを共有できるのではないだろうか」
「父親が子どもにしてほしいこと、子どもが父親にしてほしいことを、それぞれ1日ひとつだけ互いにしてあげられるためのガイドブックをつくりたい」
「父親と子どもの顔がパラパラ漫画のように変化してつながって、親子であることが面白おかしくわかるツールというのはどうだろう」
といったアイデアにそれぞれ発展していきました。
③のプロトタイプ制作は、学生たちが100円ショップやDIYなどで材料を探し、手づくりでアイデアを見える化、つまり実際のカタチあるモノにするステージです。
それぞれの例では、
「PaPaCo bunco―父親と子どもがお互いに、物語の感想を書きこんで本に挟んでおける、2種のしおりとブックカバーのセット」(写真左)
「5fun dake―5分の砂時計が本の真ん中をくり抜いて組みこまれ、それをひっくりかえすことで父親と子どものギブ&テイクが交互に1日5分だけできるガイドブック」(写真中央)
「パパパラブック―親子それぞれの顔写真を加工して、パラパラめくると子どもから父親へ変化していく、実際の親子3組で作った3冊のサンプル本」(写真右)
といったプロトタイプができあがりました。
④のプレゼンテーションでは、最初の発見や仮説からアイデアまでを伝えるための説明ボードや映像を作成し、プロトタイプと一緒に、受験生向けに行われたオープンキャンパスで展示し、発表会を行いました。
学生たちの考えたプロセスは、とても参考になります。ここでは、コト発想からモノ発想へと進んでいったのですが、実際のプロセスではそれを行ったり来たりします。どちらが先かは関係ありません。大切なのは、モノ発想だけに留まりがちなところを、コト発想を組み合わせることで、イノベーションを起こすくらいの気概を持つことです。
みなさんもふだん仕事をしていると、ついモノそのものの機能やデザインだけに目がいきがちではないでしょうか。そこに留まらず、モノを通して世の中にどんなコトを起こせるか、そしてどんな価値やスタイルを提供できるかを、ぜひ考えてみてください。
さらに、その周辺にどんな影響を及ぼすか、前後にどんな変化が表れるかを想像してみてください。そうすれば、それが未来を創るイノベーションへの第一歩につながるかもしれません。