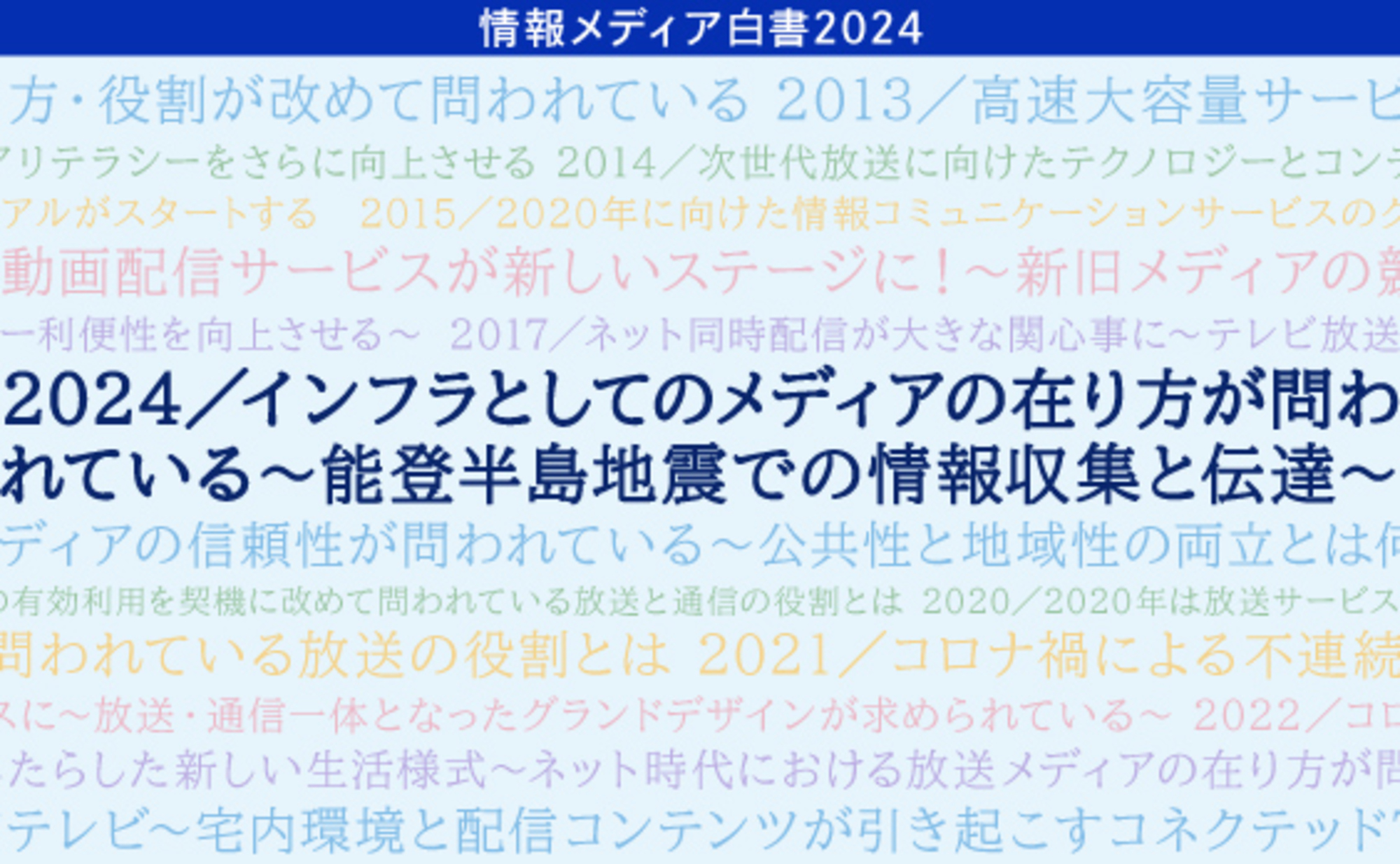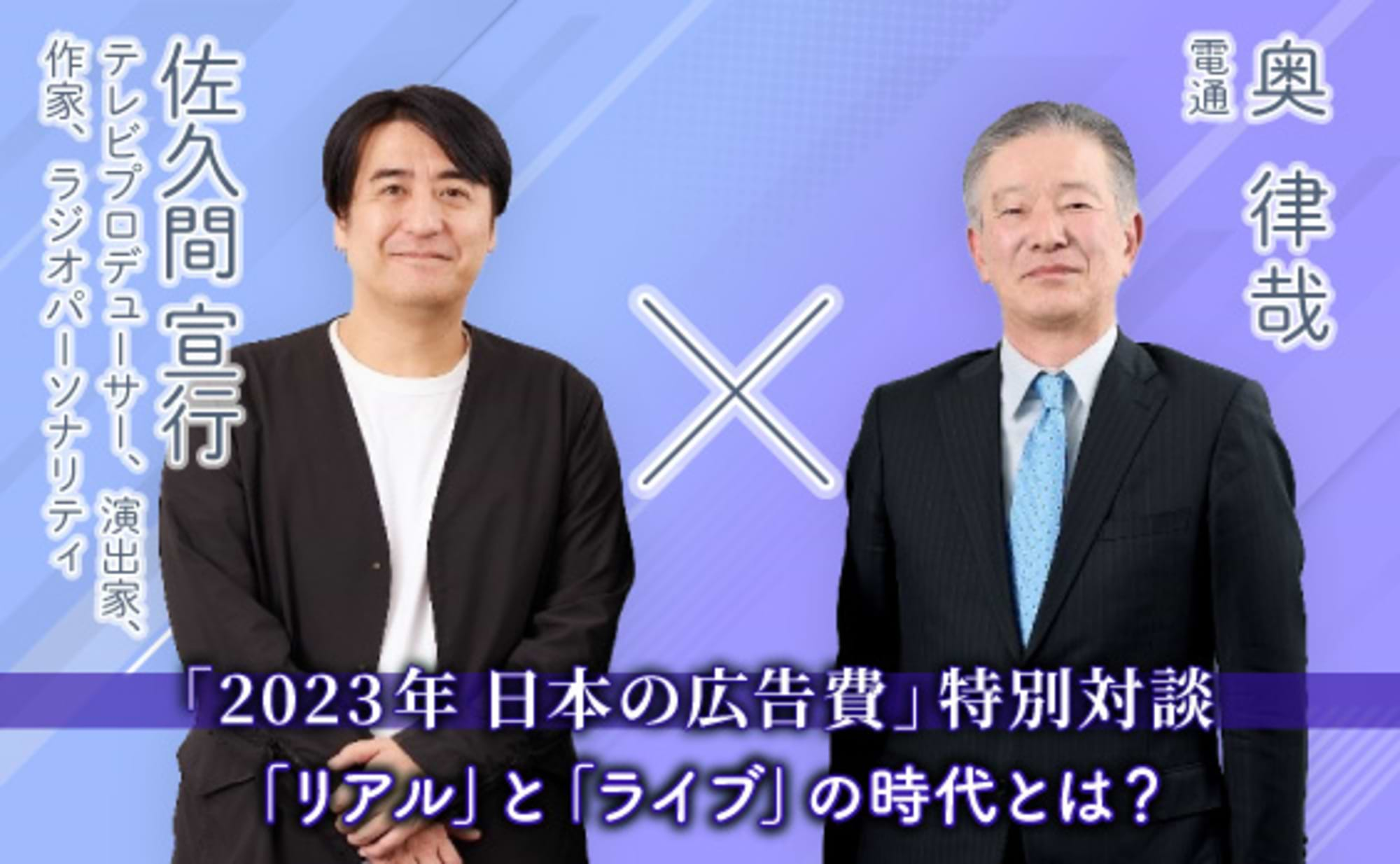なかなか厳密にとらえることができない、メディアの効果指標。デジタル・ビジネス局の植村さんは、ネットとリアルを縦横に行き来する消費者を前に、正確にとらえることの難しさを率直に口にする。一方、電通総研の奥さんは、「そうではあっても、新たな広告指標の提示は、クライアントと、そして時代の要請でもある」と強調する。2人の議論はどう深まるのか?
必ずしも一定ではない、視聴率とツイート数との相関関係
植村:メディアの効果指標の問題では、テレビとネットで、ツイッターのツイート数を視聴率と関連づける動きがありますね。
奥:ツイート数と視聴率の間には正の相関があるのは確かですね。ただ留意しなくてはいけないのは、番組のジャンルによってその相関関係が崩れることもありうること。今年の3月、WBCのキューバ戦があったときに、その日に家にいた約2500人を調査したんです。視聴率はキューバ戦を放映したTBSが一番高かったのですが、実はツイート数を含む番組関連のネット利用率はそうではなかった。裏番組の『ためしてガッテン』や『いい旅・夢気分』のほうが多かった。
これが何を意味するかといえば、番組内容によってツイートによる突っ込みやすさが違うということ。だから、視聴率が10%と20%の番組があるとすると、ツイート数の比率が必ずしも1対2になるわけではない。視聴率とツイート数との相関は、そう単純なものではないということですね。
植村:同感ですね。同じテレビドラマでも、ラブストーリーや推理ものといった、じっくり見ちゃう専念型のものは突っ込みをする余裕がない。でも、「なんだよ、これ」って言いながら観られるドラマはツイートもしやすい。まして、ジャンルがまったく違う番組では、視聴率とツイート数との相関関係は違ってきて当然ですよね。
奥:ツイッターはリードオンリーという人も多いからね。突っ込む人よりも、見ている人のほうが断然多い。その両方の数字を押さえなくちゃいけないですね。
それと、もうひとつ気になるのは、とくに若い人に多いですけど、ラインが流行ったりして、クローズドのほうにいく傾向が強まってます。ツイッターも、この前利用状況を調べたら、オープンな使い方をしているのが7割、オープンとクローズド両方使い分けているのが1割、クローズドオンリーが2割という結果でした。拡散が得意なツイッターでも、クローズに使う人が意外と多いことを再認識しました。
植村:自分がこの番組観てるっていうことを友だちにも知られたくないときだってあります。こんな番組を観ているのを知られると恥ずかしいと。当然、ツイートはしないけれど、視聴率にはちゃんとカウントされる。逆に、仮に見てなくても「オレ、これ観てるよ」って自慢したい番組のほうがツイートされがちになるわけでしょう。
奥:そういう複数の顔を持つユーザーがいるなかで、効果指標を客観的にどう引き出すかが問われている。
植村:テレビは何インチであっても画面100%にコマーシャルが出て、音もついて、露出ほぼイコール認知なんですよね。でもネットの場合は、ブラウザの画面の中で、バナーのサイズは必ずしも大きくない。だから露出と認知が必ずしもイコールではない。効果という意味では、露出量ではなく認知を調べなきゃいけないんですけど、ネットの世界はどうしても効果指標が露出かクリックかになっちゃう。やはり、露出とクリックの中間的な効果指標が必要なんですよね。つまり「認知」なんですけど、それがあって初めてテレビとか他の媒体と比較できる。
クラウドが進化すれば、厳密な「貢献度」を出すこともできる
奥:最近よく「アトリビューション」(購買プロセスの変化に貢献した要因のこと。貢献度)がよく言われるじゃないですか。これは、植村さんの言った露出とクリックの間を埋めるものになるのですか。

植村:ネットでのユーザーの購買行動をサッカーに例えていえば、“パス回し”ってのがありますよね。最終的にアマゾンや楽天で買うにしても、その前に、グーグルで検索したり、価格比較サイトで値段を調べたりとか、購入サイトにたどり着くまでに、いろいろなところを回っているわけです。しかし今は、最後にゴールした場面、つまり購入したサイトの広告効果ばかりが着目されている。でも、ヘディングでゴールする前に、コーナーキックがあったり、絶妙なパス回しがあったりする。つまり、アトリビューションですよね。このアトリビューションの計測はネットメディアが得意するところですが、でもよくよく考えてみれば、購入をプッシュしたのは、テレビや雑誌や、屋外広告の場合だってありうる。最後はスマホでEコマース決済したとしても、マス媒体の貢献度もきっとあるはずです。あるいは、最後のゴールは、ポイント欲しさに量販店で買うということもあるでしょう。
最近は「統合アトリビューション」(マス広告とネット広告の購買貢献度を一元化する概念)といった考え方もありますけど、消費者がオンラインとオフライン、リアルとネットを行ったり来たりするなかで、メディアごとに効果を厳密に割り出すのはなかなか難しくなっているというのが実感です。
奥:ただ、クライアントの要請からすると、ある仮説に基づいた効果指標の提示が必要な時代に入っていることは確かですよね。従来もテレビで分かることは、見た・見ない、好きだ・嫌いだ、CM覚えてる・覚えてないというところまでで、購買行動まで到達したかどうかは言えなかった。逆にネットは、クリックしたかどうか、本当に購入したかどうかもわかる。そういう流れの中で、アトリビューションも考えなくてはならない。
そこでひとつ忘れてはならないのは、ブランド認知という重要な要素があることですね。ブランドを知ってもらって、好きになっていただくという側面がある。実はそこに、ネットと4大マスメディアの役割の違いもある。マスメディアに、先ほどのサッカーの話でいうと必ず点の入る仕事しろと言ったら、ちょっと酷な気もします。やはり、畑は耕すことも必要。常に刈り取っているだけでは、見込み客が育たなくなる。そこはバランスですよね。クライアントに対しては、長期的な効果の部分と、今週の売り上げといった短期的なスコア、両方を提案できるようにしなきゃいけないと思うんです。
植村:どんどんターゲットを狭めて、クリック率がいいところを求めていくと、マーケットがシュリンクしてしまう。見かけの効率はいいけど、ブランド認知もビジネスも広がっていかない。クリック率を下げてでも広げていかなければ、見込み客はとれないわけですよね。
奥:それと、ちょっと先の話になるでしょうが、いろんなメディアがクラウドにつながって、そのクラウドのデータをしっかり捕捉できるようになれば、マスメディアも含めて、けっこうアトリビューションを測定できる可能性もあるのかもしれないですよね。
植村:第2回で、スマホがリモコン化するという話が出ましたが、そうなると、どのテレビを見て、どのCMを見たかが全部わかるようにもなる。それで、スマホでネット決済やコンビニ決済をすれば、購買行動のデータは理屈としては全部とれることになる。
奥:購買データとメディア接触データの塊がとれる。そういうふうに、メディアが進化していけば、統合アトリビューションが文字通り実現される可能性はありますよね。それと、どういうパス回しをしたらいいのか、テレビが先かラジオが先かとか、パス回しを多くするより、2、3回のショートカットで済ませたほうが楽ですよといった、コミュニケーションのひな形みたいなのものもできるかもしれない。
植村:そこまでいけば、究極の効果指標にもなるかもしれません。われわれの研究の余地もまだまだありますね。
〔 次回へ続く 〕