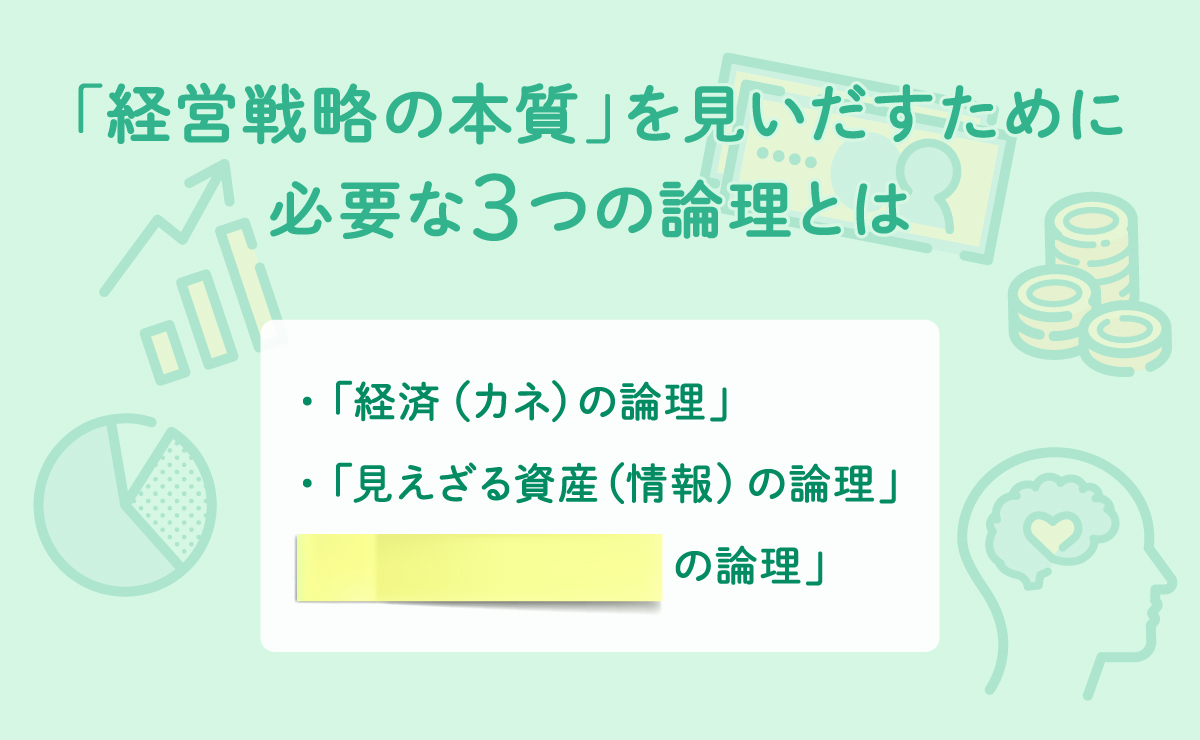大学卒業以来二十余年、なんとなく続けてきたテニスが、この年になって突然、メチャクチャ楽しくなっています。きっかけは高松市の、とあるテニスクラブ。妻の実家に帰省すると朝のうどんと夜の地魚&地酒以外特にやることもないので、暇つぶしに受けたプライベートレッスンでした。
「バックハンドのテークバックはラケットを立てた方がよいですよね?」とか「スイングの途中で体幹の回転をストップさせて、ヒジから先だけを加速させる二重振り子の原理で打ちたいんですけど…」とご託を並べるぼくに対し、コーチが最初にやったのは「球を出します。それを追いかけつつも、最後、ラケットで打たずに見送ってください」という練習。「どうです? 打たないで見送ると、胸がザワザワ、ザワザワってしませんか? それこそがボールを打つタイミングなんです」
一見スピリチュアルな(笑)このトレーニングの狙いを聞くと「山田さんはどうも打ちたがり過ぎる。自分のフォームのことばかり考えている。でも本当はもっとボールを主役にすべきなんです。飛んでくる球をよ~く観察して、観察して。結果それをどう打つか、なんてことはカラダが知っています」。
たしかに、ぼくたちの脳みそは並行していくつものことを同時に考えることができません。にもかかわらず、不規則に飛んでくるボールを相手のいないところに狙って打ち返すような複雑な動きができるのは、すべての情報を脳みそが瞬時に理解・判断しているというより、カラダのチカラなのでしょう。

カラダには、アスリートや職人さんの「勘」に代表されるような「身体的思考」をする能力があります。しかし自然のなかでの直接的な経験が減り、理性的であること、客観的であること、欲望をコントロールして生産的であることを求められる現代人は、「カラダが知っている」という実感を失いつつあるようです。
明治大学の齋藤孝先生は「腰肚(はら)文化の喪失」を指摘しています。日本人は伝統的に「腰を据える」「肚(はら)を決める」といった感覚を、文化を通じて身に付けていた。しかし戦後、その伝承は途切れてしまったというのです。先生は慎重にイデオロギー論を排しながら、日本文化に伝統的な身体感覚の訓練法を再評価すべきだと主張なさっています。
ぼく自身は人生で一度も筋トレをしたことのない軟弱者ですが、スポーツは「カラダが知っている」こと(あるいは「脳みその限界」)を知る良い機会です。文部科学省のホームページによれば、体育科目の目的は持久力や集中力、柔軟性といった「身体能力」、チャレンジ精神やフェアプレーなどの「態度」、そして運動に関する「知識、思考・判断」を学ぶことにあるそうです。しかしスポーツの経験を通じて身体感覚を鍛えることは、ここで挙げられた他の「目的」に勝るとも劣らない価値があります。せっかくオリンピックが東京にやって来る2020年に向けて、いま一度スポーツの意義を議論すべきでしょう。
この暑さの中、まわりから「そうちゃん、痩せた?」と心配されるほど頻繁にテニスをやり続けていますが、残念なことに「カラダが知っている」はずのショットの精度はまったく向上していません。ひたすらに大量の汗を流し続ける目的はただひとつで、テニス後のキンキンに冷えたビール。その悪魔的な旨さと言ったら!!
なんか前にも増して不健康な生活を送っている気もしますが、それもまた人生。今しばらくはテニス三昧で参ります。
どうぞ、召し上がれ!