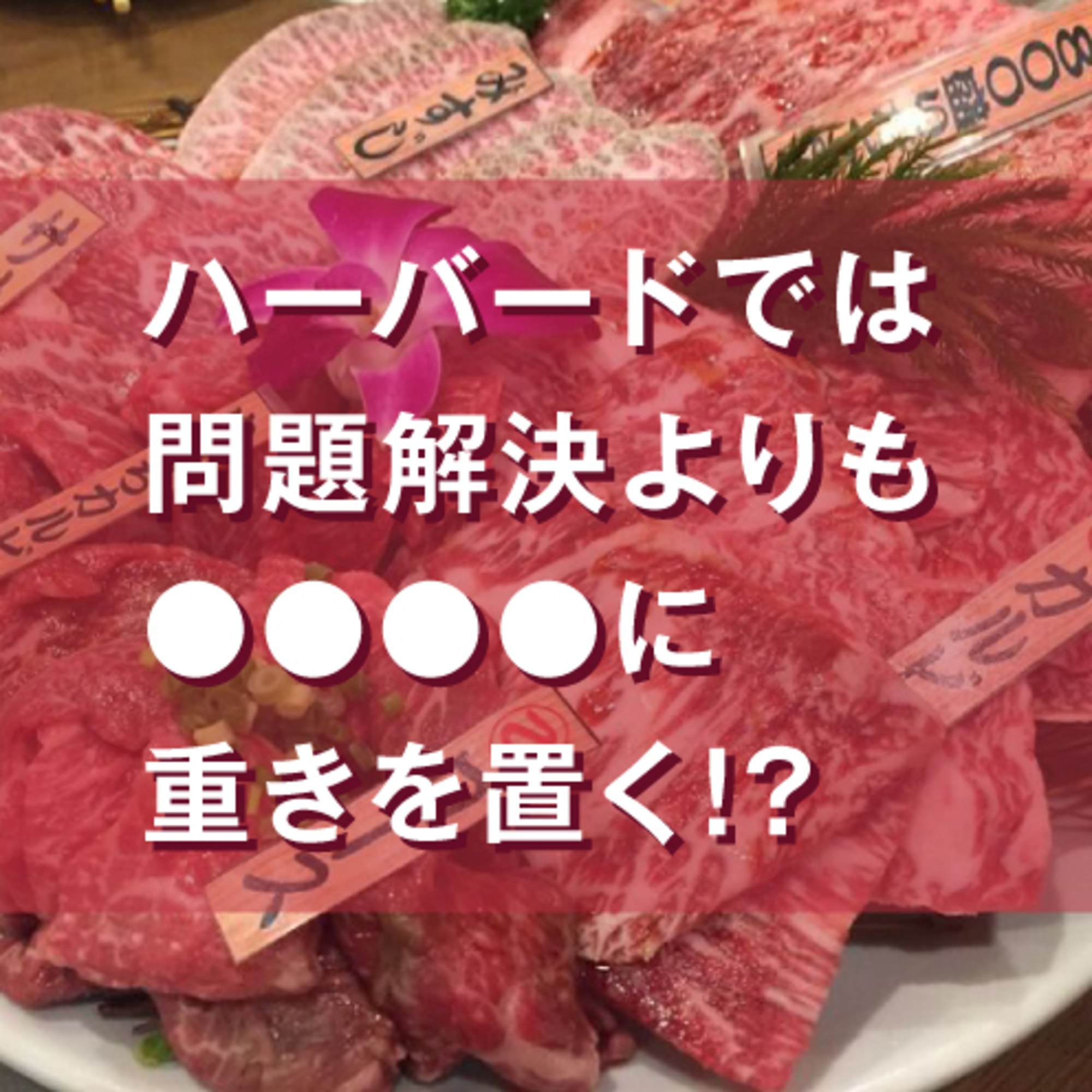学生時代の可児さん
大阪で活躍するコピーライターの可児なつみさんは、美大の学生時代、京都の中華料理店でアルバイトをしていました。その可児さんから「京都って、意外に町の中華屋さんがオススメなんですよ」と言われてはいたものの、限りある胃袋は鯖寿司やにしんそば、こってり濃厚なラーメンや豊かな牛肉文化を楽しむので精いっぱい。なかなか口にする機会がありませんでした。でもその言葉が頭に残っていたからでしょうか、たまたま本屋で『京都の中華』(幻冬舎文庫)を手に取ったのでした。
この本は、今まで京都の方々が体験的に蓄積してきた感覚を丁寧な取材によって「コトバ」にしたものです。たとえば、その中華の特徴は「静かな味」だと言います。お座敷や職人の仕事場に「におい」を持ち込むことが厳禁だったため、にんにくや強い香辛料を使わないこと。水が良い土地柄だけに中華ハムや豚骨を煮立たせて濃厚なスープを取るのではなく、良質な昆布と鶏ガラから透明感があって上品なだしを引くお店が多いこと。仕事を感じさせないのに、実はとても手が込んでいること。店内がいつでもきれいに掃除されていること。そういった事実を紹介しながら「静かな味」の正体を解き明かしてくれます。
先日、関西へ行く機会があったので、早速いくつかのお店に足を運びました。「カラシソバ」は、ゆでた中華麺をカラシ醤油で和え、海老や鶏肉、レタスや青ネギがたっぷりのあんを掛けたひと皿。混ぜようと箸を入れた瞬間、立ち上る湯気にムセるほどのツーンとした香り。それでいて口にすると全体としては薄味で、スルスル食べられました。
カラシといえば「からし鶏」(お店によってはカラシミソ)も珍しいメニューでした。鶏のから揚げに、ピリリと唐辛子が効いたやわらかい酸味のあんが掛かっています。ハルマキも玉子の風味が香ばしい皮が特徴的で、たけのこの千切りをたっぷり包んでいたり。どれも「これ、懐かしい!」感じがして、でも冷静に考えるといままで食べたことがない、そんな味わいでした。
以前、ある食品会社のプロジェクトの一環で中華料理と地域性の研究をしたことがあります。名古屋は中華でも八丁味噌的な濃厚な味つけがお好き。九州は「水炊き」とか「筑前煮」とか「皿うどん」とか、郷土料理と中華の境界が曖昧。北海道といえば茶色い「あんかけ」。そうそう、地域によって八宝菜は白いか、茶色いか。麻婆豆腐は絹か、木綿か。かに玉のあんは赤か、白か。そんな大問題もありました。(笑)関東は法事のような機会にちょっと上等な中華飯店を利用することが多いのに対し、関西は中華の存在がもっと身近で生活の中に溶け込んでいる。そんな内容でした。今回『京都の中華』という本を片手に実際にそれを食べてみて、関西らしい生活に溶け込んだ中華を実感することができました。
一方、この本の「あとがき」には次のような記述があります。
どうか本書を手に取った広告代理店や雑誌編集者のみなさま、「京都の中華」を「京都中華」と略称し、ハッシュタグにしてしまわないでください。本書で紹介されている店をしらみつぶしに訪れ「あっさりしてるでしょう、これは花街でね……」などとウンチクをたれるのではなく、京都に来れば近くに知人が住んでいるから毎回ここ、という必然性のある「付き合い」をしてください。
これはなかなか耳の痛いご指摘です。広告会社の強みは(『京都の中華』著者の姜尚美さんがなさったように)感覚的なものを言語化する能力にあります。そして、しばしばそのコトバをテコにブームを仕掛け、ビジネスを拡大してきました。しかしコトバにするという手段は本来、たとえばその文化を守ることや、今までにない文化を創造することなど、もっと多くの目的に役立つはずです。
コトバにはひとを動かすチカラがあります。そのことに対する自覚が足りないと、結果としてその文化をただ「消費」してお仕舞い、なんてことになりかねません。
今回伺った京都の中華料理屋さんとは、こっそり、静かに、長いお付き合いをしたいです。そしてあのメニューが頭に浮かぶたびに「コトバにする責任」ということを思い返そうと思います。
どうぞ、召し上がれ!