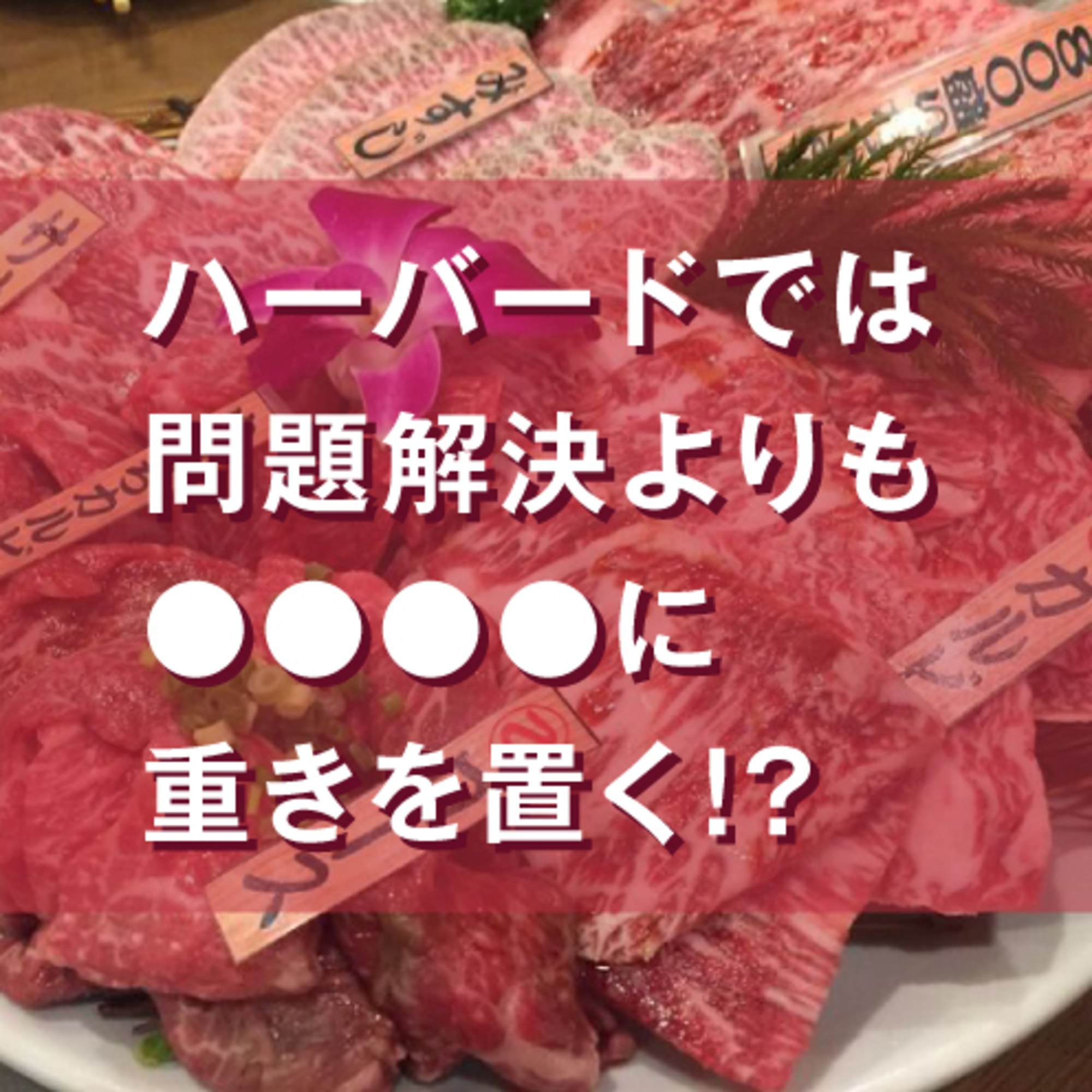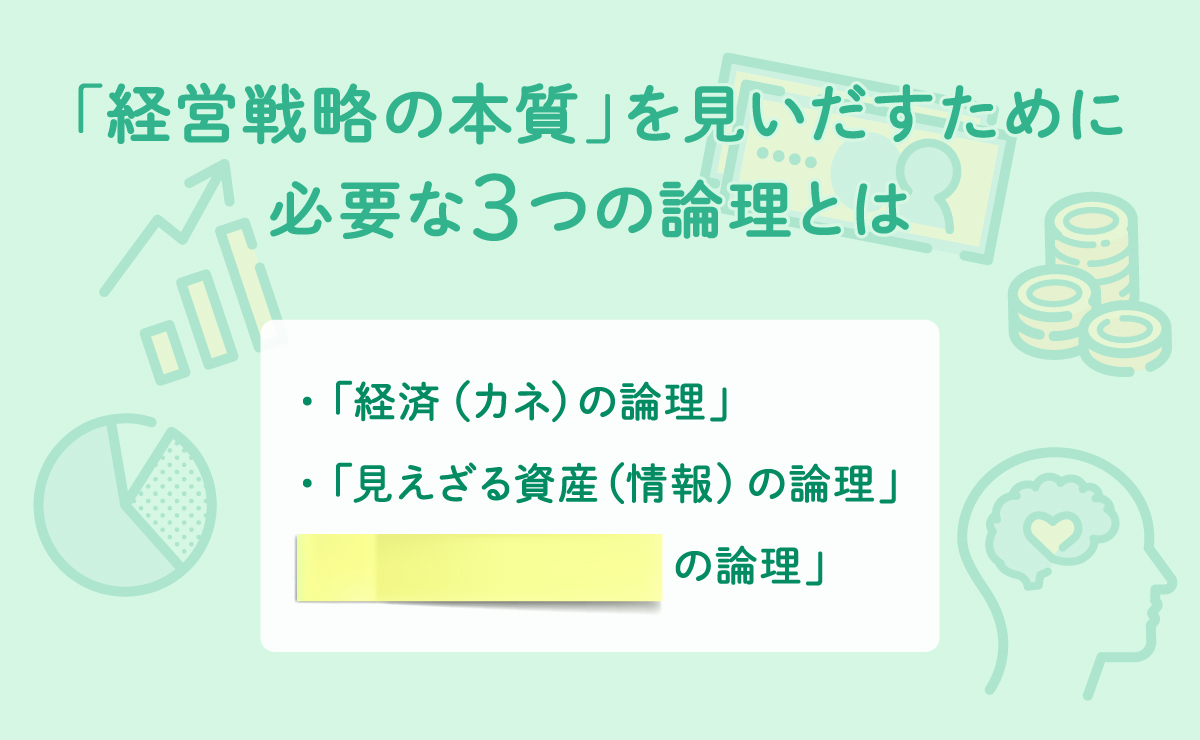アートディレクターの工藤章子さんは将来の2拠点生活を目指して八ケ岳のふもとにも家を持ち、森の暮らしを満喫しています。それがうらやましくて、うらやましくて、今年の夏、お邪魔しちゃいました。以前このコラムでもご紹介した「ひまわり市場」で買い込んだ新鮮な野菜を持ち込んで料理をつくり、それをさかなに地ビールや甲州ワインを堪能。身も心もとろけちゃいました。
さて。章子さんといえば「わたし、『台風クラブ』を見ても、正直ピンと来ないんです」のひとことが忘れられません。
「台風クラブ」とは相米慎二監督の映画(1985年)。当時から工藤夕貴さんのファンだったぼくは、完成の知らせを聞いた後もなかなか公開日が決まらず、やきもきした覚えがあります。その後しばらくして、第1回東京国際映画祭のヤングシネマグランプリを受賞。「大人から抑圧されて鬱屈した気持ちを、台風をきっかけに爆発させる」というその内容は、当時十代だったぼくの心をつかんだだけでなく、普遍的なテーマとして時代を超え、広く世界からも愛されている…と信じて疑いませんでした。
ところが章子さんいわく「大人からの抑圧って、正直あまりピンと来ないんですよね。それよりわたしは『桐島、部活やめるってよ』(2010年)ですよ」。なるほど「桐島」は生徒同士のスクールカーストと同調圧力を描いています。そこには絶対権力者であり反抗の対象でもある大人の気配は希薄です。う~む。
ぼくは「人間なんて、そう簡単に変わるもんじゃない」と信じています。いまも昔も光源氏はモテるでしょうし、世界中どこに行ったって『ヴェニスの商人』の金貸しシャイロックは嫌われるでしょう。あるいは1960年代のアメリカで広告会社DDBがつくった傑作キャンペーン(たとえばフォルクスワーゲンの「Lemon」「Think small」など)は、いまでも十分に機能しそうです。
テクノロジーの進化とともにメディアの環境は変わっても、人間の本質というか、ひとの気持ちが動く仕組みは変わらないと思うわけです。ですからたとえば研究機関のレポートに「全く新しい生活者の台頭」なんて文言を見ると(内容は大いに参考にしますが、同時に)「ちょっとタイトルがオーバーなんじゃない?」と意地悪を言ってみたくなるのです。
その一方で、やっぱり「ひと」というものが時とともに変わっていくことも、また認めざるをえません。ぼく自身も「桐島」を楽しんだように、それは「昨日まであった感覚が、ある日消滅する」とか「いままで存在しなかった感情が、突如生まれる」いうほど劇的ではないのでしょうが、ある種のバランスは確実に揺れ動きます。
コンセプトづくりの前半戦(ぐるぐる思考でいえば感じるモード&散らかすモード)で必要とされるのは、身体的な思考です。ここでは客観的な正論だけでなく、いかに感覚や経験といったフワフワしたものを取り入れるかがポイントになります。
拙著『コンセプトのつくり方』では、このプロセスを「ココロの中に住まわせた『こびと』との対話」に例えて説明しました。「こびと」とは、このターゲットならこんな反応をしそうだな!という感覚の集合体。ぼくの中の「こびと」が現実の写し鏡として生々しい機微を保ち続けるためには、ぼく自身が常に多様な価値観に触れ、それを「良い」とか「ダメ」という価値判断することなく、丸ごと受け入れる度量を持たなければなりません。
工藤章子さんの魅力は、いつでも率直なこと。「山田さん、古いナ!」と言ってくれるので、(時として大いにへこみますが)とってもありがたい仲間です。その彼女も9月にかわいらしい女の子を出産、ママになりました。現在育児休業中ですが、そろそろ紅葉が美しくなっているだろうあの森へ、おしゃべりに出掛けたいゾ!
どうぞ、召し上がれ!