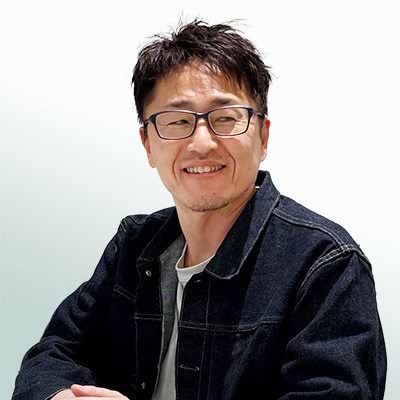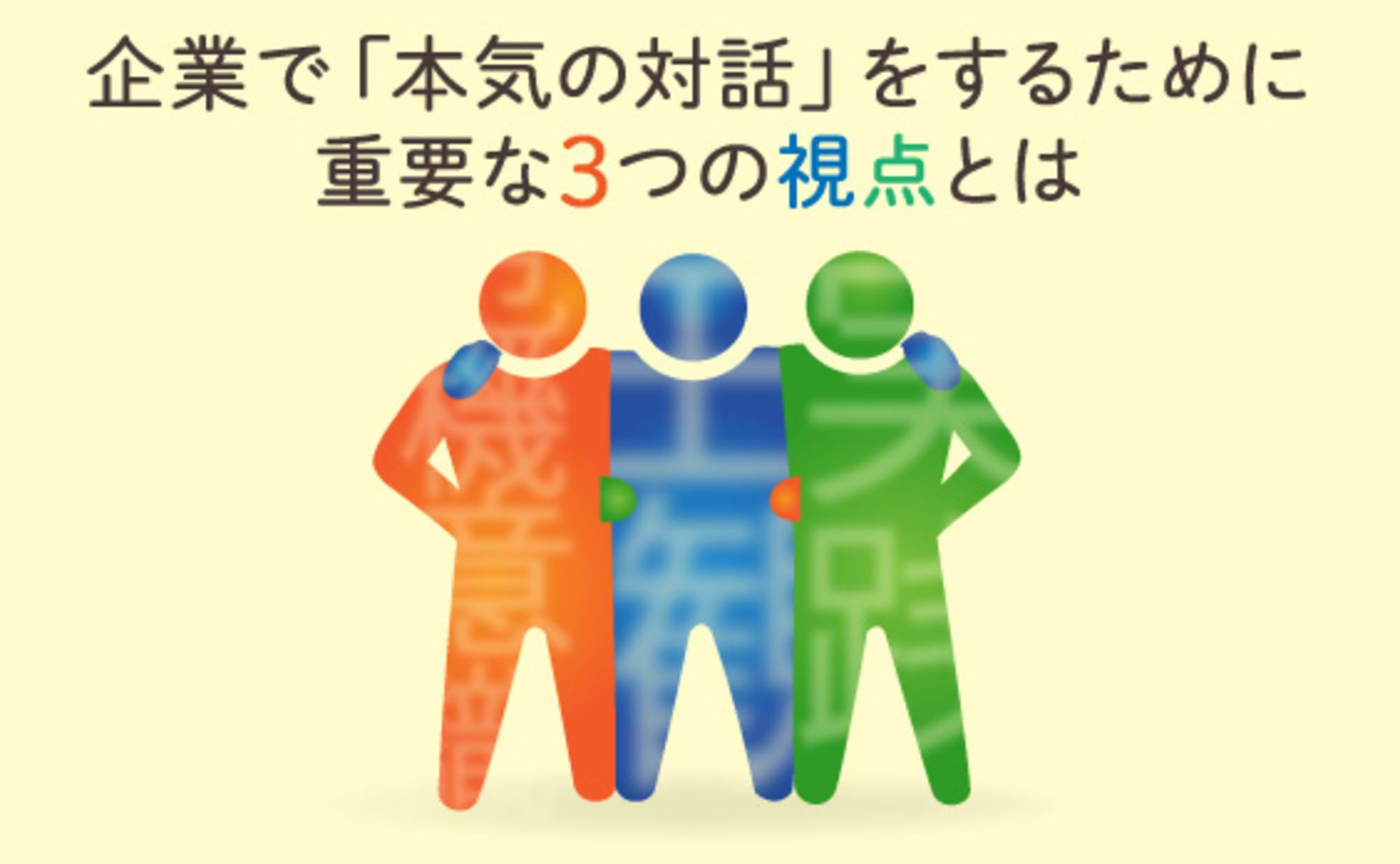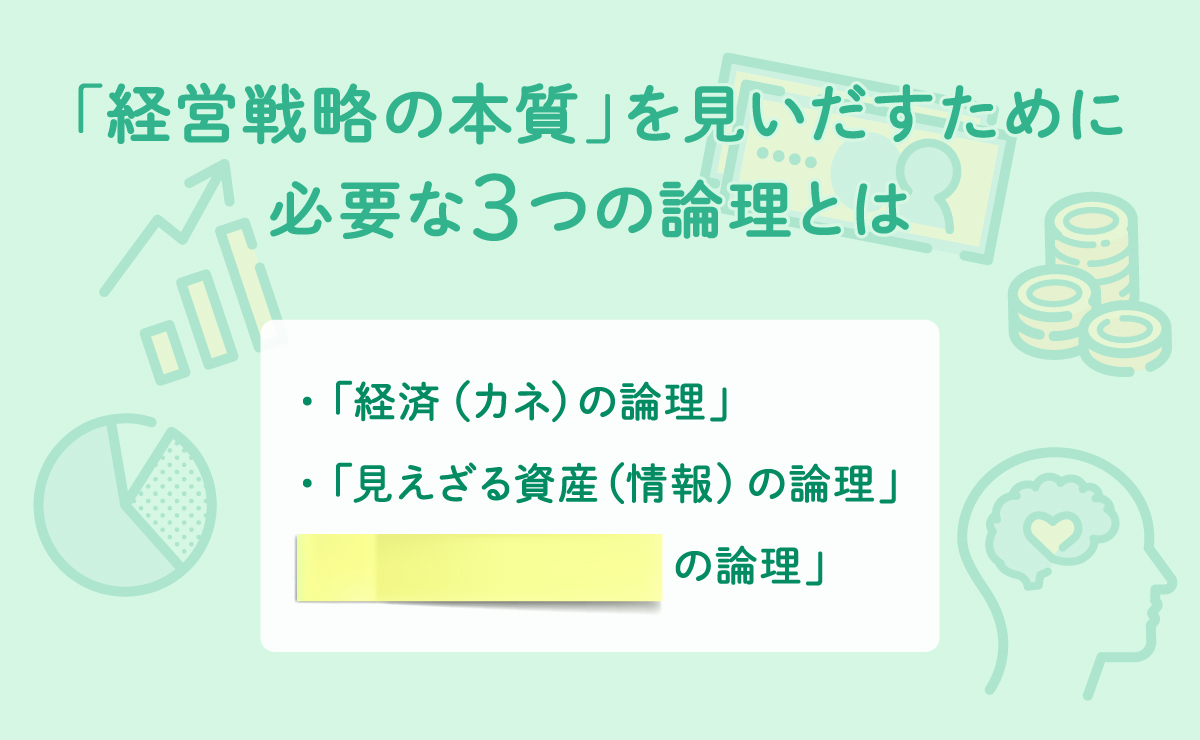近年、電通グループ内で「アイデアという商品は何を指すのか?」「どうやって作って、どうやって品質管理をし、どのようにお客さまの手元までお届けするのか?」などなどについてざっくばらんな対話を重ねる「Creative Dialogue」という会をやっています。
要はこのコラムに書いていることを、5~6人くらいのメンバーで集まってあれやこれや、のべ300回以上、話をしているのです。
今回は連載200回を記念し、そんな仲間の中からマーケティング、プロモーション、クリエイティブ、プロデューサー、デジタルなどさまざまな分野の(お互いに「はじめまして」の)プロフェッショナルな皆さまに集まっていただきました。
クリエイターの仕事は、クラフトだけではない
本日のタイトル「アイデア産業の仲間たち」には由来がありまして。電通の先輩、杉山恒太郎さんはかつて“アイデアが日本の誇る輸出産業となる日が来る”とおっしゃっていました。
そしてぼくはそれに刺激を受けて最初の本「〈アイデア〉の教科書」を書きました。今、電通グループ内でCreative Dialogueと称して「アイデア」に関する対話を重ねているのも、すべて杉山さんの言葉を心から夢見ているからなんです。

いつでもクライアントの課題と真摯(しんし)に向き合う戦略家
Creative Dialogueではアイデアを「表現のアイデア」と「構造のアイデア(コンセプト)」に整理しています。わたしは電通東日本でストラテジック・プランナー(以降ストプラ)として戦略を考える部署にいるからこそ、この「構造のアイデア」あるいは「コンセプト」といわれるものが大好きです。
ストプラというとアカデミックというか、難しいことをこねくり回している印象があるかもしれませんが、「構造のアイデア」を生み出すクリエイティビティにこそ、大きな責任があると感じています。

ある時は理論派、あるときは情熱家。可能性無限大のコピーライター
ぼく自身は「構造のアイデア」みたいな部分をもっと意識的に考えていきたいです。もちろんクリエイターとして「クラフト」と呼ばれる見せ方とか表現の工夫もめちゃくちゃ大事にしていますが、そこだけにこだわっちゃって、「なんかいい感じの表現を作る人」みたいなポジションに収まりたくはないなって思っています。
“新しい価値を生み出す”ところは、クリエイティブもマーケティングも関係なく、本質的にすごく大事なことだと思うんですよね。
のっけから面白いお話ですね。北海道の現場から見ると、いかがですか?

クライアントからの信頼が絶大な「北の大地」のクリエイティブ・ディレクター
Creative Dialogueを通じて一番感じているのは、アイデアを形にしていくのには「型」があるということです。もしかすると、クリエイティビティは今まで「個人の技」に頼りすぎていたのではないでしょうか。
例えば「コンセプトとは何なのか?」という、今まで当たり前すぎて考えてこなかったことをしっかり見つめ直すだけで、マーケティングでもクリエイティブでも、もっとみんなで意見をぶつけ合う、もっとみんなで動く「型」が手に入ると実感しています。

ニコニコ笑顔でロジックとアイデアを語るアカウントマネージャー
わたしはCARTA ZEROでデジタルコミュニケーションを中心に担当しているのですが、いまだに媒体起点というか、「YouTubeで発信するならこんな表現がいい」「クリックしてもらいたいならこの表現にしましょう」といったように、オンライン媒体になった瞬間、どうも定量でだけ評価される傾向があると思います。
そんな中、「コンセプト」をしっかり言語化していくことで、オンライン媒体とオフライン媒体の統合はもっと効果的に進むんじゃないか、と考えています。
Creative Dialogueの中では「もし日本の喫茶店が、自分たちのサービスの本質を『サードプレイス』と言語化できていたなら、スターバックスに代わって世界を席巻していたかもしれない」というお話が印象に残っています。やはり、自分たちがつくった価値をしっかり“言葉でつかまえる”ことは、とても重要だと思います。
そうですよね。どんな案件であれ「コンセプトが何であるのか?」はっきりさせることの良い点は、作業の無駄がなくなることです。本質的なコンセプトが何であるかが曖昧なまま、なんとなく“耳触りの良い言葉”を「コンセプト」として戦略の中心に置いちゃうと、結局、その案件に取り組んでいるうちに方向性が見えなくなり、迷子になるんです。
なるほど、マーケティングとクリエイティブ、オンラインとオフライン、それらをつなぐ上位概念として「コンセプト」が重要だということですね。それは当然といえば当然なのですが、「コンセプトが何であるのか?」をはっきりさせることはチーム力を向上させるカギになりそうだ、という感じでしょうか。プロモーションのプロから見ると、いかがですか?

チームを優しく見守り、温かくリードするアートディレクター
わたしは「コンセプトは、サーチライトである」というお話が一番印象に残っています。高山さんもおっしゃる通り、日々の作業ではうっかり「すてきなコピー」を「コンセプト」と混同しちゃうケースもあったんですが、まさにサーチライトとなって、仲間に対して進むべき方向を照らし出す言葉がコンセプトなんだと理解しています。
全体を俯瞰(ふかん)して「構造」として捉えることがクリエイティブ・ディレクターの仕事だし、またチームメンバー全員が構造を意識することで、現場のクリエイターの成長もより確実なものになると思っています。
確かに気の利いたキャッチコピーがあると、「それが、コンセプト」って言いがちですね。
安田さんはプロデューサーという立場から、いかがでしょうか?

冷静沈着な行動の裏に、常に熱い思いをたぎらせるビジネスプロデューサー
日ごろのキャンペーン開発業務の中で、それが「良いクリエイティブかどうか?」という判断と、それが「クライアントにとって良い結果をもたらしそうか?」という判断はどちらも重要なのですが、ともすると感覚的になりがちでした。そんな中、皆さんのお話にあった「表現のアイデア(クラフト)」と「構造のアイデア(コンセプト)」を整理することによって、明確な軸を示しながら冷静にチームを牽引していけそうだと思っています。
これからビジネスプロデューサーとして経営課題に向き合うときにも、それは大きな判断軸になりそうです。
「コンセプトの品質管理」という考え方と出合って
さて、Creative Dialogueの中では皆さんと「コンセプトの品質管理」をするための5つの基準について話をしていますが、特に印象的なものはありますか?
この①ですね。コンセプトが「新しい視点」になっているかどうかを考えるときに、「古い視点(常識)」がわからないと「新しい」かどうか判断できないという点は、シンプルに新鮮に感じました。
Creative Dialogueではコンセプトの話をするときに、必ず「サーチライト」の図が出てきて、それにのっとって話をするように求められますもんね。
そこで感じたのは、「古い常識」っていうのは「変えるべきふつうのこと」「当たり前のこと」なので、実は「それを変えた方が良いよね」ということに気が付けるかどうかがスタートラインだし、とても大事だということです。実は「変えるべきふつうのこと」がわからないから「新しい視点」としてのコンセプトが見つからない、ということが結構あるんじゃないかと思いました。
一つ質問があって、実際の仕事でこの「5つの基準」全てをかなえるのは、すごく難しいと思うんです。あえてお聞きしたいのは、この5つの中で「これを満たしていれば上出来」みたいなものって、あるんですか?
全てを満たしている必要はない気はするけど……
たぶん、①古い常識を覆しているから②新しい悩みが見つかるし、②新しい悩みが見つかっているから④市場規模とか「数字」が推計できるし……というように、5つの基準は互いに独立しているというよりは、相互連携していると思うんです。その意味では②だけ、とか④だけ満たしている状況というのが、ちょっと想像できません。
一方で、ぼくも芳田さんに賛成なのは、「すべて満点」という状況も、これもまた想像しづらいということです。
なぜなら各案件において、完璧な言語化なんて、まずできません。そして世の中がどんどん変化していく中で、そのコンセプトが描くお客さまと商品・サービスの新しいつながりの意味も、日々刻々、どんどん変わっていく。
昨日80点だったものが、きょう40点になっているかもしれない。その意味で、ぼくらが取り組むのは「絶対的に正しい答えを手に入れて満足」ではなく、「いま、ここ」での最善を探しながら、一方でとりあえず手にしたものは「仮説」に過ぎないことも知りながら、永遠のスパイラルを旅するような、そんな仕事だと思うんです。
「とあるCDが、企画時でも提案時でも制作時でもなく、実施後しばらくしてコンセプトを言語化した」。つまり実はその時までコンセプトを言語化できないけれどあきらめないで考え続けていた、というエピソードがありました。
通常コンセプトは、ある種の分析から生み出されると思われがちですが、そうでなくて「表現」のようなアウトプットから逆算しても良いのだ、と。これはまさに「いま、ここ」での最善を提案したとしても、その後も引き続き考え続けなければならない、ということかもしれないですね。
「コンセプトの品質管理」をするための基準は、もっと精緻化できる
①と②、そして③〜⑤は、同じ「良きコンセプトの類型」でも、ちょっと種類が違う気がしていて。後者の「方向性」と「数字」と「理想」は、まさしく「コンセプトの品質管理」のために必要なものです。でも前者の①と②は、良きコンセプトを新しく考えるときに最初にぶつかる壁のようなもので、ここを乗り越えるのがめちゃくちゃ大変なんですよね。
だからこそ、チーム全員でちゃんとマーケットと向き合って、一緒に考えていかないと、本当にいいものってなかなか出てこないなって思います。
たしかにこの①~⑤は、そこに何かを流し込めば自動的に答えが出てくるようなフレームワークではないですよね。だからこそ、やりがいがあるのですけど。
ぼくも藤本さんと同じようなことを感じています。①と②、そして③と④と⑤は種類が違う。そして、たとえば⑤のその組織が目指すべき「理想」は「コンセプト」を考え始める切っ掛けにはなるかもしれないけれど、④の売上高や利益額といった「数字」は企画の出発点にはなり得ない。なんとなく①②から始めて③④⑤に流れていくイメージです。
そうですよね……。実はこの5つの基準については、Creative Dialogueを始めた4年前は言葉つきや内容が今とは違うものでした。皆さんとの対話を通じて、今でも少しずつ育てている最中なんです。さっきもお話ししたように5つの要素が必ずしもMECE(モレなく、ダブりなく)になっていなし(笑)。例えば並べる順番も④の数字と⑤の理想、どっちを先にしようかなぁ、なんかコンセプトのお話が数字で終わっちゃうのは楽しくないのかなぁ……と悩んでいます。
ぼくはちょっと違う意見で、④の「数字」がとても大事だと思っています。クライアントは限られた予算の中で、どうやって売り上げを達成するかを真剣に考えていらっしゃいます。だからこそ、ぼくらにはアイデア(コンセプト)という一見頼りない言葉が、いかに数字に貢献するかを説明する大きな責任があると思います。数字で説明できれば、それはつまり「市場を創造できる」という「大きな夢」につながるので、ぼくはこの④が一番好きです。
自分の企画が「ひとりよがり」にならないための視点として、④の「数字」は大切ですよね。
結局、クライアントにそのコンセプトの価値を明確に伝えられるかということが、その企画をお買い上げいただけるかどうかの大きな分岐点になります。その意味では、高山さんのおっしゃっていることは、とてもよくわかります。
⑤では「理想」を「実現する」と書かれているけれど、④の「数字」は「約束」ではなく「予感させる」なんですよね(笑)。
デジタルをやっている立場からすると、「数字」といってもいろんな「数字」がありますよね。例えばスターバックスの「サードプレイス」をテーマに企画をするなら、「自分の居場所」なのだから、「どれだけの人がアプリでポイントをためたか?」なんて話じゃなくて、「どれだけの人がメニューを自分好みにカスタマイズをしたか?」といったように、測定指標自体も今までにない、クリエイティブなものになりますよね。
ちなみに、この評価基準①から⑤みたいなものを、日ごろの業務に生かしている方って、いらっしゃいます?
戦略立案を担うストプラとしては、今やっているプロジェクトにも、そのまますぐに生かしています。
ぼくもCreative Dialogueで「あぁ、きょうも山田さんと楽しく話したな」で終わらないように、できるだけ実践に生かそうと思っています。この前も、あるプレゼンで、ここで話されている「型」をすごく意識したりしました。
ありがたいことです。そうやってどんどん皆さんに実践していただいて、そしてまたフィードバックを頂いて、例えばこの「コンセプトの評価基準」についても、もっともっと精度を上げていかなければならないですね。
「アイデア産業」を前に進めよう
Creative Dialogueで皆さんと話し合っている「アイデア」「コンセプト」を武器に、これからどんなお仕事にチャレンジしたいとお考えですか?
新しい仕事の前にまず、Creative Dialogueの対話を通じて日々の業務を見る目が変わってきている点を一番実感しています。その上で、事業や商品のブランディング全体や、いわゆる経営課題に関するご相談に対しても対応する準備ができてきていると感じます。
大きなクライアントの仕事で、しっかりとしたオリエンが用意されており、それにいかに返すか?というお仕事も大切です。一方で、まだどこに課題があるかもわからない状態でご相談を受けて、商品コンセプトから経営方針まで伴走するプロジェクトにも取り組んでみたいと思っています。
ぼくは広告や商品・サービスとして「良いもの」を目にした時に、「なんかいいなぁ」で片づけることを禁止するために「コンセプト」が有効なのだと思っています。「なんかいい」と感じるものには、必ずしっかりしたコンセプトがあるはずで、それをちゃんと捉えられるようになりたい。そのためにも、“コンセプトをつくる技術”を、もっと使いこなしていきたいですね。
わたしはコンセプトを活用してオンラインとオフラインをしっかりつなげていきたいです。その両者の体験が一致して、ブランドに一貫性をもたらすことが大切です。当たり前のことではあるのですが、現実にはもっともっと高い質のコミュニケーションを目指せると思っています。

ぼくたち電通北海道は、クライアントの皆さまからまだまだ“広告屋さん”だと思われているんです。「川上からやりますよ」とか宣言したところで、そういう目で見てもらえていない。一方でマンネリ化した何かとか、売り上げが止まっちゃっていることに悩んでいるクライアントが確実にいることも事実です。
だからこそそういった企業で何ができそうか、広告コミュニケーション領域を超えて、自分自身で考えて、話をしてみる。それを先方が喜んでくれて、結果ブランドの根幹、企業の根幹に触れる何かができるような仕事をしていきたいと思っています。
やりたいことは二つあります。まず、電通東日本もまだまだ“広告屋さん”なのだと思います。「事業価値を再定義してほしい」とか「ビジネス・トランスフォーメーション(BX)をやりたい」と言っているクライアントは、多くない。基本的に求められているのは「広告コミュニケーション」なんです。
でも、クライアントはその奥で、潜在的にビジネスの在り方で悩んでいたりします。そうしたとき、「この一つの商品を、どうやって売ったら良いか」という仕事の延長線上としてビジネスの潜在的な悩みも解決していく、そんな仕事をやっていきたいです。
二つ目は、作業上の「無駄」をなくしていくことです。さっきも話題になりましたが「かっこいい言葉」と「コンセプト」を混同すると、確実に作業の効率が悪くなります。だからこそ「コンセプトの品質管理」を理解する仲間の輪を、クライアントも含めて広げて、そうした無駄を排除していきたいです。
わたしは会社のクリエイティブセクション自体を盛り上げたいです。手前みそですが、うちのメンバーってけっこう「優秀」だと思うんです(笑)。そういったメンバー一人一人がもっと自身の能力を高められるように、「構造のアイデア」のような根本から考えて取り組む仕事を会社内に増やしていきたいと思っているので……どしどしお仕事ください。
“広告屋さん”であることももちろん素晴らしいのですが、やはり「ぼくらはクリエイティブの会社だ」と胸を張って言える存在になっていきたいですね。
きょうはいろいろなバックグラウンドを持つ皆さまに集まっていただきましたが、それぞれの専門領域を超えてしっかり「コンセプト」が共通言語になっていることが心強いですよね。このメンバーでチームをつくったら、とてつもなく良い成果が上がる気が。読者の皆さま、お仕事をお待ちしてます!!(笑)
【メンバー紹介】
高山 勇輝
電通東日本 ストラテジック・プランナー
電通ヤング・アンド・ルビカム(現 電通東日本)入社以来、ビジネスプロデューサーとして飲食、食品、嗜好品などのブランドにおけるマスからデジタルまでの統合的なブランドコミュニケーションに関わり、現在はストラジック・プランナーとして、行政や金融・建設業など幅広く、コミュニケーション戦略立案を手掛ける。
藤本 千尋
電通 コピーライター
2001年、山梨県大月市生まれ。カンヌライオンズヤングコンペティション2024ファイナリスト。
増田 光記
電通北海道 クリエイティブ・ディレクター
札幌のプロダクションから広告業界をスタートし、電通テック(現 電通プロモーションプラス)札幌支社を経て現在に至る。「考えつづける」ことをモットーに、本質課題を捉えた戦略づくり、ストーリー構築、コアアイデアの発見~クリエイティブ表現で、クライアントが抱える課題に最適な解決策を粘り強く探します。現在は、広告クリエイティブの枠を超えて、未来づくりの領域に挑戦中。
松浦 恵
電通プロモーションプラス アートディレクター
神奈川県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒。アートディレクターを軸にプランニングから作るところまで。おいしそう・かわいい・楽しいが得意。3歳の娘と愛猫がいます。受賞はThe GLOBES Awards、CANNES LIONS ショートリスト、など。
安田 桜子
電通アドギア/ビジネスプロデューサー
入社以来ビジネスプロデューサー業に従事。大手飲料メーカー、食品メーカーの担当を経て、企業ブランディング開発、PRプロデュースなども担当。 2024年から株式会社サン・アドに出向、クリエイティブプロデューサーに従事。クリエイティブ制作プロデュースを得意領域としマス広告〜ブランディング・PR案件などを担当している。
芳田 晃一
CARTA ZERO アカウントマネージャー
映像制作会社、電通を経て 2022年からCARTA HOLDINGS。B2CからB2Bまで幅広い案件に携わり、デジタル領域を中心にマーケティング戦略からプランニング、効果検証までの業務を推進。電通グループ横断プロジェクト「電通B2Bイニシアティブ」リーダー。