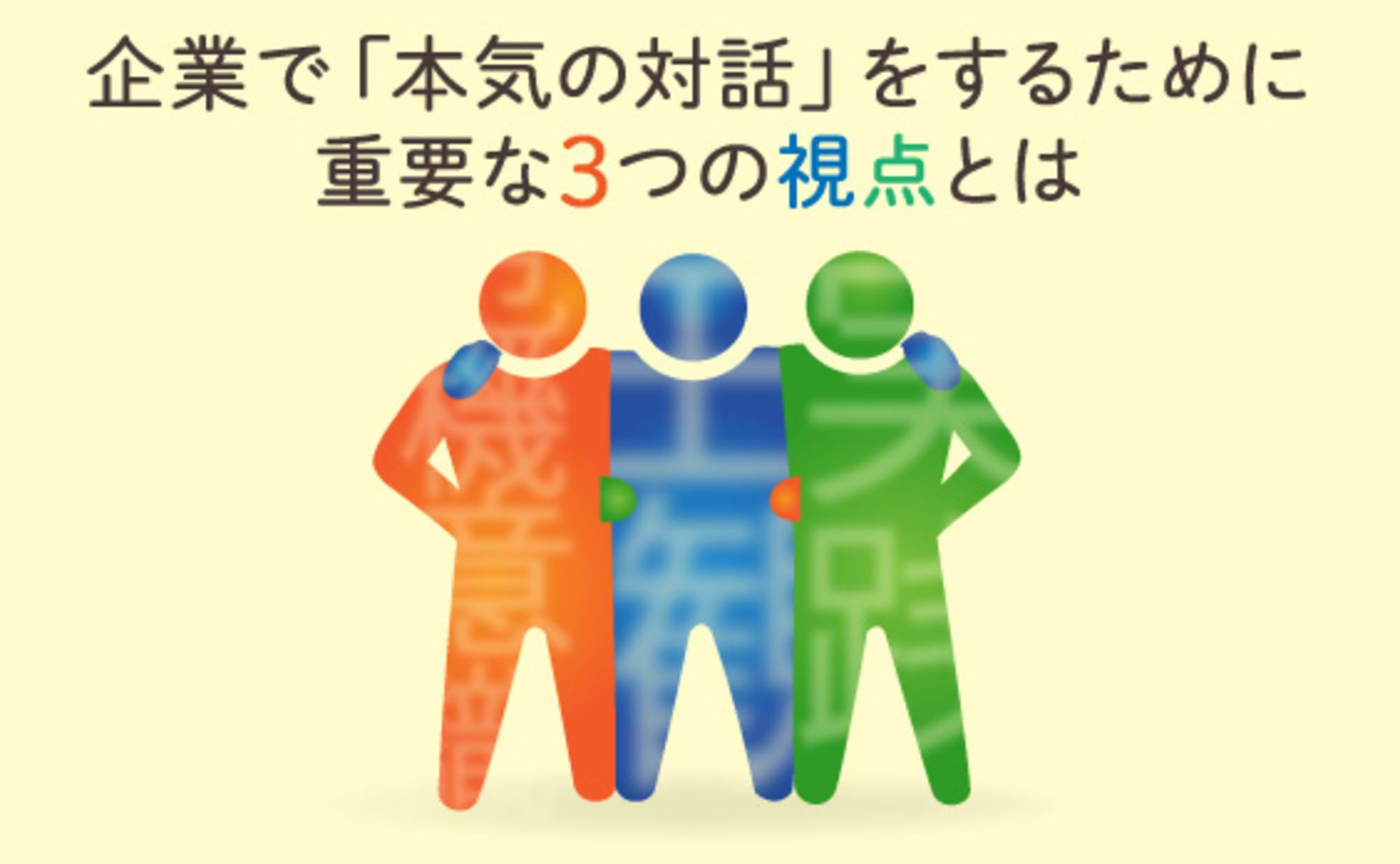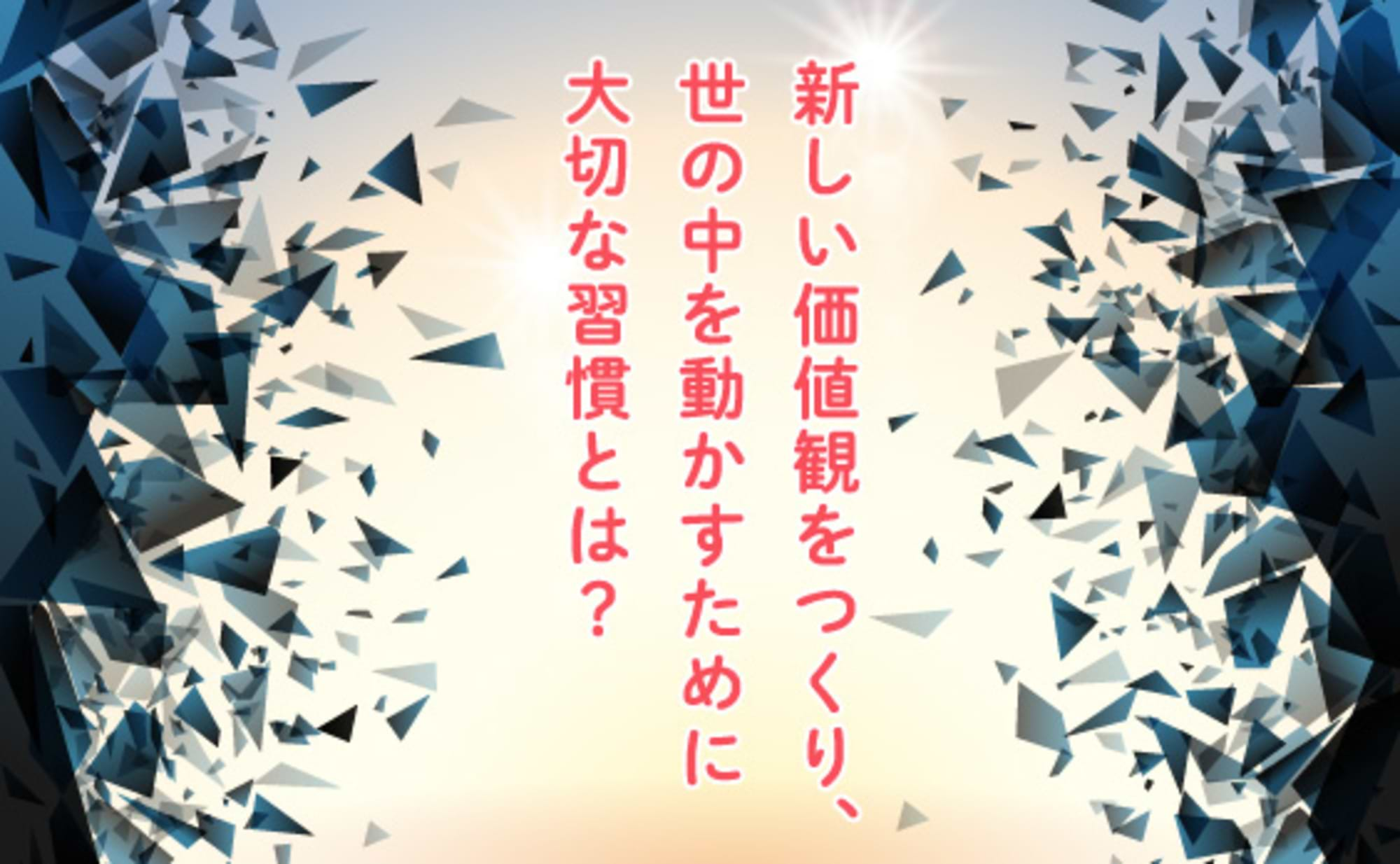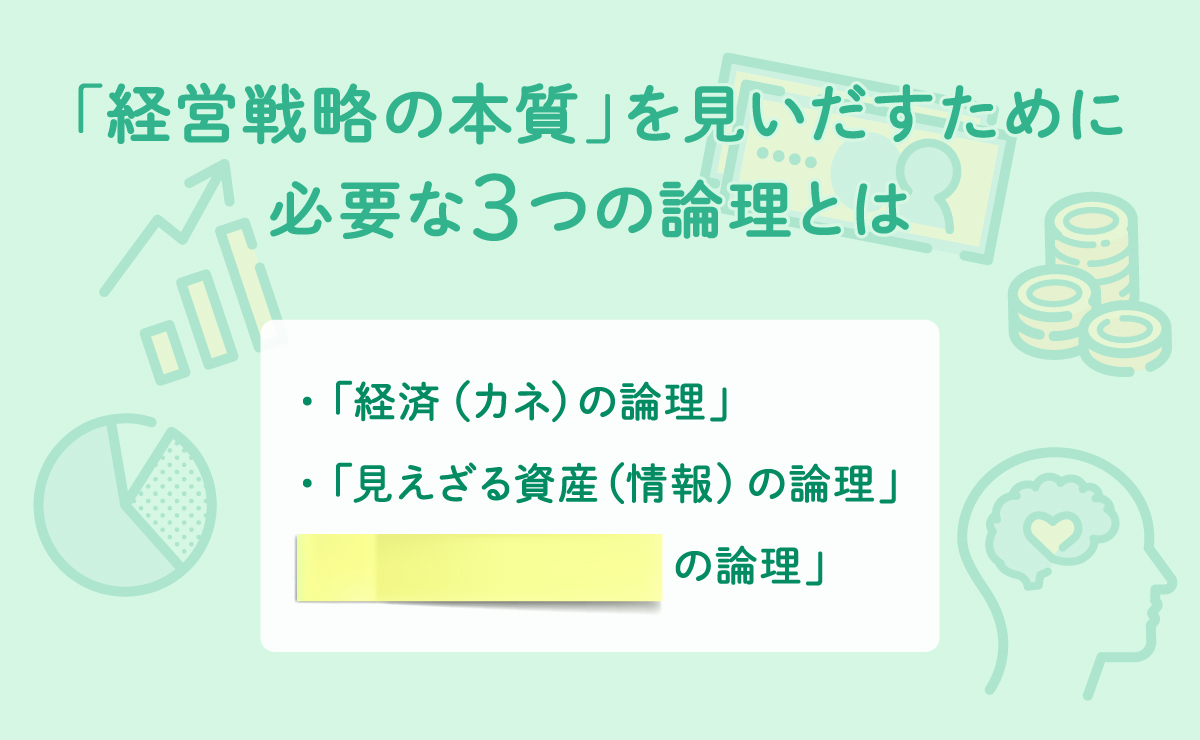むかし、むかし、ある大手食品メーカーで、圧倒的シェアを誇る調味料シリーズの商品開発プロジェクトに参加していた時のこと。
数多くのグループインタビューを実施し、定量調査やPOSデータの結果を徹底的に分析し、プロの料理人にもいろいろなレシピを教わって、数え切れないほどの試行錯誤を重ねて仕上げたサンプルを試食調査に掛けたところ、自由記入欄にも絶賛が並んで、史上最高レベルの「とてもおいしい」スコアを獲得しました。
しかし、チーム全員で大喜びしたのも束の間、聞こえてきた「正式決定」は「この商品を発売することはできません」というものでした。
なぜでしょう?
その理由は、一方で残念なことに5%を超える人が「まったくおいしくない」と答えていたから。そして「魚が腐ったような臭いを感じる」といったコメントが、いくつか並んだからでした。
実はそれには思い当たる節があって、試作品のレシピには少量の「魚醤(ぎょしょう)」を隠し味に使っていたのでした。その独特の風味が、多くの方が「コク深い」と評価する一方で、一定の方にとっては「腐ったような臭い」と答える原因となったのでしょう。
この時、「発売しない」判断をした部長さんがおっしゃったのが「もしかしたら、この商品は売れるかもしれない。でもあの企業がつくる商品は、最近腐ったような臭いがする……なんて評判が立ったら、山田さん、責任取れますか?」という言葉でした。もちろん反論などできるわけもなく、いまでもそのシーンが脳裏に焼き付いています。
実はぼくがこの経験を通じて学んだのは、トップブランドにも付け入る“スキ”はあるということでした。彼らにとっては、ちょっとした悪評も「蟻(あり)の一穴」。嫌われないことにも当然、意味があります。
一方で業界10位とか20位とかの企業であるなら、嫌われる心配をするよりも、誰かに強烈に支持してもらうことの方が大切なはず。極端に言えば、8割の人々には見向きもされなくていいから、たった5%、場合によっては1%の熱狂を徹底的に追求する覚悟が有効です。
ところが実際には、大中小規模、さまざまな企業の方々と商品開発をご一緒しましたが、皆さん共通して、嫌われることを恐れていらっしゃいました。トップブランドと同じことをしていては、業界の秩序を根底から覆すジャイアント・キリングはおろか、目先の利益確保ですら難しくなるでしょう。
戦略の要諦の一つに、競合相手の嫌がることを徹底的にやり抜く、ということがあります。自らがリードする市場で他ブランドが(たとえ一部であっても)「これはうまい!」と熱狂を生むことは、まさにトップブランドが嫌がりそうな取り組みです。今回は「魚醤」にまつわるとても小さなお話でしたが、そこには大きなヒントが隠れていると思います。

「魔法の豆」。
スポーツなどで、格下のチームや選手が格上に勝利する「番狂わせ」。この意味で使われている言葉「ジャイアント・キリング」が、童話「ジャックと豆の木」の原題「Jack the Giant Killer(ジャック・ザ・ジャイアント・キラー)」に由来することを知ったのは、つい最近のことでした。
お母さんが窓から捨てた「魔法の豆」からスタートする冒険譚。しかし改めて読んでみると、ジャックは大男から金貨や金の卵を産むメンドリを繰り返し泥棒しているんですよね。しかも、それに怒って追いかけてきた大男を殺しちゃうわけで。
ジャックを英雄視するストーリーには、いまひとつ釈然としないのですが、それでもやっぱり初夏の蒸し暑い夜は「ビールと豆の日」。以前にも一度ご紹介(※)しましたが、枝豆の「味変」に、ちょっと魚醤を振りかけるのもオススメです。
どうぞ、召し上がれ!

山田壮夫が取り組む「Indwelling Creators」について詳しくは、ロゴをクリック。