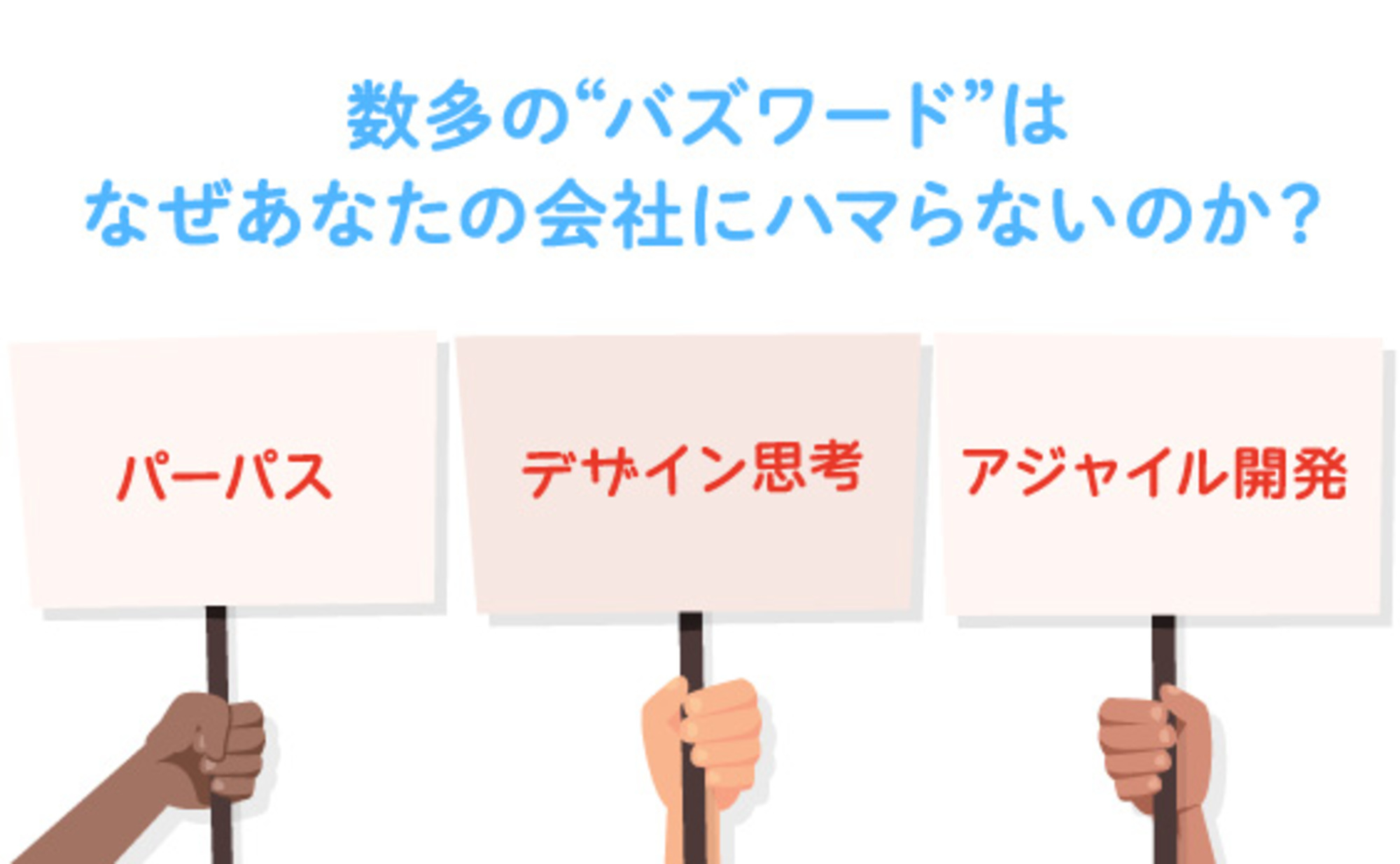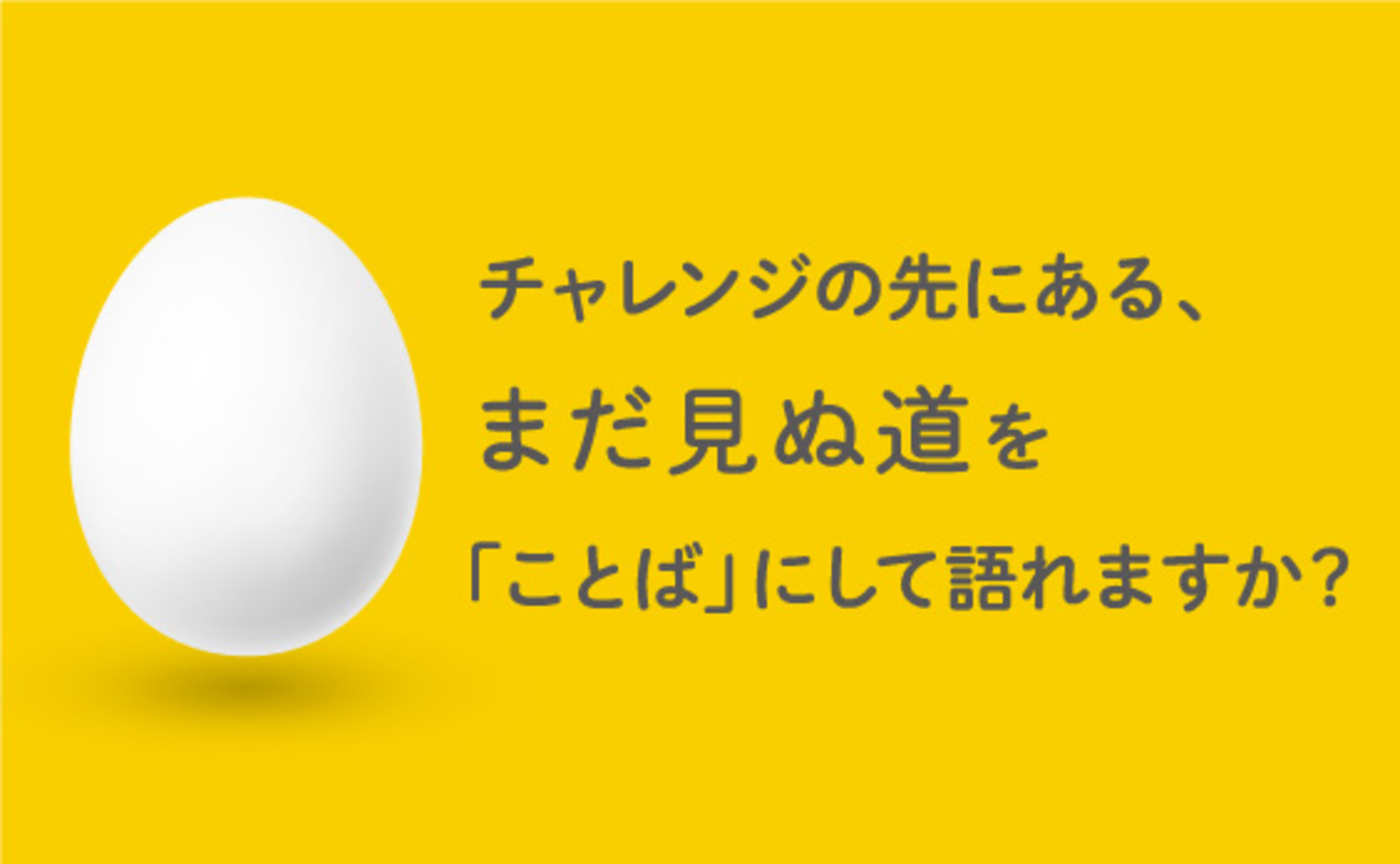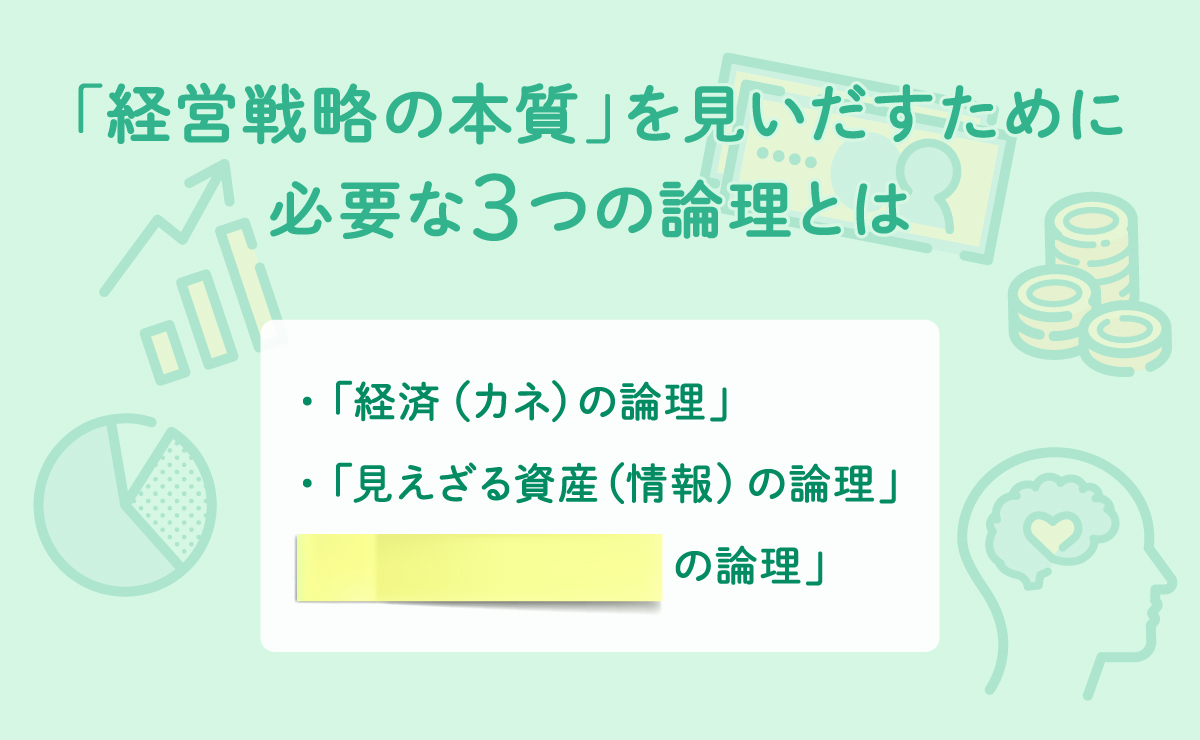「最先端のツールや外部の専門家に頼っても、なかなかイノベーションが進まないんだよなぁ…」というお悩みを解決するために、このたび「Indwelling Creators」というサービスをご提供することになりました。
「Indwelling(インドウェリング)」については、また回を改めてご説明しますが、その意味は「棲み込む」。文字通り、経験豊かな電通のクリエーターが契約時間、クライアント内に棲み込んで、組織メンバーの創造力を活性化し、イノベーションが自発的に、持続的に起きるような風土づくりを目指していくものです。
そして今日は、Indwelling Creatorsが「組織とは何か?」、そして「組織を動かす原動力とは何か?」について、どう考えているかをお話ししましょう。
Indwelling Creatorsでは「組織」を、「情報処理装置」ではなく「知識を創造するエコシステム」と捉えています。そして「組織を動かす原動力」は「正しい指示」ではなく、「対話」にあると考えています。もしかすると「ふーん、まぁ、そんなもんだよね…」って感じかもしれませんが、とても大切なことなので、もう少しお付き合いください。
たとえば、社長から現場まで多くのメンバーを動員、みんなで合意した内容を「パーパス」にまとめたものの、今度はそれがなかなか組織に浸透しないことに悩み、結局一向に変革が進まない…なんて話を聞くことがあります。Indwelling Creatorsではその原因が、「パーパス」という「正しい指示」をすれば、「情報処理装置」である組織が自動的に正しく機能するだろうという「組織観」にあると考えます。
誰からも反対意見の出ない「正しい」指示は、実はみんなを縛りつけている常識の枠内にあるからこそ「正しい」のであって、それをいくら忠実に実行したところで、常識を破るイノベーションなど起こらないのは当然のことです。
ここで必要とされるのは「対話」です。「新しい価値」というのは、一見相いれないような二つの価値観の間に起こる激しい相克(対話)から生まれます。両者の中から一つを選ぶのではなく、それを両立させるためにはどうしたらいいかを考え抜く、行ったり来たりの「動的」なプロセスが求められるのです。
先ほどの「パーパス」でいえば、経営者が唱える「現実的な理想主義」と「現場の現実」との間にギャップがあって初めて組織の中にゆらぎが生じ、激しい相克が始まります。そして、両者を行ったり来たりするせめぎ合いの中から「新しい価値」は生まれます。
「対話」を重視する背景には、「知識を創造するエコシステム」という組織観があります。組織メンバーは合理的に行動できない部品などではなく、ひとりひとりが個性豊かなクリエーター候補生だと考えるからこそ、「正しい指示」ではなく、あえて目の前に矛盾を示し、それを一緒に乗り越えようとするのです。
実は多くの方が無意識のうちに「情報処理装置」と「正しい指示」の呪縛にかかっているように思われます。これから解放するのが、Indwelling Creatorsの役割です。
この取り組みは、全体として野中郁次郎先生の経営学をベースにしています。たとえば、トップダウンやボトムアップという一方通行ではなく、ミドルを中心にした「対話」を重視する姿勢は「ミドル・アップ・ダウン」理論によっています。
Indwelling Creatorsが目指すのは、メンバーひとりひとりの個性が発揮され、その組織「らしい」イノベーションを実現することです。すでにいくつかの実績はありますが、まだ始まったばかりの本プロジェクト。ご関心をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】
opeq78@dentsu.co.jp 担当:山田
ところで毎年この時期このコラムと言えば、わが家のおせち料理。
今年も大騒ぎしながら作り終えたのですが、毎回難しいのがお煮しめ。里芋、京人参(きょうにんじん)、蓮根、うど、筍、慈姑(くわい)、さやえんどう、銀杏(ぎんなん)、生麩を一つずつ鍋を変え、味つけを変えて炊くのですが、たいてい何かが満足いきません。素材一つ一つとの「対話」が足りないんでしょうね。それがプロとアマチュアの決定的な差なのかなぁ…。
どうぞ、召し上がれ!