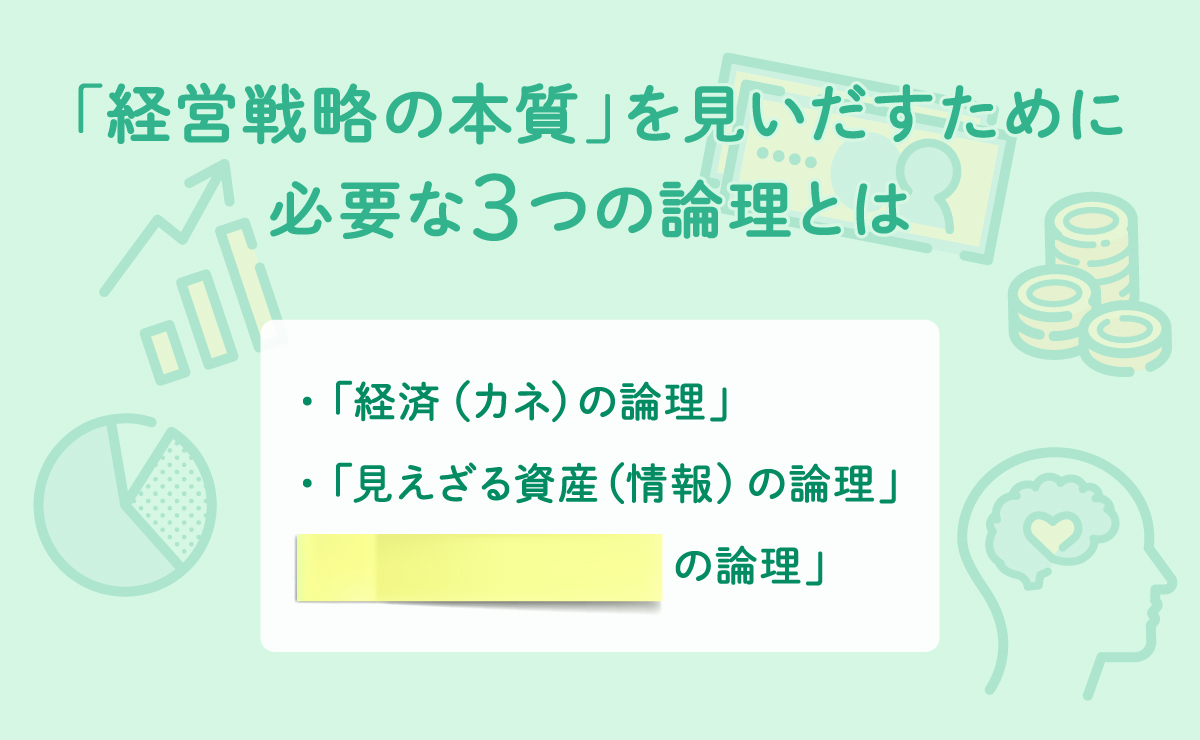企画することと提案すること
これはまったく架空のお話ですが。

とある地域に、カリスマ創業社長が経営して急成長を遂げている精肉店がありました。
そこでは、和牛、国産牛、輸入牛を取り扱っているけれども店頭には「しゃぶしゃぶ用」「焼肉用」「煮込み用」といった、あらかじめスライスされた商品はありません。「大人5人でBBQ」とか「2000~3000円で肉塊がゴロゴロのカレーをつくりたい」とか、鶏でも豚でも、おおよその予算で何をしたいのかを店員さんに相談してはじめて商品を提案・カットしてもらうスタイル。正直、値段は安くないけれど、確実にファンを獲得し続け、週末には行列もできる人気店に。
そこでカリスマ創業社長は、地元の調味料メーカーと漬物(主にキムチ)メーカーを買収。「総合ミートエンターテインメント」をコンセプトに据え、東京進出を計画。コミュニケーション計画全体を広告会社に相談したところ……。
広告会社の担当者は、「総合ミートエンターテインメント」という創業社長が立てたコンセプトに基づいて、新しいロゴ、PR計画、そしてテレビ、デジタル、OOHを統合したトリプルメディアの広告企画を提案しました。
……という(しつこいですが、まったく架空の)話なのですが。ここまで聞いて皆さんは、この広告会社のお仕事をどう思いますか?

想像するに、もしかしたらその「カリスマ創業社長」は自信満々であまり他人の話を聞くタイプではないのかもしれません。そして広告会社としても、新規取引でクライアントに怒られたくはないという心理が働くのも当然です。
しかし一方で思うのです。「最終的にどのような提案にまとめるかは置いておいて、いったんフラットに生活者とクライアント企業との関係を見ることから企画を始めませんか?」と。
ぼくがその広告会社の社員だった場合、少なくとも先の話を聞く限りでは、このお店が成功した秘訣は、店員さんに相談しないとお肉を買えない仕組みにあるように思われます。つまりそこにあるお客さまとお店のつながり(コンセプト)は「お肉のコンサルティング」的なことと推察されます。
あるいは、現地で詳細な観察をしてみた結果、(実はもっと店員さんの役割が大きな)キャストが主役の「ミート劇場」みたいなコンセプトが適当だという提案になるかもしれません。
そしてお店のコンセプトが実際のところ「お肉のコンサルティング」であるなら、PR等で伝えたいのも「こんな独自で面白い提案があるんですよ」になるでしょうし、キャストが主役の「ミート劇場」なら「こんなに面白い店員さんがいるよ」という人物紹介は欠かせません。
「『総合ミートエンターテインメント』というコンセプトを出発点にしないと、あのカリスマ創業社長に嫌われる」という思考停止は、提案の質を下げるリスクにつながってしまうのです。
言い換えると、残念ながら「総合ミートエンターテインメント」はどこにも焦点が当たっていない「コンセプトもどき」です。最終的に何か具体的な施策を挙げて「……というのが、御社の目指す『総合ミートエンターテインメント』の実践です」というふうに提案するにせよ、いったん企画段階では「お肉のコンサルティング」や「ミート劇場」といった、生活者との独自のつながりを見いだして基点にしないと、このお店の魅力を伝える独自の具体策も生まれません。
最近社内でCreative Dialogue※を重ねる中、クライアントの良きパートナーになることとクライアントに言われたことを丸呑みすることは違うんだけどなぁ……なんてことを感じる機会が何回かあり、「企画すること」と「提案すること」の違いについて考えたのでした。
※Creative Dialogue:コンセプトの“製造”や“品質管理”の方法論について考える対話の場。電通社内で300回以上実施されている。(詳しくはこちら)

さてさて。思い返すと、山形県尾花沢市の雪降り和牛をお手伝いしてから10年以上の月日が流れました。ありがたいことに、きょうも銀座三越、片葉三でそのおいしいお肉を買うことができます。

そういえば、片葉三のロゴにある「CONNOISSEUR OF BEEF」とは「牛肉の目利き」という意味。まさにこの店に相談すれば、和牛の楽しみ方をいろいろと提案してもらえます。今晩も雪降り和牛の切り落としを炒めて、冷凍してあった粒山椒をパラリ。誰が調理をしても間違いなく、絶品。無限にお酒もごはんも進みます。
どうぞ、召し上がれ!
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

山田 壮夫
株式会社 電通
第1CRプランニング局
クリエーティブ・ディレクター
明治学院大学 非常勤講師(経営学) 「コンセプトの品質管理」という技術を核として、広告キャンペーンやテレビ番組製作はもちろん、新規商品・事業の開発から既存事業や組織の活性化といった経営課題に至るまで、クライアントに「棲み込む」独自のスタイルで対応している。コンサルティングサービス「Indwelling Creators」主宰。2009年カンヌ国際広告祭(メディア部門)審査員等。受賞多数。著書「〈アイデア〉の教科書 電通式ぐるぐる思考」、「コンセプトのつくり方 たとえば商品開発にも役立つ電通の発想法」(ともに朝日新聞出版)は海外(英語・タイ語・前者は韓国語も)で翻訳・出版 されている。