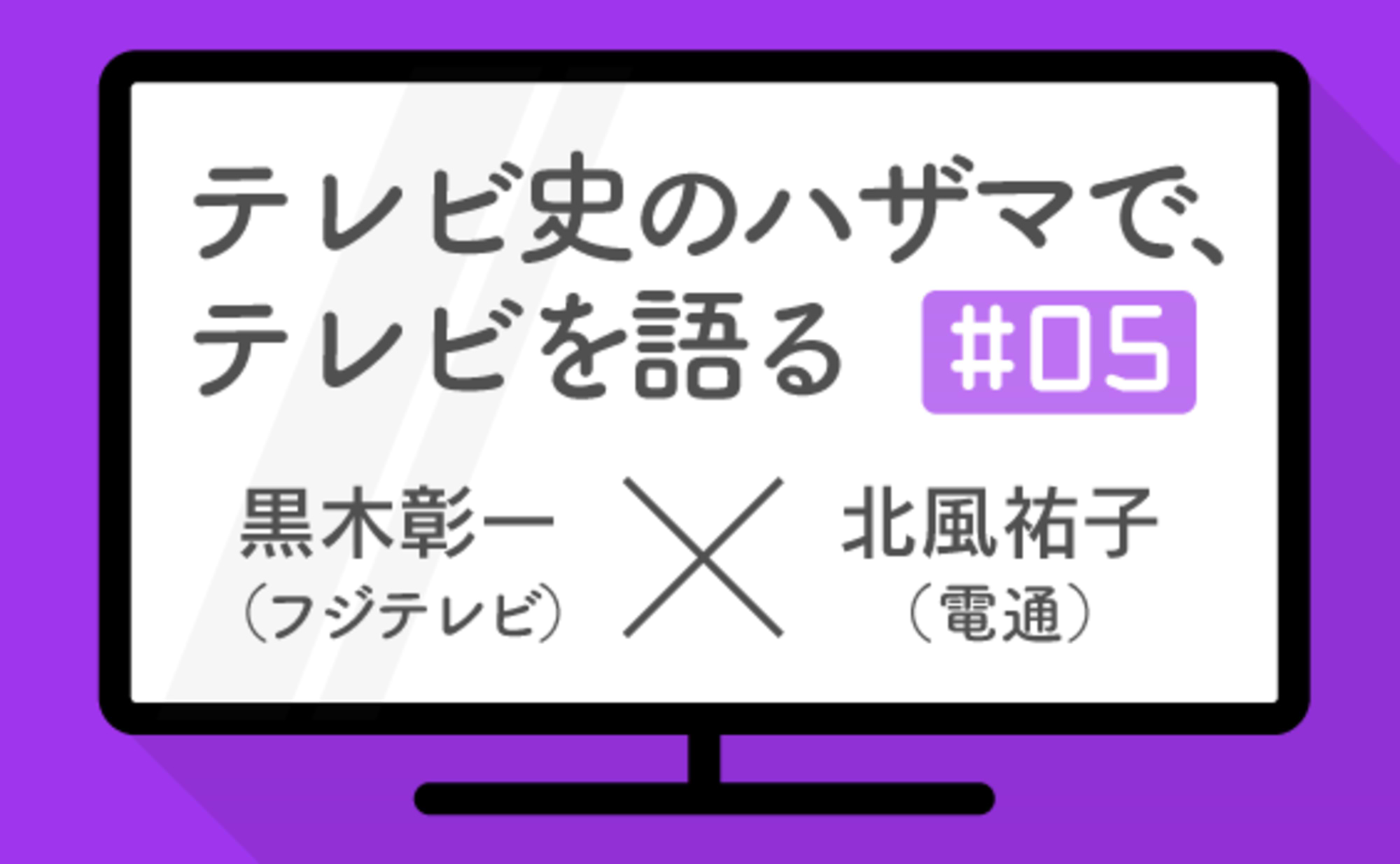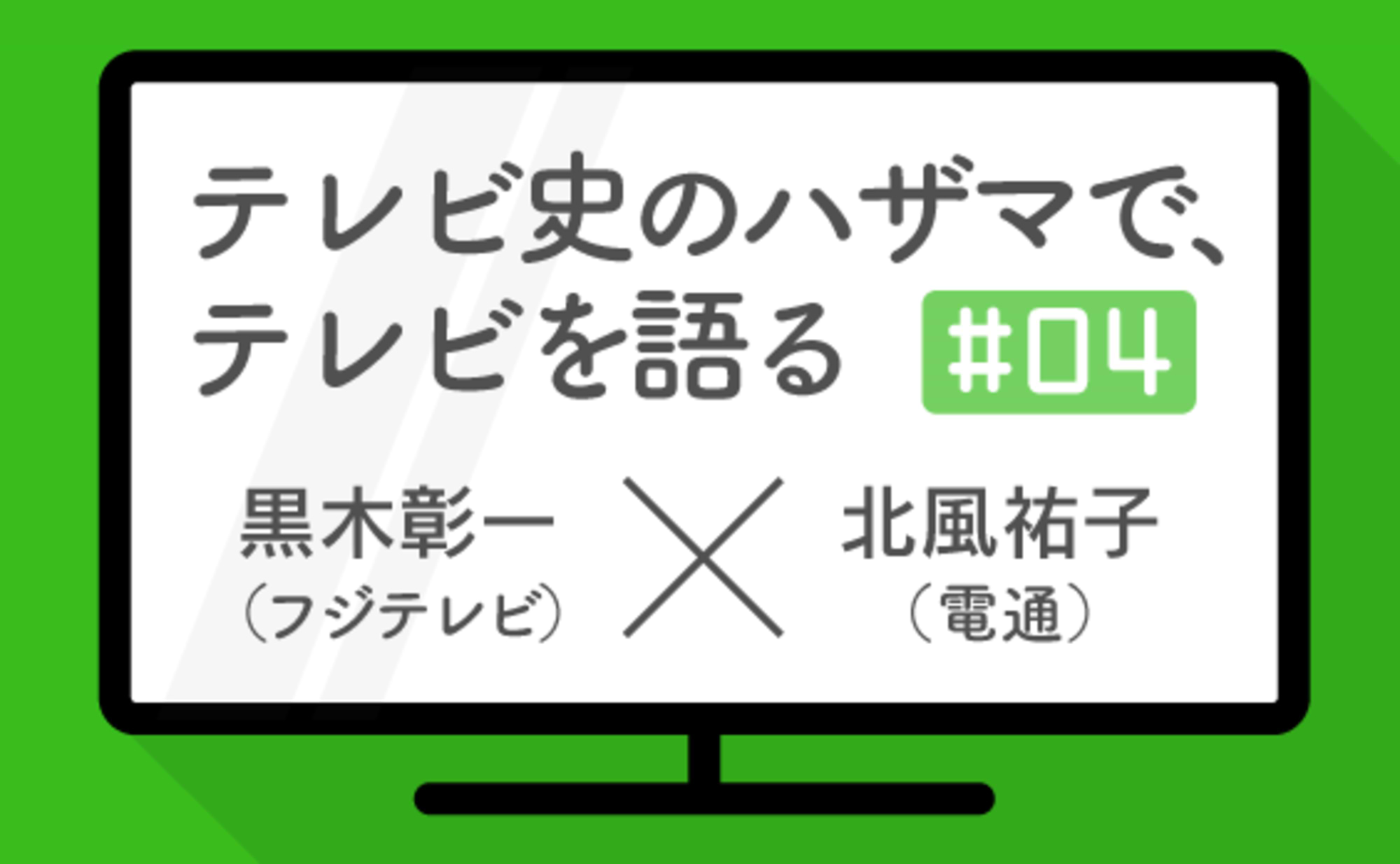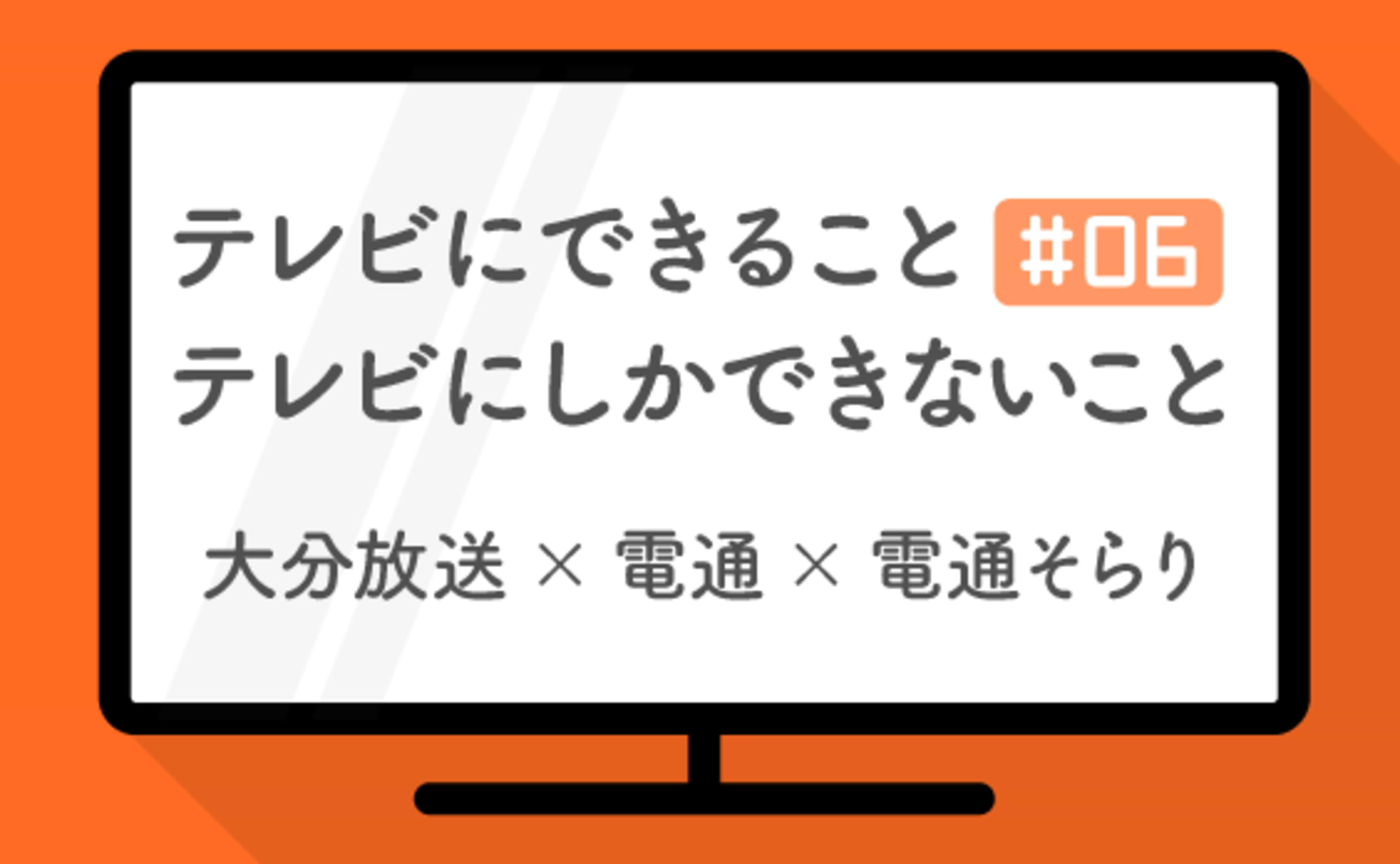「テレビ史のハザマでテレビを語る」と題し、フジテレビの黒木氏と電通の北風氏の対談を5回連載でお送りした本特集。続編となる#06で取り上げるテーマは、大分放送と電通と大分県別府市にある「太陽の家」のコラボにより、2019年11月15、16日に開催された「太陽の家カンファレンス2019」。「障がい者雇用」という社会課題に対する、放送会社と広告会社のタッグによる新たな取り組み。そこに至った経緯や今後の展望についての「座談会」(※)の模様を振り返ることで、テレビというメディアの未来像について掘り下げてみたい。

(左から)電通 川崎寛氏、電通そらり 清水恒美氏、大分放送 宮地寛哉氏、野上敦史氏
※以下の座談会の模様は、シナプスの記事から抜粋の上、再編集したものです。
座談会の全文は、こちら。
──今日は、「太陽の家カンファレンス2019」の企画者として、大分放送の宮地さん、野上さん、電通そらりの清水さん、電通の川崎さんにお集まりいただきました。まずは、「太陽の家カンファレンス2019、企画の経緯とこれから」について伺えれば。最初に、皆さんがそれぞれ「太陽の家」と出合ったきっかけについてお聞かせください。
宮地:私は、大分放送に入社して13年ほど報道部にいたので、取材を通じて「太陽の家」およびその創設者である中村裕先生について知りました。中でも最も印象的なのは、中村先生の提唱で始まった大分国際車いすマラソン(以下、車いすマラソン)で、毎年この車いすマラソンの取材をしていたので、背景にある「太陽の家」、そして中村先生の存在の大きさを肌で感じることができたんじゃないかなと思っています。

大分放送 宮地寛哉氏
野上:私は大分にUターンで当社に転職して、地元で営業を8年やりましたが、やはり入り口は車いすマラソンでした。
川崎:僕は電通のラジオテレビ局に在籍しているのですが、昨年の上司に「大分の車いすマラソンを見に行って、その足で太陽の家も一緒に見よう」と誘われたのがきっかけです。実際に行ってみたら、その2~3日間で心境の変化があったんです。

電通 川崎寛氏
── 一方、清水さんは電通から移籍して、電通そらりの社長に就任されました。電通そらりは、障がいのある方の就業、雇用を促進する電通の特例子会社ですが、やはりそのお仕事を通じて、「太陽の家」についてお知りになったのでしょうか?
清水:はい、電通そらりの社長に就任するまでは、30年ほどクライアント営業の仕事をしていました。ずっと営業畑で忙しくしていたのですが、友達のお子さんに障がいがあって、それで私もB型事業所に行くようになったことから障がい者の就労支援について興味が芽生えたんです。

電通そらり社長 清水恒美氏
私自身そこで働く障がい者の方々と接する中で、すごくまじめでピュアで、彼らと話すことに私自身、違和感も感じず、理解を深めるうちに、自分に合っているのでは、私も障がい者の方の力になれる仕事をしたい、と思いました。それで自分の会社周りを調べてみたら、障がい者の就業や雇用を促進している電通そらりという会社がある!と分かって。人事と掛け合って、出向させてもらいました。
それが今から2年半前ですね。そして1年ほど前に、川崎さんと、当時の川崎さんの上司である永井局長が突然来社されて、とうとうと車いすマラソンや「太陽の家」について熱く語られました。「車いすマラソンや太陽の家にもっとスポットを当てたい!電通で何かしたい!」って。
──実際にカンファレンスを開催してみて、反響はいかがでしたか?
清水:カンファレンスに参加された企業の方々は、忙しいけど意欲のある人たちばかりだから、事業所視察からワークショップまで予定をぎっしり詰め込んだ超過密スケジュールだったのですが、「もっと見学したかった」「もっと互いの課題を語り合いたかった」という声があがっています。さらには「で、来年はどうするの?」みたいな(笑)。ものすごい意欲・熱意をひしひしと感じます。
宮地:カンファレンス終了後に「太陽の家」の山下理事長にも伺ったところでは、今回のような東京をはじめとした大都市圏の企業に加えて、次回は地場の九州の企業の皆さまにも参加していただいて、もっと輪を広げていきたいというお話もありました。
野上:大分県にカンファレンスの説明をした際に、「大分県の企業は参加しないんですか?」と職員の方からも聞かれたんです。県としても、県内企業における障がい者雇用の活性化に期待しているのだろうなと感じました。
──実際に企画された皆さまとしての感触はいかがでしたか?
野上:あのスケール感は電通さんだからこそ出せたものだと感じました。われわれの発想だけでは、あそこまでの企画は生まれなかったです。

大分放送 野上敦史氏
野上:企画検討の初期段階で川崎さんから頂いた企画書には、“サミット”と書いてあったんです。「別府でサミットを開く!」って。すごい絵を描くんだなぁと驚きました。われわれだけでは描けないスケールでしたから。そして、今回のカンファレンス開催をご一緒して、これから先の広がりが少し見えたような気がしています。
川崎:今回関わってくださった方々には、概ね良かったという印象を持っていただけているみたいですし、自分としても手ごたえがありました。その上で、次回については開催時期も含めて、規模や誰の目線で開催するのか、そして招待するお客さまの広がりなど、いろいろとブラッシュアップしていく必要はあると感じています。
──次回のカンファレンスは来年になるのでしょうか。皆さんの話を伺っていると、さらに良い企画に仕上がりそうな期待がふくらみます。一方で、現時点で皆さんが課題として感じていることもあると思うのですが、いかがでしょうか?
清水:障がい者の雇用は引き続き継続する中、業務の拡大は、常に必須です。そらりは2年目から、正社員登用をしており、社員が定年まで勤務できる環境は必要です。だからこそ、これまでの枠に捉われず、異業種とも組んでいきたいと考えています。
宮地:社会課題に対してアイデアを出し続ける、その永続的な流れをつくるということを、われわれローカル局の立場としても考えていかなければならないと感じています。それはこれまでのような放送や広告ビジネスという枠組みとは異なりますが、地元を盛り上げる・応援することもわれわれの使命じゃないか、と。
清水:そうですね、障がい者雇用の取り組みは、東京だけではなく地方都市でも広がっていくべきですよね。東京に本社がある会社が、地方で、障がい者の雇用を市と組んで行っているケースもあります。地方都市では、雇用先が厳しいエリアもあり、また、地方創生にもつながりますよね。そんなふうに、東京のような中央の大都市圏と地方とどう組めるかというのも課題のひとつだと感じています。
川崎:われわれ、広告会社としても、広告業という現状から脱却して、時には事業の主体に回る勇気を持たないと生き残っていけないという危機感があります。
広告の受発注をするだけでなく、未来の社会に必要なことだと感じたことに対しては、リーダーシップや求心力を持って積極的に新しいものを生み出す活動を行っていかないと、どうしても頭打ちになってしまうと思っています。
宮地:それは当社のようなローカル局においても、川崎さんが今おっしゃったことと同じような考え方が必要だと思います。大分には「太陽の家」があって、その理念が地域に根付いていて、実際に別府の町も協力してきたという素晴らしい歴史があります。でも、これからの時代は、別府そして大分という枠を超え、この素晴らしい歴史と理念を大分の外に展開して、社会が発展していけるよう、ローカル局として、化学反応を起こすような触媒的な役割も担う必要があるのではないかと思っています。
川崎:「太陽の家」はただの箱ではないので、その思想・理念を広げていくことが大事ですよね。そういう社会的な問題に、テレビというメディアが光を当てるツールとして機能していくことが、今後ますます求められていくのかもしれないと感じています。そうすることによって、いろんな人にとってのより良い生活や社会に発展させていける可能性があります。僕はそういうところにテレビの可能性を感じています。
(編集部雑感)
「障がい者雇用」という、いまだ多くの企業や人に「自分には関係ないこと」として認識されているであろう「小さなテーマ」を探り当て、世の中に情報発信する。ここまでが、従来のテレビのあり方だった。ネタをフォーカスした時点で、番組としては成立している。探り当てたネタを、「ドキュメント風」に仕立てて発信したら、ある意味、それでおしまい。ということだ。
でも、時代は、世の中は、明らかにその先を求めている。その先を探ってこそ、これからのテレビの「真価」が見えてくる。そんな思いから、今回の「大分放送×電通」の座組みが出来上がったのだと思う。
自分には関係ないことを「自分ごと」化してもらうため、ドキュメント風ではなくリアルな「ドキュメント」として配信する。そうすることで、小さなテーマを「大きなムーブメント」にしていく。ネットの世界では、当たり前に行われていることを、テレビというメディアを使ってなんとか実現できないものか。そうしたチャレンジ精神から生まれたのが、「太陽の家カンファレンス2019」だ。
想像するに、従来の番組づくりのプロセスとは、こういうものだ。すなわち、「地域のいいネタを見つけた→それを、深く掘り下げる→地域に発信する。以上」。そのプロセスが、電通とのコラボにより、このように変わっていった。「地域のいいネタを見つけた→それを、広く発信する→協賛企業を含め、みんなで深く掘り下げる→行政すらも巻き込んで、新たな仕組みやビジネスを起こしていく→その仕組みやビジネスを全国的なムーブメントに拡大していく」。そうしたプロセスが、「ローカル発」の新たなダイナミズムを生んだ。
注目すべきは、「掘り下げる」「発信する」の順番が、従来とは真逆である、ということだ。メディアが、メディアの権限のもとで「掘り下げる」に前にネタそのものを「発信する」(=オープンにする)。それも、広く。そのネタに共感した人や企業が、自然と集まってくる。集まってきた人みんなで、議論をする(=掘り下げる)。そこで生まれたアイデアを、単に「発信する」のではなく、具体物(公共的な施設、商品など)や仕組み(制度やサービス)に転換。誰もが実感、共感できるカタチあるものへと具現化していく。
大分放送の野上氏は、川崎氏の「大分で、障がい者雇用をテーマとしたサミットを開催しましょう!」という旨の提案に、衝撃を受けたのだと言う。ポイントは、そこにあるのだと思う。街頭テレビから流れてくるプロレス中継に、全国民が熱狂したように。4Kで放送されたラグビーの試合に、列島が釘付けになったように。テレビというメディアの本質は、いつの時代も、広く人の心をつかみ、動かすことにある。リアリティーの魅力は、速報性ばかりではない。情報の深度や、熱量、スケール感といったものも、欠かせない要素なのだ。
「テレビに、できること。テレビにしか、できないこと」をとことん掘り下げて、みんなの知恵と力を、結集させる。人の心の深いところを揺さぶり、社会現象としてのムーブメントを起こせるのは、やはり「テレビ」というメディアならでは。大分放送による取り組みは、“テレビ史のハザマ”における、小さいながらも確かな一歩。そこに、これからのテレビの大いなる「可能性」を見た。
「テレビ史のハザマでテレビを語る」#01〜#05の記事は、こちら。