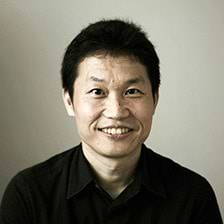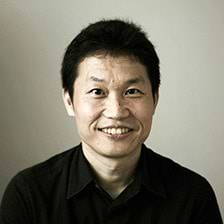次のコミュニケーションを考える一冊。
今回は、今村直樹さんの『幸福な広告』を取り上げます。
帯に「現場でつのる危機感」とありますが、著者の今村さんは、現役のCMディレクター。30年以上CMづくりの第一線で活躍されていて、最近では吉永小百合さんが出演されたシャープのアクオスのCMなどを監督されています。
僕もコピーライターとして、一度お仕事をさせていただきましたが、「クラフトマン」という言葉がぴったりの、誠実なものづくりをされる監督です。
その今村さんが、長くCM制作の現場にいた肌感として、90年代後半あたりから、「気がつけば、がらりと空気が変わっていた」と言います。
その変化は、大きな流れでいえば、大量生産・大量消費の行き詰まりとメディア環境の推移によって、CM自体が効きにくくなったこと。その結果、「予算がない」「スケジュールがない」現場で、文字どおり「現場監督」としての役目をディレクターが果たさざるを得なくなった、ということなのですが、そうした現象だけを見れば、「時代の流れ」という一言で片づけられてしまうかもしれません。
けれど今村さんは、もっと本質的な原因を探ろうと2010年から1年間、早稲田大学の大学院に通って自分なりの研究を進めます。
50代も半ばになって、大学院に通う熱意にも頭が下がるのですが、見方を変えれば、それほどまでに、今村さんの中で違和感が膨れ上がっていたのかもしれません。
「CMといまの時代の間にある、このズレの正体は何だろう」
「広告とは何か」から始まり、慣れない言葉の定義や指導教授とのやりとりを通じて、徐々に明らかになってきたのは、より本質的な問題は、経済構造やメディア構造の変化よりも、「広告主と制作者の信頼関係の喪失」ではないか、ということでした。
広告も含めたコミュニケーションは、つながりを生み出すためのもの。「企業と消費者」「製品と生活者」とのいい関係をつくる現場で、「広告主と制作者」がいい関係になければ、いいコミュニケーションなど生まれるはずもない。
そんな、当たり前の結論に達したのです。
その仮説を裏付けようと、今村さんは成功していると思われる広告コミュニケーションの関係者に取材し、事例研究を進めます。たとえば、サントリーの烏龍茶。たとえば、三和酒類のいいちこ。たとえば、ソフトバンクの一連のCM。それらの制作現場に共通していたのは、「広告主と制作者の信頼関係」、それも強い想いをもった「個と個」のつながりでした。
「人と人が向き合うこと。対等に、フラットに。信頼や広告の継続性は、その結果もたらされるものでしかない。それこそが、『幸福な広告制作の現場』に共通して言えること、つまり普遍性ではないかと思うのだ」
そんな個と個がつながる「幸福な現場」から生まれたCMは、結果として生活者とも「幸福なつながり」を生み出します。それは、つくり手の想いがCMを通して生活者に伝わり、積み上げられることで、「強いブランド」になっていくからです。
ところで、今村さんが挙げているキーワードに、「対等」「個と個」「つながり」「信頼感」があるのですが、これらはまるごと、いまのネット時代のキーワードでもあります。というより、そもそもこれらのワードこそが、「コミュニケーションの本質」であり、インターネットやソーシャルメディアの登場によって、その本質がますますあらわになってきた、ということではないでしょうか。
いま思えば、マスメディア全盛の時代から、送り手が一方的な情報発信をしても受け手には伝わらないことを、現場の優秀な人は知っていましたし、実践もしてきました。
現在、企業や制作者のさまざまな事情で、「消費者の利益を優先することを許さない空気」が現場に生まれていることを、今村さんは強く危惧しています。今村さんは、こんな言葉で、ある項を締めくくります。
「確かにぼくは、マスメディアの側にいる『送り手』かもしれないけれど、一度も、漠然と『受け手』や『消費者』という人に向かって何かを伝えようとしたことなどない」
「広告も、CMも、それがコミュニケーションである以上、広告を作る上でも、消費者に届ける上でも、対等に、個と個として、信頼感に結ばれる関係を目指していくべきである…(中略)…たとえそれが、広告にとって苦手なことだったとしても、もともとそれは、広告が目指すべき本質だったはずなのだから」
コミュニケーションというものに、現場で真摯に向き合ってこられた今村さんの言葉には、強い説得力があります。それは、TVCMであれ、ソーシャルメディアであれ、あるいはメディアを超えた企業と生活者のつながりであれ、すべてのコミュニケーションやエンゲージメントに通じる本質ではないでしょうか。