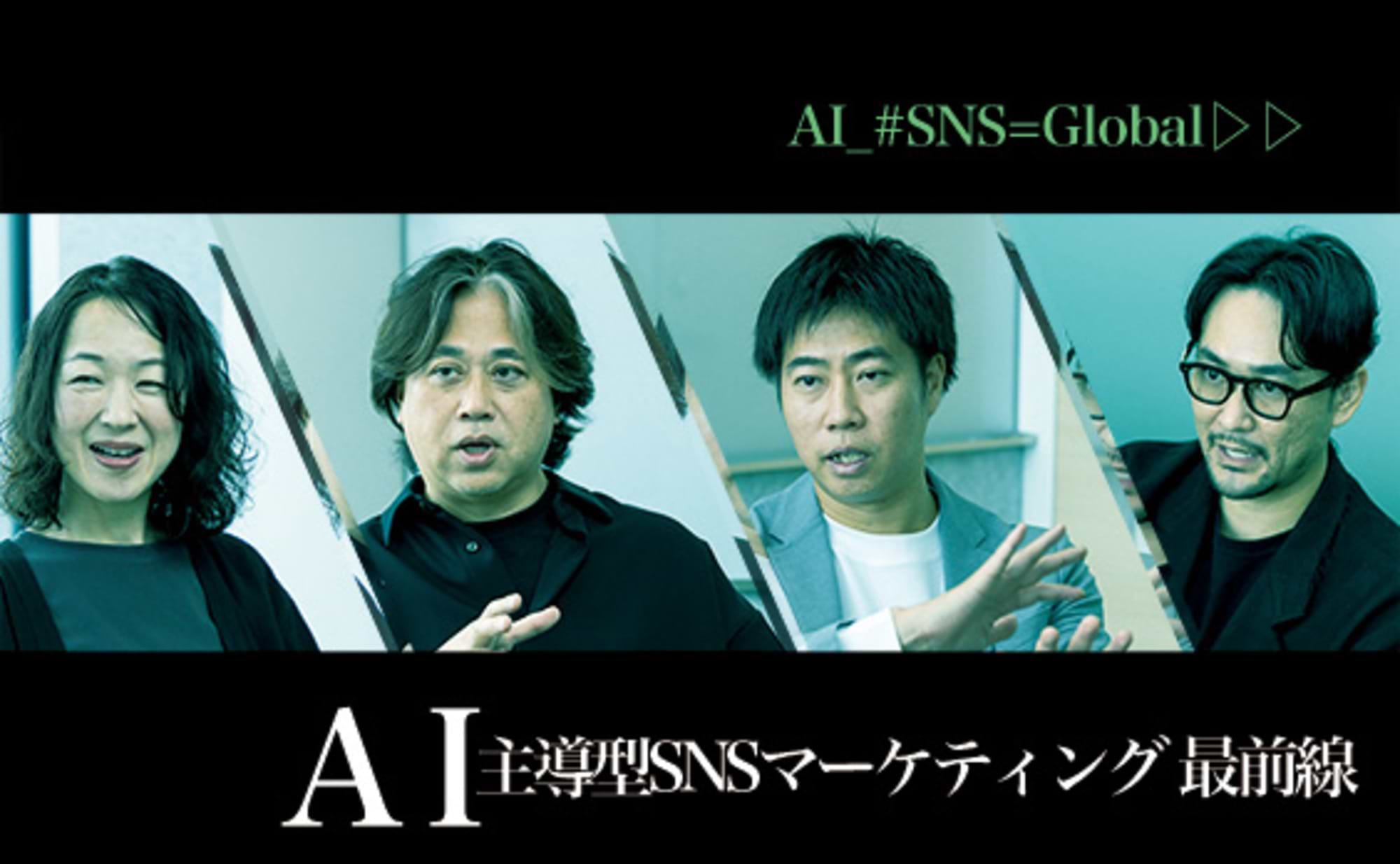斬新な映像体験で空間演出 「UN-SCALABLE VISION」 電通ライブ×IMAGICA GROUP
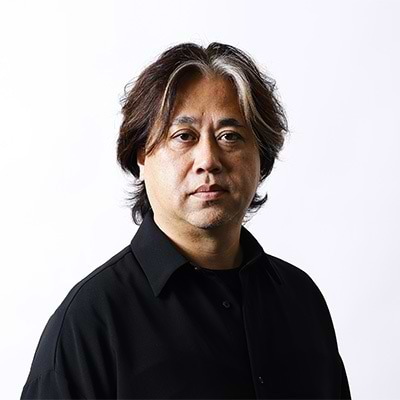
前澤 克文
株式会社 電通ライブ

諸石 治之
株式会社 IMAGICA EEX
壁面全体をワイド画面にした70メートルにもおよぶモーターショーのステージ空間。駅舎をスクリーンにしたプロジェクションマッピングによる斬新な映像体験。映像テクノロジーは、コロナ禍で生まれた新たなニーズもあいまって、実現に10年かかると言われていたことが数年で可能になるくらい、急速に進化を遂げています。
今年5月、電通ライブとIMAGICA GROUPは共同で、映像表現による新たな体験を創造するソリューション「UN-SCALABLE VISION」を立ち上げました。その狙いとは?思い描く映像体験の未来とは?電通ライブの前澤克文氏とIMAGICA EEXの諸石治之氏に聞きました。
※本記事は、Transformation SHOWCASE掲載の記事をもとに、追加取材を行い、再編集しています

あらゆる環境に最適化された自由な映像表現を実現
──はじめに、「UN-SCALABLE VISION」とはどのようなソリューションで、どのような経緯から生まれたのでしょう?
前澤:「UN-SCALABLE VISION」は、電通ライブとIMAGICA GROUPが手を組むことで生まれた、映像分野における最先端のソリューションです。場所や空間にとらわれず、サイズやアスペクト比にも制限されない、あらゆる環境に最適化された自由な映像表現を実現することを目指しています。映像制作や体験開発はもちろん、映像機器の手配・設置から、送出システム開発までワンストップでサービスを提供しています。
諸石:「UN-SCALABLE VISION」というネーミングには、映像表現の多様性を追求していくことがチームの使命である、という思いが込められています。いわゆる16:9のモニターやプロジェクションマッピングの中の映像コンテンツをつくるということではなく、それらを組み合わせて自由自在に映像表現をすることから生まれるオリジナリティこそ、「UN-SCALABLE VISION」が目指すところです。
前澤:このようなソリューションを提供するに至った背景には、クライアントから寄せられる要望の変化があります。以前は「ビル壁面の大型ビジョンに流す映像コンテンツを制作してほしい」といった依頼が中心だったのですが、ここ数年は「本社ビルのエントランスを、映像テクノロジーを駆使して、社の“顔”になるような空間にしてほしい」といった問い合わせが次々と寄せられるようになりました。これからは「空間×演出×映像」という新しいソリューションが必要かもしれない、と考え始めたところで、諸石さんと出会ったんです。それが「UN-SCALABLE VISION」の発端と言えますね。
IMAGICA GROUP(※)とは以前から一緒に仕事をする機会があって、映像編集や配信技術の高さがトップクラスであることは実感していました。それにIMAGICA EEXは、コロナ禍を経て、さらにチャレンジングな取り組みでエンターテインメントを進化させようとしていたので、ぜひ協業したい、とお声掛けしたというわけです。
※ IMAGICA GROUP:映画フィルムの現像を事業として1935年に創業。その後、映像テクノロジーの進化に伴い事業を多角化。現在はアニメやCG、広告やプロモーション、デジタルや空間体験の制作にも進出しており、クリエイティブとテクノロジーを融合した幅広い領域で映像関連事業を展開している。
──諸石さんが代表取締役社長を務めるIMAGICA EEXについて、もう少し詳しく伺えますか?
諸石: IMAGICA GROUPのグループ会社としてMAGICA EEXを立ち上げたのは、2020年7月のことです。当時はコロナ禍でイベントが開催できない、人が集まれないという状況が深刻化していました。そうした状況だからこそ、クリエイティブとテクノロジーを融合し、エンターテインメントの新しい未来をつくり出せるんじゃないかという強い気持ちが起こりました。グループ内に新しい会社を立ち上げるという前例は少ないのですが、社会全体が鉛色の雲の下にある中、自分たちの挑戦で光の兆しを生み出したいという強い意志がありました。
映像と通信の力を合わせたエンターテインメントで社会課題に向き合うことを目標にスタートして、最初はライブ配信が主な事業。そこでXRやヴォルメトリックキャプチャ(撮影した画像から3Dデータを構成する技術)などを活用して、映像だからできる新しいライブエンターテインメントを打ち出していきました。世界初となる、12K映像が照明や電飾と同期をしたVISIONS SUPER LIVE VIEWINGなどは、見てくださった方々も新しいライブ体験として感じてくださいました。最近では、メタバースやデジタルツイン(物理的な空間をデジタル上に再現すること)などの概念を取り入れつつ、新たな体験価値の提供を進めています。

──前澤さんと諸石さんの出会いをきっかけに協業が実現するわけですが、IMAGICA GROUPの側からは電通ライブとの協業をどう捉えていましたか?
諸石:IMAGICA GROUPは、長年、コンテンツ制作でのさまざまな映像技術や表現のノウハウは持っていましたが、施工やスペース構築といった、映像をアウトプットしていく場づくりには課題がありました。電通ライブは、多くのクライアント企業との連携やコミュニケーション関係がありますし、企画の出口もたくさん持っているので、両者が交われば良いものがつくれるのでは、という確信がありました。
新しい形のクリエイティブエコシステム
──まさにお互いの強みとニーズが合致して今回のソリューションチームの結成に至ったのですね。続いて、「UN-SCALABLE VISION」の強みについて教えていただけますか?
前澤:空間そのものを演出するような大型映像の制作は、通常の映像制作とは異なるアプローチが必要となり、より多くの視点が不可欠となります。電通ライブは、70メートルにおよぶステージ空間演出で話題になったTOKYO MORTOR SHOW 2019 TOYOTAブースメインステージのコンテンツプロデュースを手掛けるなど、施工を必要とするスペースづくりからイベントプロデュース、映像制作まで一気通貫で行っている会社ですので、「スペース」「イベント」「映像」の3つの分野に経験豊富なプロデューサーが多数います。そこへIMAGICA GROUPのテクノロジーやクリエイティビティといったエンターテインメント力が加わることで、より拡張した表現ができるのではないかと思います。

諸石:日本のものづくりは、制作の過程がある意味フォーマット化されています。仕事を受注して、いくつかのセクションや役割分担の中、最終工程で監督やクリエイターが加わってディレクションするというように、作業のプロセスが多いのも特徴です。最初からアウトプットのイメージを持っているクリエイターが参加できるチームビルディングを行うことで、ゴールのアイデアをみんなで膨らませることができるようになります。「UN-SCALABLE VISION」は新しい形のクリエイティブエコシステムです。チームの中で継続して知見を重ねていけるのも大きな利点だと思います。
──今年5月に「UN-SCALABLE VISION」の立ち上げが対外発表されたわけですが、その後の反響はいかがでしょうか。
前澤:まだ対外発表から間もないのですが、いくつかの大型イベントに関わっていく計画も動き出しています。われわれ電通ライブは、5年先、10年先のプロジェクトに携わっていることも多く、そこに「UN-SCALABLE VISION」を組み込んでいくというチャンスも多くなっていきそうです。
諸石:IMAGICA GROUPの社内の反応としては、とても期待値が高いです。電通グループとはこれまでも多くの案件でご一緒させていただいてきましたが、「UN-SCALABLE VISION」は、映像制作だけの限定的な関係ではなく、ワンチームとして全体的な枠組みでクリエイションやプロデュースに参加できる点がこれまでとの違いです。
コロナ禍でテクノロジーは大きな変化を遂げました。とりわけ映像業界は10年かけて変化していくだろうと思っていたものが、3年で急激に変容したという印象です。当社としては、映像の大きな未来を見据え、取り組んでいきたいと思っています。そのためにも今回の「UN-SCALABLE VISION」は重要な位置付けとなっています。
前澤:総合的なクリエイティブチームとしては、より多くのパートナーとも協力していきたいですね。「UN-SCALABLE VISION」は、IMAGICA GROUPと電通ライブのチームではありますが、さらに日本のエンターテインメントを変えていくために業界全体で取り組んでいきたいという気持ちがあります。海外のライブエンターテインメントチームと並ぶほどのクオリティにするために、海外ネットワークを有効利用し、先進的なクリエイターと協力して、より魅力的なコンテンツを生み出していきたいですね。
大型展示会・空間のシンボルから街づくり・アリーナ開発まで
──「UN-SCALABLE VISION」の具体的な活用例としては、どういったものを想定していますか?
前澤:活用イメージの1つは、大型展示会や大型イベントにおける超大型スクリーンサイズでの映像体験です。アクティング、ライティング、サウンド、ホログラムなどの技術を複合して新しいエンターテインメント体験がつくり出せます。また、屋外ビジョンとして、ビルの壁面をはじめ、駅の柱、電車の中、店頭などあらゆる場所を映像プラットフォームとして空間演出を可能にします。空間のシンボルづくりなどにも活用していただけると思います。
そして今後、よりニーズの高まりが期待できるのが街づくりやアリーナ開発です。多機能複合都市やIoTを導入した次世代スマートアリーナなど、地域の活性化や継続的な発展に役立てることができると思っています。

諸石:「UN-SCALABLE VISION」の強みは、従来のフレームにとらわれず、あらゆる空間をメディア化できることだと思っています。空間の中にモニターがあって、そこにコンテンツが流れているということではなく、映像も含めた空間そのものがメディアになることで、これまでにない体験価値が生まれていきます。
今はテクノロジーの進化によって、扱える情報量が膨大なものになっていますから、その場に最適な形でオリジナリティの高いアウトプットをすることが求められています。そういう観点で考えると、「UN-SCALABLE VISION」はフォーマットの枠を超え、フレームから解放された自由な発想でキャンバスをつくり、多彩なテクノロジーという絵の具で自在な絵を描くというコンセプトなので、高精細や低遅延などのメディアテクノロジーの劇的な進化と伴走している、と言えるかもしれません。

前澤:仮に20メートルの壁面に「UN-SCALABLE VISION」の技術を用いるとすると、まずは前を通る人や近隣のオフィスに勤める人など、その場所を利用する人の立場で空間の意味を考えます。その空間を利用する人に「心地良い」と感じてほしいからです。海外のオフィスでは、壁面映像をインテリアとして活用している事例も映像クオリティの進化とともに増えてきました。木目調の壁かと思えば、革製の壁になるというように、変化するインテリアとして捉えることもできるのです。
誰も見たことのない未来のスタンダードを生み出したい
──最後に、今後の展望について教えてください。
前澤:イベントに関わる人だけでなく、映像制作とは程遠いと感じているようなビジネスパーソンこそが、「UN-SCALABLE VISION」を取り入れてみたくなるような提案もしてみたいですね。先ほどお話ししたようなインテリアとしての可能性があれば、オフィスプランニングにも使えるのではないかと。
これまでの映像体験は、見る者にとって受動的なものが多かったと思います。テレビ番組やCMなどもそうですよね。「UN-SCALABLE VISION」は、既に出来上がったコンテンツを楽しむといった面だけではなく、人とナチュラルに共存するようなイメージで映像をつくることができます。その方向性をもっと掘り下げていきたいですね。
諸石:「UN-SCALABLE VISION」は、新しいコミュニケーション、エクスペリエンスになっていくという可能性があります。大型イベントや都市開発領域など、いろんなパートナーの方々と連携して、誰も見たことのない未来のスタンダードを生み出したいと思います。
また、物理的な空間だけに縛られず、リアルとサイバーを融合した世界で、AIやデジタルツインの概念を内包した新しい体験を提供したいとも思っています。新たな価値や文化を創造し、豊かな社会を実現していく意気込みで、これからも取り組んでいきたいと思います。
この記事は参考になりましたか?
著者
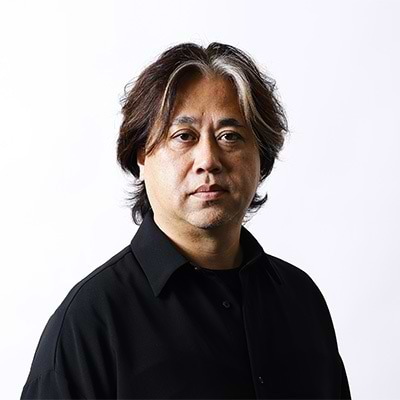
前澤 克文
株式会社 電通ライブ
コンテンツ&テクノロジー開発部
チーフクリエイティブディレクター
SNS施策やデジタルコンテンツ施策、 実践的なAI施策に取り組む。先進デジタル領域におけるソリューションメーカーとして次世代コンテンツ開発を行う。 ドローンショー協会理事も担当する。

諸石 治之
株式会社 IMAGICA EEX
代表取締役社長 CEO/CCO
最先端テクノロジーとクリエイティブを融合した事業のプロデュースやクリエイションを手掛ける。映像と空間を組み合わせた空間演出および体験設計、プロジェクションマッピング、8Kや12K 高精細メディア、XRやデジタルツインなど、クリエイティブとテクノロジーを融合したエクスペリエンスやコミュニケーションをデザインする。