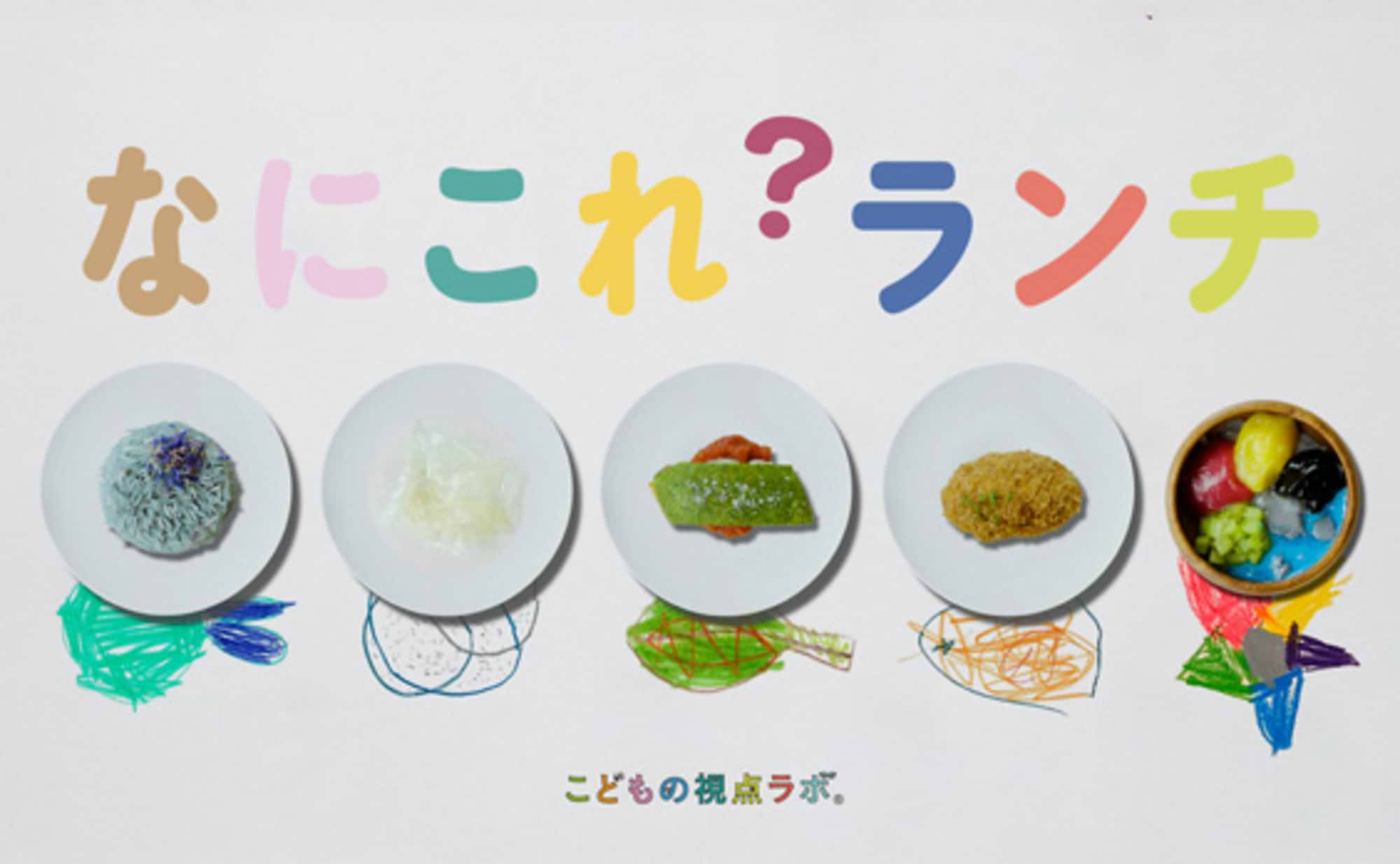このままおむつをつけ続けていいのだろうか?
保育園ではクラスのお友だちに合わせる形で、おむつではなくパンツで頑張っているけれど、家ではもっぱらおむつで過ごしている3歳の娘。親としては“お漏らし”や“こどもトイレ探し”を考えるとトイレトレーニングがおっくうではあるが、同じ年ごろのお友だちと比べるとおむつ離れが遅い気がして、少し不安になってしまう今日この頃。
今回の研究は、そんな不安を抱えて過ごす尾崎賢司と、一番下が1歳で絶賛おむつ真っ盛りの娘をもつ3児のママの太田久美子が、おむつの世界を深掘りしてみました。
パンパンのおむつで動き回るのは、ハードトレーニング!?
パンパンに膨れあがったおむつで動き回っているけれど、重くて動きづらいとかないのだろうか?気持ち悪かったり、くさくて、おむつを替えたいとか思わないのだろうか?こどもの気持ちを想像すると湧いてくるおむつについての疑問の数々。いろいろとおむつに関する記事に目を通しても、なかなか答えが見つからない。
そこで、おむつのことは、おむつのプロに!ということで、ユニ・チャームさんにご協力いただき、実際におむつを研究・開発しているチームにインタビューさせていただきました。インタビューに応じてくださったのは、マーケティングの松田優子さん、研究部門の丹下明子さん、商品開発の河田ひかりさんです。
尾崎:3歳になる娘のおむつを見ていると、全然漏れなくて、すごく性能が高いように感じています。最近のおむつってどれくらいまでおしっこやうんちを溜(た)めておけるものなんでしょうか?
ユニ・チャーム(以下UC):保水量(おむつを絞っても押しても水分が出てこず、おむつがしっかり保持する量)と吸水量(ひっくり返しても水分が出てこない程度におむつが保持する量)という2つの量の考え方のもと設計しています。3歳くらいだと、使っているおむつはLサイズと夜用ですかね。保水量でいうと、Lサイズで330g程度、夜用おむつで450g程度になっています。吸水量でいうとLサイズで450g程度、夜用で600g程度になっています。もちろん、おむつの種類によって多少異なりますが。
尾崎:なるほど。すごく溜めておけるんですね。それに甘えて、ついついつけっぱなしにしてしまう時がありますが、その状態って大人に換算すると約2.18kg(※)の重りをお尻につけているってことになるんですね……。

UC:そうですね。そんな状態で公園を動き回っていたりしますから、こどもにとっては相当なハードトレーニングをしているようなものかもしれませんね。
太田:こどもたちに申し訳ない気持ちになってきました……。それでも、こどもたちって、割と平気な感じでいますけど、「こんなものか」ぐらいに思っているんでしょうか?
UC:おしっこの1回あたりの量は約40gとそれほど多くなくて、徐々に重くなっていくので、それに順応していく感じで重さに気付きにくいのかもしれませんね。
尾崎:徐々に重さに慣れていくとは、ホントにトレーニングみたいですね。
「気持ち悪い」も「くさい」も、社会性が成長してから
太田:重さについては、徐々に重くなっていくから気づきにくいとしても、そもそもおしっこをたくさん溜めた状態って気持ち悪く感じていないんですか?
UC:快・不快の定義が難しいんですが、おしっこが肌に流れている感覚はわかっていても、それが「気持ち悪い」と理解するには、社会性の発達が必要だといわれています。
太田:おしっこが出ている感覚はあっても、それを「気持ち悪い」とは感じていないんですね!おむつがパンパンでも平気そうにしている謎が解けました。
UC:ちなみに、うんちを「くさい」と感じるのも社会性の成長だといわれています。
尾崎:「気持ち悪い」に社会性の成長が必要だというのは、なんとなく理解できるのですが、「くさい」は本能的なもののように思えますが。
UC:もちろん、匂いを感じる感覚機能は生まれながらに備わっていることは、生後まもない乳児が水の脱脂綿と母乳の脱脂綿のどちらに顔を向けるかなどの実験で示されています。そして、本能的に危険を感じる匂いについては避けると考えられています。しかし、うんちは生命を脅かすものではない。うんちの匂いを「くさい」とする認識は、実は社会性によるものなんです。
尾崎:ラボの他の研究でも、大人が生まれつきとか当たり前だと思っていた感覚が実はこどもの成長にともなって獲得されるものだと知らされるケースがしばしばあります。「気持ち悪い」や「くさい」も、こどもの成長が関わっていたんですね。
UC:そうなんです。ただ、これだけでなく全般に言えることですが、実証実験がないものがほとんどです。そのうえで、こういう身体的発達、神経的発達をするから受容しているんだろう、感じているんだろう、理解しているんだろう、という理論の立て付けになっていると思うんです。本当はもっと赤ちゃんたちは奥深い感受性を持っている可能性だってあります。
おむつの中は、雨季の熱帯雨林並みだった!
太田:1歳の娘がおむつを外した瞬間におしっこを発射してくることがよくあるんですが、「気持ち悪い」と感じるのがもう少し後だとすると、あれはおむつを外した時の気持ち良さや開放感からくるものじゃなかったんですね。
UC:あるあるですよね。おむつを卒業するまでは、反射で膀胱(ぼうこう)からおしっこがあふれ出るような排せつをしているので、気持ち良いという開放感から出しているわけではないんです。おむつ内の湿度は高いときで90%以上もあるので、外した時に入ってくるヒヤッとした空気による冷感刺激で反射的に膀胱がキュッとしまって、おしっこがあふれ出るという生体機能だと考えられています。
尾崎:あの現象は、開放感とかではなく、刺激によるものだったんですね!湿度90%以上って、雨季の熱帯雨林並みの湿度ですね。そりゃ、きっと冷感刺激も強いはずです。
UC:そうですね(笑)。おしっこを溜めすぎると、「おむつ内気候」はまさに熱帯雨林並みと言えるかもしれません。
尾崎:「おむつ内気候」って言葉があるんですね。
UC:家政学に「衣服内気候」という言葉がありますが、おむつにも「おむつ内気候」という言葉があり、その「おむつ内気候」をモデルの人形を使って評価していたりします。初めのうちは完全におしっこを閉じ込められても、繰り返していると吸水できずにおむつ内に残る水分が多くなり、おむつ内の湿度を高くする原因になります。
太田:お尻がかぶれてしまったこともあるのですが、かぶれを考えると、やはり「おむつ内気候」が熱帯雨林並みになってしまうまでに替えるべきですよね。
UC:湿度が高いと、肌が蒸れてふやけてしまいます。そうすると、物理刺激にも弱くなってしまいますし、菌とかカビとかの生物的な刺激も中に入りやすくなってしまうので、肌のかぶれに対しては良くないと言えます。もちろん個人差はありますが、かぶれてしまうかは、おむつを替えるタイミングというよりは、そこまでにどれだけ皮膚がふやけているかがカギになります。
太田:おむつ替えはこういう時にしましょうというタイミングは特にないんですね。
UC:おむつ替えについては、タイミングの推奨というのは特にしていないんですが、清潔のためにこまめに替えてくださいとは発信させてもらっています。
尾崎:菌の繁殖を防ぐ意味でも、ちゃんと替えなきゃってことですよね。気をつけます。
尿意をコントロールできるのは、3歳ごろから
尾崎:と言っても、親としてもおむつ替えできる場所がなくて、こどもに我慢してほしいなぁなんて思う場面もあります。そもそもこどもって、何歳くらいからおしっこを我慢できるのでしょうか?
UC:実はおしっこを我慢するには、尿道の括約筋(かつやくきん)がちゃんと発達していなければいけません。それに加えて、ここはトイレだから出してもいいという認識の発達や自分の意思で括約筋を縮めたりするための神経の発達も必要です。トイレトレーニングが落ち着くころ、つまり近年の平均でいくと36カ月〜39カ月ごろから、大人のように尿意をコントロールすることができるようになります。
尾崎:ということは、それまでは我慢できないんですね。
UC:2歳くらいまでは、尿意を感じると、排尿を十分コントロールできずに排せつが起こってしまうといわれています。
太田:ちなみに、こどもとお出かけなどする際に、「トイレ大丈夫?」と聞いて「大丈夫!」と言ったのに、その5分後くらいに「トイレ行きたい!」と言い始め、「だからさっき言ったのに!」と叱るような場面があったりします。我慢といっても、そんなに我慢できないものなんですかね?
UC:我慢ができるようになってすぐは、数分は我慢できても、しっかり長く我慢できるようになるまではもう少し時間がかかります。
太田:こどもにとっては、尿意も突然やってくるし、それを我慢できる時間はまだ長くないんですね。
UC:「だからさっき言ったのに!」と叱られても、自分もこんなにすぐに行きたくなるなんて夢にも思ってなかったのかもしれません。こどもはいつ尿意が来そうか、どこまで我慢できるかなどの自分の身体感覚の経験値もまだつかめていません。さらに、お出かけでの電車の時間など状況の経験も少ないですから、仕方ないですよね。
太田:今はしたくないけど、もう少したったら行きたくなるから行っておこうみたいに、大人はある程度さじ加減をわかっていますが、それって経験値が高いからだったんですね。叱っていたけど、かなり大人の感覚で考えてしまっていたんだなと反省です。

ユニ・チャームさんとのリモートインタビューの様子
スムーズにおむつを卒業するための3つの成長
尾崎:最後に、おむつの卒業に向けてのお話について聞かせてください。先ほど、トイレトレーニングが落ち着くのが36カ月〜39カ月ごろとお話ししていただきましたが、3歳の娘はいまだに家ではおむつを愛用しています。うちのようにトレーニングが進んでいなくて、少し不安になる親御さんも多いと思いますが、どうやったらスムーズにおむつを卒業することができるんでしょうか?
UC:実は子どもの自律できる発達を待ってからトレーニングすれば、スムーズにおむつを卒業できることが、昭和大学医学部小児科学講座教授の池田裕一先生とベビージョブさん、ユニ・チャームの3者による共同研究でわかりました。未熟な早期から始めると長くかかるし、パンツを履いてても漏れちゃうし。その時期を見極めてから始めることが大切です。では、その適切な時期はどうやって見極めたらいいか?なんですが、それにはこどもの3つの成長にひもづくポイントがあります。
UC:これらは、保育士さんたちとの実験で導いたもので、この3つのポイントがそろっているとトレーニングが早く終わることが多いです。特に3つ目は一般のママパパには難しいかもしれませんが、保育の現場で見極められます。絵本遊びの時に、「はい終わりです、次は外遊びです」という場面転換を2回言ってもきかないと保育がスムーズではないという判断ができるんですが、そういうこどもはトレーニングが進みにくいということが実験でわかりました。コミュニケーション能力の成長が未熟で、トレーニングを始めるにはまだ早いということですね。
太田:もっと早く知りたかったです(笑)。たしかに3つ目は少し難しいですが、家での声がけや会話の時にでも、ある程度コミュニケーションの発達は感じられる場面がある気がします。
尾崎:こどもがおむつを卒業した親からは、「もうすぐ外れるよ」とか言われるんですが、トレーニングの渦中にある親はそれどころじゃない。これら3つを知ったら、そんな気持ちがだいぶ落ち着く気がします。
おむつは、まだまだ進化する
尾崎:娘がおむつを卒業しないのは、おむつが快適すぎるのもあるんじゃないかとすら思っていました(笑)。実際、自分の母親から昔の育児話を聞いたり、海外にいる友人から現地での育児話を聞いたりしていると、日本のおむつのすごさを改めて実感させられます。
UC:おむつは昔に比べるとかなり進化していると思いますし、いまや日本のおむつは、世界の中でも全然漏れないハイスペックな仕上がりで、世界の基準になっていたりします。ただ、正直まだまだだとも思っています。自分たちでも大きめのものをつくってはいたりして試していますが、それはそれは不快です。ガサガサ締め付けられるし。そんなおむつをさらに進化させるべく、われわれの研究所ではいろんなアイデアを出し合い、日々実験を重ねています。
尾崎:まだまだ進化するんですね。でも、その進化に甘えることなく、おむつの衛生面をこまめにチェックしたり、こどもの成長をしっかり見極めたりと親の務めはしっかりやらねばと、皆さんのお話を受けて心に誓いました。丹下さん、河田さん、松田さん、本日は貴重なお話ありがとうございました。
UC:おむつの開発に関しても、赤ちゃんのおむつはまだまだ研究が進んでいないし、大人の視点がたくさん残ってしまっています。皆さんの質問を受けて、子どもの視点って必要だなと改めて感じました。こちらこそ、ありがとうございました。
おむつのことを深掘ってみたら、「気持ち悪い」や「くさい」と感じることや、尿意の我慢とコントロール、そしてスムーズにおむつが卒業できるトレーニングの開始時期など、こどもの成長が深く関わっていることがわかりました。今回のまとめです。
●おしっこでパンパンのおむつは、大人に換算すると2.18kgの重りをお尻につけてハードトレーニングしているようなもの。こまめに取り替えてあげたい。
●社会性が成長するまでは「気持ち悪い」「くさい」といった感覚がなく、こどもからは訴えてこない。おむつ内が蒸れると湿度90%以上になることもあり、肌がふやけて菌やカビも入りやすくなるので、こまめに衛生状態を気にしてあげたい。
●尿意をコントロールできるのは3歳くらいから。それでも、我慢できる時間は大人よりもずっと短く、尿意に対する経験もまだ浅い。「トイレ大丈夫?」「大丈夫!」も本人は本当にそう思っているので、大人がうまくトイレに誘導してあげよう!
●トイレトレーニングは「膀胱」「発達面での成長」「コミュニケーション能力」の3つが成長してから開始すると、スムーズにおむつを卒業できる。体と心の発達には個人差があるので、急いで始めなくても大丈夫。
さて、実は今回の研究を通して学んだことを、実際に巨大なおむつの中に入って、目と耳と鼻で味わう体験コンテンツを絶賛、制作中です。
2025年2月1日(土)から2月25日(火)まで二子玉川ライズホールで開催される「もっと!こどもの視展」にて、今まで発表してきたすべての研究と合わせて体験していただける予定なので、ぜひ足をお運びください!
【もっと!こどもの視展 開催概要】
会期:2025年2月1日(土)~2025年2月25日(火)
時間:11時〜19時(最終入場18:30)
※最終日は最終入場16:30
会場:二子玉川ライズ スタジオ & ホール
(東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 2F)
料金:大人 1,500円 18歳以下 1,200円 小学生以下 無料
主催:「こどもの視展」製作委員会
協力:イケア・ジャパン株式会社、ユニ・チャーム株式会社、株式会社CRAZY KITCHEN、株式会社エスピージャパン、株式会社ユニエイム、株式会社泉宣宏社、株式会社グラトリエンジニアリング、株式会社空間芸術社、株式会社エアロテック、株式会社アタリ、蔦屋書店、ITOCHU SDGs STUDIO