4つの栄養素&食材でツジツマをあわせよう!食品業界が力を合わせる「ツジツマシアワセ」とは?

飲み会後の〆のラーメン、食後の別腹スイーツ……たらふく“シアワセ”を楽しんで、次の食事を考える時に、ふと襲ってくる罪悪感。
でもそんな時こそ、「まぁいっか」の気持ちで、その前後の食事でゆるやかに栄養バランスの“ツジツマ”をあわせれば大丈夫!
そんなユニークなアプローチで注目を集めているのが、国内の主要食品メーカーを中心に多くの企業が合同で取り組む、“楽しく栄養バランス”普及プロジェクトの「ツジツマシアワセ」です。
本記事では、プロジェクトの事務局で運営に携わる味の素株式会社の山口卓也氏、味の素株式会社食品研究所で栄養評価システムの開発などに取り組む神通寛子氏に、電通の北島陽介氏がインタビュー。
日本人が抱える食生活の課題をひもときながら、食品メーカーやメディア等が横断で取り組む意義、今後の展望などを語っていただきました。
<目次>
▼日本の食品メーカーが集結。「ツジツマシアワセ」ってどんな取り組み?
▼日本人に足りない2つの栄養素や食材と、摂りすぎている2つの栄養素とは?
▼日本人の栄養改善に役立つ4つの栄養素と食材、その特徴を深掘り
▼「ツジツマシアワセ」に食品業界全体で取り組んで、“社会ゴト化”していきたい
▼「ツジツマシアワセ」の実践と継続につながる仕組みづくりを!
日本の食品メーカーが集結。「ツジツマシアワセ」ってどんな取り組み?

北島:国内の食品メーカーや動画レシピメディアが集合した、“楽しく栄養バランス”普及プロジェクトについて伺っていきます。まず、「ツジツマシアワセ」とはどんなものなのでしょう?
山口:人生100年時代といわれますが、これからは「健康寿命」をいかに長く保つかが重要になってきます。そのためには、やはり毎日の食事でバランス良く栄養を摂ることが大事なのですが、一方で毎日栄養バランスを考えた食事をすることは、生活者にとって大きな負担になってしまうのも事実です。
北島:誰だって、できるものならバランスの良い食事をしたいはず。だけど現実には、1日3食、栄養バランスを考えた食事をすることはハードルが高いですよね。
山口:そうなんです。もちろん不調を感じたり、何か特定の健康問題を抱えていたりすると、真剣に食生活を気にするようになると思います。でも、そういった状況にない人、特にまだ健康に不安を感じることが少ない若い世代が、予防的に食生活の改善を行うことは難しい。
そこで、主に「まだ健康課題が顕在化されていない層」に向けて、栄養を考えるハードルを下げながらも、同時に楽しく幸せな食生活を実現する手法として提案するのが、「ツジツマシアワセ」です。
「食べたいものを楽しく食べて、シアワセしちゃっても、その前後でゆるくツジツマをあわせていけば、健康的な食生活を実践できる」
ということをコンセプトにしています。
神通:栄養バランスを考えた食事というと、どうしても「1食ごと」に、バランスの取れた献立にしなきゃいけないと思われがちです。でも「ツジツマシアワセ」では、一定の期間トータルで栄養バランスを考えればOKとしているのが特徴です。
例えば、「昨日、今日と外食が続いて油っぽいものを食べすぎた」と感じたら、翌日から何日か野菜多めや塩分控えめなどのメニューを意識して、1週間程度を目安に栄養バランスのツジツマをあわせていくという考え方です。
日本人に足りない2つの栄養素や食材と、摂りすぎている2つの栄養素とは?

北島:1食単位ではなく、一定期間内でゆるくツジツマをあわせることで、シアワセな食事と栄養バランスの両立ができるというわけですね。
神通:はい。「ツジツマシアワセ」では、日本人の食生活の課題を取り入れた栄養プロファイリングシステム「Japan Nutrient Profiling System」(以下JANPS)を採用しています。その中で、一定期間での食事の栄養バランスをシンプルに分かりやすくするために、“4つの栄養素と食材”に着目しました。
このJANPSの考え方を、誰でも手軽に生活に取り入れやすいように開発したのが、「ツジツマシアワセ」マークです。

〈2つの推奨栄養素/食材〉
野菜、たんぱく質
〈2つの制限栄養素〉
塩分、飽和脂肪酸
北島:日本人が積極的に摂取すべき栄養と、逆に過剰に摂りすぎてしまいがちな栄養を、それぞれ2つずつにまとめたことで、考え方をシンプルにしたわけですね。
神通:そうなんです。推奨栄養素である「野菜」「たんぱく質」の目標値を25%上回ること、制限栄養素である「塩分」「飽和脂肪酸」の目標値を25%下回ることを示す4種類のマークに加え、4つのスコアすべてが一定水準をクリアしていることを示す「栄養ゴールデンバランス」があります。

このマークをどう使うのかというと、参画企業の各メニューや献立をJANPSの基準に基づき評価し、それぞれの条件を満たしたものに付与されます。マークを参考にしてメニューや献立を選べば、栄養素に詳しくなくても、「栄養バランスの調整」が簡単に実践できる仕組みです。
山口:「ツジツマシアワセ」のポータルサイトには、参画している食品メーカー各社の「ツジツマシアワセ」メニューのレシピがたくさん掲載されていますが、条件を満たしたメニューにこれらのマークが掲出されています。さらにサイトでは、食生活で気になる点や使いたい食材に合わせてメニューを検索することができます。

ポータルサイトでは、参画企業の「ツジツマシアワセ」メニューを紹介。メニューの下に「ツジツマシアワセ」マークを掲出することで、自分に必要なメニューを大量にチェックできる。
実際にポータルサイトを活用しているユーザーの方々からは、「不足している栄養素に合わせてメニューを選べて便利」「栄養バランスを考えた献立づくりに役立つ」などのうれしい声をいただいています。
日本人の栄養改善に役立つ4つの栄養素と食材、その特徴を深掘り

北島:改めて、「ツジツマシアワセ」の栄養バランスを考える上で評価の指標となる「JANPS」について伺います。これはどのように開発されたのですか?
神通:ベースとなっているのは、2020年に味の素株式会社食品研究所で開発した「The Ajinomoto Group Nutrient Profiling System」(以下ANPS)というシステム(※)です。当グループでは、スープなどの加工食品や冷凍食品などの自社製品の栄養評価や製品改訂、またレシピ開発にこの「ANPS」の仕組みを活用しています。
※NPS=食品中に含まれる栄養成分(Nutrient)の量を科学的な根拠に基づいて評価し、その食品の栄養面での品質を分かりやすく表現(Profiling)する手法(System)。
山口:ただ、生活者の栄養改善を実現するためには、この「ANPS」の仕組みをより普及しやすいカタチに変えて、社会実装していくことが重要だと考えていました。
そこで、国内の主要な食品メーカーなどにお声がけをして、今回のプロジェクトを立ち上げ、「ANPS」に各社の知見も取り入れながらバージョンアップさせてきているのが「JANPS」です。
神通:「JANPS」では、現代を生きる日本人の食文化と健康課題に沿って、4つの栄養素と食材に着目しました。ツジツマシアワセマークにもなっている、「野菜」「たんぱく質」「塩分」「飽和脂肪酸」です。
北島:日本人の食生活の課題とは、どういったことでしょうか?
神通:日本人の食文化の特徴であり、大きな課題としてまず挙げられるのが、「食塩」(ナトリウム)の過剰摂取です。最近でも、調査対象者の88%以上が1日の食塩摂取量の目標値である男性7.5g未満、女性6.5g未満(厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」より)をはるかに超えて摂取しているといった研究結果が出ています。
北島:7.5gや6.5gというと、ラーメンや丼ものを食べたら、一食でオーバーしてしまいそうですね……。
神通:はい。ナトリウムの過剰摂取は、さまざまな生活習慣病を引き起こす要因にもなるため、減塩は日頃から意識的に取り組むことが大事です。
そしてもう一つ。近年は、食の欧米化が進んだこともあり、肉類やバター、生クリームなどに多く含まれる「飽和脂肪酸」の摂りすぎにも注意が必要です。飽和脂肪酸の過剰摂取は、脂質異常や循環器疾患に影響を与えるとされています。
北島:たしかに、「塩分」「飽和脂肪酸」は、意識しないと摂りすぎてしまいますよね。逆に、日本人に足りていないものについてはいかがでしょうか?
神通:これは多くの人が感じていると思いますが、大きくいうと「野菜」が足りていない傾向があります。野菜には食物繊維やカリウムなどの栄養素が含まれており、生活習慣病の予防や、健康的な生活を維持する上で欠かせません。
厚生労働省の「令和5年国民健康・栄養調査結果」では、日本人の目標摂取量350gに対し、平均摂取量が成人男性で約262g、成人女性で約251gと不足しています。日頃の食事で野菜の摂取量を上げていく必要があります。そして、もう一つの足りていない栄養素が「たんぱく質」です。
北島:肉や魚、卵など身近な食材から摂取できそうですが、意外と不足しがちなんですね。
神通:そうですね。たんぱく質は、特に超高齢社会という観点でも重要です。加齢に伴って、徐々に身体的機能や認知機能が低下していく「フレイル」や、運動器の障害などによって移動が困難になる「ロコモ(ロコモティブシンドローム)」の予防には、たんぱく質の摂取が有効だといわれています。
でも高齢の方は、食事量の低下によってたんぱく質不足を招きやすい傾向にあります。日頃から、たんぱく質が多く含まれる食材やメニューをチェックしておくとよいでしょう。
山口:まとめると、「野菜」「たんぱく質」「塩分」「飽和脂肪酸」のバランスを考えることで生活習慣病を予防でき、健康寿命の延伸に貢献できると考えています。
多くの生活者の皆さんにこの「ツジツマシアワセ」という概念をインプットしていただき、先ほどのポータルサイトを活用して、食生活の改善のために実践してほしいですね。
「ツジツマシアワセ」に食品業界全体で取り組んで、“社会ゴト化”していきたい
北島:今回のプロジェクトのユニークなところは、国内の主要な食品メーカーなどが協業しているところです。1社だけでなく食品メーカーやメディア等が横断的に取り組むプロジェクトは珍しいですよね。

山口:私の知る限り、ここまで横断的な取り組みは他にないかもしれません。さらに、理念に共感して、新たに参画してくださる企業も徐々に増えています。プロジェクトを立ち上げ、川崎市でPoC(概念実証)を実施した2023年時点では6社でしたが、2025年現在は15社に増えています。
北島:多数の企業で横断的に取り組むことになったのは、どういった理由があるのでしょうか。
山口:生活者の食生活を考えた時、食材、調味料、加工食品、お弁当など、1社の製品だけということはないですよね。内食、中食、外食など、食事をするシチュエーションもさまざまです。そうしたことを考えたとき、やはり味の素一社ではなく、「食」に関わる業界全体を巻き込んでいかないと、生活者の栄養改善を実現することは難しいと思ったのです。
また、業界横断で取り組むことによって、社会的なインパクトも生まれます。専門家・行政の活動も大事ですが、生活者が日頃なじみのある食品業界全体で「栄養バランスを良くしていこう」と訴求していくことで、食生活の改善というテーマを“社会ゴト化”していけるのではないでしょうか。
北島:私たち電通も事務局として、参画企業の皆さんと一緒に本プロジェクトを推進していますが、日本人の誰にとっても他人ゴトではない食生活の改善を、“社会ゴト化”していく視点は本当に大事ですよね。
実際に、各企業にお声がけをしていく中で、「ツジツマシアワセ」のコンセプトを説明すると、「いい取り組みだね」と言っていただけることが非常に多い印象です。
山口:今回協業している食品メーカーの中には、一部のカテゴリではライバル関係にある会社も含まれます。でも、食の領域で日本人のウェルビーイングに貢献するという目的に対しては、一致団結して取り組めているのがうれしいですね。
神通:私たち研究職も、他社の研究職の方々と栄養評価の仕組みや栄養の目標値の考え方などを直接話し合う機会が得られて、非常に刺激を受けています。それと同時に、他社の皆さんも「生活者の栄養改善を実現したい」と熱い思いを持っていることを実感し、業界としての連帯感も覚えています。

「ツジツマシアワセ」の実践と継続につながる仕組みづくりを!

北島:プロジェクトのローンチ以来、「ツジツマシアワセ」を広めるためにさまざまな施策を展開してきました。山口さんや神通さんが感じている手ごたえや期待感、また、今後の展望などをお聞かせください。
山口:インターネットや店頭サイネージでの広告のほか、俳優の速水もこみちさん、近藤千尋さんにご登壇いただいたPRイベントを行ったり、6人のインフルエンサーにSNS発信をしていただいたり、さまざまな施策を行ってきましたね。幸いにもこれらを各メディアなどで好意的に取り上げていただいた結果、徐々に「ツジツマシアワセ」という取り組みの認知率も上がり、生活者に浸透してきている実感はあります。
今後の課題は、認知度だけでなく、実際の行動に移してもらうことです。「ツジツマシアワセ」マークの分かりやすさや実践しやすさといった利点を生かしながら、今後は生活者が続けたくなる仕組みの整備により一層注力していきたいです。
神通:私も、何より生活者に「ツジツマシアワセ」を実践していただき、継続してもらうことが重要だと感じます。味の素株式会社食品研究所にはさまざまな知見もありますので、今後はより科学的にどうアプローチできるのかといった視点も交えながら、レシピの開発など、協業企業の皆さんと一緒に考えていきたいです。
北島:私も、まだまだ可能性を広げていける魅力的なプロジェクトだと感じています。業界横断というお話をしてきましたが、今後は、食品メーカーやメディアだけでなく、地域の食に携わっている地方企業や、自治体なども巻き込んでいきたいですね。さらなる認知向上、そして実践者の拡大に向けて、電通も全力でサポートしていけたらと思います。本日はありがとうございました!

この記事は参考になりましたか?
著者
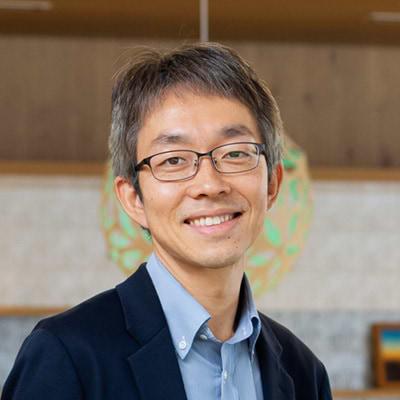
山口 卓也
味の素 株式会社
食品事業本部マーケティングデザインセンター マーケティング開発部
戦略プロジェクトグループマネージャー
通信事業者でインターネットサービスの企画開発、海外での新事業立ち上げ等に携わった後、味の素株式会社入社。ベトナム法人での販売企画・DX推進等を経てマーケティングデザインセンターに配属。新たなマーケティング手法を探索・導入するプロジェクトを推進。

神通 寛子
味の素 株式会社
食品研究所 ウェルネスソリューション開発センター 情報開発グループ
研究員
食品研究所において、食や健康に関するデータを活用した研究を通じて、生活者の健康課題の解決やWell-being向上に貢献するソリューション開発を推進。管理栄養士。

北島 陽介
株式会社 電通
第4マーケティング局
プランニングディレクター
プランナーとして、官公庁事業などにおいて、さまざまな日本の社会課題を解決するためのコミュニケーションの戦略立案を行う。他、インバウンド観光・自動車・飲料・家電・住宅などの分野で新商品・サービス開発にも携わる。


