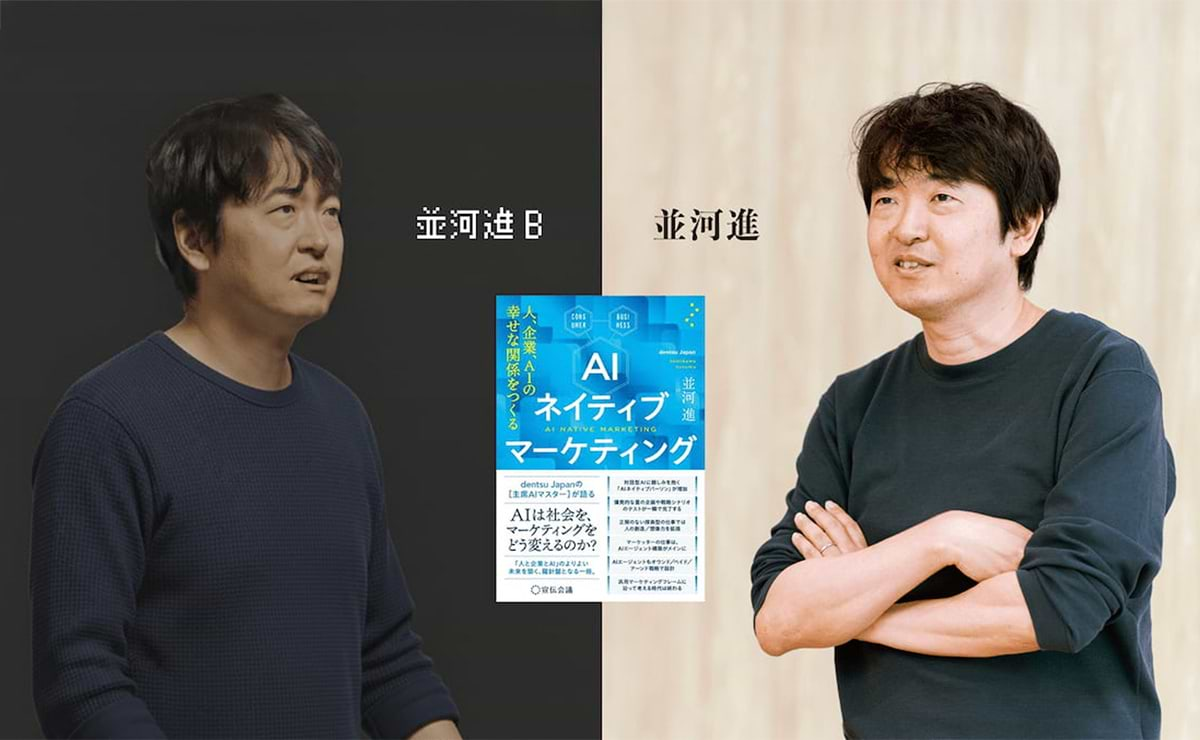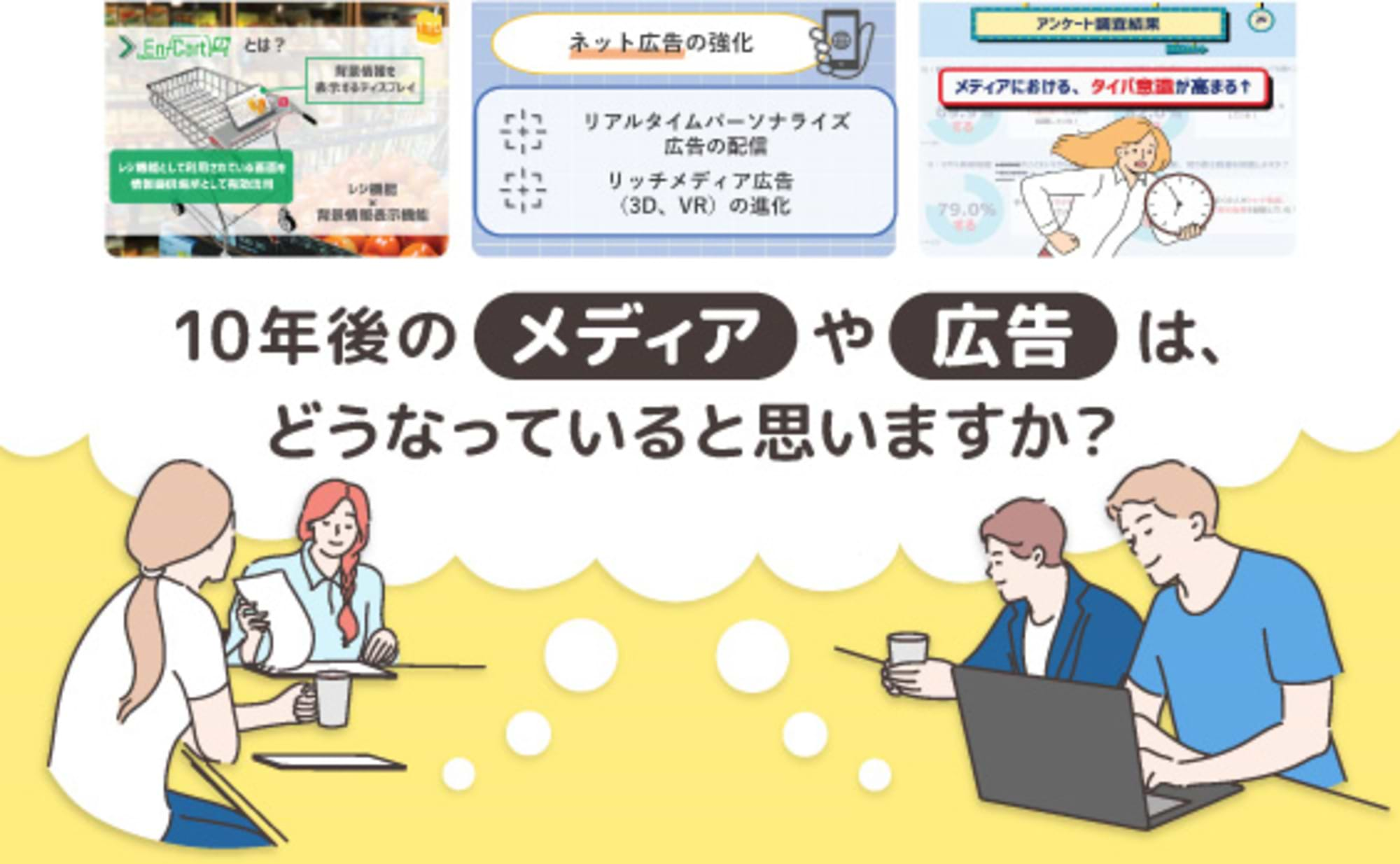電通では、自社グループ内のメンタルヘルスの不調経験者やサポーター、大学などで心理学を学ぶ社員が自発的に集まり、2021年に有志の「電通メンタルヘルスラボ」がスタートしました。
本連載では、私たち電通メンタルヘルスラボのメンバーがラボ活動を通して学んだメンタルヘルスを取り巻く状況と、社内での取り組みについてご紹介しています。
今回は、電通メンタルヘルスラボがどのようにして設立されたのか――。そのきっかけや背景を振り返りながら、運営する上で大切にしているキーワードやポイントをラボメンバーの竹本奈央がお伝えします。また、不調経験者と一緒に取り組む「メンタルヘルスカフェ」を深掘りし、実際の取り組みの様子についてもご紹介します。
電通メンタルヘルスラボが生まれた背景ときっかけ
うつ病に代表される気分障害などを含む精神疾患は、2013年度から、癌、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病と並ぶ5つの重要疾患のひとつとなり、2023年、その患者数は、603万人で糖尿病(552万人)を超えました。
また、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業または退職した労働者がいる事業所の割合は、事業規模に比例して年々増加し、2023年、300人以上の事業所で74.1%、1,000人以上の事業所では91.2%に上っています。(厚労省「労働安全衛生調査」2023年)
電通メンタルヘルスラボは、2021年初頭、代表の渡邊はるかの「メンタル不調による制約があっても、自分らしく働ける社会をつくりたい」という思いがきっかけとなり、始まりました。
渡邊も、うつによる長期休職経験があります。会社の制度のおかげで、約2年にわたる療養後に復職しましたが、当時つらかったのは、うつによる不調だけではなかったと言います。
それは、周囲への申し訳なさに加え、
「メンタル不調=ダメな人だとレッテルを貼られるのでは」
「一度休職したらキャリアが閉ざされるのでは」
という不安感や、周囲から置いてきぼりにされたような孤独感でした。当時から電通には、メンタルケアに関する制度や相談窓口はありましたが、さまざまなネガティブな感情から、周囲に相談することが難しかったそうです。
復職して6年経った頃、渡邊は「社内で、同じような不調経験をした人と話せる場」や「不調経験があっても働き続けている人の話を聞く機会」があれば必要以上に苦しまず、自分にとっても周囲にとってもちょうどよいバランスで働くヒントになるのではないかと、社内有志と共にラボの立ち上げに向けて動きはじめました。
専門家による知識の共有ではなく、メンタルヘルスに関する当事者目線でのコミュニティづくりや情報発信を目指したアプローチは、今でこそERG※1と定義されますが、当時、まだ珍しい試みでした。
※1 ERG=従業員リソースグループ、社員による自発的なコミュニティ活動。Employee Resource Groupのこと。
時には、渡邊が自ら出向いて同じ思いを持っている人に活動の参加を依頼することもあったそう。
その中の一人が、当時CXクリエーティブセンターのマネージングディレクターだった並河進(dentsu Japan グロースオフィサー/エグゼクティブクリエイティブディレクター/主席AIマスター)です。
並河自身も、メンタル不調で仕事から離れていた経験があり、さらに渡邊と同じ思いを抱えていることを、ラボ初期メンバーの一人が聞いていたことから、本人に活動への参加を依頼しに行きました。
当時のことを思い出して渡邊はこう話します。
「並河さんへの提案はとても緊張しましたが、開口一番、『ぜひやりましょう!これはやりたいと思ってたんです』とおっしゃったんです。すごくうれしかったし、並河さんが同じ方向を向いてくれて、安心感と心強さがありました」
渡邊は、センシティブな領域に誠実に取り組むため、業務と並行して通信大学やゼミで臨床心理学やカウンセリングを学び、知識を深めていきました。
社内の健康推進部門や産業保健スタッフのほか、大学やゼミでお世話になった医学博士・臨床心理士の沢哲司先生、心理学を学ぶ過程で知り合った心療内科医の鈴木裕介先生にも、たくさんのアドバイスをいただきながら、2021年4月、メンタルヘルスラボは社の公認ラボとなりました。

メンタルヘルスラボのイベントで自身のメンタル不調体験を語る渡邊
ラボのメンバーは皆、自身や周囲の不調経験者。運営する上で心がけていることは?
「他でもない自分自身が、メンタル不調への偏見にとらわれ、自分を否定していた」と語る渡邊は、ラボの活動を通じて、メンタルヘルスについて話しやすい空気をまず作りたいと考え、セミナーや研修、メンタルヘルスカフェの開催などさまざまな取り組みを行っています。
活動5年目に入る電通メンタルヘルスラボは、現在10人ほどのメンバーで運営しています。参加のきっかけ、バックグラウンドはそれぞれですが、どのメンバーも、自身や周囲の不調経験から、メンタルヘルスに興味や課題意識を持った仲間たちです。
私、竹本は、ラボの存在はラボ主催のセミナーで知っていましたが、「まさか自分が不調になるなんて」と、自分自身の不調をしばらく受け入れられず、仕事上最小限の人にしか打ち明けていませんでした。
そんな中で意を決して参加したメンタルヘルスカフェで、「不調は克服するものではなく付き合っていくもの」と客観的に捉え、自身の経験や糧の一つにしながら前に進んでいるある参加者の姿を目の当たりにしたのです。あの人のように私も自分自身を受け入れられたら――、不調を経験しても同じ会社で働き続けるということに、ほんの少し光が見えたような気がしました。
さらに、私も(計らずも)不調を経験した一人として、どうしても感じてしまう同僚への申し訳なさやレッテルへの不安感を分かち合ったり、他の人のリカバリーの役に立ちたい、この経験からタダでは起きまい、そう考えるようになり、ラボのドアをノックしました。
コミュニティづくりやモチベーションの観点からラボに関心を持ち参画しているメンバーもいます。
あるメンバーは、自身の経験から、「入社・異動・出向といった変化や挑戦にはメンタル不調はつきもので、誰でもなりうる」という考えから、現在、広告業界専門の産業カウンセラーとして活動中です。また別のメンバーは、ラボ活動を通してダイバーシティにも範囲を広げ、特例子会社で活動を始めました。
どのメンバーにも共通しているのは、自分自身の目線で自身と社会課題としてのメンタルヘルスに向き合い、積極的に知識を深めていることです。所属部署での活動のほかにも、大学に通ったり、産業カウンセラーやキャリアコンサルタントなどの資格取得、各種検定受験にも取り組んだりしています。
さらに、ラボが当初から目指す、当事者によるメンタルウェルネスのきっかけづくりに関して、以下のポイントやキーワードを日々心がけながら、活動を積み重ねています。

参加者それぞれが自らと向き合う時間「メンタルヘルスカフェ」
そんなラボが、2カ月に1回、昼休みに開催しているのが「メンタルヘルスカフェ」です。2022年以来オンラインで定期開催し、25年7月に22回目を迎えました。
同じ文化を共有する自社グループ内で、似た経験を持つ人同士が話すピアグループをつくったら、社員にとって心のよりどころになり、不調のケアやメンタルフィットネス※2の実践となるのでは、と考えたことが出発点です。
※2 メンタルフィットネス=心の健康を保ち、ストレスに対処するための方法や習慣
立ち上げにあたっては、医学博士・臨床心理士・医学博士の沢哲司先生に監修していただきました。また、当時すでにグループ内でピアグループとして確立されていた、がんサバイバー向けの「ラベンダーカフェ」を主催する高田愛さんに相談しながら、方針を固めていきました。

イラスト:渡邊はるか
カフェへの参加はその都度事前申込制で、通常業務において予定を共有している他の方にはわからないオンライン会議システムを使っています。
参加人数の上限は設けていませんが、毎回さまざまな部署や会社から10人程度が集まって、自身の経験や感情と向き合い、共有しています。
実施にあたっては、毎回、沢先生の立ち会いのほか、社の公式窓口紹介など専門家との連動や、秘密保持をはじめとするグランドルールも設けています。
心理的安全性担保と、参加できる健康レベルの目安として、カメラONの顔出しをルールとしていますが、発言したいと思った時にしたい人がする、自主性に任せた進行をしています。そのため、考え込んだり、話そうかためらったりする「沈黙」の時間もしばしば発生します。
私たちは業務で日々、問題解決型の思考を求められる機会が多いため、初めての参加者を中心に、最初は沈黙に慣れず戸惑い、違和感を抱く方もいるようです。ラボのメンバーも、同じでした。
しかし、カフェは問題解決のためのミーティングではなく、「参加者それぞれが自らと向き合う時間」です。沢先生からも「沈黙こそ価値のある時間」というお話をいただき、今では沈黙の時間も意味のあるものとして受け止められるようになりました。
試行錯誤を重ね、テーマは「メンタル不調を経験して気づいたこと」で定着していますが、その回のメンバーや、季節ごとの傾向、社会的なニュースがアップデートされるので、毎回全く違った様相の1時間になります。
そのたびに、不調の原因も症状も、それを経ての思いも、今抱える葛藤も、それぞれで、ひとくくりにはできないと実感します。これこそが、効率化重視の社会で、メンタルヘルスが「捉えがたいもの」「対応し難いもの」と敬遠される要因なのではないでしょうか。だからこそ、自分を含め、「当事者と個別に向き合う時間」の必要性を感じており、メンタルヘルスカフェがその時間の一部となれればと考えています。
専門家から見る、「メンタルヘルスカフェ」の役割と効果
監修の沢先生は、メンタルヘルスカフェの取り組みや役割について、以下のように解説しています。

医学博士・心理士/公認心理師 沢哲司先生
「時代が進み、技術が発展しても、メンタルヘルスの問題は依然として人間にとって重要な課題であり続けています。また、生き方について考え続けることは、人類の歴史の中で常に行われてきました。
しかし、その答えが見つかるどころか、むしろ、複雑化する一方です。
立ち止まると気づけることですが、誰でもがもうかる方法がないように、メンタルヘルスにおいても、画一的な答えや解決策を求めるのではなく、一人ひとりが自分の心と向き合うことが大切です。
メンタルヘルスラボのような場が電通に5年近く存在し、社員が利用できること自体が大きな成果だと感じています。
社内文化の中で個々が立ち止まり、自己理解や課題の正体を深める機会を提供しているという点で非常に価値のあるものだといえるでしょう」
運営に携わるラボメンバーとしては、このようなコメントをいただけて、とてもホッとしています。また、これまで約1000人の社員が参加したラボ主催のイベントに寄せられた多くのあたたかい声にも、とても励まされています。
近年は、電通グループが発表した「Diversity, Equity & Inclusion Report 2023」の健康とウェルネス領域で、dentsu Japanの「メンタルヘルスラボ」がリストに入り、社内のERG活動の代表として紹介されました。
少しずつ、メンタルヘルスについて考える機会が当事者以外にも広がり、メンタルヘルスに向けられる視線に変化がうまれ、一人ひとりがメンタルヘルスについて考えたり話したりしやすい時代の空気が醸成されてきた、と言えるかもしれません。
業務においては、即効性があり定量的でインパクトがある効果や成果を求めてしまいがちですが、ラボ活動においては、まずは安心できる安全な場づくりを続け、一人ひとりの声に耳を傾けることをこれからも大事にしていきます。
電通メンタルヘルスラボのこれから
ラボのメンバーは、自身の体験に加えて、カフェで参加者の不調体験を追体験することで、n=1の理解を深めています。さらに、前述の通り、メンバーそれぞれが、自身とメンタルヘルス領域の課題を見つめ、メンバー同士切磋琢磨しています。
ラボ全体としては、不定期ですが、専門家の先生と勉強会を開催したり、メンバーのグループチャットではほぼ毎日、何らかのメンタルヘルスにまつわる情報交換や企画を画策したりしています。
「メンタル不調による制約があっても、自分らしく働ける社会」を、一日でも早く、現実にできるように――。
目まぐるしい毎日の中でも、電通メンタルヘルスラボは、少し立ち止まって考えることができる場を作り続けます。

沢先生とそのゼミ生にお越しいただいて開催した勉強会の様子
当記事では、メンタルヘルスラボの成り立ちと、ラボが運営する当事者が自分自身と向き合う場所「メンタルヘルスカフェ」についてご紹介しました。
次回連載最終回では、ラボが最難関課題として取り組んでいる、不調の当事者「以外」へのかかわり方についてお話しします。