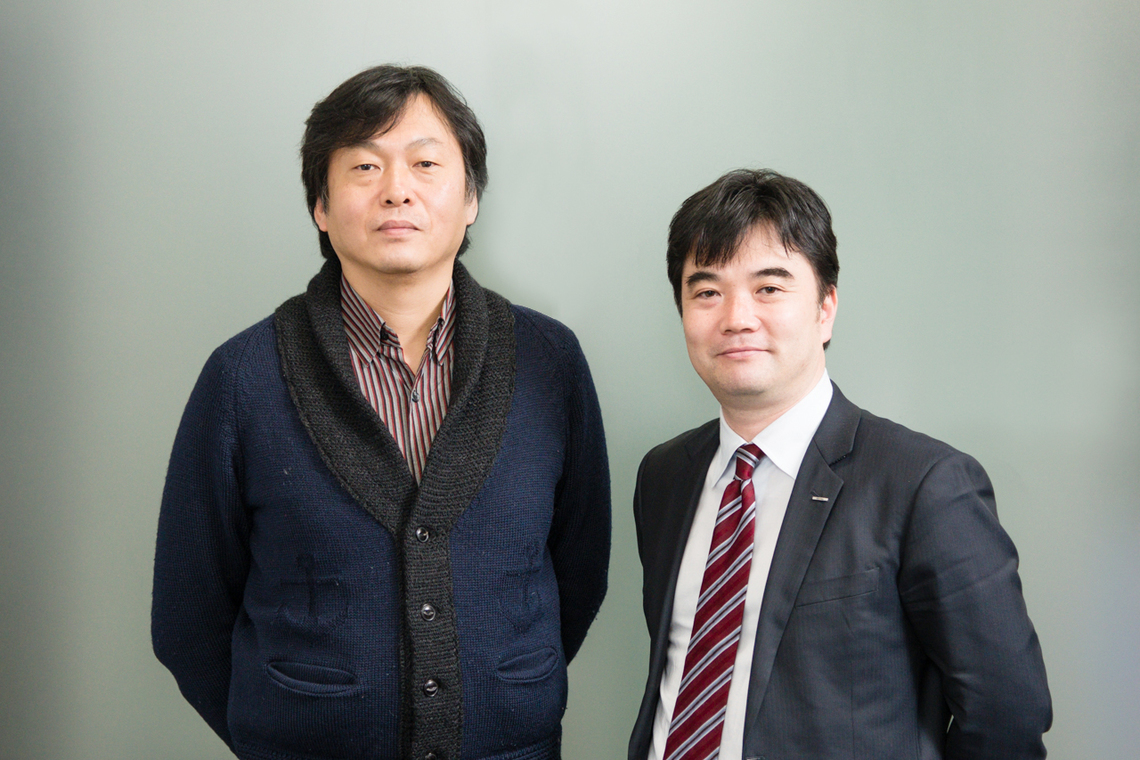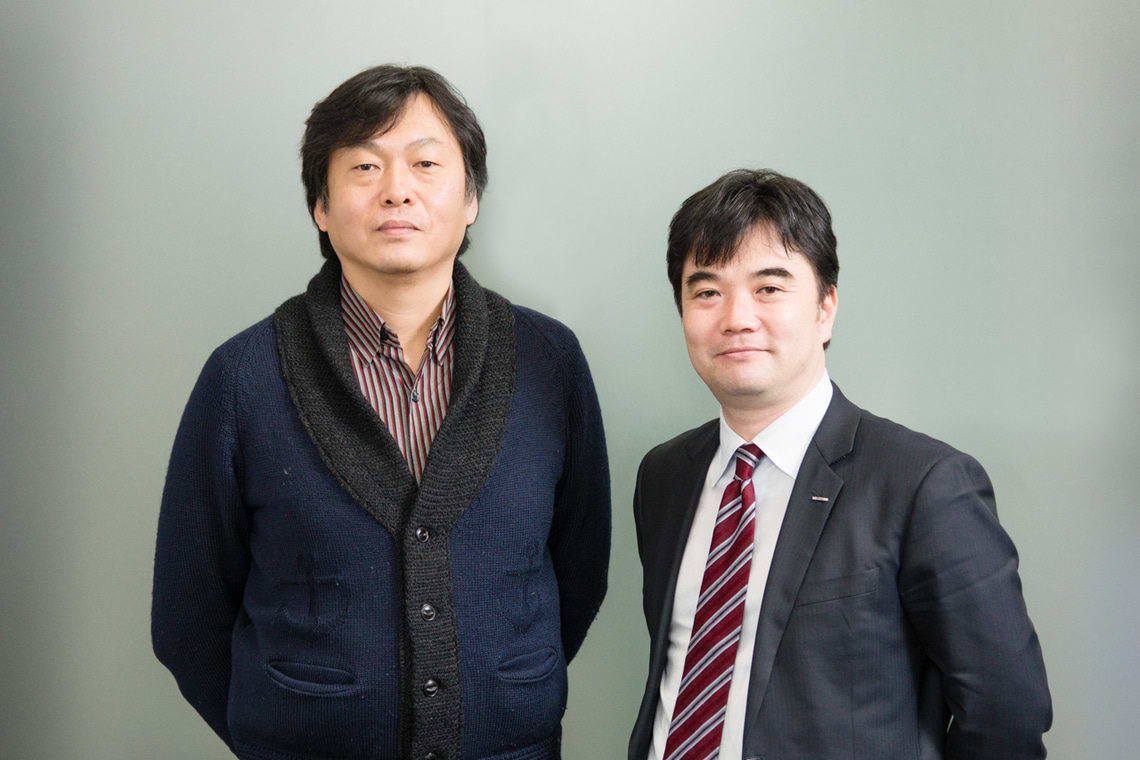日本が誇る文化を世界へ。本企画は、電通の全社横断プロジェクト「チーム・クールジャパン」のメンバーが、クールジャパンをさまざまな角度から捉え、“日本の魅力の発信”について考えていきます。初回は、チーム・クールジャパンの野上章さんが、年始に放送され大きな反響を呼んだNHKスペシャル「ジャパンブランド」を手がけたプロデューサーの小堺正記さんにお話を聞きました。「ジャパンブランドとは何を指すのか、定義を徹底的に議論した」と小堺さんは話します。
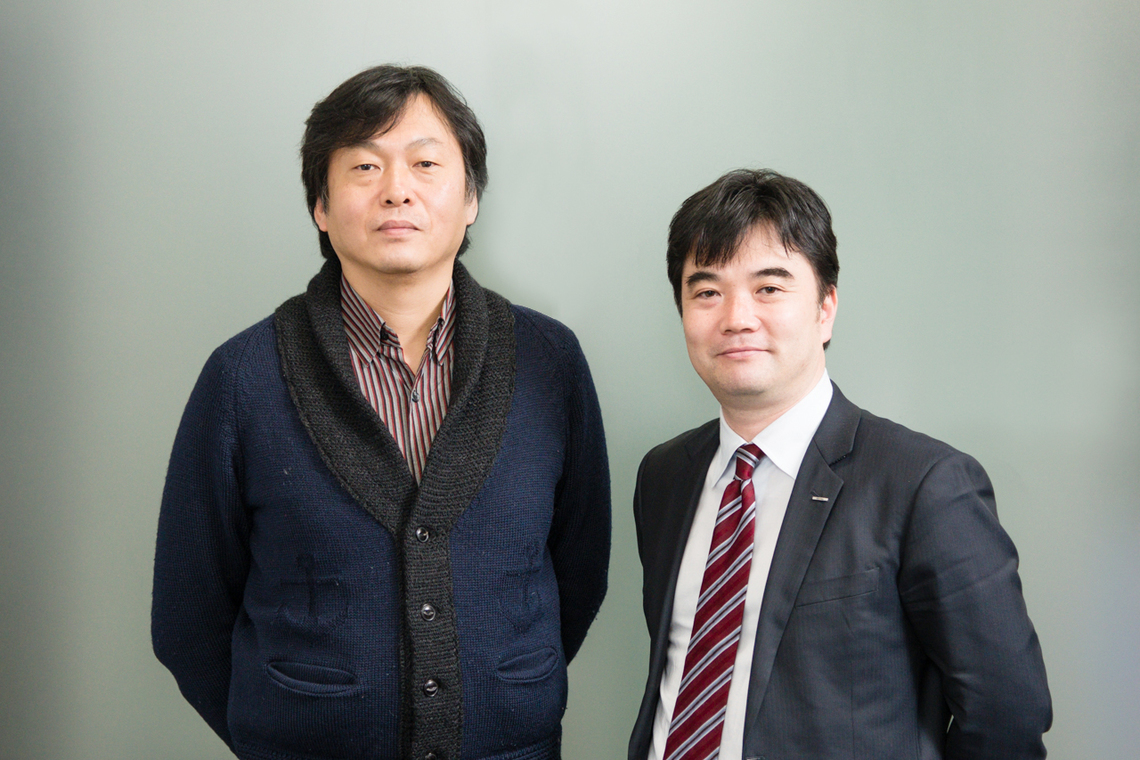
日本人の仕事の根底に流れる細やかさと職人気質
野上:今年1月に放送された、シリーズ ジャパンブランド「“食と農”に勝機あり」「“日本式”生活インフラを輸出せよ」の2回とも、大変興味深く拝見しました。反響も大きかったと伺いましたが、どのような経緯で制作されることになったのでしょうか?
小堺:ジャパンブランドは、製造業に注目した2012~13年放送のシリーズ「メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ」の続編に当たります。
元々、近年の日本企業はどうしたらかつての勢いを取り戻せるのか、という問題意識があったのですが、2012年には円高のせいもあって名立たるメーカーが軒並み大赤字を喫し、海外勢に水をあけられました。そこで状況を批判してばかりいても仕方ないので、番組として地に足が着いた対策を打ち出すために、「メイド・イン・ジャパン」では経済番組としては珍しく年表を用意して歴史軸で考えました。
これが好評を得て、次は製造業にとどまらず日本経済全体に視野を広げようと、今回のシリーズにつながったのです。
野上:“ジャパンブランド”というネーミングは、どこから生まれたんですか?
小堺:メイド・イン・ジャパンの制作を踏まえて、改めて日本の力を示すキーワードを考えたとき、そこには業種を問わず何か共通した精神性が流れていると感じたんです。ジャパンブランドという言葉は、皆でコンセプトを考えているときにメンバーの一人がたまたま口にしたんですが、それにピンときまして。
でも、こういう大型のシリーズ番組はコンセプトの設定がとても大事なので、制作に入る前に「この番組における“ジャパンブランド”とは何なのか」を徹底的に議論しました。日本国内で生まれたものならいいのか、“日本的”であれば海外で外国人がやっていてもいいのか、そんな議論にいちばん時間を割きましたね。
野上:そうなんですね。そこで、どのような内容に収束したのでしょうか?
小堺:ジャパンブランドとは何かというと、やはり日本人の細やかさとか、人に見られていなくても手を抜かずに高みを目指す、職人気質が込められたものだろう、と。
たとえば新幹線の清掃スタッフの徹底した仕事ぶりや、野菜の甘みを追求するために土づくりから研究するなど、誰に言われたわけでもない「ここまでやらないと自分が納得しない」という強いこだわりが価値を生み出しています。番組では、そういう商品やサービスに焦点を当て、日本の強みを再発見するようなつもりで取り組みました。

目先の勝ち負けばかり追うと発展がない
野上:たしかに、日本にいると鉄道の車内のきれいさなどは当たり前に思ってしまいますが、外国人から見ると驚かれそうですね。鉄道会社の方も番組内で「普通にやっていることにこれほど価値があるとは気付かなかった」と言われていましたが、取材を通して、こうしたら日本の価値をより発信できる、と思われたことはありますか?
小堺:まず、日本って何なのかを見つめることが、逆説的に「外からどう見られているのか」を考えることになっていたと思います。それに加えて、多分、目先の勝ち負けを考えてはいけないんだろうなと。
野上:目先の勝ち負け、とは?
小堺:言い換えれば、損得というか。番組でも取り上げましたが、タイの治水事業で、日本企業の連合チームが予算の都合で折り合わなかった、というエピソードがありました。たしかに、この1回だけで考えれば見合わなかったかもしれませんが、次につながる可能性は大きかったのではないかと。ほかの取材でも、5年後、10年後を考えているのかな、と思うことがしばしばありました。
元々日本では、近江商人の「三方よし」の精神で商売がなされてきました。それなのに、大手企業の多くがいつの間にか分かりやすい短期利益追求型に変貌してしまったような印象を受けます。そこは、見直されるべきじゃないかと思います。
同時に、チームの組み方にも問題があると感じました。タイの治水事業に参画する、というくらいの規模になると、日本を代表する大手企業が集結しますが、そうすると全員が4番バッターのようなチームになってしまってうまくいかない。10社なら10社の合意を取っていくと、最大公約数に落ち着かざるを得ず、しっかりと長期のロードマップを組み立てるのも難しくなります。
一方、タイの新都市交通のプロジェクトでは、最終的に日本の大手商社が旗振り役となってチームをまとめていました。日本チームと手を組んだ理由をタイのゼネコンの会長は「情熱があった、本当にタイのために尽くしてくれると感じた」と話していました。新興国ビジネスにはリスクもあります。それを乗り越えて一緒にやりましょう、と言える人が少なくなっているのは残念ですね。
自分たちが乗り越えた経験を新興国で生かす

野上:日本に根付いていた「三方よし」の精神や、他者に与えたらそれがいつか返ってくるといった考えが、現代では維持しにくくなっているんですね。
短期的な結果を求められる現代の環境の中でも、強みを発揮して新興国に貢献している事例はありますか?
小堺:たとえば、大手住宅設備メーカーがケニアの貧困層向けに、インフラ設備が不十分でも住める再生エネルギーを使った住宅の実験を行っています。
ケニアはアフリカの中でも日本との外交がとてもうまくいっていて、JICA(独立行政法人国際協力機構)を介して日本人が現地で技術指導をしたり、逆にケニアからたくさんの留学生を日本に受け入れたりと、特に人材育成を通して信頼を築いています。その縁で、現地の課題の解決に日本企業が乗り出すことができました。
この試みはもちろん他国にも展開できますし、10年20年先のビジネスモデルがつくれる可能性も十分にあります。さらに、省エネや節水は今後先進国でも課題になりますから、その方向でも事業性が高い。外務省の援助事業を通してなど、実はこのようなマッチングの種は世界中にまかれているのですが、縦割りの組織構造のこともあって、なかなかビジネス分野との連携ができていないのが現状です。
もうひとつ、北九州の国際化へ向けた動きも好例ですね。市が地元企業のセールスマンになって、高い技術力がある中小企業と新興国との橋渡しをしていました。
野上:番組でも、かなり詳細に取り上げられていましたね。
小堺:そうですね。これも非常に官民の協力がうまくいっていました。成功の理由は2つあると思っていて、ひとつは、北九州市がすさまじい公害を克服した経験を踏まえてブランディングしていることです。公害に加えて、シャッター商店街や高齢化、大都市なのに貧困率が高いなど、自分たちの課題への取り組みを、新興国に生かそうとしています。
もうひとつは、国際化を意識するようになった20年以上前、まず留学生の受け入れに取り組んだことです。それも1000人単位で。国費留学生ですから学力も意欲も非常に高く、国に帰れば要職に就いていく。すると、国同士のプロジェクトでどこと組むかを検討するとき、必ず日本を選んでくれます。
ここまで大きな展望を持って企業が取り組むには、会社の体質や組織論、教育の問題などいろいろな問題がからんできますが、戦術ではなくビジョンを持った戦略を立てていく必要があることは学ぶべきだと思います。
(次回へつづく)