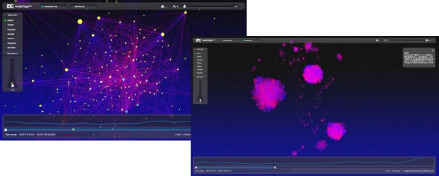今回のマスター・オブ・イノベーションマネジメントは、株式会社ONTROXの有田一樹さんをお招きし、日米でのイノベーションやスタートアップの違いについて、人やコミュニティー、取り巻く環境をテーマにした対談前編をお送りします。シリコンバレーの“今”が日本の“今”とどう違うのかを有田さんとともに探っていきます。

テック系とサービス系のイノベーションと言語の問題
志村:今回は、国内外でご活躍されている有田さんと、日米の企業支援環境の違いからイノベーションの話をしてみたいと思います。有田さんが共同創設者をされているONTROXは、ジェトロ(日本貿易振興機構)のイノベーション支援プログラム「ジェトロ・シリコンバレーイノベーション・プログラム」(SVIP)に選定されていますが、ここから何か事業を始められるのでしょうか。
有田:ONTROXでは現在、IDG(Insight Digger Technology)という統合解析フレームワークに力を入れています。このIDGは、簡単にいえば点と線で関係性をマッピングするフレームワークで、膨大なデータを解析し、ビジュアライザーで関係を可視化できるものです。たとえば、ツイッターで誰が何をつぶやき、それに対して他のユーザーがフォローやメンションなどの行動をどのように起こしたかをマッピングできるもので、電通の「くちこみデザイナー」にも採用されています。
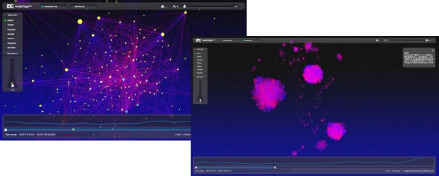
IDGのイメージ
SVIPに選定されることによって、米国でIDGのビジネスを行うことを考えています。日本からシリコンバレーに乗り込んで成功しているケースは、少ないと言わざるを得ません。ジェトロもこれまでは補助金などでベンチャーを支援してきたのですが、それだけではなく、ノウハウをつけるような取り組みを行い始めていますね。
志村:海外でアイデアを出して、絞り込んでダイバーシティーに適応していくということは、論理的には分かっていても、コアな事業として成立させることは非常に難しい状況です。日本と米国でも環境やビジネスに対する考え方が大きく違うと思うのですが、日本と海外の両方を経験されている有田さんは、生々しい知見をお持ちであると思い、今回対談させていただきました。
日本と米国では、イノベーションの起こり方がテック系で始まるか、サービス系で始まるかの違いがありますが、有田さんはどのようにお考えでしょうか。
有田:日本は技術を開発している会社は数多くありますが、テックカンパニーとしてのスタートアップや世の中にない技術を売りにしたスタートアップは圧倒的に少ないと思います。米国では、ビッグデータブームで解析の市場が脚光を浴び、テックカンパニーが多く出てきていますね。しかし、米国でもビッグデータブームの前はSNSなどのサービス系のスタートアップが多かったのではないでしょうか。現在は、サンフランシスコはサービス系が多く、シリコンバレーではテック系が多いという話を聞きます。
志村:米国では変わりつつある中で、日本ではサービスが中心となっているのは、コストがかからないとか、すぐにローンチできるというのが理由なのでしょうか。
有田:サービスがB2C寄りであると考えるなら、一発当てると大きく成長できるのが魅力ですよね(笑)。また、サービスの場合は専門家がいなくとも、SEやプログラマーとアイデアを出し合っていくことができます。一方で、テクノロジーをメーンにすると、テクノロジーを育む土壌やチームが必要になり、テクノロジーを知らなければアイデアも出すことができません。
志村:日本の方が、手段となる技術の知識が少ないということでしょうか。
有田:皆、勉強はしてきているのですが、大学のカリキュラムによるところが大きいですよね。たとえば、以前、私が米国で事業を起こすために人工知能(AI)に関する本を探しても、日本の書店にはほとんどありませんでした。今は、書店の棚一面にAIの本が並んでいますし、アルゴリズムを理解しなければならないというように変わってきていると思います。
志村:論文や技術に関するドキュメントは英語で書かれており、世界中で知識をシェアするときにも英語が使われます。言語の問題から、日本は受け身でいなければならないと感じることも多いのですが。
有田:昨年(2013年)にIEEE(米国電気電子学会)の学会に行ったのですが、日本人がエントリーするために日本語の論文を英語に翻訳しても、論文の内容の前に「英語がひどいと返されることもあるようです。英語のライティング能力や、英語圏の人たちの思考に沿ってないと理解されないということはありますね。
志村:言語の問題で、英語圏以外の人たちがナレッジシェアやコラボレーションに参加しづらく、そこの障壁が結構大きいと感じます。それを打開しないと、知識を集約してブラッシュアップするようなイノベーションが起こりにくいと思いますね。
チーミングの重要性とシリコンバレーのルーキーの素養
有田:以前、大企業が訴訟を起こすときに大人数の弁護士団をつくっても、それらをまとめるマネジメントにコストがかかってしまうという話を弁護士から聞いたことがあります。3人くらいが一番いいチームで、そのうちの優秀な1人が戦略立案すれば、大弁護士団と変わらない仕事ができるというのです。エンジニアの世界も同じで、プログラマーが100人いてもイノベーションは起きません。少人数のチームの方がイノベーションを起こしやすく、うまく回せると思います。

志村:チーミングと役割分担は重要で、どうやって必要最小限の母集団に区切っていくかや、どのようなスキルのメンバーを集めるかが課題だと思います。自然に3人が集まってくるのか、システマティックに組んでいくのかについては、どう思いますか。
有田:チーム編成はしっかりと考えないといけないと思います。たとえば、アルゴリズムはすごく考えられて数学的にも優れていても、情報工学の基礎がなければ、サーバーなどのインフラのことが分からず、大量のデータを扱うようなアプリケーションを動かすことができません。数理的な部分が優れた人と、アルゴリズムをある程度知っていて情報工学に詳しい人をチームにしないと、製品化が行えないことになります。
志村:海外では、ルーキーと呼ばれる人や大学を卒業する人が、日本よりもさまざまな知識やスキルを持っていて、チームの複数の役割を負えるという印象があります。そのあたりも、テック系のイノベーションを日本で起こしにくい要因となっている気がするのですが。
有田:シリコンバレーやベイエリアの優秀な大学は、学費が非常に高く、お金持ちでない人はローンを組んで大学に通っています。また、四年制大学を出てもエンジニアとしてはまだまだなので、Master(修士課程)やPh.D.(博士課程)にも進み、MBAを取得するころには30歳のルーキーとなっているのです。ローンも多く抱えているので、彼らは、社会人1年目から高額な給料をもらえるところへ流れていきます。
志村:一発当ててお金持ちになりたいという人がシリコンバレーには多いと思うのですが、マインドセットから違うのではないでしょうか。大手企業に入ってそれなりの給料をもらいたい、というよりは、アイデアを生かして一発当てたいといったハングリーさは、米国と日本ではかなり隔たりがあると思います。シリコンバレーの1年目のルーキーは、どういった気構えで企業に入り、アイディエーションなどを行っているのでしょうか。
有田:とあるシリコンバレーの企業では、入社するとバルーンを机に付けられます。そのバルーンは2週間もすればしぼんでしまうので、それまでにアイデアを必ず出さなければなりません。アイデアを2週間で出すことで、仲間として認められることになります。
志村:日本では、入社したらまずマナーなどの研修ばかりで、アイデアに対して時間を使うという発想にはなっていませんね。入社時のマインドセットとスキルセットから違うし、集合研修などをしなくてもシリコンバレーのルーキーたちはアイデアをひらめかせる素養があるのだと思います。
有田:日本の会社もシリコンバレーのまねをして、ビリヤード台を置いてみたり、バランスボールを置いてみたりしています。しかし、シリコンバレーでは、オフィス環境を30歳すぎまで勉強してきたキャンパスに近い雰囲気にして、できるだけ発想しやすい環境にしているんですよね。
どこまでアイデアを公開して何を守っていくのか
志村:シリコンバレーでは定年まで会社にいるという考えもなく、よいアイデアを持っている人は出て行きたいと思っているでしょう。日本とは、知的財産やアイデアの囲い込みに対する考え方も違いますよね。アイデアを買うよりも人ごと買ってしまうようなヘッドハンティングがあるなど、環境が違い過ぎると思います。
海外では、知財やアイデアを持っているときに、人に言ったりするのでしょうか。それとも、形をつくり上げてから人に見せるのか、チームや仲間だけには話すのか、どのような形でコアなアイデアを表に出していくのでしょうか。

有田:スタートアップの場合は、少人数で始めて、たとえばテック系であれば、コアな技術を短期間で飲まず食わずで仕上げている場合もあります。コアな技術については、ファウンディングするときや、企業に使ってもらうときには、当然話に上ることになります。玉ねぎにたとえて、むかないと食べられないし、むきすぎると小さくなってしまうというように、どこまで見せるかというバランスが問題ですね。
志村:オープンソース化するところはして、守るところは守るということが非常に手慣れていると思いますね。お金がない企業もあるので、特許でコストがかかるよりもコミュニティーをつくってデベロッパー間で相互に守り合うような取り組みも行われています。
有田:オープンソースを、日本の組織が中心になって扱っていることがほとんどないですよね。
志村:僕らも業務中にオープンソースにするとか、APIでとか、話には出ますが、実際には全然やっていません。本来は、APIを1分間に何回使わせて、どこから課金するかなど、タクティカルに技術を売っていく必要があるのに、根本的な話になっていないケースが多々あると思っていて、海外に比べて手慣れていないと感じます。
有田:ONTROXでも、Ruby(日本で開発されたプログラミング言語)で書かれているIDGのプログラムをエンジニアがオープンソースにしたいと言ったことがあったのですが、結局は誰も使ってくれませんでした。一度もオープンソースのコミュニティーに入ったこともないのに、コミュニティーの主体になってもうまくいくはずがなく、コミュニティーをしっかりとつくれなければなりません。オープンソースのコミュニティーに積極的に参加して、近い関係にある人が何かをオープンソース化すれば、結構使ってもらえると思います。
志村:イノベーションマネジメントツールにアイデアを出してください、とオンラインで呼びかけているのですが、オンラインのコミュニケーションの関わりを持っていない状態で、ソースやアイデアだけを入れて、後で見てブラシュアップしてというのは、なかなかうまくいかないかもしれないですね。最初からコミュニティーに属している人がいて、ここまでレディネスができているから、次にこのソースやアイデアと出していけば幅が広がっていくということですね。日本でも、アイデアを出し、さらに広義のネットワークに知識を流していくことのできる人を育てていかないといけないですね。