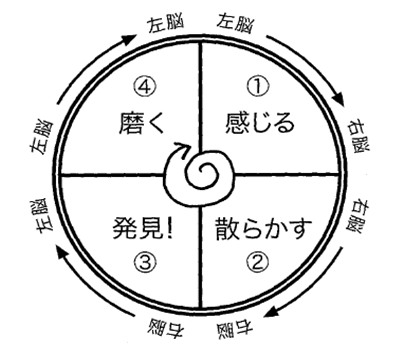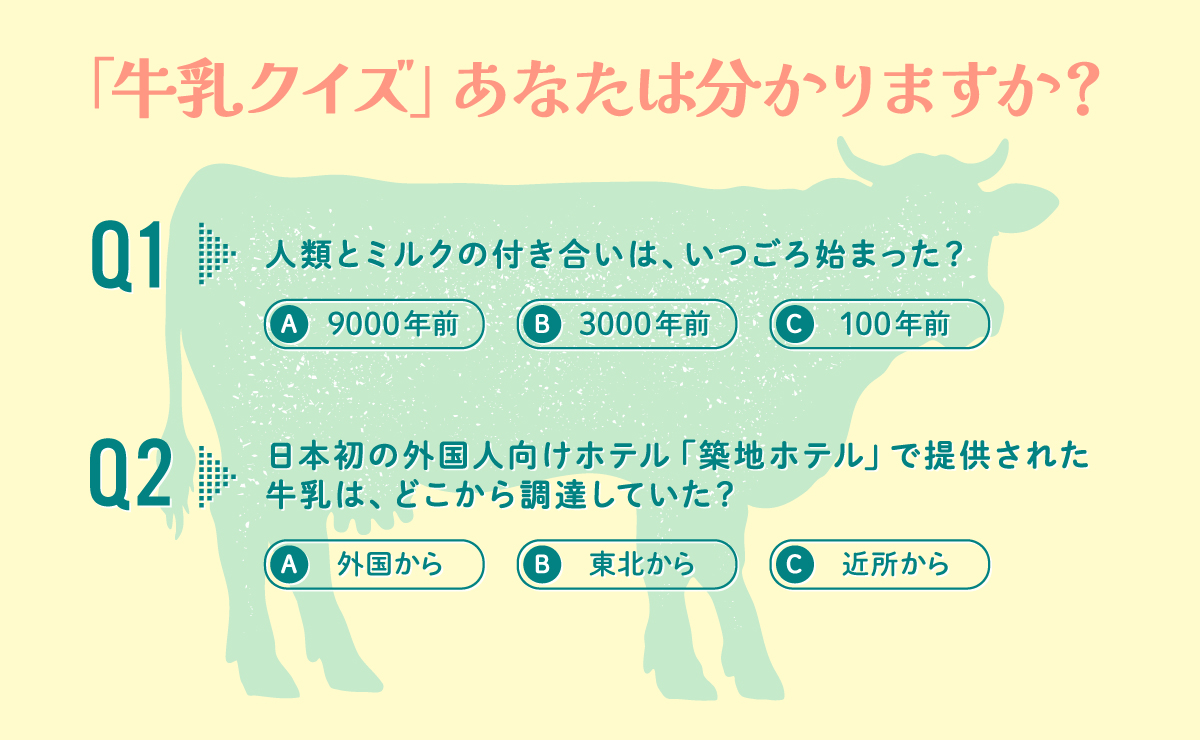アイデアの材料が手に入ったら、次は「散らかすモード」の出番です。ビジネスの世界では資料を入手したらすぐ「整理」するのがジョーシキかも知れませんが、ここでは思い切り散らかします。
とはいえ闇雲にカオスを突き進んでも仕方がありません。考えるべきは一点。「ヒトとモノ・コトの新しい結びつき」です。

新しい結びつきをさがせ!
当たり前のことですがヒトには無数の側面があります。たとえばぼくはきっとやさしくて怒りっぽく、甘党の辛党、社交的で人見知り、サディスティックのマゾヒスティック…。一見すると矛盾する無数の側面で構成されているはずです。
モノ・コトについても同様です。大学の授業でよく「若者にもっと豆腐を食べてもらうアイデア」を課題に出すのですが、「安価な」「ヘルシー」「白い」ものというレベルでとらえている限り、なかなか妙案は生まれて来ません。「武士のタンパク源」とか「豆腐屋の朝は早い」とかあらゆる側面を用意して、どうすればそのヒトはそのモノ・コトを手に取ってくれるのか、しつこく行き来しながら「新しい結びつき」を考え散らかすのです。
新人アートディレクターの高嶋結さんは石川県の高校時代『マルゲリータ女王のピッツァ』※1という本に出会ってデザインの道を志したと言います。
タイトルにもなっているエピソードは有名です。19世紀後半ようやく統一が叶ったイタリアの女王が南部にある大都市ナポリを訪れた時のこと。街角で目にしたお店の看板メニュー「ピザ」をどうしても食べたくなった彼女は反対を押し切り、ただちに届けるよう命じたと言います。その時困った職人ドン・ラファエレ・エスポジトが即興でこしらえたのがトマト(赤)、チーズ(白)、バジル(緑)でイタリアンカラーを表した「マルゲリータピザ」だった、というお話です。

これは目黒の名店「ラ・バラッカ」のマルゲリータ。絶品です。
筆者である蓮見孝先生※2はラファエレの行動を次のように解釈なさっています。
ラファエレは、城からの突然の注文を受けた時、直観的に「女王さまに喜んでもらおう」という「ポジティブ(前向き)なインスピレーション」を持ちました。そうでなければ即興でオリジナルのピッツァをつくるなどという面倒臭いことはしなかったはずですからね。モノづくりに取り掛かる時に、「誰かを喜ばせてあげたい」という気持ちを持つこと、これはとっても大切なんです。それは時代を超越したコミュニケーションの基本であり、決して忘れてはならないことです。ちょっとクサい話になりますが、〝愛〟こそが全ての行動の起点なのです。
少し引用が長くなりましたが、ここは重要なポイントです。ビジネスになるとみんな急に生真面目になってこの「基本」を忘れてしまいます。数値データで適当に正しいと証明さえされれば「まぁ、この程度でいいか」なんて妥協しがちです。しかしそんな中途半端な「(自称)アイデア」でヒトの気持ちを動かせるわけがありません。「南イタリアの国情が安定しているかどうか心配している」という女王の側面をとらえてピザのトッピングを(それも極めてシンプルに)工夫したラファエレのように「愛」をもって「新しい結びつき」を求めなければなりません。

新人ADでよんななクラブも一緒にやっている高嶋さん(左)と同じく新人ADでセッシャー1も手伝ってくれている浮島さん。ふたりともデザートまで完食。
この辺の七転八倒の仕方については次回、つづきをお話ししましょう。
どうぞ召し上がれ!
※1 蓮見孝『マルゲリータ女王のピッツァ』筑波出版会、1997年より抜粋。
※2 札幌市立大学学長。高嶋さんは筑波大学で師事。