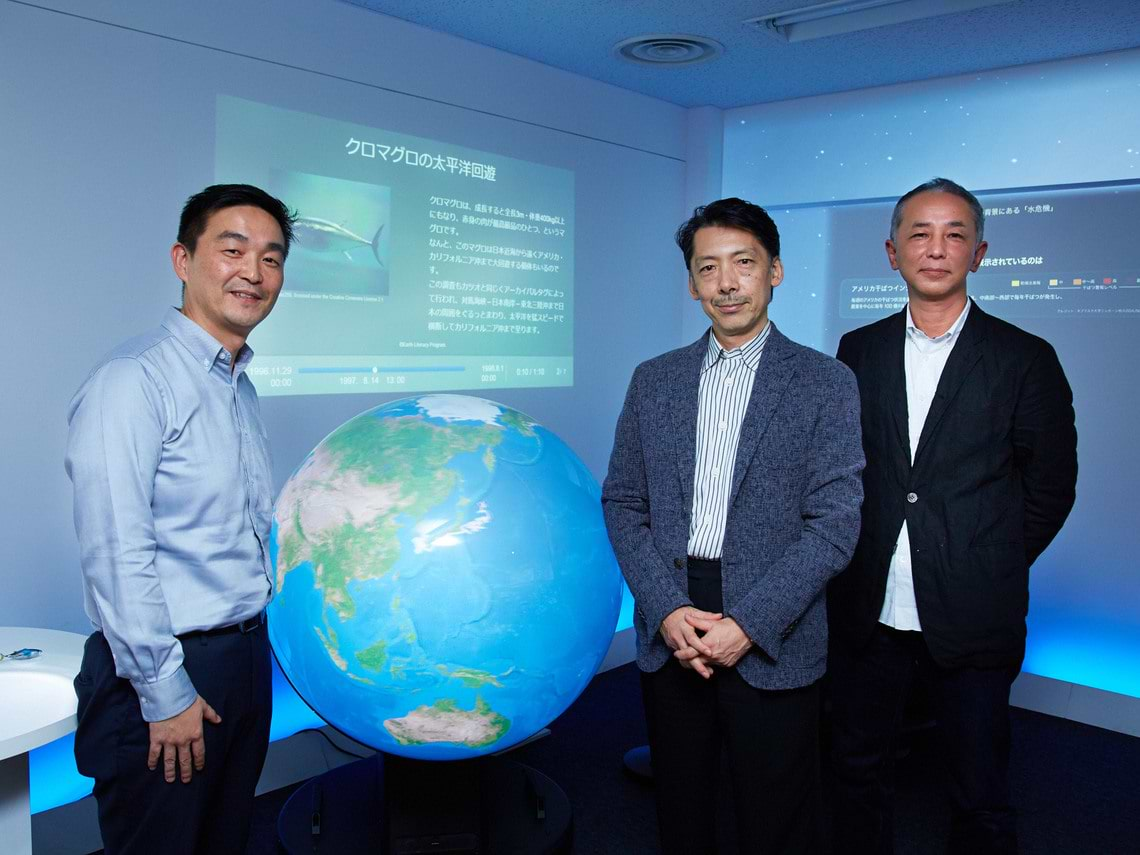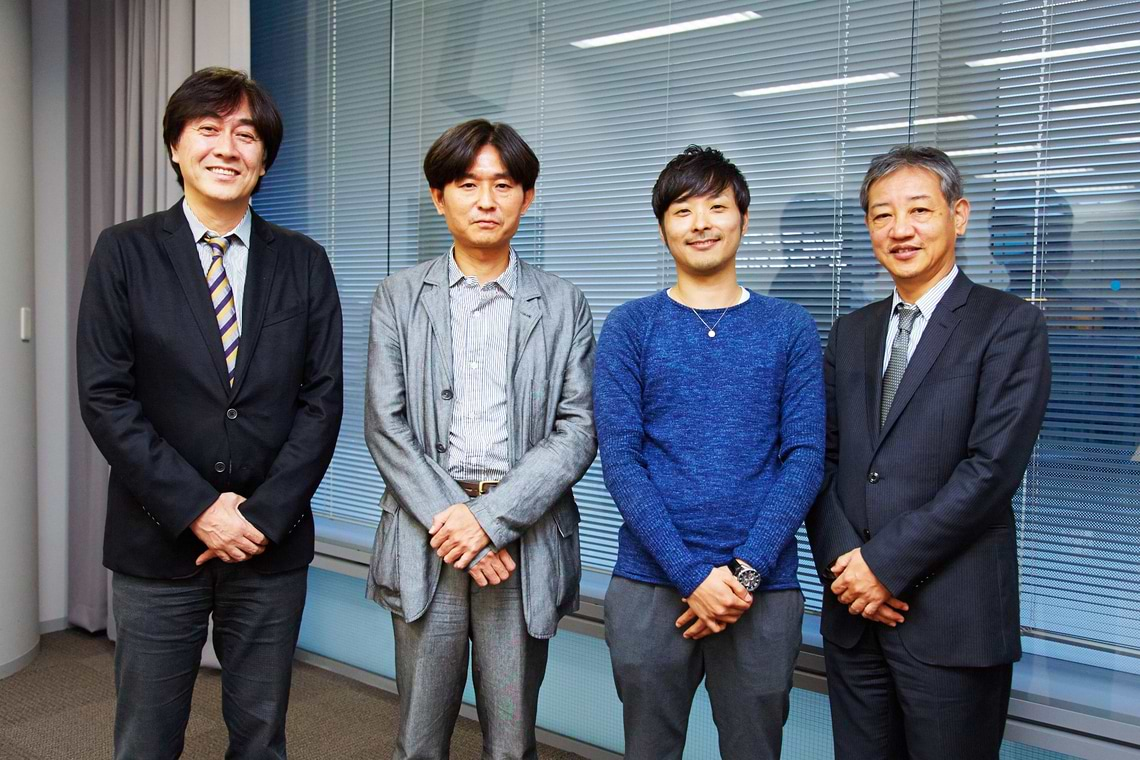11月8日、ミツカングループ(愛知県半田市)が「ミツカンミュージアム」(MIM=ミム)をオープンしました。ミュージアムの建築設計を手掛けたNTTファシリティーズの小川大志氏、展示の映像作品をつくったロボットの清水健太氏、企画を担当した電通テックの遠藤聡氏と、プロデューサーである電通イベント&スペース・デザイン局の内藤純氏が5年にわたる制作過程を振り返り語り合いました。
取材・編集構成:金原亜紀 電通イベント&スペース・デザイン局

(左から)内藤氏、小川氏、清水氏、遠藤氏
■記憶、過去から未来への「つながり」のつくり方
内藤:11月8日にミツカンミュージアムがオープンしましたが、電通がこの作業をスタートしたのは2010年の3月でした。東日本大震災を挟んで5年半の長きにわたるプロジェクトは、私の電通人生の中でも一番長いプロジェクトじゃないかと思います。初めて半田という町に行ったとき、運河沿いに黒塀の建物が連なる町並みは非常に個性的で、土地の持つ力をすごく感じました。
ミツカングループは江戸時代から半田の地でずっと、酢づくりという営みを重ねてきた。江戸時代から脈々と続く先代たちのものづくりへの思いをどう表現するかということを考えたら、「食といのちの春夏秋冬」というテーマに行き着きました。ミツカングループが提供する食の技術や歴史と、半田という土地を通した四季や、食をめぐる季節感の表現を目指して計画したわけです。
建築ではNTTファシリティーズが全体の設計・監理をされましたが、まず一番初めに小川さん、全体の建築をどのように考えられましたか。
小川:内藤さんがおっしゃるように、初めて計画地を訪れた際、何とも言えない、ゆったりとした独特の時間が流れているのを感じました。200年続く酢づくりの歴史が醸し出しているものなのかもしれません。ミツカングループは、本社地区の再整備という一大事業を決断されたわけですが、目的を達成する中で昔の景観を焼き直すのではなく、真に歴史を継承する場を創造する必要があると考えました。抜け殻みたいなテーマパークを創っても「生きた景観」にならない。前の施設を新しい機能に更新しながら土地の記憶を継承するという難しい課題でした。
内藤:展示でも土地の持つ「感覚」や、ここで先人たちがずっと働いていたという「記憶」が、新しい形で見えるように、「大地」「風」「時」「水」「光」の五つのテーマゾーンに分けました。
小川:地区全体でも「継承しながら新しくつくる」考えで、エリアごとにテーマを与えています。運河を挟んでミュージアムの向こうの第2工場側は、「伝統」を継承しようという考えで前のまま残しています。一方、発展を続けるミツカンの中枢である本社や研究棟は「革新」のかたちです。そして今回のミツカンミュージアムはその間にあって「伝統・革新・環境」が融合する場となっています。

■「温故知新」をどう建築設計に落とし込むか
小川:多くの人の記憶に残る街路沿いや運河沿いの景観を損なわずに新しさを感じさせる必要がありました。この建物は、外装には機能面から金属を用いていますが、屋根は瓦葺といった特徴的な構成になっています。
また建物ボリュームは、新たな機能のために昔より一回り大きくなっており、セットバックしたり屋根勾配を従前に近づけるなど、空間の余白のプロポーションを変えない工夫をしました。昔ながらのシルエットをつくる運河沿いに対し、現代的な水平ラインの中庭側が別の建物のように表情が異なるのも大きな特徴となっています。
内藤:僕も景観に対しては、絵画的なこだわりがありました。よく京都とかへ行くと、建物の中から外を見ると、庭が切り取られる日本的な美がありますよね。何とかその「風景の切り取り」を実現したいと思って、「風の回廊」の最後に景観が見える切り取り窓を作りました。
遠藤:中身の展示も「温故知新」から始まっていて、展示の順番としても、半田に育った酢づくりの産業をミツカンが起こしてきた歴史、そして未来に向かってというつながりになっています。完全アテンド方式の施設なので、ストーリーの流れは大切でした。
内藤:江戸時代からの長い営みを、めぐる季節の重なりとしてうまく伝えたいという思いと、ミツカングループのグループビジョン・スローガンである「やがて、いのちに変わるもの。」を訴求したくて、「水のシアター」をロボットにお願いしました。
清水:4年ぐらい前に内藤さんから「食といのちの春夏秋冬」というテーマを頂いて、日本の食は「春・夏・秋・冬」という季節の記憶と深く結びついていることを水のシアターでは表現しました。これだけの時間をかけて撮影をやらせて頂いたのは我々としても初めてで、実際に四季をきちんと1年間追いかけて撮影ができた貴重な経験でした。長い時間をかけて撮ることの難しさもある半面、その醍醐味もありましたね。
内藤:最近はCGが多いけれど、あらためて今回の映像を見ると、ロケをして季節を追いかけている映像が本当に美しいと思った。ロケ地の地元の人が出演していたのも良かったですね。
清水:やはりリアルですよね。例えば、青空の下で食べたおにぎりがうまい!という感覚は誰にでもあると思うんです。おいしかったとか幸せだったとかは、大体共通した人間の体験や記憶としてあると思うから、映像ではその「誰の中にでもある記憶」を確実に呼び覚ましたかった。
みんなの記憶の中にある、おじいちゃんやおばあちゃんのイメージを求めて、現地でおじいちゃんやおばあちゃんに声を掛け撮らせてもらうことを繰り返していたのですが、それを地道に積み重ねた価値やリアリティーが、結果としてすごくあったと思いました。
内藤:皆さんに出演をお願いして、すぐに出ていただけるものですか。
清水:最初のうちは、やっぱり「恥ずかしい、恥ずかしい」って感じでしたけれど、話しながら緊張を解いていくと段々といい顔が出てきて、その笑顔というのは心を許してくれた瞬間の、タレントさんの演技ではない本当の笑顔なので、やっぱり強いですよね。出てくださった方たちには、とても感謝しています。
内藤:そのあたりのすごく繊細な表現が、内覧会で号泣した人を生んだんですね。