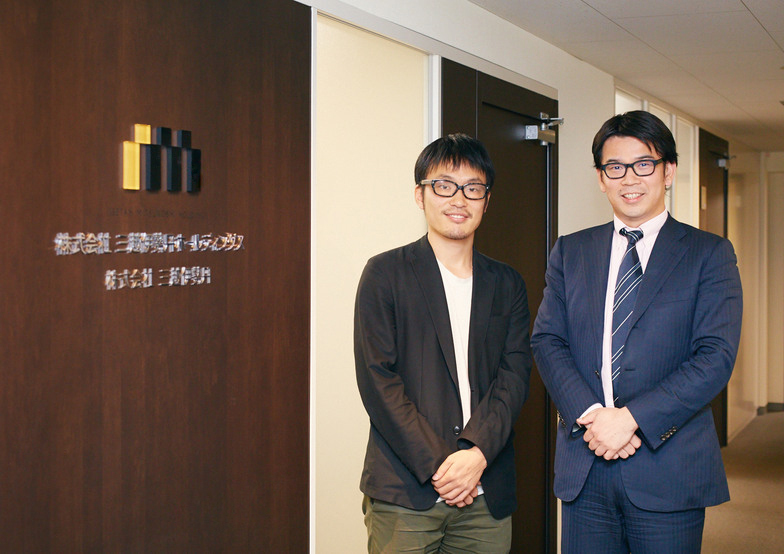「会いたい人に、会いに行く!」第3弾は、三越伊勢丹ホールディングス(HD)秘書室特命担当部長の北川竜也さんに、電通イベント&スペース・デザイン局の尾崎賢司さんが会いに行きました。3年前に大西洋社長に誘われ入社し、新しいビジネスモデルの探求や、デジタルテクノロジーと百貨店が培った「売りのノウハウ」「体験価値」のコネクトを推進する北川さん。そんな北川さんが考える、未来の百貨店のあり方とは?
百貨店の300年の歴史が培ってきた資産を、どう生かすか
北川:旗艦3店(新宿伊勢丹、銀座三越、日本橋三越)を中心とする百貨店は、われわれにとっての文化そのものなのです。そこでお客さまとの関係性が築かれた歴史があり、とてつもない価値が300年の歴史や暗黙知の中に詰まっている。
一方で、世界から来ていただくお客さまとの接点として、イセタンサローネ、イセタンハウス、イセタンミラー(※)など、気軽な接点として小さなお店を軸につながっていっていただく。あくまでそこはお客さまとの接点であって、将来的には、そこで今までと同じように物を売り続けるかどうかは正直なところ分からないですよね。物を買うという手段はオンラインでもご提供できるわけなので、そこにしかない豊かな時間を過ごしていただくための空間になっているかもしれない。
※イセタンサローネ、イセタンハウス、イセタンミラーなど中小型店について
三越伊勢丹HDの強みである編集力を活かして顧客接点拡大のため進めている中小型店舗の出店戦略の一環。
「ファッションセレクトストア」として昨年4月に六本木にオープンしたイセタンサローネ、同12月に丸の内にオープンしたイセタンサローネメンズ、「中型セレクトストア」として4月に名古屋にオープン予定のイセタンハウス、首都圏を中心に12店舗展開する「ラグジュアリーコスメセレクトストア」のイセタンミラーなどがある。
尾崎:その上で、これは三越伊勢丹として守り続けるということは何ですか。
北川:「本質」に寄り添う会社でなきゃいけないと思います。テクノロジーの進化は生活を大きく変えましたが、15年前を振り返って考えると、本質的に人間が追求しているものは今も変わっていないのではないでしょうか。おいしいものを食べて、友達と会って、家族と過ごして、音楽聴いて、映画見て、ふだんの日常の行動はあまり変わっていなくて、変わっているのはそこに至るまでの過程だったり、その情報なり、データを得る手段だったり、間をつなぐものの変化が大きいということだと思います。
我々が本質的に追求していかなきゃいけないのは、お客様の人生を豊かに生きたいという思いに常に寄り添うことだと思います。そこの本質さえ外さなければ、提供する商品、サービス、その提供手段は多種多様でいい。お客様の美を追求したいという思いを例にとれば、15年後に今と同じ化粧品が販売されているかどうかさえ分からない。何を売るかという定義ではなくて、女性の美に一番近いところにいて、しかも一番手にとりやすい手段でご提供するという本質にどれだけ寄り添えるか、それは多分譲っちゃいけないこと。そういうことを追求すべきだと思うのです。
「コミュニティー」づくりに、テクノロジーを活用する
尾崎:僕らの仕事のやり方も、変えていかなければなりませんね。
北川:広告宣伝の在り方もすごく変わるだろうなと思っています。インターネットの時代になって、クラウドを活用して空間を超えてある特定のコミュニティを形成する、という事が可能になりました。その代表格の一つがアメリカの手づくり品販売サイトのエッツィ(Etsy)かもしれません。
マニアックな趣味を持っている人が、東京エリアでは500人しかいなくても、日本全国に枠を広げて考えたら1万人いるかもしれない、全世界へ広げてみたら10万人いるかもしれない。この10万人を一カ所に集めようとしてもほぼ不可能ですが、インターネットだと可能になるわけです。もしこのコミュニティに、その趣味に適合するコンテンツをご提供できれば、これほどコンバージョン率の高いマーケティングはないわけです。これからのマーケティングは、いかにそういうスモールコミュニティーをたくさんつくり、お客さまの濃いニーズ、よりパーソナライズされた情報に寄り添っていくか、が重要だと思っています。
要は、どうやって社会、お客様とコミュニケーションをとっていくのかという、コミュニケーションの在り方から設計していかないと、そこに置くもの、空間や商品は定義できなくなると思うのです。コートを買おうと思って百貨店に来て、帰り際お店を出るときにすごく格好いい傘を買ってしまっていた、という体験には、元々の気持ちを変えてしまうほどの幸せなコミュニケーションがそのプロセスで起こっています。そういうコミュニケーションの種をまきたいですね。
尾崎:まきたいなあ。
そのテクノロジー施策、企業の「本質」を捉えてますか?
北川:その本質から考えると、よくテクノロジーの活用例であるのが、商品の説明をデジタルコンテンツとして提供するというアイデアです。これは実体験からくる反省も含めて言うと、それ単体ではなかなかうまくいかないことが多い。
尾崎:企画会議でもそういう意見、山ほど出ます(笑)。
北川:うまくいかない原因は、もしかすると説明で終わってしまっていて、その商品の先に広がる自分の世界とのコネクトをお客様がイメージできていないからではないか、と思うわけです。それを考える別の例としては、例えば伊勢丹新宿店の2階には、広いスペースに靴がバーッと並んでいて、それがなぜ楽しいのかといったら、一瞬でで全部見渡せて、あれやこれや比較しながら、それを使うシーンが想像できるからではないでしょうか。オンラインで全部見ようと思ったらとんでもない時間がかかります。
お客さまの購買の決め手は多様ですが、特に高額なものをお買い上げいただくときには、その世界観や、それを手にした先の自分の未来が見えるということがとても重要だと思います。そういう未来を想像させるというマーケティングをやるためにこそ、テクノロジーは使われるべきですよね。
おもてなしを科学する。科学できれば、自動化できたり機械化できたり、科学で証明できる部分とそうでない部分の組み合わせができる。人対人でしかご提供できない、ゾクゾクしたり、時間を使いたいと思うようなことを付加させられるような、デジタルインフラを今からちゃんと整えておこう、お客さまがデジタルテクノロジーを意識しないような、水や空気のような状態にちゃんとつくり込んでいこうということです。
尾崎:そうなると、将来その基盤ができて、魅力的な体験をつくるアナログの部分は、スペシャリストを招き入れるような、そういう空間プラットフォームになっていくのですね。素晴らしいビジョンですし、僕もぜひ何かでお手伝いしたいです。