電通総研は、「ジャパノロジープロジェクト」として、世界に広める価値がある日本の思想・文化・事象・アイデアを識者と共に探っている。今回は、5月20日に東京都内で開かれた国際会議「The Culture Factor@Tokyo 2016」でのパネルセッションと、同会議のために来日したオランダ・ワーゲニンゲン大のヘルト・ヤン・ホフステード准教授のインタビューから、異文化との向き合い方や相互理解のための重要なポイントを探った。
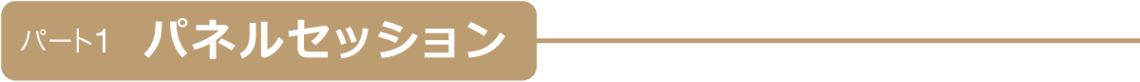
グローバル経験豊かなパネリストに聞く
「異文化との向き合い方」
多様な文化的背景の中で自身を効果的に機能させる能力は、「文化の知能指数=CQ(Cultural Intelligence Quotient)」と呼ばれる。電通総研ジャパノロジーチームでは、このCQを、IQ、EQに続くこれからの企業経営者に必須の能力と捉えている。
同チームはこのCQの考え方を背景に、パネルセッションを企画。グローバルビジネスの現場を知るパネリスト5氏が「世界の中における日本」「文化の境界のまたぎ方」「世界でビジネスをするための資質」の3視点で、異文化との向き合い方について語り合った。モデレーターを務めた電通総研の宮林隆吉主任研究員が5氏の持論の要旨をまとめた。

まずは自分たちの文化の相対的な位置を知る
宮森千嘉子氏
イティム・ジャパン 代表
国際経営学者のヘールト・ホフステード氏(ヘルト・ヤン氏の父)は、世界を六つの切り口で見ています。ここでは、代表的な三つの切り口を紹介します。
一つ目は、「権力格差」という次元。人々が権威や権力に対してどう向き合っているのかを表す切り口です。二つ目は、「個人主義—集団主義」という次元。社会に対して個人として向き合うのか、自分が属している集団として向き合うのかを示す切り口です。三つ目が、「不確実性の回避」という次元。曖昧なことをどこまで受け入れられるかという切り口です。こうしたフレームワークを使い、相対的に自分たちの文化がどういう位置にあるかを知ることで、他国に対する理解もより深まると考えています。
異文化との相互理解こそが重要課題
渡辺寧氏
株式会社かえる 社長
私は現在、組織改革の仕事をしています。以前、日系メーカーの欧州支社に駐在員として勤務していたとき、日本で育った“純ジャパ”の私は、異文化マネジメントで大変苦労しました。例えば、本社から高い経営目標を要求され、同時に本社への細かい報告責任がありました。これが現地スタッフには理解されない。これはホフステード理論でいうところの「男性性」「不確実性の回避」の高い日本企業の特徴的な行動で、現地の人たちに理解してもらうにはなかなか厳しいものがありました。
この経験があったからこそ、異文化理解についてきちんとした知識を持つことが、グローバルビジネスにおいて重要だと感じています。
相手の文化的背景を理解しようとする姿勢を
水島淳氏
西村あさひ法律事務所 弁護士
私がMBAを取得したスタンフォード経営大学院の必須科目の中で、多くの回数を割いて行われるのが「バイアス」(偏見)についての授業です。例えば日本を表す言葉として「出る杭(くい)は打たれる」ということわざがありますが、そのクラスの教授から、「それは日本だけの話ではなく、米国も、また、他の国にも同様に当てはまる」という指摘から始まるような感じです。
こうした授業を通じて、われわれが陥りがちなバイアスのわなを避け、ニュートラルな視点で文化という枠組みを理解し、実践を繰り返す。議論を通じ相手を理解しようとする姿勢こそが、グローバルでマネジメントやビジネスで成功するために必要なのだと考えています。
川﨑選手に習う、堂々とそして謙虚に
井上威朗氏
『クーリエ・ジャポン』編集長
最近、メジャーリーガー川﨑宗則選手のクーリエ・ジャポンの記事がネット上で大きな話題になりました。川﨑選手は、ほとんど英語ができないうちから、カタコトの英語とジェスチャーで全米のファンを大爆笑させました。
彼はこう言います。「確かに海外では、『日本人はおとなしい』というイメージが強い。でも、感情的にならず、いつも落ち着いている日本人も、世界で必要とされているんじゃないかな。だから『自分を変えなきゃ』なんて思わず、そのままの自分で体当たりすればいい。実行して失敗しながら、自分の役割はちゃんとあるって知っていけばいいんだから」
堂々と、でも謙虚に世界に出ていくことが必要なのではないでしょうか。
テクノロジー文化が創るクロスボーダー組織
大野智弘氏
株式会社Kudan 社長
私は日本、そこからタイ、米国、オランダ、フランス、ドイツ、そして英国と、大手経営コンサルティングファームで働きましたが、あまり文化の壁というものは感じませんでした。これは恐らく経営コンサルタントという世界が、個に対して求めるパフォーマンスが明確で、国文化に左右されないことが大きいと思います。
私は現在、複数の国で多国籍の社員が所属するAR(拡張現実)/VR(仮想現実)テクノロジー企業を経営していますが、少数精鋭の専門集団のため各人の個性の方が圧倒的に強く、文化的な違和感を意識したことはありません。これはテクノロジー文化が多様な組織を横串でつなぐものとして存在しているからといえるかもしれません。

異文化への露出経験がアイデンティティーの認識につながる
ホフステード氏
グローバリゼーションの進展による異文化との摩擦は日本だけの問題ではなく、欧州においても非常に大切に扱われているトピックです。もちろん欧州は地続きで旅行もしやすいですし、テレビから英語やフランス語、ドイツ語などが自然と流れてくるため、異文化に触れる機会が多く、この環境が社会の多様性を支える基盤となっています。
特に重要なのは、幼少期の「異文化への露出経験」です。例えば日本において、自分たちのことを「日本人」だと誰が意識するでしょうか。自分とは違うものの中に放り込まれてはじめて、自分たちのアイデンティティーを認識するのです。島国である日本において、その「露出」をどう担保していくのかが課題です。それを解決するために、幼児向けから企業幹部まで幅広く異文化理解のための教育コンテンツの開発が求められていると感じています。

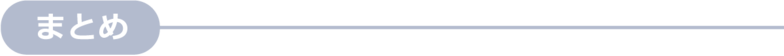
CQの資質は教育によって高められる
宮林隆吉氏
電通総研主任研究員
セッションとインタビューを通じての学びは大きく三つあると考えます。一つは、バイアス(偏見)にとらわれないニュートラルな視点を持つことの重要性。日本にいると「島国日本」「グローバル人材不足」というメディアの報道を前に、自分たちだけが極端に何かが欠落したような空気に、めいりそうになります。しかし、これはグローバルでビジネスを行う全ての国・企業が直面している共通の課題であり、日本および日本企業だけの課題ではありません。実際、欧米の教育機関では当たり前のように異文化理解についての授業が存在しています。謙虚に足りないものを認め、解決していく姿勢が必要だと考えます。

二つ目は、世界と自分を相対的に見ることの重要性。例えば、日本は集団主義の国だといわれることがありますが、それはあくまで対米比較したときの話です。世界を相対的に捉えると、そもそも個人主義が強い国は一部の先進国でしかないことが見えてくるし、社会主義の国からは日本も個人主義的な色合いの強い国だと思われる可能性があるということです。また組織のサイロ化※に苦しむ欧米企業を見ると、日本で比較的ネガティブな文脈で語られがちな「稟議(りんぎ)システム」が、実は組織間の壁を越えて合意形成をしていくのに非常に有効な手段にも見えてきます。
そして最後に、異文化理解は後天的に学べるものだということです。よく偏見を持たない幼少期の海外経験が大事だという議論を耳にしますが、ホフステード氏の言葉を借りれば、大切なのは他者を自分たちと同じように見ることではなく、お互いの「違い」を尊重する姿勢です。それには自己のアイデンティティーの確立が欠かせません。よって、私たちは幾つになったとしてもCQを高めることができるし、学び続ける姿勢こそが大切だと考えます。現在、電通総研ではこのCQおよび組織文化理解のための診断サービスを開発・提供しています。 自己と他者を知り、その中に自分たちのスタイル(=ジャパノロジー)を見つけていく姿勢こそが、これからのビジネスパーソンに求められている資質なのではないでしょうか。
※組織の業務プロセスやシステムなどが、他部門と連携せずに自己 完結して孤立してしまうこと。
この記事は参考になりましたか?
著者

宮林 隆吉
株式会社電通
金融・通信・エンタテイメント企業のブランド戦略・新規事業開発に関わった後、社内横断組織サトナオ・オープンラボにてソーシャルメディア時代の新しい消費者行動モデル「SIPS」の開発を行う。電通総研では「企業文化/異文化マネジメント/インナーコミュニケーション」を研究テーマとしながら、外資系企業を対象とした日本市場攻略のための知見開発に従事。イエセ経営大学院 修士課程修了。一橋大学大学院 国際企業戦略研究科博士課程在籍。国際大学大学院MBA・グロービス経営大学院非常勤講師。