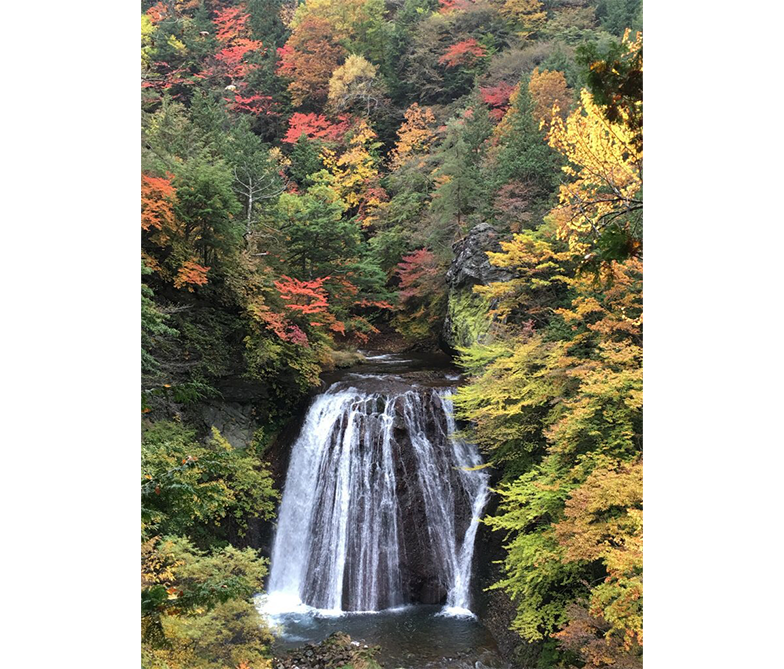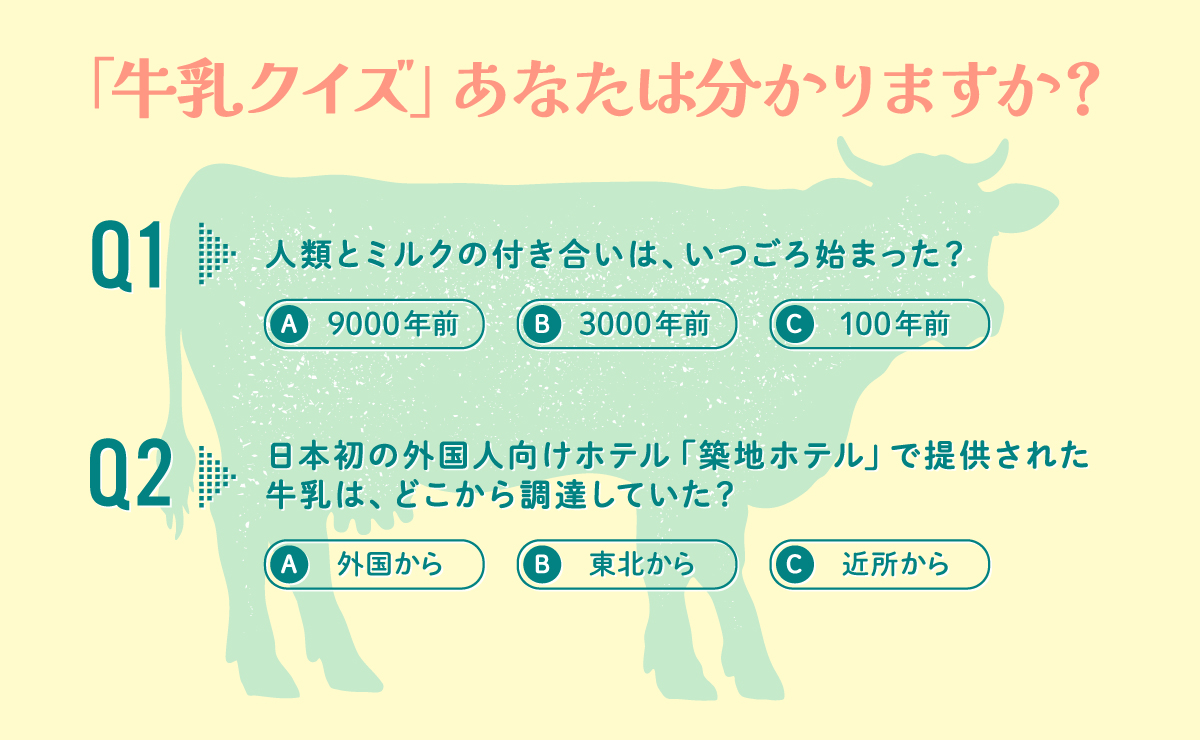ある会社の後輩が「ウェディングケーキを焼いてもらえませんか?」と声を掛けてきたのにはびっくりしました。仲間が集まってお祝いする非公式の小宴で「ケーキカットをすると、中からメッセージ映像入りのDVDが出てくる」というサプライズをしたかったそうで。
その彼は知らないのでしょうが、ぼくはローストビーフを焼けても、ケーキは大の苦手。たしかに料理は好きですが、目分量で適当につくるだけ。計量カップをきっちり守って、すべてをレシピの段取りに従わなければならないスイーツづくりなんて、ほとんど経験もありません。しかもウェディングケーキとなると、デコレーションも見当がつかないし。犬を描いてもクルマに見えちゃうレベルで絵心もないし。スポンジの中にDVDを忍ばせる芸当なんてできるのかしら? でも、お祝い事ですもんね。断るのも野暮かと、なんとなく勢いで引き受けることにしました。
で、いざ始めてみると…いやはや、これが楽しいのです。どんなケーキにしようかな?丸?四角?イチゴ?メロン?銀色の粒(アラザン)は欲しいよね、うんぬん。頭に浮かぶイメージをスケッチしながら、この酒臭いおじさんのどこにこんなにカワイらしい趣味があったのかしら?と不思議に思えるほど遊んじゃいました。

恥ずかしながら
拙著『コンセプトのつくり方』は前著『〈アイデア〉の教科書』の大筋を踏襲していますが、いくつか新しい試みをしました。そのひとつとして、コンセプト(アイデア)づくりの方法論であるぐるぐる思考のプロセスを、カラダの中の「こびと」のメタファーで説明してみました。

「こびと」とは「あのターゲットならこう言うだろうな」「この人ならこう反応するだろうな」という感覚の集合体。カラダの中に女子高生やサラリーマン、老人などさまざまなキャラクターの「こびと」を養うのです。このこびとはいろいろな資料によって手に入れた「目」と、ぼく自身の「カラダの反応(官能)」が一体化した、いわば半分客観的で半分主観的な存在です。
特にコンセプト(アイデア)を考え散らかすタイミングでは、実際に試作品をつくり、それを生々しく評価しなければなりませんが、そのときにこの「こびとのホンネ」が大いに役立ちます。「こびと」との対話を通じて、ぼくの独断でもなく、数値データが示す薄っぺらな判断でもない方向に思考が進むからです。

こびとの世界
そしてこの「こびとの世界」を維持するためには、出来るだけ多くの価値観を経験し、女子高生、サラリーマン、老人たちの鮮度を保たなければなりません。「価値観の経験」といっても、そんなにややこしいことではなく、全然違う世代や環境の友人を持つことだったり、ぼくにとっての「ケーキづくり」のような、ちょっとした挑戦をするだけで十分なのですが。
反省しなければならないのは、ぼくの「挑戦」がいつも食べものまわりばかりだということ。先日も「ルバーブ」を見かけ、柄にもなくジャムを炊きました。たぶん、子どものころに読んだ森村桂さんのエッセイが影響しているのでしょうが、ジャムづくりの鍋から漂う香りに包まれると、とても善良な生活をしている気分。「大草原の小さな家」をはじめとする西洋のお話の世界へ誘われるのです。正直、ルバーブ自体は単調に酸っぱいだけで「どこがおいしんだろう?」だし、第一、ジャムを使う時の絶望的な砂糖の量(おおよそ使う果物の半量。1kgのリンゴなら砂糖500g!)からすれば、とても「善良」なんて言い難いのですが。それでもついつい、ヨーグルトと一緒に(日頃二日酔いで口にしない)朝食を楽しんじゃうのでした。

…なんかおいしそうじゃないケド
日ごと寒さが募ります。お漬物がおいしくなる季節ですので、次回は長野からそれをテーマについて書きましょう。
どうぞ、召し上がれ!

無事、DVDも