MITメディアラボをテーマとしたシリーズ第3回として、今回は若い研究者たちの声を取り上げる。AIやウエアラブル、IoT、電気自動車など、それぞれ領域の違う研究グループに属しつつ、最先端のフロンティアを追究する研究者たち。彼らは、それにどのような思いで取り組み、そこから人間とテクノロジーのこれからについて何を感じ、考えているのだろうか。メディアラボの現場から見えてくる未来像を、それぞれの視点で語ってもらった。
人間の神経系の延長としてのAIやウェアラブル
~ナン・ツァオ氏(MITメディアラボ・リサーチアシスタント)
【プロジェクト紹介】
彼女が手掛けるプロジェクト「Halo」では、照明を天井などに固定せずに〝ウエアラブル照明〟とし、照明器具は一人一人の人にウエアラブルデバイスとして付いて回る。それは照度や色を変えることで、ユーザー自身の外見を変えることもできるし、逆にユーザーの感情や環境に応じてユーザーの目に見える世界の姿を変えることもできる。

現在の端末は、キーボードで操作をし、全ての情報はディスプレー上に凝縮されます。でもそれは、実はとても限定的な形であって、未来で使われることはないでしょう。私たちの研究グループでは、センサーやアクチュエーター(駆動装置)を、人間の神経系の延長として位置付けて開発しています。そのためには、人間と端末との間にもっと自然なインターフェイスが必要になってきて、それはある種の人工知能(AI)を用いたシステムでもあるはずです。
AIは既に私たちの生活に浸透し、購入すべき商品や旅行先をお勧めしてくれたりしますが、私はAIがさらに人間の神経系を拡張するインフラになり得ると考えています。人間にとってAIは脅威となるのでは、との声もありますが、意思を持つのはあくまで人間ですから、どのような未来の世界に住みたいか、どのようなAIを設計するかは、人間が決めること。私が開発しているのは、人間をより深く理解するためのAIです。
もしAIがウエアラブルになれば、身体に密着することで、人間をさらに深く理解するようになるでしょう。産業界に新たなビジネスモデルを示唆するような、有益なデータを収集してくれる可能性も高まります。光が人間のホルモンや生体リズムに影響を与えることは知られていますが、私たちのプロジェクトでは、人間の身体の状態を把握し、外的環境に頼ることなくその人だけのための照明を作り出す、ウエアラブルデバイスの開発に取り組んでいます。
ウエアラブルが物理的にどのような形になるかによって、デバイスと人間との関係も変わってきますね。例えば、人間に依存するロボットというのもあって、MITメディアラボで作ったBOXIEというロボットは、段ボールでできていてとっても可愛いんですが、歩くのが苦手なので人間が運び回る必要があります。
ウエアラブルって、私たちと外の世界をつなぐ窓なんですよね。未来のウエアラブルは、もっとファッショナブルで、私たちの着る服に自然に組み込まれているようになってほしいです。今はまだウエアラブルデバイスには形やサイズの制限がありますが、新しい形や素材もどんどん開発されていますので。
AIと人間の協働によって、人間の経験に響き合うストーリーをつくる
~ラッセル・スティーブンス氏(MITメディアラボ・デプロイメントリード)
~ユージーン・イ氏(MITメディアラボ・デプロイメントストラテジスト)
【プロジェクト紹介】
彼らが所属する「ソーシャルマシンズ」の研究グループは、マスメディアからオンラインメディアまでの幅広いデータを解析して活用し、社会的な諸問題の解決に役立てることを目指している。最近手掛けたプロジェクトでは、米国大統領選挙に関する膨大なツイートやニュースをデータベース化し、AIを活用してそれをトピックスごとに細分化して、ジャーナリストが使えるような関係図のマップを作成した。


今、AIや機械学習は自動化が進んでいて、そのプロセスから人間の関与は排除されようとしています。しかし、私たちのプロジェクト「ソーシャルマシン」では、人間もそのプロセスに組み込まれるべきだと考えています。
取り組みの一例ですが、ジャーナリズムの領域で、AIに記事を書かせるのではなく人間がより良い記事を書くためのツールとして、AIを開発しています。例えば2016年の大統領選では、5000万のツイッター投稿と30のニュースメディアを分析し、それをAIでトピックスごとに細分化したものをジャーナリストに提供しました。
このようなデータジャーナリズムによって、ジャーナリストは自分一人では得られることのなかった深いレベルの洞察を持って物事を語れるようになる。単純なスポーツや経済記事であれば、AIだけでも書けるでしょう。でも、より複雑な物語を語るためには人間が必要なのです。良いストーリーとはその核心に、人間の経験と響き合う真実を備えていますから。人間とAIが協働することで、将来的にはアートに匹敵するような美しいものをも生み出せるのではないかと思っています。
また、AIのアルゴリズムに人為的な要因による偏りが見られることも、強く問題視しています。アルゴリズムのコードの書き手に起因する場合もあれば、データ自体にバイアスがかかっていることもある。何を「美しい」と思うかは人によって違いますが、例えば、“田舎のおばあちゃん”の感覚は、おそらくそのデータには含まれていない。だから私たちは、今までアルゴリズムの対象になることのなかった人々の声を、幅広くデータとして反映することを目指しています。さらに、専門知識がなくても誰もが使えるように、アルゴリズムが「オープンな」ものになることも重要だと考えています。
未来では、人間と機械はもっと密接に結び付き、相互に連携し合うでしょう。人間をシステムに組み込むことで、機械が人間を見下ろすのではなく、機械よりもまず人間が優先される世界を思い描いています。
テクノロジーの魔法が現実世界に解き放たれる
~エドウィナ・ポルトカッレロ氏(MITメディアラボ・リサーチアシスタント)
【プロジェクト紹介】
彼女は、子どもたちの遊び場をデジタルやネットワークの技術で生まれ変わらせるプロジェクトを手掛けている。その一つ、「聴く木」(Listen Tree)というプロジェクトでは、実際に公園などにある生きた樹木を骨伝導技術によるスピーカーに仕立てあげ、それをデジタルのネットワークで結び、その樹木に人が耳を当てればそのネットワーク経由の音楽や人の声が聞こえてくる、といった試みを行っている。

私はずっと、触れることができる現実の物質に引かれてきました。触感だけでなく、モノが持つ物質性や、その存在があることで生まれる人間の思いに興味があるんです。テクノロジーを正しい場所で用いることで、このような物質とデジタル世界の関係をもっと深く探れるのではないかと考えています。
日本には素晴らしい公園がたくさんありますね。遊び場は、テクノロジーにとってこの上ないプロトタイピングの場となります。テクノロジーの存在を意識せずに、それがもたらす体験だけを純粋に味わうことができますから。私たちのプロジェクトでは公園の木々に装置を取り付けて、街の外にある森とWi-Fiネットワークでつなぎました。公園にいる人々が木に耳を当てることで、街の向こうから運ばれてくる“物語”を聞くことができるわけです。
このような遊び場を街の中心に置くことで、コミュニティーを一つにする力が生まれる。テクノロジーは、人々を結び付ける手段であるべきです。世代的、あるいは社会文化的な違いから、テクノロジーは、その恩恵を受ける人とそうでない人を分断しかねません。でも、テクノロジーを公園の木と組み合わせれば、子どもでもお年寄りでも、誰もが容易にテクノロジーを享受できる。人々の生活においてなじみ深いモノに、テクノロジーを埋め込んでいきたいと考えています。
デジタルテクノロジーの進化で世界は狭くなり、あらゆる情報や知識にアクセスできるようになりましたが、人間にとって自分の置かれた物質世界との関係を維持していくことは依然として大切です。素材やモノに内在する神話的、原始的な物語やその可能性を見つめ、テクノロジーによって魔法の力を授けたい。そのように、スクリーンやピクセルから現実の世界へとテクノロジーを解き放ちたいと思っています。
自動運転車に必要なのは、デザインとの対話とローカライズ
~マイケル・リン氏 (MITメディアラボ・リサーチアシスタント)
【プロジェクト紹介】
彼が手掛けるプロジェクト「説得的な電気乗り物」(PEV: Persuasive Electric Vehicle)は、三つの車輪を持った車の形をしており、足でこぐモードにも電動で動くモードにも切り替えられる。ユーザーになるべく足でこぐことを促すため、例えば、足でこぐモードにすれば車の外観の色が変わったり、あるいは今どれだけの他のユーザーが足でこいでいるかの実数がリアルタイムで運転席のパネルに表示されるなどの仕掛けが施されている。

過去70年間にわたって、都市は車社会のために設計されてきました。そこには、運転する人間は間違いを犯すものだという前提があった。グーグルが生み出した自動運転車は、道や信号、インフラなどを新たに設計し直す必要があるのでは、という問いを私たちに投げ掛けています。
都市計画においては、政策とデザインとテクノロジーを三位一体で捉えなくてはいけません。テクノロジーとデザインが対話をすることなくバラバラに進められていることは大きな問題です。テクノロジーのローカライゼーションもまた重要です。自動運転車の応用は、東京と米国では違って当たり前。米国ではハイウエーでの通勤に使われるし、地下鉄網が発達している東京では、例えばごみ収集車や移動型の自動販売機など、もっと公共的なサービスに適しているかもしれません。
コンピューターは1980年代には単純な計算に、90年代には主にビデオゲームに使われました。2000年から10年間は、人間とコンピューターの親和性を高めるインターフェースに焦点が当てられました。私は次の進化の主役は、人間に良い影響をもたらしてくれるテクノロジーだと考えています。
例えば、私たちのプロジェクト「PEV」では、人をより健康的なライフスタイルへと導いてくれる「説得的テクノロジー」に取り組んでいます。PEVはペダルをこぐようにもできる電気自動車で、通常運転のエネルギー消費の高いモードから、自転車程度の低いモードに切り替えることができます。それぞれの街の特性に合わせて渋滞の解消を始め、公共的なサービスやロジスティクスなど、生活の改善につながるさまざまな応用が考えられます。
テクノロジーは人間のために設計されるべきです。私たち一人一人のデータは収集され、人工知能(AI)で考えていることや生活パターンが解析されます。AIは正しい形で扱われないと、危険なものになりかねない。ビジョンを持ったポリシーの策定が急がれます。
この記事は参考になりましたか?
著者
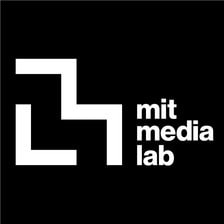
MIT media lab
<a href="https://www.media.mit.edu/" target="_blank">https://www.media.mit.edu/</a>

小野 裕三
株式会社電通
ビジネスプロセスマネジメント局
91年入社。マーケティング局、営業局、新聞局を経て2000年より一貫してインターネット広告の業務に携わる。共著に『広告新時代~ネット×広告の素敵な関係』。ウエブ電通報では、「デジタルの旬」シリーズのインタビュアーを手掛ける。


