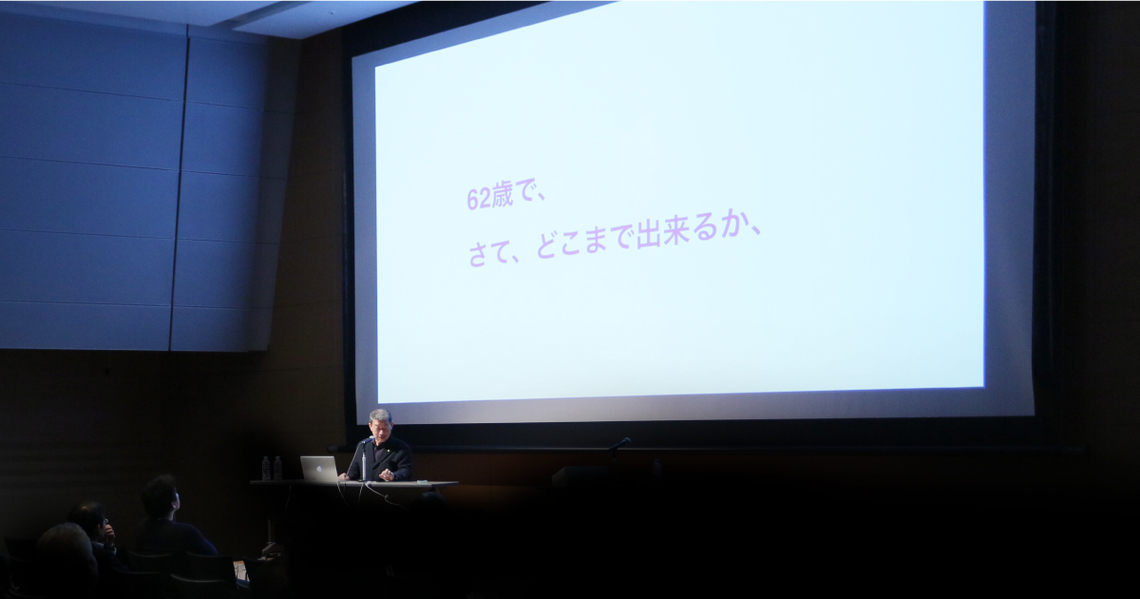今回の電通デザイントークは編集者の菅付雅信さんをお招きして、写真をめぐる「いま」を俯瞰します。トークセッションのメンバーは、電通からドリル、そしてPARTYを経て「もり」を設立し、世界の広告賞で審査員を務める原野守弘さんと、写真専門誌「コマーシャル・フォト」編集長の上松清志さん、2016年にカンヌ、NYADC、D&AD、ワンショーと受賞ラッシュし、写真への造詣も深い電通のアートディレクター上西祐理さんです。誰もが写真を撮る時代だからこそ、プロの目線で写真を批評し、写真を真に「見る」とはどういうことなのか語り合います。

(左から)編集者 菅付雅信さん、当日はスカイプで参加した「もり」代表 原野守弘さん、「コマーシャル・フォト」編集長 上松清志さん、電通 上西祐理さん
フィルムへの回帰が起きている
菅付:2010年代の写真はデジタルの浸透によって、二つの領域で大きな変化が起きています。まず一つ目は「写す道具のデジタル化」、そして二つ目は「見せるメディアのデジタル化」です。
写す道具のデジタル化は、なんといってもスマートフォンが象徴的です。iPhoneだけを見ても、半年前の統計では世界で約10億台が売れています。スマートフォンにはカメラが付いており、ほとんどの人が常時、カメラを持って生活しているわけです。
見せるメディアも変化しました。僕らのメインデバイスであるスマホで写真を見せ合う機会も増えています。広告の世界でもデジタルサイネージが普及し、有名なニューヨークのタイムズスクエアも昔はプリント広告が中心でしたが、今はほとんどデジタルサイネージに代わっています。
一方で、こうしたデジタルの普及に対して「フィルムへの回帰」という反動が起きていますよね。
上松:はい、コマーシャル・フォト読者のプロフォトグラファーに対して「フィルム撮影に興味があるか」と調査をしたところ、20代や30代に「非常に興味がある」「フィルムで撮影してみたい」「実際にフィルムを使っている」という人が多くいました。仕事では圧倒的にデジタルの依頼が多いようですが、特に最近フィルムに興味を持つ人たちが目に付くようになりました。
菅付:ポラロイドフィルムを新たに提供しているインポッシブル社も好調ですし、イギリスの大手ファッションサイト「BoF」でもファッション写真がフィルムに回帰している、という特集記事を出していました。
上松:これまではプロカメラマンの機材は、プロしか扱えませんでした。しかし今は、iPhoneで撮った写真を広告に使えるし、アマチュアでもドローンを飛ばすことができます。一眼レフのカメラで撮影すれば、すぐにモニターで確かめることができるし、手ぶれだって自動的に直してくれるため、失敗がないわけです。そういう中で「プロの存在意義は?プロの技術は何?」と問われています。
菅付:まさに、そういう中で新世代のカメラマンが台頭してきたわけです。この10年間で最も成功したカメラマンの一人であるライアン・マッギンレーにインタビューしたとき、「技術がアートをつくるわけではない。アートは人の心を動かすことだという強いビジョンを持っている。自分にとっての写真は、世界とうまくつながるための言葉である」と話していました。
また、日本の新世代のカメラマンの代表格である奥山由之は「フィルムにはデジタル技術がいくら進歩しても追いつけない何かがある」と言っていました。こうした世代の言動には、デジタルへの反動がかなり大きいのではないかと僕は感じています。
上西:私自身もデジタルに「嫌だな」と感じる部分もあります。シャッターを切る瞬間の緊張感のなさに虚無感やうそくささを感じてしまいます。最近の仕事の8割はフィルムのカメラマンと組んでいます。フィルムでしか撮らないと決めた覚悟に引かれることもありますし、やはりフィルムでしか写らないものに引かれます。
原野:いまの話を聞いて、現代は「ノンフィクション性」が重要になっている、ということかなと思いました。僕はビデオの仕事が多いのですが、OK Goのミュージックビデオ「OK Go: I Won't Let You Down」もワンショットで撮りましたし、本田技研工業の「Honda. Great Journey.」も、普通はCGを使うシーンを人の手で作った模型を手動で動かして撮りました。
そうすることで、その写真や映像に「これは世界のどこかで人々が集まってつくりあげたのだな」という、そのモーメントを感じさせることができます。インターネットが普及して情報量がとてつもなく多くなってしまったからこそ、「一瞬への価値」や「制作プロセスへの価値」が高まっているのかなと思います。
菅付:原野さんの言う「ノンフィクション性」は、新世代のカメラマンに共通するところだと思います。一瞬にかける緊張感をもう一度、取り戻そうとしているのかもしれません。
写真がなぜ頭脳的になるのか?
菅付:僕は2010年代の写真の一番の特徴は、「写真がより頭脳的になってきていること」ではないかと思っています。頭脳的な写真は昔からあり、現代美術の写真は極めてコンセプチュアルですが、最近は商業写真の中でも特にファッション広告の写真がものすごく頭脳的になっています。
例えば、イネス&ヴィノードが撮ったファッションブランド・ディオールのキャンペーン写真は、有名な絵画であるマネの「草原の昼食」へのオマージュです。また別のカメラマンによるクリムトの絵を元ネタにした写真もありますし、過去の名作を再現するような写真も撮られています。
最近のファッション写真には、なぜあからさまな元ネタがあるのでしょう。上西さんはどう思いますか。
上西:そうですね、現代美術の文脈に近いのではないでしょうか。知識ゲームのように、元ネタを知っている人が楽しんでいますよね。ファッション業界はクライアントもハイブランドですし、顧客も文化層ですから、ある種のコミュニティーを形成しているのかなと思ったりします。
菅付:僕もその通りだと思います。ファッション写真は、広告を通じてある種の「知能テスト」をしているのです。誰もが知っている美人や有名人が出ていて一見するとわかりやすい美しい写真でも、その裏には何層ものレイヤーがあって、わかる人にしかわからない構造になっている。それが最近のラグジュアリーのファッション写真の撮り方なのです。
人気ラグジュアリーブランドのマーク ジェイコブスの去年のキャンペーンは、デヴィッド・シムズが撮りました。そのモデルは10代女子に人気のモデル、さらにマリリン・マンソンから日本の前衛ミュージシャン灰野敬二まで、わかる人にわかるキャスティングになっています。
さらに最近のルイ・ヴィトンのキャンペーンでは、3人のトップカメラマンを起用して、それぞれ違う被写体を撮り、アートディレクターがさまざまな組み合わせで広告をつくっています。また、このキャンペーンに影響を受けてか、カルバン・クラインも3人の若手カメラマンを起用して、若いミュージシャンからクリエーターなど、有名無名を交ぜたキャスティングをして、「誰これ?」「あ、あの人か」「この撮っている写真家は同世代じゃない?」みたいな、強力な同世代感、同時代感を演出してます。
上松:話題づくりと多様性が狙いですよね。ファッションも男性、女性、中間向けに分かれているなど、より多様になっていますし、多く人の心に響くためには、たくさんのテイストを用意した方がいいということではないでしょうか。
菅付:そうですよね。カルバン・クラインの広報は「もっと若い世代にアプローチするために、同世代の写真家に同世代を撮ってもらいたかった」と言っていました。ハッシュタグの「#mycalvins」というのがコピーで、インスタグラムなどSNSで拡散されることも期待して、大きなキャンペーンを仕掛けているわけですね。
※後編に続く
こちらアドタイでも対談を読めます!
企画プロデュース:電通ライブ クリエーティブユニット第2クリエーティブルーム 金原亜紀