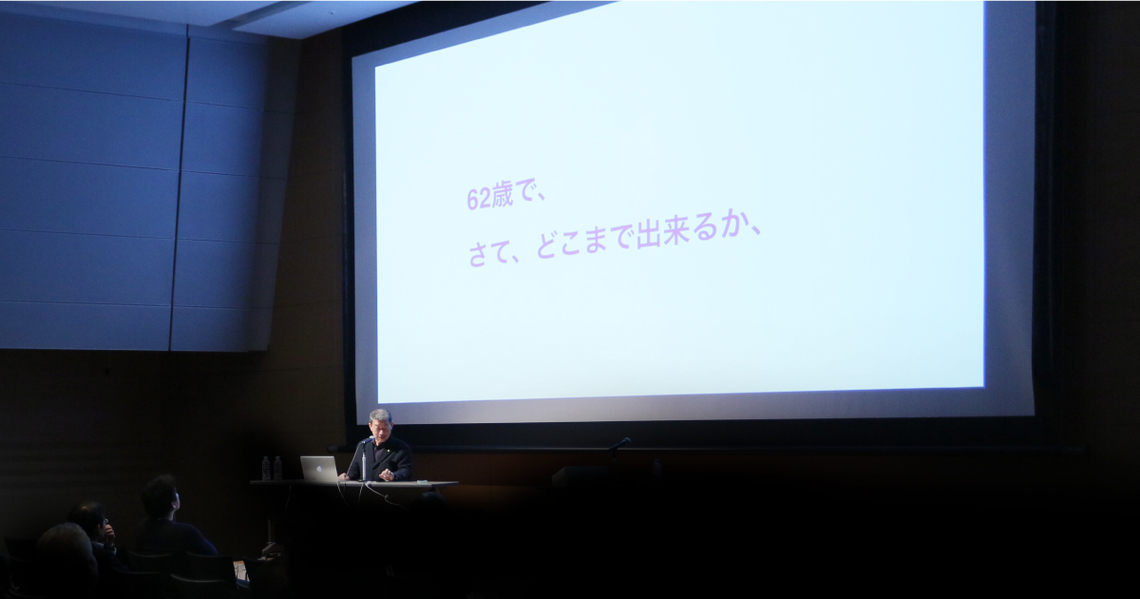今回の電通デザイントークは編集者の菅付雅信さんをお招きして、写真をめぐる「いま」を俯瞰します。トークセッションのメンバーは、電通からドリル、そしてPARTYを経て「もり」を設立し、世界の広告賞で審査員を務める原野守弘さんと、写真専門誌「コマーシャル・フォト」編集長の上松清志さん、2016年にカンヌ、NYADC、D&AD、ワンショーと受賞ラッシュし、写真への造詣も深い電通のアートディレクター上西祐理さんです。誰もが写真を撮る時代だからこそ、プロの目線で写真を批評し、写真を真に「見る」とはどういうことなのか語り合います。

(左から)編集者 菅付雅信さん、「コマーシャル・フォト」編集長 上松清志さん、電通 上西祐理さん
ファッション広告の魅力はわからないこと?
菅付:昨年の秋に話題になった、バレンシアガの広告写真にはまったく服が写っておらず、ブランドロゴが小さく入っているだけでした。東京の表参道駅をジャックしていたので、見たことがある人もいるかもしれません。
この広告はマーク・ボスウィックという写真家が、クリエーティブディレクターを兼任して制作しました。なぜファッションブランドのキャンペーンに服が写っていないのか。ボスウィックは「広告から離れた広告をやろうとした。なぜなら広告とは、人をイライラさせるものだからだ」と語っています。
このキャンペーンで、バレンシアガの売り上げは前年の2倍になりました。キャンペーンとして大成功だったわけです。
上西:けんかを売っているような挑戦的な表現は、すごくいいなと思います。こういうテイストを好きな人たちが、バレンシアガの服も好きなのでしょうね。
菅付:僕もバレンシアガの姿勢がすごく伝わるキャンペーンだと思いました。最近の潮流から思うことは、ファッション広告の魅力は「見てすぐにわかるものではない」ということです。もちろん広告としては見てすぐにわかることは重要ですが、一目見ただけではよくわからないことも大事だと思っています。
上松:たしかに、これだけ世の中に写真があふれてくると、広告とわかった時点で見られなくなることが起きています。まさにバレンシアガのキャンペーンのように「何だ、これ?」という謎が多ければ多いほど、人は調べたくなりますよね。
上西:ビジュアルを見て「歩いていたけど止まった」「気になって覚えた」「心が動いた」とか、そういう「ひっかかり」をつくっていますよね。その狙いはいつの時代も変わらない気がします。
上松:広告に掲載された写真を見ても、一般の人たちは「この写真は誰が撮っているか」なんて気にしていません。でも、そうしたことに興味がある人もいて、「きれいな写真だな」「面白い映像だな」とか気になって調べてみると、ネットでいろいろな情報がどんどん出てくる。こういう仕組みが大切になっているのかもしれません。
例えば原野さんの「OK Go」を面白いなと思って調べていくと、実はドローンで撮っていることが分かる。詳しく知れば知るほど、さらに面白くなった人たちが、その情報をウェブ上に上げていくのです。現代は隠れていた広告写真のレイヤーが明かされていく時代なのだと思います。
菅付:最近のほとんどのラグジュアリーファッションの広告は検索されることが前提でつくられていますよね。メイキング動画やアザーカットをウェブで公開することが主流になっていますし、舞台裏まで含めたキャンペーン設計になっているのでしょう。
逆に言うと、僕は「誰でもわかるものは、ラグジュアリーではない」と思うのです。誰にでもわかることは重要な価値だとは思うのですが、誰でもわかってしまうと、ラグジュアリーの中心にいる人たちは「自分たちのものではない」と思ってしまう。原野さんはどう思いますか?
原野:僕はグラフィックの表現は「ハテナ」と「ビックリマーク」で構成されていて、その間に矢印がある「?→!」と思っています。
そして、その矢印の長さが広告制作者の腕の見せ所だと思うのです。矢印がすごく長いとエッジは立っているがわかりにくい表現になるし、ものすごく短いと日本のCMのようにわかりやすいが深みのない表現になる。
欧米のグラフィック広告ではその距離感の取り方が重要で、わかりやす過ぎてもカッコ悪いし、難しいと誰にもわからない。そこで、ちょうどいい距離感を見つける競争がひとつの決まりごとになっています。
そういう意味では、ラグジュアリーブランドはスタンダードな広告よりも距離を長くすることによって、よりセレクトされた人たちの表現に見せたいのではないしょうか。
ただし最近の欧米の広告を俯瞰的に見ると、昔は矢印の距離が長い表現が多かったのですが、今はどんどん短くなっています。それはやはりSNSの影響で、シェアされるためには一瞬で伝わる、わかりやすさが必要だからです。カンヌで審査をしていても、昔は欧米の広告でセレブリティーが出てくる表現はほとんどありませんでしたが、今は増えていますね。そのぐらいにデバイスの変化やSNSの台頭で広告に求められるスピード感が変わり、表現も影響を受けていると感じています。
成熟社会で求められる写真とは?
菅付:1件の仕事で1億円の報酬が支払われるようなカメラマンが、ニューヨークで活躍している。なぜ彼らが「1億円プレーヤー」なのかというと、知能テストをやり続けられる知性を持ち、そういう生きざまをしているからです。戦略的に写真を撮り、自分のブランディングにものすごく力を注いでいます。
日本でも、パルコがM/M(Paris)というグラフィックチームや、オランダの若手女性写真家のヴィヴィアン・サッセン、ユルゲン・テラーなど話題の写真家を起用した、ラグジュアリー文脈に乗った広告をしています。
しかし、日本にはこういうラグジュアリーの文脈で撮れる写真家がまだまだ少ない。
上西:私は広告をベースにアートディレクターをしているので、排他的な表現に迷うことも多いです。もちろん高価な商品やハイブランドのような、品格が備わっているブランドは、相応に見せる必要があると思います。
ただ本当にいいものは、より多くの人が「いいな」と思うはずだと考えると、やはり、まずはパッと見た時に感動したり、心が動いたりするような表現を大切にしたい。元も子もないですが、そうすれば意外と全部クリアできちゃうのかな、みたいなとこころはあります(笑)。
菅付:森村泰昌さんの名言の中に、すごく好きな言葉があります。「見える世界を通じて、見えない世界にいたること」。これは写真も同じだと思うのです。
さらに最近は「成熟化社会」といわれます。多摩大学大学院教授の田坂広志さんは、社会が成熟していくと知恵や信頼、文化といった目に見えないものが大切になると話しています。現代のような成熟社会では、そこに写っていないものを感じさせる写真こそ「成熟した写真」だと思うのです。
僕はそういったものをつくったり、提供できたり、ディレクションできたりできるようになりたい。
上松:ただ一方で、広告にはクライアントがいて、企業の理念を代弁しないといけない面もある。クライアントに「もっと早いスピードで」と言われれば、さきほど原野さんが紹介されていたように矢印の距離はどんどん縮まっていくでしょう。
企業の裏側の理念までしっかり見せてほしいという依頼であれば、たとえその商品が安価であっても、ときにはラグジュアリーな考え方が必要になると思います。広告の世界は、クライアントに何を求められるのかによって変ってくる。
原野:僕は菅付さんが話した「成熟した社会でどうクリエーションしていくか」という視点は、すごく大事なことだと思います。写真家だけではなく、広告やテレビ番組など、クリエーティブ全体にも言えることではないでしょうか。
多くの企業やメディアが基本的に消費者のことをバカだと思っている。わかりやすい表現が一番の正義、というのは聞こえはいいが、要するにそういうこと。消費者が持っている知性を信頼して、正しく尊敬する態度があって初めて、双方向的に感じあえるコミュニケーションが成立します。
消費者に対する尊敬のレベルをどのくらいに設定できるのかが、菅付さんが話された、成熟社会における発信者側が持つべき姿勢なのかなと思いました。
菅付:まったく同感です。成熟化した社会に対応できるものを世界に発信できるような表現のできる人が、日本に増えてほしいと切に願っています。
現代は作品や生きざまがネット上に記録されていく時代です。写真家に限らず、クリエーターは好むと好まざるにかかわらず、可視化される存在になっていくわけです。
そこで、ここ数年自分が言い続けているのは、より良きクリエーターになるために「人生を作品化」するしかないということ。つまり、それは「より良きクリエーター人生」という作品をつくっていくことです。自分もそういう人たちのお手伝いをしたいという強い思いを持っています。
<了>
こちらアドタイでも対談を読めます!
企画プロデュース:電通ライブ クリエーティブユニット第2クリエーティブルーム 金原亜紀