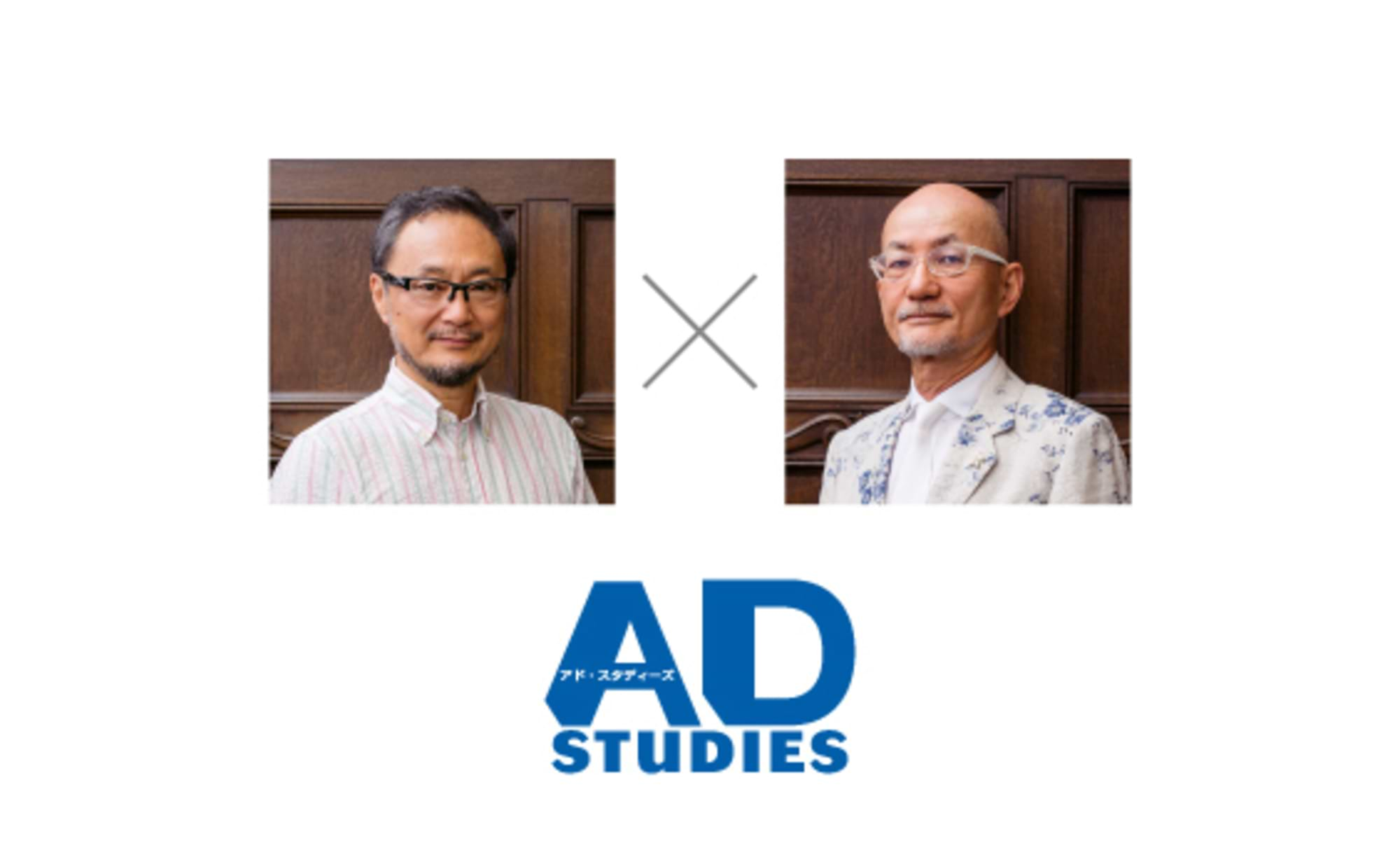インクルーシブを強みにした社会をどうつくるか
—個人・企業・社会そしてマーケティングの挑戦—

社会的弱者やマイノリティとして捉えられている人々を含めて、あらゆる人々をどのように社会に包摂(インクルージョン)していくのか。
これまで幾度となく浮上してきたテーマだが、ここにきて公的セクターやNPOに解決を委ねるのではなく、企業がビジネスでアプローチするケースが目立ち始めた。企業は多様性やそのインクルージョンをどう捉えるべきか、最前線にいる2人に語っていただいた。
目次
▼社会課題の解決がビジネスになる
▼多様な人々が少しずつ付加価値を出す社会
▼ディスアビリティをサポートするビジネス
▼大学は新たなコミュニティになりえるか
▼組織を変えるには、トップのボランティアから
▼ダイアローグで社会の意識を変えていく
社会課題の解決がビジネスになる
林:本日のテーマはダイバーシティ&インクルージョンです。このような社会課題は、これまでは企業の中で社会貢献やCSRの文脈で語られ、ビジネスの外側の話として扱われがちでした。しかし、潮流が変わり、いまはもっと本業の部分でアクティブに、かつ戦略的にアプローチしていくことが求められる時代になりつつあります。先生はどうお考えですか。
野田:世界ではすでに、社会課題をビジネスで解決することが当たり前です。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から2030年までの国際目標)を見たとき、日本企業の人は「いろいろな社会課題があって大変ですね」という反応をしますが、世界、特にヨーロッパ企業の人は、「これは飯の種だ」と目をキラキラ、いや、ギラギラさせる。SDGsには17ゴール169のターゲットがあり、具体的にはダルエスサラームの交通渋滞のような社会課題が挙げられています。これを見た瞬間に、政府の援助で何とかしようと考えるのか、ビジネスで何とかしようと考えるのか。マイケル・ポーターのCSV(Creating Shared Value)ではないですが、いま世界では後者が主流です。
林:世界の中でも、とりわけヨーロッパ企業が社会課題の解決に熱心なのは、何か理由があるのでしょうか。
野田:社会課題解決型の企業になるときに重要なのは、現場を見る、感じるということ。その点、ヨーロッパ企業は開発途上国を見る機会が他の地域の企業に比べて多かったのではないでしょうか。元々植民地だった関係性に加えて、ヨーロッパはマーケットが小さく、しかも成熟しています。外に出る以外に活路がなく、実際に現場に出ざるを得ない。すると、現地でいろいろな社会課題に気づくことが多かったのかなと。
林:一方、日本企業はこれまで社会課題を積極的にビジネスにする意識が欠けていたところがあったのではと思います。これは文化的なものでしょうか。
野田:いや、日本にも昔は社会課題をビジネスで解決しようとした会社が数多くありました。例えばヤクルト。戦前、日本は栄養状態が悪く、疫痢、いまでいうアメーバ赤痢でお腹を壊す子どもが多く、中には命を落とすケースもあった。これはまさに解決すべき社会課題ですよね。これを何とかしたいと考えた代田稔博士が乳酸菌の研究をして発見したのが、殺菌力の強いシロタ株です。ただ、錠剤のままでは子どもが飲みにくい。そこで開発されたのがヤクルトで、いまでは東南アジアに広く展開されるくらいの立派なビジネスになっています。
ほかに有名なところでは、花王もそうですね。花王は「清潔な国民は栄える」を社是にして、国民に清潔な生活を提供するという課題に取り組んで大きくなりました。本来ビジネスは社会課題解決向きであり、日本でもそれは変わらなかった。最近の日本人は楽をして頭をあまり使わなくなりましたが、本当は社会課題の解決が得意なはず。もう一回、原点回帰すべきです。

林:日本には創業100年を超える企業がたくさんあります。それらの企業も元々は日本という国を良くするという社会的なビジョンを基盤にビジネスを築いてきたのだと思います。ただ、現在の従業員たちは平和で豊かな国で育ってきたので、創業者たちがかつて取り組んだ社会課題がリアルではないことも多い。その結果、かつてのビジョンがいまも理念として掲げられていても、従業員の雇用やその家族の生活を守る、という違うコンセプトのほうが重視されてしまう。日本企業が社会課題をビジネスにするには、新たな課題をどうやって見つけ、それを自分たちの資産とどうマッチさせていくのかということが非常に重要になると思います。
野田:おっしゃるとおりで、企業が雇用を守ることに汲々として、新しいところに目が向かない状態は非常に危険です。企業は玉乗りしているピエロ。動き続けていないと転んでしまいます。大企業だろうと中小企業だろうと、変化し続けなければ死んでしまうという危機感を持つべきです。
日本は、開発途上国とまた違った意味で課題が満載の国です。それに対して政治ができることは限られています。企業が課題解決の先兵とならなくてはいけないのに、その意識を持っていないのは本当に残念です。
林:課題は満載なはずなのに、それが見えていない、あるいは見る気はあるけど見つけられていない企業が多いのかもしれません。私はどんな企業においても身近な課題であるはずのダイバーシティ&インクルージョンに目を向けることがいい切り口になると考えていますが……。
野田:企業の方は「うちはイノベーションを起こしたい」と言います。だから「いいですね。どんな問題を解決したいのですか」と聞くと、「いや、何でもいい」と言う。イノベーションは課題解決のための手段なのに、それ自体が目的になっているんですよね。「いや、イノベーションは手段なので、それによってどんな問題を解決したいのか、考えてみてください」と改めて問うても、結局「ない」という答えが返ってくる。本当は課題がたくさんあるのに、あまりに同質的な人と長い間過ごすことによって心理学でいうところの「順化」をしてしまって、見えなくなっているのでしょう。
まさに、多様な視点を持った人々が共に語り合える組織をつくることが最善の道です。
多様な人々が少しずつ付加価値を出す社会
林:日本が抱えるさまざまな社会課題の中でも、野田先生が注目しているものは何ですか。
野田:最も大きいのは人口の問題でしょう。人口をどうやって増やすのかという課題設定は、もはや無意味。人口が減る中で幸せな国をどう維持していくのか、もっと幸せな国にするにはどうすればいいのか、という課題設定が必要です。
実は人口問題に先行して取り組んで、成功したのが北欧の国々です。北欧は1990年代に1度、社会保障費が膨らんで破綻しています。そこから立て直すとき、北欧の国々はこう言った。「私たちは小さい国です。だから老若男女、ハンディキャップのある人、外国人、全員が働いて付加価値を生まなければいけない。逆に言うと、小さな国なのでみんなで少しずつ付加価値を生めば豊かになる」と。当時、面白いことを言うと思って注目していたら、現実に北欧はそうやって復活しました。
日本は2100年に人口が5,000万人になるといわれています。さらに減少は続きますが、下降のカーブを見ると私は3,500万人前後で下げ止まると予想しています。それでもヨーロッパの大規模国家と同じくらいですが、いまと比較すれば3分の1以下になる。だとすると、日本も北欧のように、みんなが小さく付加価値を出し続け、手を携えながら生きていく国にならざるを得ないと考えます。いま政府は「働き方改革」を打ち出していますが、これから求められるのは「成果の出し方改革」。さまざまな人が付加価値を生める成果の出し方を各企業が模索することが、人口問題という大きな社会課題を解決する近道ではないでしょうか。
林:企業は、生産人口が減って生産能力が落ちるから社会にとって人口減少は問題だ、と考えます。しかし、人は特定の事業体に属して、そこでのみ生産活動をするわけではない。先生のおっしゃるように、国であれ地球であれ、あらゆる人がとにかく生きていくことを通じて世の中に価値を提供し、それをみんなで共有していくモデルに可能性を感じます。
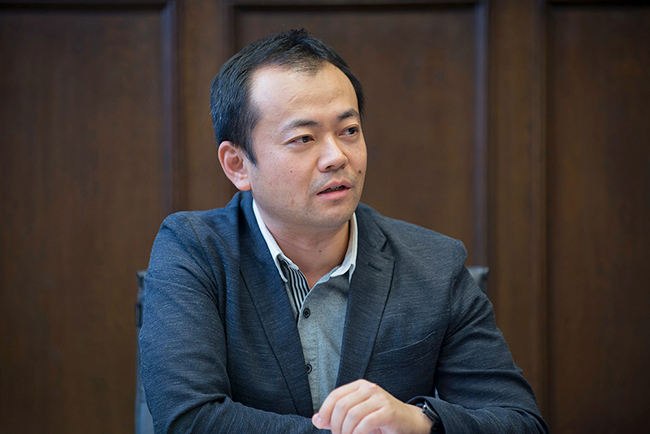
野田:つまり「消費者」ではなく「生活者」なんですよね。私の記憶では、少なくとも1980年代初めから野村総研では生活者という言葉が使われていました。当時、先輩方は「俺たちは消費しているだけでなく、生産もしている。家事労働も立派な生産。それが生活するということ」と話していて、これからはみんなが生産しているという考え方でマーケットを捉えなければならない、と教えられたことを覚えています。
ユニークな例がドイツです。ベルリンの壁が崩壊したとき、西ドイツは生産性の低い東ドイツと合併すると国際競争力がガタ落ちすることを心配しました。国際競争力が落ちるとマルクが急落して何も輸入できなくなり、自給自足の必要が生じます。そうなると消費者ばかりの大都市は成り立ちません。そこからがドイツ人のすごいところですが、彼らは10万人1単位で自活力の高い中小規模の生活都市圏をつくり始めました。
具体的にいうと、まず都市の周囲はヴァルト(森)で覆われています。この森は生産財で、薪を取ったりシカを育てたりできます。その内側に農地があり、さらに農地を裏庭とした住宅地がある。川はマスを放流するために人工護岸をはがして自然護岸に。中心部は小さな工業地帯やマルクトプラッツ(市場)、教会や市庁舎がある。普通の生活者が小規模な農地を耕し自給力を上げるのが「クラインガルテン(小さな庭)」です。いまクラインガルテンは、日曜農業を指す言葉になったようですが、当時はクラインガルテンの集合体で国をつくり直そうとしたのです。
これはすごい発想です。人々が企業で働くだけでなく、生活者として生活に密着した形で生産し、国を支えていく一つのモデルとして、日本も参考にしたほうがいいと思います。
林:ドイツの例は、人々が企業で働き、そこで生産されたものを消費するという、企業を中心にした従来のあり方とは違うエコシステムですよね。これから新しいエコシステムの時代になるとして、その中で企業はどのような役割を果たすべきでしょうか。
野田:企業は、ピンポイントに集中して価値をゼロから生む力が強い存在なので、新しいエコシステムにおいても、その能力を研ぎ澄ませていくべきです。方向性としては、いま存在しているコミュニティの中で課題解決をビジネス化していくこと。あるいは世界中にある社会課題を解決して外貨を稼ぎ、それをコミュニティに還流させること。いずれにしても、社会課題を解決することを価値創造の中核に置くべきです。いま企業は作業生産性を高めて利潤を生むことに一生懸命ですが、それは算術級数的にしか儲かりません。幾何級数的に儲けようと思うなら、ソーシャルイノベーションを起こすことに持てる能力を集中させたほうがいい。
ディスアビリティをサポートするビジネス
林:私たちが提唱しているインクルーシブ・マーケティングは、企業が社会課題を解決する際の切り口になると考えています。実は企業がダイバーシティをテーマにビジネスをすると、「マイノリティを利用して金儲けするのか」と批判されるリスクがある。しかし、価値を創造して利益を出さないと持続可能な解決になりません。そのあたりはどうお考えですか。
野田:マイノリティはマジョリティに斉一化されることによって、我慢させられている場合が多いですよね。それによってマイノリティの幸せは損なわれるし、幸せな人で溢れていないマーケットはいずれ滅びていく。その意味で、マイノリティに対して何かすることは、マイノリティのみならずマーケット全体にとってもいいこと。企業に対しては、批判を怖がる前にとにかくやってごらんよ、と言いたいですね。
具体的には、企業はマイノリティの生産力をサポートするビジネスをするといいと思います。例えば、サイバーダインというベンチャーは、装着型のロボットを開発しています。いまのところは介護補助用ですが、将来は筋力の落ちた高齢者の作業を援助できるかもしれない。こうしたサポートによって、多くの人が楽しみながら仕事をすることができれば、全体として生産性も伸びるはずです。
サポートするのは、特別なことではありません。カリフォルニア工科大学のある学生が、講義中に障害者を差別する発言をしたそうです。それを聞いた先生は学生に眼鏡を外させて、小さな文字が書かれた本を読ませました。学生が「眼鏡がないと読めない」と抗議すると、「君も視覚に障害があるようだ。しかし、君は眼鏡という道具があるから健常者と変わらない生産性を出せている。いまほかに障害のある人が、健常者と同じような生産性を上げていないとしたら、それは道具を開発できていない我々エンジニアの怠慢だと思わないか」と諭したそうです。この先生が言うように、マイノリティに限らず私たちには、みんな少しずつ何かのディスアビリティがあります。それをサポートすることが全体の底上げにつながるし、企業にとっても大きなビジネスチャンスになるのではないでしょうか。
林:ディスアビリティをサポートし、生産性を高めることは重要です。ただ、インクルーシブ・マーケティングでは、人は生産能力が高いから価値があるわけではく、一人ひとり違うから価値があるという点がポイントになると考えています。
野田:そうですね。マイノリティとマジョリティ、あるいはマイノリティ同士でもいいですが、違った考えの人が議論すると、これまでにないユニークなものが生まれます。これは知的活動による生産であり、オープンイノベーションの一種といえますが、みんなこの生産性の高さを忘れている。手を動かすことだけが生産ではありません。エコシステムの中にマイノリティが存在していること自体、立派な生産活動です。そういう前提があった上で、ディスアビリティゆえに従来できなかったことができるよう、サポートしていくべきです。
林:マイノリティやマジョリティが混ぜこぜになって出会っていく仕組みは、どうやってつくっていけばいいのでしょうか。
野田:鍵を握るのは企業でしょう。企業は素晴らしい人材育成道場で、家庭や学校では育成が難しいイノベーターを育てています。彼らを野に放って、いままで出会ったことのない人たちと触れ合わせることで、新たな課題を発見したり、その課題解決が自社のビジネスになるかもしれません。企業は社員にプロボノ(社会人が自らの専門知識やスキル、経験を生かして参加する社会貢献活動)でも副業でも、どんどんやらせたほうがいい。
林:現役の社員だけでなく、定年退職した人が企業で培ったものを社会に返していく仕組みがあるといいですね。これらは企業の中の人が社会に出ていく話ですが、逆に企業の中に多様な人々が出会う場をつくることも可能でしょうか。
野田:地方では、社会と一体化している会社の事例がすでに数多く出てきています。例えば「自分の妹は障害があるが、何とかしてやりたい」と身近なところから障害者雇用が進んでいたりする。あるいは高齢者雇用もそう。先日私がお邪魔した菓子メーカーは、平均年齢75歳。60歳くらいだと若手と呼ばれていました。東京にいると企業から障害者や高齢者は排除されていきますが、田舎は人が足りない課題先進地域であり、課題解決のために地場に根を下ろしてインクルージョンを始めています。その点でいうと、一番遅れているのは大都市の一部上場企業かもしれない。
林:先日、『Share金沢』という地域コミュニティを運営している佛子園の雄谷良成理事長にインタビューをしました。そのとき感じたのは、混ぜこぜの世界をつくるには、地域やご近所といった基盤が大事だということ。人が誰かと生きるとき、相手のことを知らないというのはリスクです。でも、相手のことを知ったら、それが高齢者だろうが子どもだろうが障害者だろうが、ちょっと力を貸してここで楽しく暮らしていこうという方向に行く。そうやってお互いを知ることができる基盤があるかどうかで、インクルージョンも左右されやすい。その点、東京は不利です。マンションでさえ、隣に誰が住んでいるのかわからない状態で、ご近所というものがありませんから。
野田:大都市圏は課題の最後進地域なので、そこから始めるのは難しいかもしれません。東京でもニュータウンに行けば地域コミュニティが再生されつつありますが、タワーマンションではコミュニティをイメージしづらい。やはり適度な経済力と文化、歴史がある地方の中核都市から実験を始めて、これからの日本の姿を描いたほうがいいと思います。
林:先生が実際に訪れて注目している地方都市はありますか。
野田:1つ挙げるなら小豆島です。小豆島では、小豆島ヘルシーランドという会社が大きなオリーブ園を運営しています。この会社はオリーブ園だけでなく、オリーブを使った商品を作ったり、観光農園をやったり、さらには出版社や古民家ギャラリーもやっている。いわばオリーブを中核としたコングロマリットです。
興味深いのは、都市生活でメンタルを病んだ若者たちを迎え入れて、農園の仕事に就いてもらっていること。彼らは自然とコミュニティの力で回復していくのですが、都市では消費者でしかありえなかった彼らが小豆島では生産者になっている。いまは心の問題がある若者だけですが、コングロマリットなので、車椅子の人や耳が聞こえない人にもできる仕事が何かしらあるはず。みんなで少しずつ付加価値を出していくモデルが、この島で実現されるのではないかと期待しています。

林:先ほどお話にあったドイツのクラインガルテンの日本版ですね。
野田:はい。しかも、同社は生産した商品を全国に通信販売しています。その先には海外への販売もありうる。東京を通さなくても世界とつながれるという点でも面白いと思います。
林:『Share金沢』もさまざまな事業体があるコングロマリットで、インクルーシブな経営を実現していました。ただ、大企業も多くの事業体を抱えるコングロマリットですよね。いま例に出た地域と、どこが違うのでしょうか。
野田:小豆島ヘルシーランドのコングロマリットは曼荼羅なんです。最初にある種の世界観に基づいた曼荼羅図があって、それを埋めるようにして事業をつくっていく。この事業をやればシナジーが生まれて儲かるというちっぽけな話ではなく、全体でホリスティックに価値を生んでいくというイメージ。そこは大企業の今までのコングロマリットと大きく違うところです。
私は常々、「イメージできないものはマネージできない」と言っています。起業家にとって最も大切なのは未来を思い描くイマジネーションです。ヘルシーランドにはそれがある。逆に大企業にイマジネーションが欠けていますね。
林:大企業がイマジネーションを持つにはどうすればいいのでしょう。創業当時は社会課題を解決する熱量があったのに、新入社員が入ってきて人が入れ替わるとともに消えてしまう。これもイマジネーションの欠如が問題なのかと。
野田:冒頭でお話ししたことに立ち戻るのですが、一番大切なのは、現場を見ることです。社会課題の解決をビジネスにして成功した例として、私はよくバングラデシュの天候不順保険の話をします。バングラデシュは治水が不十分で、毎年大洪水が起きて農民が困窮します。この状況を変えるために開発されたのが、天候不順に対して即座に保険金を支払う天候不順保険です。実は、この保険をつくったのは携帯電話会社。各地に基地局を建てていく中で、農地が流されて泣いている人たちを見て問題に気づき、その課題解決をビジネスにした。大企業も内にこもっていないで現場を見るところから始めないと、何もイメージできないでしょう。
もう1つ、バルク(量)からレシオ(率)に発想を変えることも大切です。マイノリティの課題を解決するビジネスは、バルクでいうと小さいかもしれません。でも、利益率すなわちレシオなら勝負になるし、将来は大きく育つ可能性もある。それなのにバルクの発想しかないから、見逃してしまうのです。私はいろいろな会社の役員研修をやっていますが、役員の方々は「最低でも1,000億円のビジネスにならないとやる気がしない」と言う方が多い。「実際にあるの?」と聞いたら「ない」と返ってくる。それなら発想をレシオに切り替えたほうがいい。
大学は新たなコミュニティになりえるか
林:大学はどうですか。社会課題を解決するビジョンやイマジネーションを持った若い人材を育てているのでしょうか。文科省は2014年からEDGEプログラムというグローバルアントレプレナー育成促進事業(Enhancing Development of Global Entrepreneur Program)をやっていますが。
野田:こっちに火の粉が飛んできましたね(笑)。文科省もやっているし、各大学も取り組んでいます。ただ、大学はカリキュラムやプログラムより雰囲気や空気で学生を動かすべき場所。その意味でいまの大学にイノベーティブな空気があるのかというと、まったくない。カリキュラムやプログラムできっかけをつくり、それが空気にまで浸透するには、まだもう少し時間がかかりそうな印象です。
林:そうですか。大学って、本当は非常にダイバーシティな場所ですよね。しかも企業ともつながっていて、都市部では消えてしまった地域コミュニティの代わりになりうる。そういう意味で可能性を感じるのですが、中から見ていかがですか。
野田:コミュニティが成立する条件は、接触時間が長く、接触頻度が高いことです。その意味で、週に1度出席するだけの授業はコミュニティになりえません。可能性があるとしたら、接触頻度の高いゼミとサークルでしょう。ゼミや研究室をコミュニティとして活用するという手は、確かにあると思います。ただ、それにはまずゼミを主宰する先生にその意識を持ってもらわないといけない。現在、大学でファカルティ・ディベロップメント(教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組みの総称)が行われていますが、それがどこまで有効に機能するかの勝負でしょうね。
一方、サークルは学生の運営なので、大学側が何かするのは難しい。私はサークルのリーダーを集めてリーダーシップ教育を長年やっていますが、なんとなく砂地に水を撒いている感じがあって……。もっと徹底的に関与すれば、砂地も池に変わると思います。いつか花開くといいなと思って地道な努力を続けています。
組織を変えるには、トップのボランティアから
林:経営者や大学の先生には、社会課題の解決がビジネスになることに気づいている方もいます。ただ、それができる組織に変えていくために、どこから手をつけていいのかわからない、という悩みも多いはずです。例えば社内の教育制度でやるのか、そもそもビジョンからつくり変えるのか、はたまた評価制度に手を入れて社員の背中を押すのか。先生はどう思われますか。
野田:軸は2つあります。まず、草の根からやるか、トップからやるか。もう1つは、制度で強制的にやるか、自発性に任せるか。最終的にこの2軸からなる4つの象限をすべて埋めていくべきですが、最初に手をつけるべきはトップだと思います。効果が高いのではないかと考えているのが、トップのボランティア活動です。
欧米だとトップも休日は教会に行きます。教会には金持ちもいれば貧しい人もいるし、LGBTの人たちもいる。そうした身近なところからダイバーシティを実感するわけです。一方、日本の経営者は毎日大勢の人と会っていますが、案外、同質的な人としか会ってない。休日もゴルフでカントリー“クラブ”です。それでは多様性がわかりません。まず経営者がボランタリリーにダイバーシティな環境に身を置くべきです。
林:経営者ほど自由なイマジネーションを広げる機会が限られるのかもしれないですね。そういえば、『Share金沢』の理事長は青年海外協力隊の経験者でした。起業家海外協力隊をつくって、上から連れていくと面白いかもしれない。
しかし、まずトップから始めたとして、次は現場の社員ですね。これにはどのようなアプローチが考えられますか。
野田:マイナーなマーケットに強制的に出ていくことが、いい経験になるんじゃないでしょうか。GEメディカルシステムが中国市場に超音波診断装置を売ろうとしたことがあります。高品質な医療に超音波診断装置は必要です。ただ、当時は1台1,000万円の高価な機械で、そのままでは売れない。そこで彼らは知恵を働かせて、専用機ではなく、パソコンにソフトを入れて画像処理する方式を開発しました。結局、中国市場用に開発した廉価な商品は、本国のアメリカでも救急車用として売れてヒットしました。これはいわゆるリバースエンジニアリングの事例ですが、まずマイナーなマーケットに出たからこそ問題を発見し、それを創造的に解決する力を身につけることができた。最初から本国の市場だけを見ていたら、そうはならなかったでしょう。
ビジネスのきっかけは何も日常の仕事の中からだけ得られるものとは限りません。オフサイトの経験から始まることもある。例えば豊田通商がクロマグロの養殖ビジネスに参入しましたが、きっかけは若手対象の研修でした。研修プログラムで事業創造という課題が出たとき、環境問題に興味を持っていた社員が近大マグロを思い出して、「大学は養殖ができても、売る力がない。それをチャネル構築力がある我々がサポートしたらどうか」と提案しました。そのアイデアを上が聞きつけて、「うちらしいからやってみよう」という話になったそうです。社会課題を解決することに企業が集中しているなら、研修でさえ問題発見の機会になり得ます。
ダイアローグで社会の意識を変えていく
林:私が気になるのは、クロマグロ養殖への参入のアイデアが生まれたのが、単なる偶然で幸運だったのか、あるいはそういうものが生まれるように、会社として意図的な仕掛けができていたのかという点ですね。会社は意図的にやりたいわけですが、果たしてそれが可能なのでしょうか。

野田:2012年、グーグルが「プロジェクト・アリストテレス」で創造生産性の高いチームの条件を分析しました。そこで見えてきた条件が、心理的安全感、つまり自分は素のままでこのチームに受け入れてもらえるという感覚でした。おそらく豊田通商には社員が心理的安全感を抱ける風土があり、若手は臆することなくアイデアを話せたのでしょう。
社会課題の解決でイノベーションを起こそうとするなら、何かアイデアが生まれたときに「それ、ビジネスにならないよ」と水を差すような環境ではダメ。そうなりがちな職場では組織開発的な意味での風土改革が必要です。
林:ビジネスという言葉がいけないんでしょうか。ビジネスは価値を次々に生み出していくエコシステムの原動力ですが、世の中では単に利益を出すという意味にしか使われていない。だから何か提案したときに「ビジネスになるの?」と言われると、「ドキッ、すいませんでした」となってしまう。ビジネスの本質は単に利益を出すことではなく、社会課題の解決こそビジネスになるのだという認識を、企業のみならず世の中にどうやって広げていけばいいのか。悩ましいところです。
野田:難しいですね。本を書いてもテレビで話しても、なかなか伝わらないのが実情です。方向性として一つあるのは、タイアローグ、つまり対話です。
少し脱線しますが、マーケティングで行われるグループインタビューはあまり当てになりません。お客自身が自分の欲しいものをわかっていないのに、何が欲しいか聞いても意味がない。ならばどうするかというと、ダイアローグの中で「この人は何に困っているのか」を探っていくしかない。そして困っている問題に対して解決策を素早くプロトタイピングして、「これでどう?」「いや、少し違うかな」「なら、これは?」とダイアローグを重ねていく。そうすることでお客は自分でも気づいていなかったことに気づくわけです。
社会課題の解決がビジネスになるという考え方も、世の中にダイアローグとプロトタイピングで示せばいいと思います。とにかく現場に出て、社外の人を一緒に巻き込んで問題解決のワークショップを始めてみるのです。そこでイケると思ったら、そのままビジネス化する。そのとき関わった社外の人を社内に取り込んでもいい。組織のバウンダリー(境界線)を意図的に下げて、ソーシャルなオープンイノベーションに大勢の多様な人を巻き込みつつ輪を広げていく。それが一つの解ではないでしょうか。
林:いま地球には70億の人が暮らしています。それによって過去最大の難題を生んでいますが、70億人が協力して暮らせたら、それは史上初の素晴らしいこと。この状況をポジティブな方向に持っていくには、やはりビジネスの力が欠かせません。
といっても、「私は生産者で、あなたは消費者」という従来のビジネス観では、おそらく70億人の地球を支えられません。人が誰かと出会い、そこで生まれたものを企業に持ち込んだり、逆に企業で培ったものを社会の側に持ち帰ったりして、次の価値をつくっていくエコシステムの一部として、ビジネスを位置づける。今日お話を聞いていて、そうした捉え方が必要だと改めて強く感じました。
〔完〕
※こちらは吉田秀雄記念事業財団のサイトでご覧いただけます。
この記事は参考になりましたか?
著者

AD STUDIES
吉田秀雄記念事業財団
<a href="http://www.yhmf.jp/index.html" target="_blank"><span style="color:#336699">http://www.yhmf.jp/index.html</span></a><br/> 公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団では、研究広報誌「AD STUDIES」を年4回発行しています。毎号、広告・コミュニケーションおよびマーケティングに関する特集を組んでいます。当財団ホームでは創刊号から最新号までのバックナンバーをご覧いただけます。
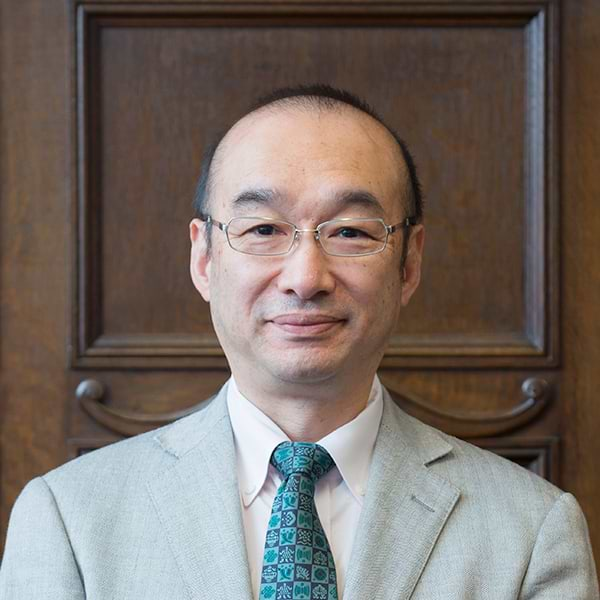
野田 稔
明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科
教授
一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。野村総合研究所経営コンサルティング一部部長、リクルート新規事業担当フェロー、多摩大学経営情報学部教授を経て、2008年4月より現職。専門分野は組織論、経営戦略論、ミーティングマネジメント。ベンチャー立ち上げ支援を含め、幅広いテーマで実践的なコンサルティング活動を行う。『当たり前の経営』(ダイヤモンド社)、『人を動かし、自分を導くリーダーシップ』(KADOKAWA)、『実はおもしろい経営戦略の話』(SBクリエイティブ)など著書多数。
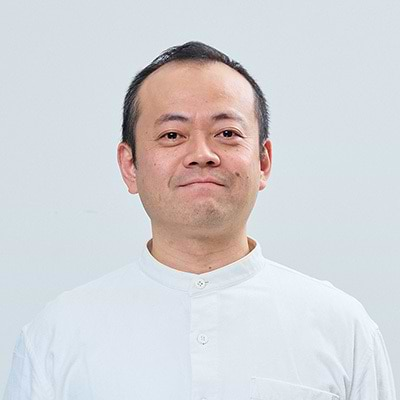
林 孝裕
株式会社電通
サステナビリティコンサルティング室
dentsu DEI innovations 代表
2003年電通入社。戦略プランナーとして、コミュニケーション戦略から、事業戦略、商品開発、イベント・スペースプロデュースに至るまで戦略領域全般に従事。2011年より社内タスクフォースである電通ダイバーシティ・ラボに参画し、2025年1月よりその後継であるdentsu DEI innovationsを立ち上げる。2017年に「インクルーシブ・マーケティング®」を立ち上げ、社会のDEI課題と企業のビジネスを結び付けていく新しい戦略論として普及促進活動を行う。講演、執筆、コンサルティング実績多数。DEIコンサルタント/UCDA認定2級プロデューサー/一級建築士