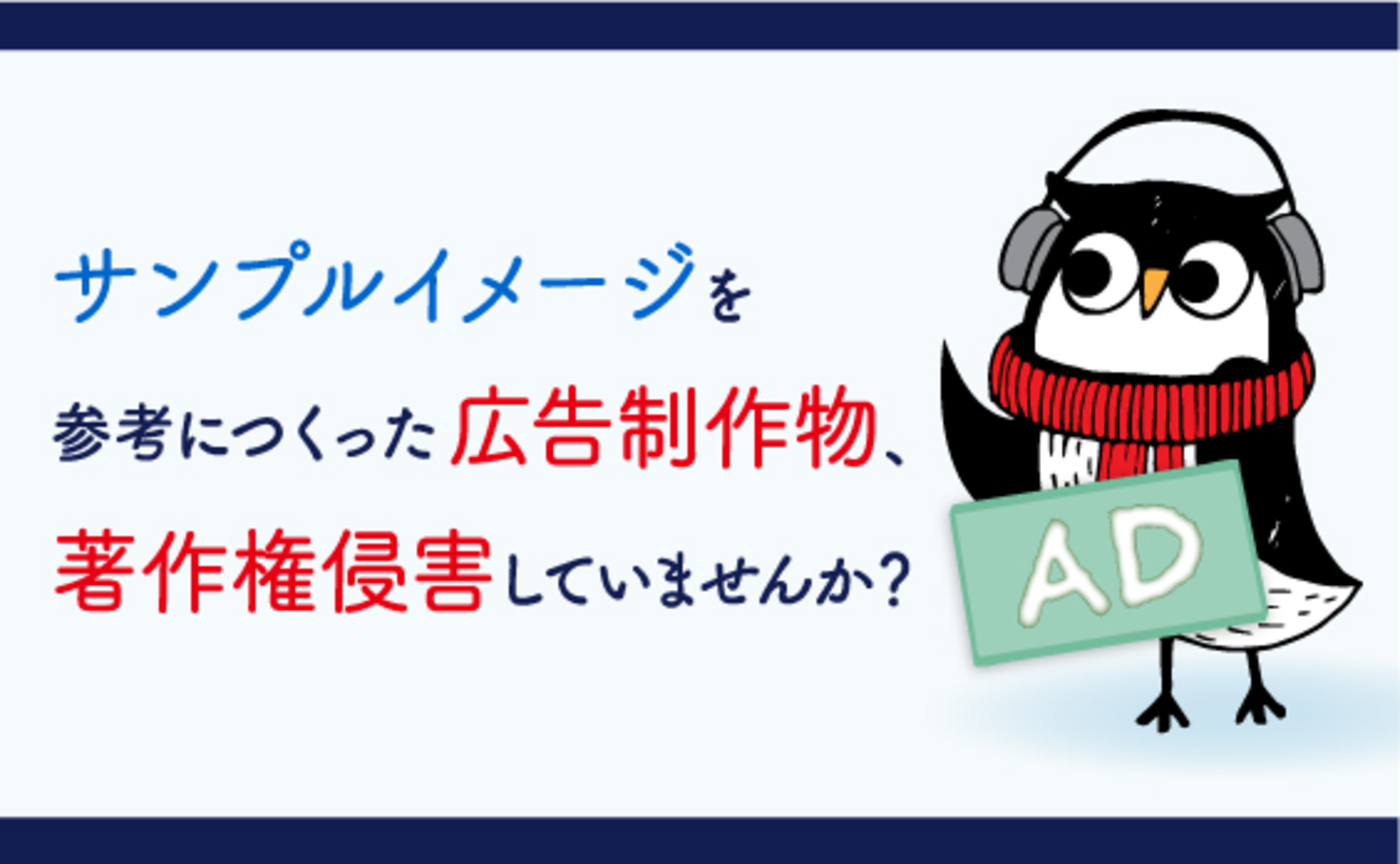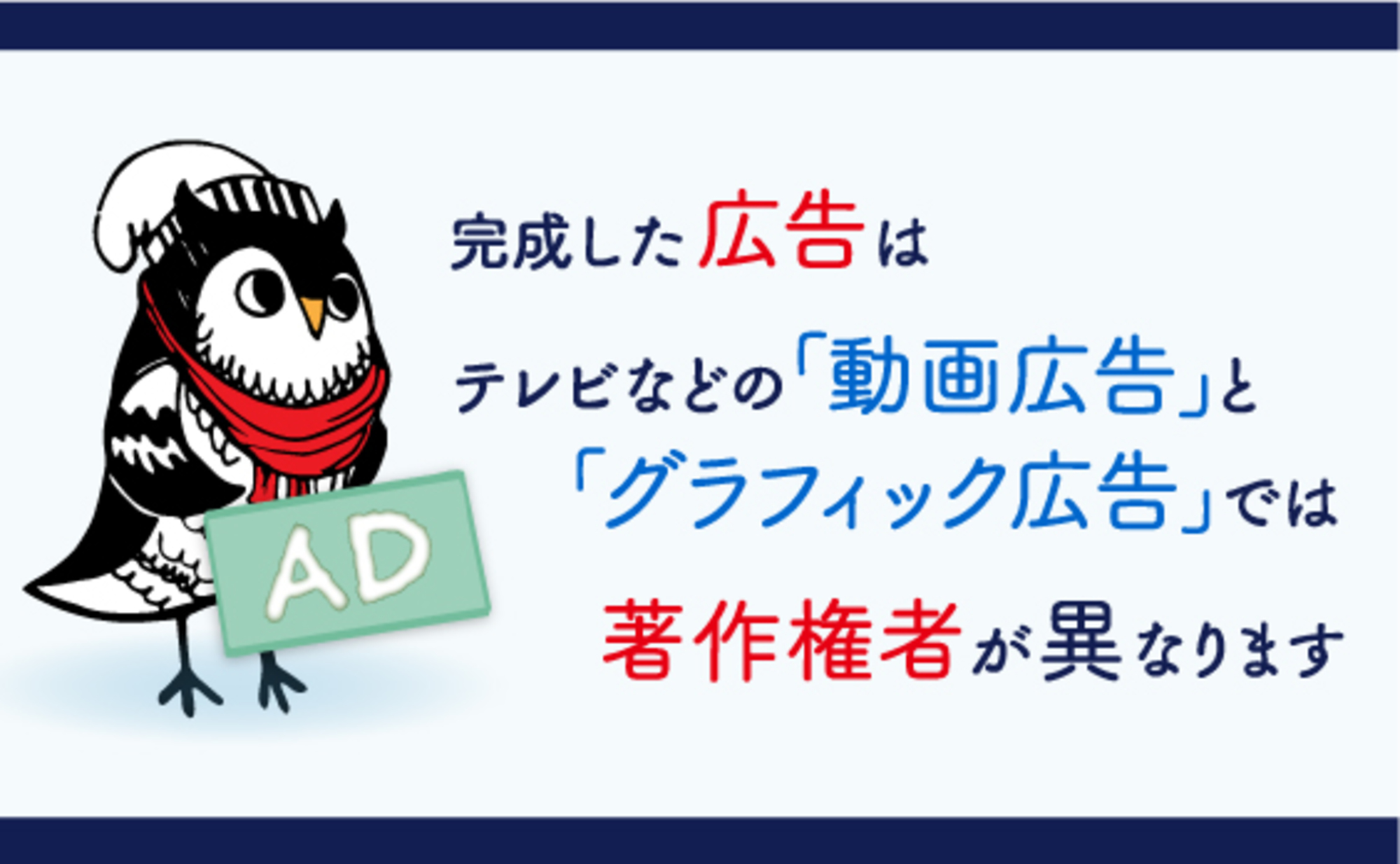この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。
今回は、「広告の表示内容」という切り口で、景品表示法の不当表示について取り上げます。
Q.広告で、商品の性能の素晴らしさや、サービス料金の安さを訴求していこうと思っています。
どのようなことに注意をしなければならないでしょうか?
広告、自社ホームページにおいて、商品・サービスを告知するに当たっては、その性能の優良さや価格の安さなどについて、積極的に訴求していくのが通常です。ただし、実際のものよりもかなり良いものであると偽って表示をした場合に、問題となりそうなのは理解できるでしょう。
A.商品・サービスの内容・性能等について実物よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示や、価格などの取引条件について実物よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。【基礎知識】
広告の表示内容はいろいろ法律の規制を受けますが、その代表的なものが景品表示法です。景品表示法は、不当な景品類と不当な表示を規制する法律です。
ここでは、不当表示について解説します。
1.不当表示とは?
景品表示法において、不当表示は以下の三つが規定されています。③については、商品・サービスごとに具体的に不当表示となるケースが規定されていますが、ここではより一般的な①②を中心に解説をしていきましょう。①②のケースでは、実物よりも著しく良い表示をした場合に不当表示となり得ます。
①優良誤認表示
商品・サービスの品質・規格等の内容について、一般消費者に実際よりも著しく優良であると示す表示
②有利誤認表示
価格などの取引条件について、実際のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
③その他誤認される恐れのある表示
2.不実証広告規制
消費者庁長官は、事業者に対して,商品・サービスの品質・規格等の内容に関する表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。消費者庁長官から資料の提出を求められてから15日以内に提出ができない場合には、その表示が不当表示とみなされることになります。
3.打消し表示
広告においては、品質の内容や価格等についての良い部分を強調した表示(「強調表示」といいます)をすることがあります。
この強調表示の内容が制限されたり、条件が付されていたりするケースにおいて、そのような制限・条件に関する表示(「打消し表示」といいます)を明瞭に行わないと、一般消費者がその商品・サービスに関する制限・条件について認識できないことがあります。その結果、一般消費者が、実際の商品・サービスよりも著しく優良または有利であると誤認するような場合には、景品表示法の不当表示に該当します。
従って、打消し表示を行うに当たっては、配置箇所、強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス、打消し表示の文字の大きさなどを総合的に勘案する必要があります。
4.景品表示法の違反
景品表示法に違反した場合には、消費者庁による措置命令がなされることがあります。
措置命令の内容は,以下の通りです。
①景品表示法に違反したことを一般消費者に周知徹底すること
②再発防止策を講じ、これを事業者の役員および従業員に周知徹底すること
③その違反行為を将来繰り返さないこと
④①および②について消費者庁長官に報告すること
これに加えて、措置命令を受けた事業者は,商品パッケージに不当表示の記載があれば商品の回収、テレビコマーシャルのナレーションの内容に不当表示があればコマーシャル素材の差し替え、ポスターに不当表示の記載があればポスターの回収、などをしなければなりません。この点も合わせて、事業者にかなりの負担がかかるといえます。
また、事業者が優良誤認表示または有利誤認表示をしたときは,消費者庁長官は,当該事業者に対し,課徴金の納付を命じなければなりません。
課徴金の額は原則として、次の通りです。
課徴金の額 = 課徴金の対象となる期間に取引をした商品・サービスの売上額の3%
以上のように、不当表示をした場合には、事業者には大きな経済的な負担が生じることになりかねません。しかし、問題はそれだけではありません。不当表示は一般消費者を欺く行為でもあり、深刻なレピュテーションの問題が発生することもあり得ます。ぜひともご注意ください。
詳しくは、広告に関連する法規制を網羅的に、実務的に、理論的に解説を試みた『広告法』を手に取ってみてください。