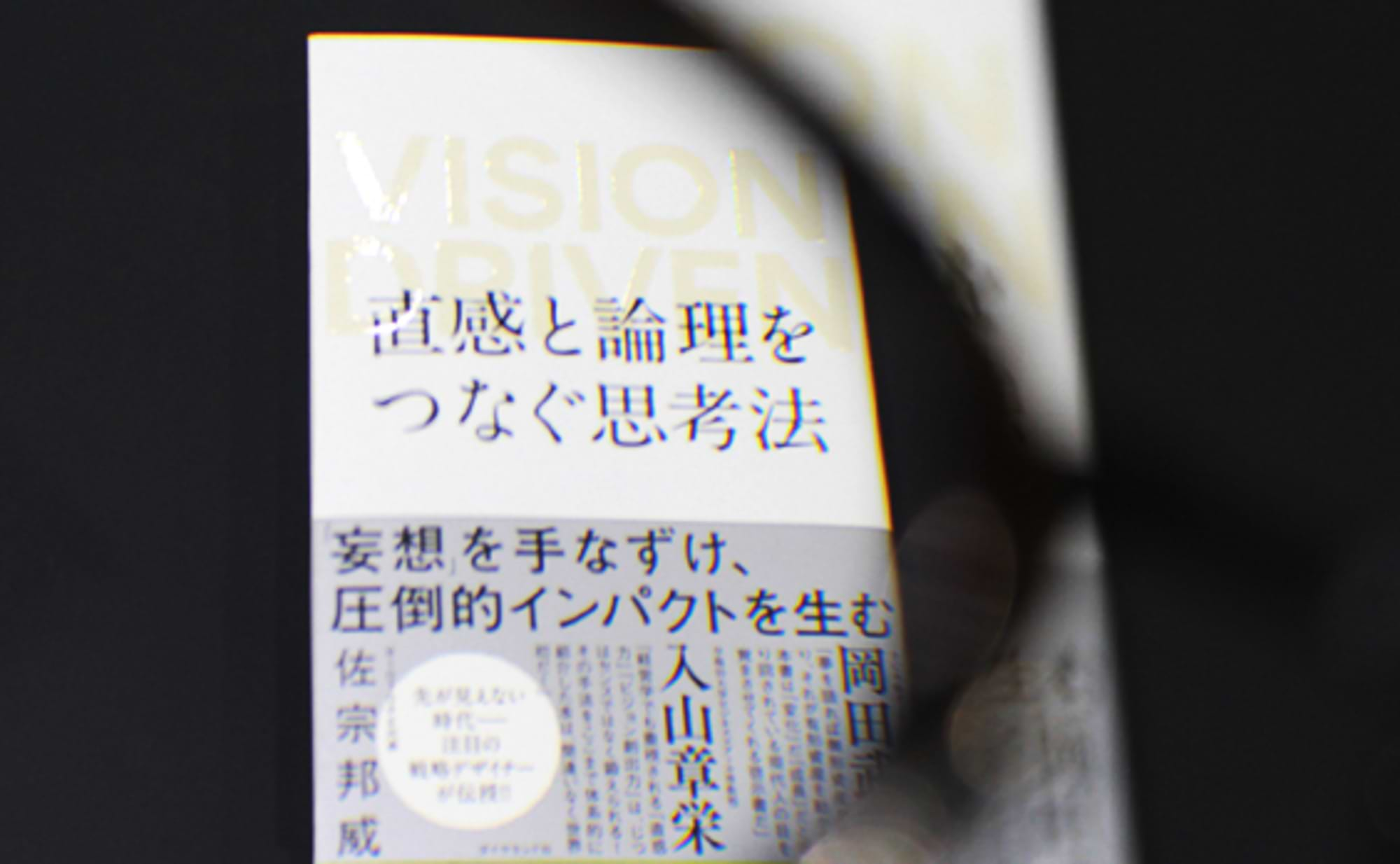『読みたいことを、書けばいい。』は、湧きあがる勇気の書だった。
困った。困り果てている。
確かにこの本を読んで、僕は心が動いたんです。だからこそ、読了後、衝動的に著者の田中泰延(ひろのぶ)さんに直接連絡し「しょうもない読書感想文で恐縮ですけど、書かせてほしい!」とお願いしたのです。
でも、この原稿を書くためにPCに向かっている今の今、なんであんなに感動したのかさっぱり思い出せない。読み終わって、もう一度本書のタイトルを見るにつけ、この本が一体なんの本だったのかうまく言い表せないんです。なんやったんや、あの衝動は…。
困った。仕方がないので、もう一度読んでみたいと思います。

まず、タイトルが謎
今回ご紹介するのは『読みたいことを、書けばいい。』(田中泰延著/ダイヤモンド社)。
著者の田中泰延さんは元電通のコピーライターであり、ライターであり、青年失業家であり、写真者であり、ひろのぶ党党首であり、Twitter無双であり…ご存じない方は何言ってるのか分からないかもしれませんが、すべてご自身でおっしゃっている肩書なのです…。
まずは、分からなくなってしまった胸の内を正直に書いていきたいと思います。
そもそも、本書のタイトル『読みたいことを、書けばいい。』。これが、ことをややこしくしている。タイトルだけだとよく分かりませんが、副題に目をやると「人生が変わるシンプルな文章術」と書いてある。これでようやく「文章術の本なのか」となる。
しかし、結局3回読んでしまった僕がハッキリ言いますが、この本は文章術の本ではありません。
なので、元コピーライターと一流編集者が考え抜いて付けたであろうタイトルと副題は、まったく機能していないことになります。先輩にタメ口でツッコミますけど「24年も電通おって、なに学んどってん!」。
文字が異常にデカい
本書を開いてまずびっくりするのは、文字の異常なデカさです。凡百のビジネス書とは一線を画す級数です。これは明らかに著者の狙いによるものでしょう。
事実、序章に
大切なことは文字が少ないことである。本書はできるだけ文字を少なくし、無駄な記述を徹底的に排除したつくりになっている。(P15)
と書かれています。
ところが、どうでしょう。無駄な記述を徹底的に排除すると書いた直後から、読者にとって何の興味もない著者の財布に関わる描写が数行にわたって続くあたり、「どっちやねん!」「何がしたいねん!」です。
しかし、とにかく字が大きいうえに1章ごとの文章量も少ないため、かつ、何より「徹底的に排除した」はずなのにやたらめったら登場する「無駄な記述」がオモロすぎるため、ついつい夢中になり、次の章、次の章と読んでしまうのです。
なお、読み進めていくと下記引用のように、「書く」という行為に対する洞察めいた(失礼)定義の話や、要素を分解した本質の追求風(失礼)の記述など、割と真面目に(失礼)書かれた箇所もちょくちょくあります。
わたしが随筆を定義すると、こうなる。
「事象と心象が交わるところに生まれる文章」
(中略)
そしてネット上で読まれている文章のほとんどはこの「随筆」にあたるものである。(P54,55)
言葉に対する思考の最初になくてはならないのは、「ことばを疑うこと」だ。
(中略)
自分自身がその言葉の実体を理解することが重要で、そうでなければ他人に意味を伝達することは不可能なのだ。(P65~67)
しかし、残念ながら、多すぎる「無駄な記述」に邪魔されて、これらの「真面目な記述」が本気なのか冷やかしなのか分からないまま、読み進めることになります。
他人の人生を生きてはいけない
そうして読者を油断させておきながら、本書も中盤に差し掛かる頃に、それはやってきます。
読み手など想定して書かなくていい。その文章を最初に読むのは、間違いなく自分だ。自分で読んでおもしろくなければ、書くこと自体が無駄になる。(P99)
書いた文章を最初に読むのは自分。
当たり前やんけ!…でも、なんだか、油断してユルんだガードのすきまから鋭いジャブを一発もらったような、なんでしょう、この感覚…。
書いた文章を読んで喜ぶのは、まず自分自身であるというのがこの本の主旨だ。満足かどうか、楽しいかどうかは自分が決めればいい。しかし、評価は他人が決める。他人がどう思うかは、あなたが決められることではない。
(中略)
だが、ほめてくれる人に、「また次もほめられよう」と思って書くと、だんだん自分がおもしろくなくなってくる。
(中略)
他人の人生を生きてはいけない。書くのは自分だ。だれも代わりに書いてくれない。あなたはあなたの人生を生きる。その方法のひとつが、「書く」ということなのだ。(P114,115)
他人の人生を生きてはいけない。
今度は、ノーガードのみぞおちに重たいボディーブローを食らったような感覚。同時に、なぜかなぜかなぜか、目頭が熱くなってしまっている自分に気が付いてしまったとき、自分で自分のリングにタオルを投げ入れ、心の中で著者に土下座していたのです。
僕はいつも社内で後輩たちに「自分らの仕事を一言で言うたら、“相手の気持ちになって考える”、これだけや」とエラそうに言い続けています。特に僕たちビジネスプロデュース職(かつての営業職)は、生活者の気持ちになって考え抜くことはもちろん、いついかなる時も、クライアントの気持ちや、チームメンバーの気持ちも考え続けて、コミュニケーションを紡ぎ続けることこそが仕事なのだと考えています。
しかし、相手の気持ちを考える行為も行き過ぎれば、著者の言う「評価の奴隷」になってしまいかねません。
相手の思惑に気を遣い過ぎてしまうあまり自己を見失って「他人の人生を生きない」よう、自分の意志を磨き続けることを決して怠ってはならないぞ、そして、ビジネスの現場でも、チームで最後に何をどうするのかは、自分たちビジネスプロデュース職こそが自信を持って決めるんだ、と…そんな、ちょっとばかり熱い思いが湧きあがってきたのです。
ああ、この本は文章術の本のフリをした勇気の本なんや。ひろのぶさんは青年って嘘ついて失業家のフリをした村田諒太なんや。観戦すると(読むと)目頭が熱くなって勇気が湧いてくるんや(全然ボクシングのこと知らんのになんでボクシングに例えたのか自分でも分かりません。それくらい興奮したんやということで許してください)。
ようやく、なぜ自分が本書に心を動かされたのかが見えてきました。
「書く」を、自分の「do」に置き換えて読んでみる
自分のなかで、「これは勇気の本なのだ」という定義ができてから読み進める後半は、すべての章が明日への糧になっていくような感覚で、一気に読んでしまいました。清々しく次のリングに向けてトレーニングに打ち込むかのように(まだボクシングで例える)。
愛と敬意。これが文章の中心にあれば、あなたの書くものには意味がある。(P185)
書くことは世界を狭くすることだ。しかし、その小さななにかが、あくまで結果として、あなたの世界を広くしてくれる。(P225)
書くこと、そして読むことは、その相互の孤独を知り、世界への尊敬や愛情や共感をただ一回の人生で自分のものにすることなのだ。(P247)
「書く」という行為にフォーカスして語られているこれらの言葉ですが、ひろのぶさんの「書く」は、だれかにとっての「do」と置き換えることもできるのだと思います。
例えば、「書く」を僕が好きな「料理」に置き換えてみましょう。休日に家族の食事をつくることにも「愛と敬意」があるからこそ、家族はその意味を受け取ってくれるし、料理や食材の話題に花が咲きます。
そして「料理をする」ということは、その瞬間は半径数メートルの家族の空間だけの出来事かもしれないけれど、それによってレストランやスーパーに行くことが楽しくなったり、同僚家族を自宅に招待して料理をふるまったり、SNSを通じて、出会うはずもなかった料理好き友達ができたり、確実に僕自身の世界は豊かになってきています。
人生、するか、しないか、その分かれ道で
著者のパーソナルな随筆連載「ひろのぶ雑記」(「街角のクリエイティブ」https://www.machikado-creative.jp/ にて連載)のなかでいくつか、何度も読み返してしまう記事があります。そして、どの記事のなかでも、とてもとても好きなのが、最終段落なのです。
本書もその例にもれず、最終章「おわりに」を何度も読み返してしまいます。
最後の最後の最高のオチをここで紹介するような野暮はしませんが、やっぱり、このとてつもないストレートパンチを紹介しないわけにはいきません。
わたしが何度も見返す映像に、映画評論家・荻昌弘の『ロッキー』の解説がある。
(中略)
荻昌弘は評論家としてしっかり調べた上で、この映画に関わったすべての人間が、挑戦し、栄光をつかんだ過程を語る。荻さんは言う。「これは、人生、するか、しないかというその分かれ道で“する”というほうを選んだ、勇気ある人々の物語です。」(P259,260)
いや、これやん!絶対これのせいやんか!ボクシング全く詳しくないのに、何回も例えに使ってしまってたんは!!
分かれ道で“する”という方を選んで、読んだ人だれもに勇気を与える素晴らしい本を生み出された著者に心から敬意を表するとともに、本稿の冒頭でタメ口をきいてしまったことを深くお詫び申し上げます。猛省して、僕なりに「読みたいことを、書いて」みました。
【電通モダンコミュニケーションラボ】
この記事は参考になりましたか?
バックナンバー
著者

本田 祐哉
株式会社電通
ビジネスプロデュース局
広告会社を経て、2007年電通入社。以来、営業として、鉄道、旅行、電機メーカー、エネルギー、外資系製薬会社など多岐にわたるクライアントを担当。広告キャンペーンはもちろんのこと、CRMシステム構築支援からイベント会場の便所掃除まで割といろいろと経験させていただいています。特技は関西弁のなにわ系ドブ板営業。