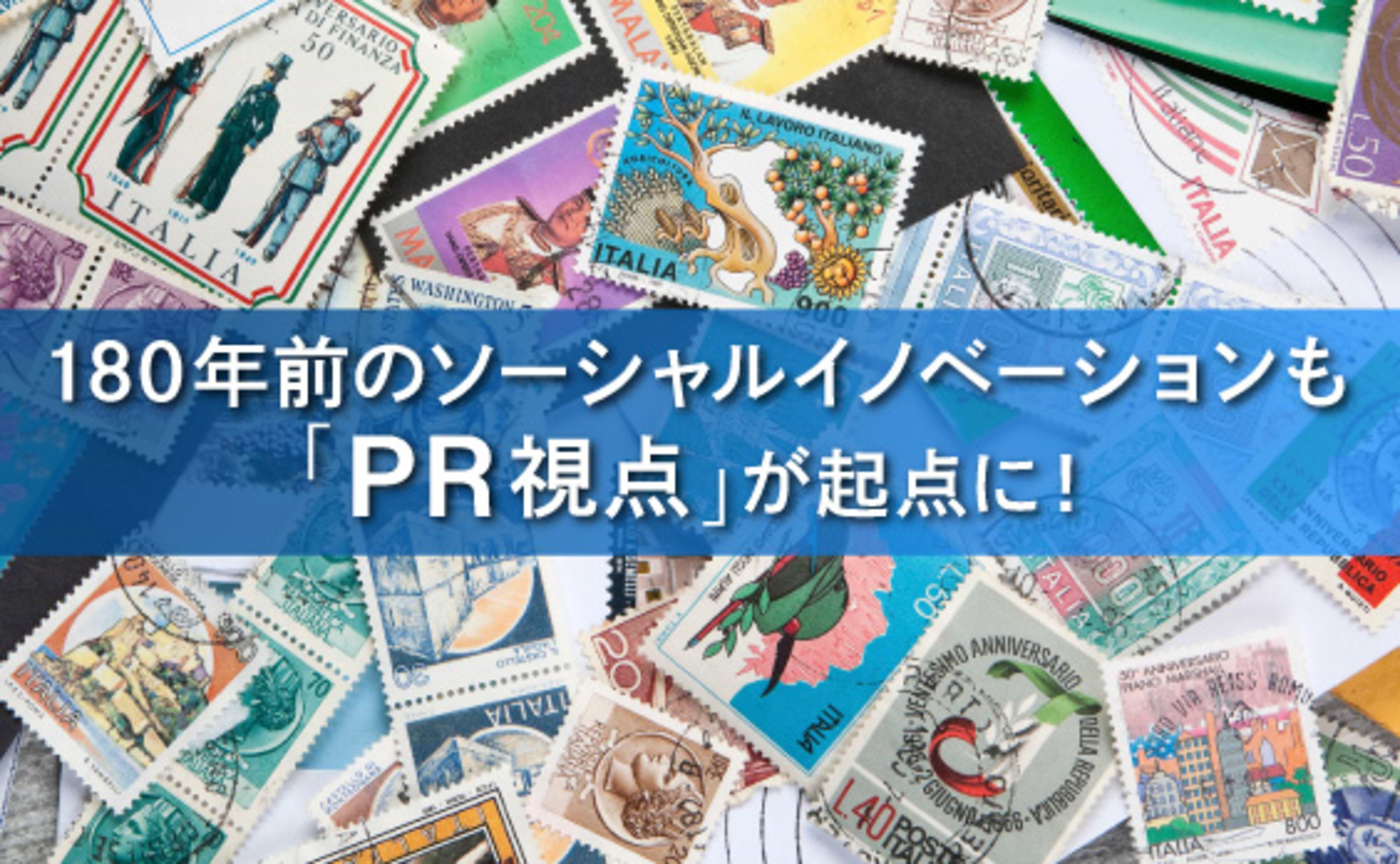清少納言も歌舞伎役者もPRを体現?~カタチのないPRを可視化したPR展の挑戦

世界では、戦争、格差、分断——境界線がますます深く引かれつつあります。日本でもソーシャルメディアを中心に他者への不寛容や誹謗(ひぼう)中傷が後を絶ちません。そんな分断と対立が深まる時代にこそ、信頼と共感を生み出すPR(パブリックリレーションズ)の力が求められているのではないでしょうか。——しかしその問いかけも「PRの本質が“関係を築く”ことにある」という理解がなければ、共感すら得られません。
日本人の9割が、「PR」が何の略称かを正しく理解していないという事実をご存じでしょうか。「PR」という言葉は日常的に使われていますが、それが「Public Relations(パブリックリレーションズ)」の略であると認識している人は、わずか1割未満にとどまります。
一般的には多くの方が、PRは「プロモーション」や「宣伝」といった意味合いで使われており、たとえば、「自己PR」や「#PR」といった表現の広がりが、こうした誤解をさらに広げる一因となっています。
そこで、PRをもっと身近に、そして正しく理解してもらおうと、2024年アドミュージアム東京においてPR展「What is PR? ~PRって何だろう? 身近な活動から社会を変えるチカラまで」を開催しました。この開催が好評だったことから、PR展は現在も都内各所で不定期に開催されています。
“単なる情報発信”ではなく、組織と社会の間に持続的な関係と信頼を築く——そんなPR本来のあり方を、清少納言から現在の社会課題まで幅広くひもといて、一般の方にもわかりやすく伝える試みです。本連載では前編でその企画背景や構成意図を、後編ではPRの歴史とPRが社会とどのようにかかわってきたのかを掘り下げていきます。
“誤解”を“展示”でひもとくまでの道のり
PRが社会の中で正しく理解されていない——その課題に強く向き合うきっかけとなったのは、「ウェブ電通報」で公開した「PR誤解されがち問題」という記事でした。公開後は社内外から多くの共感の声が寄せられました。PRという言葉が社会の中で「プロモーション」や「宣伝」と混同されている現状を、あらためて痛感させられたのです。
そこで今度は、その記事で指摘した誤解を“可視化”し、展示という形で「そもそもPRとは何か?」という問いをより多くの人にわかりやすく届けようと考えました。こうして生まれたのが、PR展「What is PR? ~PRって何だろう? 身近な活動から社会を変えるチカラまで」です。
開催場所となったのはアドミュージアム東京。主旨にご賛同いただき、ミュージアム関係者のご協力のもと、会場は比較的早い段階で決まりました。このミュージアムを運営しているのは「吉田秀雄記念事業財団」です。吉田秀雄氏は、電通の第4代社長であり、日本に初めてPRを“ビジネス”として導入した人物でもあります。広告会社の社長でありながら、PRの将来性を見据えていたその先見性——そのビジョンに連なる場所で、PR展を開催できたことには、大きな意味がありました。

しかし、開催までの道のりは決して平たんではありませんでした。いざ展示の構成を考え始めると、すぐに大きな壁にぶつかったのです。それは、PRには広告のように「目に見えるカタチ」がないという現実です。PRをどうやって“見える化”し、展示として成立させるのか——この難題と向き合うことになりました。
紆余(うよ)曲折、悩んだ末に私たちがまず着手したのは、漠然とした“PR誤解されがち問題”を「数字」で具体的に示すこと。定量的な調査結果から、社会に根づく誤解の深さを明らかにすることが、展示の出発点となったのです。
9割が知らない“本来のPR”
2024年9月、電通PRコンサルティングが実施した「PRの認知度に関するウェブアンケート(※)」で、結果が明らかになりました。前述の通り、日本では、PRの正式名称を「知らない」または「誤って理解している」人が9割以上にのぼったのです。予想はしてはいたものの、ここまで顕著な数字が出るとは、筆者自身も思ってはいませんでした。中でも最も多かった誤解は、PRを「プロモーション」や「宣伝」の一部と捉えるものでした。
たしかに日常では「自己PR」や「#PR」といった言葉を目にする機会は多いですが、PRが「Public Relations(パブリックリレーションズ)」の略であることを知る人は、裏を返せば1割にも満たなかったということです。実際に展示会場を訪れた来場者の中にも、「PRって、ずっと“プロモーション”の略だと思っていました」と話す方が多く、PRへの誤解がいかに根強いかを実感する場面も少なくありませんでした。

そもそもPRとは?PRを見える化する7つの視点
こうした実態を踏まえ、本展示ではPRを以下の7つの視点から、いかにわかりやすく“見える化”するかに注力しました。テーマごとに要点をまとめた数ページのオリジナル冊子を作成し、加えて動画やPOPを活用することで、視覚的にも直感的にも伝わる展示構成にしています。
① そもそもPRって何だろう?
② PRっていつできた言葉?
③ 現代のPRの定義
④ 広告とはどう違うの?
⑤ PRは日常のさまざまなところにある!?
⑥ 紀元前から存在するPR
⑦ PRは世の中を変えるチカラも。


展示会で特に注目を集めたのが、米・ニューヨークにあるThe Museum of Public Relationsと連携して展示した「PR Timeline」です。これは、古代の洞窟壁画から現代のAI技術に至るまで、PRの歴史とその社会的役割の変遷をたどる内容になっています。
たとえば「情報拡散の始まり」とされるのは、古代エジプト人が象形文字を用いて、神殿や記念碑、墓などにメッセージを刻み、より多くの人々に伝えようとした行為。また「スポークスパーソンの登場」については、神のお告げを伝える預言者の存在が聖書に描かれており、これをスポークスパーソンの原型と見る説もあります。中でも一部の歴史家は聖パウロの宣教活動を「PRキャンペーン」と表現しています。「知らなかったことばかりで勉強になった」という反応も寄せられ、改めてPRの歴史や背景を可視化する意義を実感しました。後編では、この「PR Timeline」とこれを制作したThe Museum of Public Relationsをご紹介します。
清少納言は“広報官”?歌舞伎役者は“インフルエンサー”?
展示では、日本の歴史や文化の中に見られる「PR的視点」も紹介しました。たとえば、平安時代の随筆「枕草子」で知られる清少納言。彼女は、一条天皇の中宮定子(皇后)の人柄や魅力を巧みに伝え、多くの人の共感を呼んだまさに“腕利きの広報官”ともいえる存在です。現在ではそのような見方が定説となっており、「枕草子」は“よくできた広報誌”として展示の中で紹介しています。
また、歌舞伎は、現代でいえば、企業の商品やサービスを自然な形で登場させるプロダクトプレースメントの役割も担っていました。江戸時代の歌舞伎役者たちは、庶民の憧れを集める存在であり、現代でいえば“インフルエンサー”のような存在で、人気の高い役者ほど、演技だけでなく、その言動や発信が強い影響力を持ち、観客の心に深く残ったといいます。
現代のPRにおける手法と通じる要素が随所に見られることは、コミュニケーションの本質が時代を超えても変わらないことを示しています。こうした視点から見れば、PRとは現代に限ったものではなく、歴史や文化を通じて人々に影響を与えてきた社会的な営みであることがわかります。

“身近なPR”から“社会を変えるPR”へ
PRは現代の身近なところにもあると気づいてもらうために、たとえば、「就職活動は自分をどう見せるか、まさにPRそのもの」や「大切な人に贈り物を考える視点は既にPR思考」といったトピックを取り上げ、PRは特別な人だけのものではなく、誰もが日常的に関わっていることの気づきになればと紹介しています。
それだけでなく、PRには社会を変える力もあります。カンヌライオンズのPR部門で受賞したグローバル企業の事例もあげながら、ジェンダー平等といった社会課題への取り組みがブランドを通じて一国の法改正を推進するなど、社会に大きなインパクトを与えたことを伝えています。PRは単なる「伝える手段」ではなく、世論を動かし、価値観を変え、社会に影響を与える力を持つ、そのことを、実例を通じて実感してもらえたらと思います。


分断の時代こそ。 “正しく伝える”ことで開く、PRの新しい可能性
PRを正しく知ることは、自分と他者、そして社会との関係を見つめ直すことにもつながるのではないでしょうか。「9割の人がPRを正しく理解していない」という調査結果は、PR業界にとっても看過できない課題です。繰り返しになりますが、PRとは「パブリックリレーションズ」のことであり、広告やプロモーションと同義ではありません。PRは本来、経営戦略のレベルからゴールにアプローチし、社会課題を俯瞰(ふかん)的に捉え、ロングテールで価値を創出できる力を備えています。にもかかわらず、「短期的なマーケティング施策」としてとらえられている現状があるとすれば、それはあまりにももったいないことです。
今回のPR展が、一般の生活者にとってはPRを“正しく理解する”きっかけに、そして実務者にとっては、自らの仕事を“本質から見つめ直す”ヒントになるような機会となればと考えています。そしてこの展示が、次世代のPR人材育成や業界の新しい動きを生む一歩になればうれしく思います。
冒頭でも述べたように、分断・対立が深まり、加えてAIの進化によって「真実」と「フェイク」の境界も曖昧になっているいま、私たちは、「何を信じ、誰と向き合えばいいのか」が見えにくい時代を生きていると言えます。そんな中でPR(パブリックリレーションズ)は、「人と人」「企業と社会」をつなぎ、信頼と共感を育む関係構築を築いていく役割として、これまで以上にその価値が問われています。
匿名の誹謗中傷ではなく対話を。
一方的な発信ではなく、双方向の関係構築を。
いま求められているのは、他者との対話を恐れず、相手の立場に立って関係を築こうとする姿勢です。それはまるで、分断・対立が加速していく危機のときほど基本に立ち返る必要があることを示しているようにも感じられます。
2024年秋にスタートしたPR展「What’s PR?」は、現在も都内各所で不定期に開催を続けています。まさに“移動するPRミュージアム”と呼べるこの展示を通じて、世の中に根強く残る「PR=宣伝、プロモーション」という誤解が、少しずつでも解きほぐされていくことを願っています。どこかでこの展示に出会ったときは、ぜひ足を止めてみてください。きっと新たな気づきがあるはずです。
<資料協力>
The Museum of Public Relations(NY)
アドミュージアム東京
日本パブリックリレーションズ協会
International Public Relations Association
Public Relations Society of America
NPO法人Change the Ref
エデルマン・カナダ
電通、電通PRコンサルティング
<制作協力>
たきコーポレーション
この記事は参考になりましたか?
著者

中川 郁代
電通PRコンサルティング
統合コミュニケーション局
チーフ・コンサルタント
官公庁・企業のPRイベントの企画立案、実施運営に長く従事。育休復職後は管理部門で社員の働き方含め、ナレッジシェアなど社の業務効率化を推進。また自社の企業理念の開発業務にも携わり、現在は社内外のブランディングをサポートする他、インターナル施策などの企画実施も行う。共著書に「企業ミュージアムへようこそ」(時事通信)、「PR4.0への提言」(宣伝会議)などがある。日本PR協会認定PRプランナー。