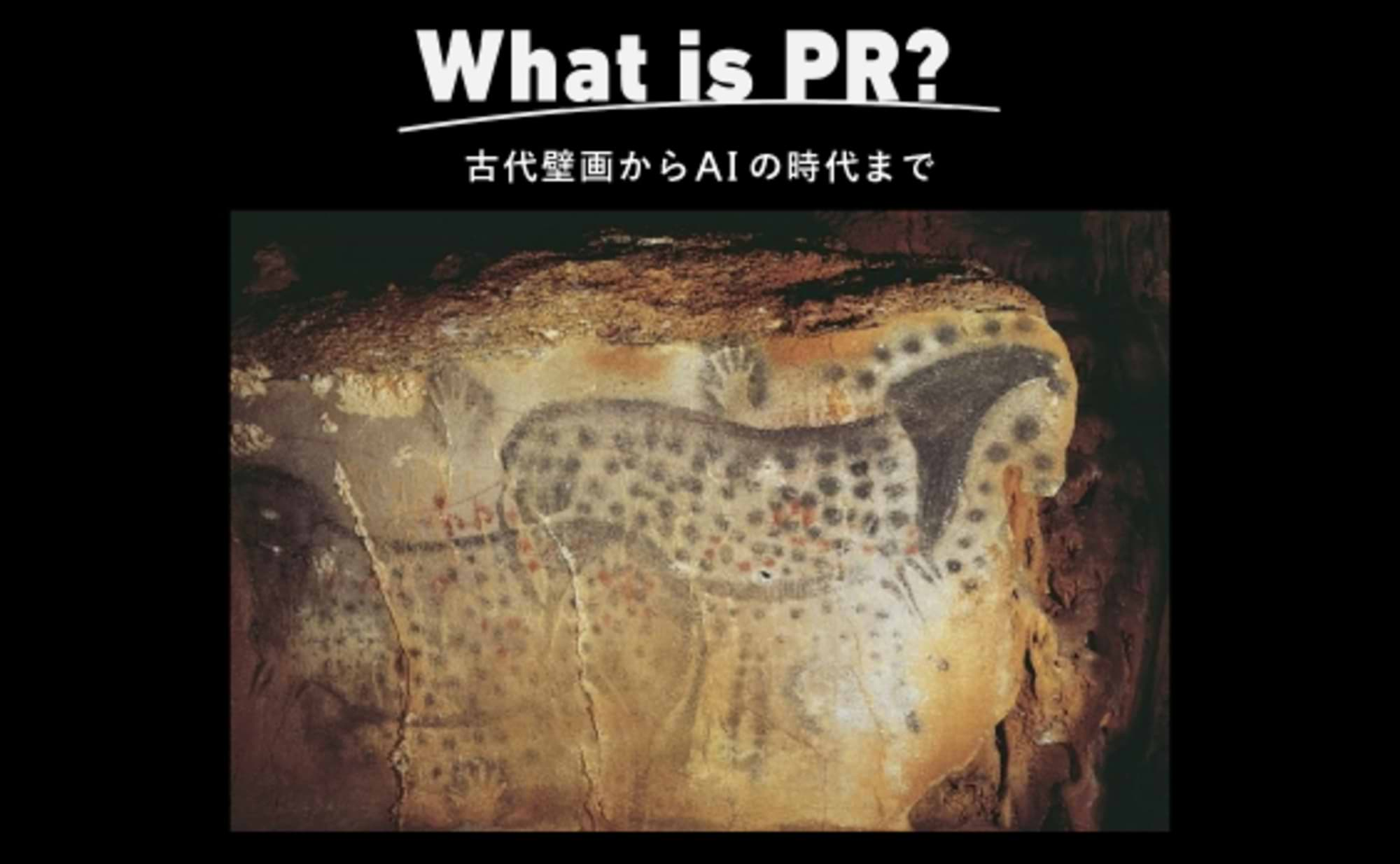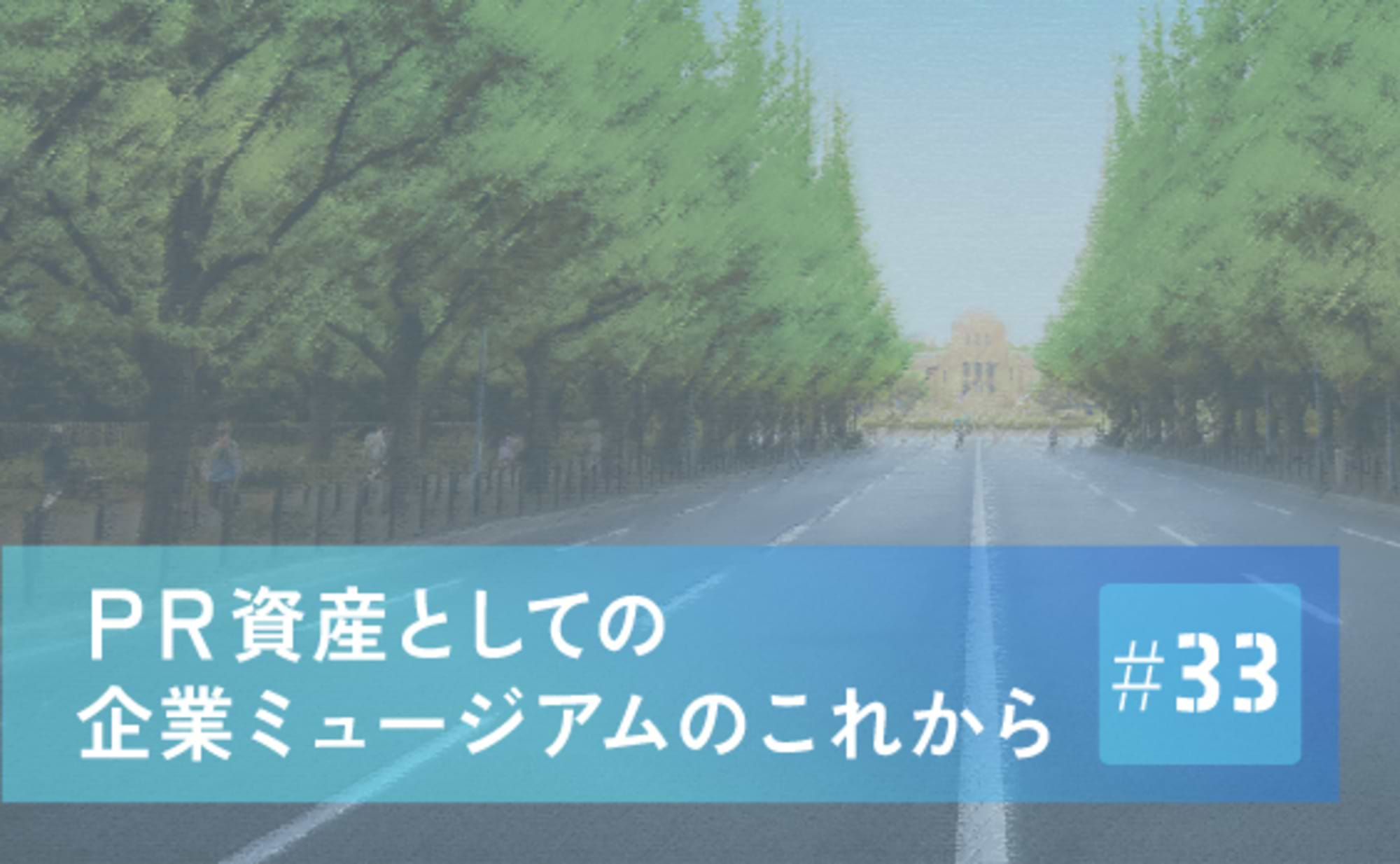古代壁画からAIの時代まで――米PRミュージアム「PR Timeline」で歴史から未来を学ぶ
電通PRコンサルティングが昨秋から都内各所で展開しているPR展「What’s PR?~PRって何だろう?身近な活動から社会を変えるチカラまで」では、ニューヨークの「ザ・ミュージアム・オブ・パブリックリレーションズ」の協力を得て、同ミュージアムのコンテンツの一部を展示しています。本稿ではこのPRを専門に展示するユニークなミュージアムの紹介と、PRミュージアムが目指すもの、さらには、われわれが展示会を通してそこから学んだこと、日本で伝えたいことをご紹介していきます。
マンハッタンのPR専門の常設ミュージアム
私たちが「パブリックリレーションズ(以下PR)」と呼ぶ営みは、古代壁画に始まり、国家の碑文、宗教的スクロールを経て、印刷物・ラジオ・テレビ・デジタルプラットフォームへとメディア環境の革新にともなう、“コミュニケーション技術の進化”を基盤として発展してきました。その歴史的な足跡を1カ所で俯瞰(ふかん)できる常設施設が、マンハッタン南端のウォールストリートにある「ザ・ミュージアム・オブ・パブリックリレーションズ(以下PRミュージアム)」です。
この施設は、ニューヨーク州教育局(Board of Regents)から公式認可(ミュージアム・チャーター)を取得した登録博物館であり、私設展示ではありません。運営母体も、非営利の教育法人(501(c)(3)団体)として認可を受けています。PRを唯一のテーマに据えた常設登録ミュージアムは、世界でここだけとされています。所在地は金融街の高層ビルの23階。研究者、学生、PR実務者が集う「知のアーカイブ」としての空間が広がっています。
ザ・ミュージアム・オブ・パブリックリレーションズ
所在地:120 Wall Street,23階,New York, NY 10005
営業時間:平日(月〜金)11 :00~17 :00、土日は休館
入館料:学生 $10、教育関係者 $15、一般 $25

1997年、PR史研究家のシェリー・スペクター氏とその夫でありパートナーでもあるバリー・スペクター氏が、近代PRの父の一人であるエドワード・バーネイズの私蔵資料を引き継ぎ、まずはオンライン博物館として公開し、その後、物理的なアーカイブとしても拡張しました。ミュージアムの基本姿勢は「PRの歴史から未来を学ぶこと」。過去の記録を保存し、次世代が活用できる形で共有することに重きが置かれています。
5000点を超える所蔵品と展示ハイライト
PRミュージアムのコレクションは5000点を超えます。エドワード・バーネイズとともに、もう一人の近代PRの父と呼ばれるアイビー・リーのプレスリリース草稿、エドワード・バーネイズの初版本や、企業PRの父と呼ばれる元AT&TのPR担当副社長アーサー・ペイジの社内覚書、大手PR会社バーソン・マーステラ(現バーソン)の創業者ハロルド・バーソンのメディアトレーニング資料など、PR黎明(れいめい)期から現代までの原資料が体系的に保存されています。
加えて、このミュージアムには第1次世界大戦期のプロパガンダ資料、ベトナム戦争下の政府PR記録、企業の危機対応文書なども収蔵され、政治・社会運動・企業実務が交錯する多層的な展示構成が特徴です。
われわれは、東京でPR展を開催するに当たり、展示内容を以下のような方針で構成しました。
1)ニュートラルで営業色のないものとすること
2)「グローバル視点と日本の視点」「過去と現在」といった多層的な展示とすること
3)PRを単なる実務やビジネスとしてではなく、より広い社会的営みとして提示すること
そこでわれわれが目をつけたのが、ニューヨークにあるPRミュージアムでした。同ミュージアムにアプローチし、シェリーとバリー両氏の協力の下、同館の貴重なコンテンツを和訳・編集し、展示に盛り込むことにしました。
PR Timeline

PRミュージアムのコンテンツの一つに、「PR Timeline」という、PRの歴史をまとめたものがあります。これは、同ミュージアムと米ホフストラ大学が共同で制作したもので、「Public Relations through the Ages(時代を超えて見るパブリックリレーションズ)」というタイトルの下、PRの進化と人類のコミュニケーションの発展との関係を示した歴史年表です。時代を超えて、「メッセージ」と「伝え手」をつないできた重要な人物、出来事、技術発明の数々が紹介されています。
このタイムラインは、古代洞窟壁画から始まります。これまで洞窟壁画は人類による初期の芸術的表現と見なされてきましたが、近年では、動物を描いた壁画の周りに見られる螺旋(らせん)、楕円、手形、交差する線などの抽象的な記号に注目する文化人類学者が増えています。これらの記号は、単なる装飾ではなく、視覚的な世界を抽象的な記号に置き換える文字の始まりであると考えられるようになっています。そして人類がことばを持つ前の、初期のコミュニケーション手段であった可能性があるとされ、「PR Timeline」ではPR史の出発点と位置付けています。
聖書に見られるスポークスパーソン

「スポークスパーソン(代弁者)」という重要なPRの役割は、実は紀元前に書かれた旧約聖書にその起源を見いだすことができます。「出エジプト記」は旧約聖書の2番目の書で、ヘブライ人がエジプトでの奴隷状態から解放され、神との契約の下に民族として形づくられていく過程を描いています。その中に出てくる預言者モーセは、神からイスラエルの民 を導き出す使命を受けますが、自身の話し下手を理由にためらいます。そこで神は、雄弁な兄アロンに「彼の口となる」役割を与え、モーセが神から受け取った意志をアロンが民やファラオに伝えるという形で「神→モーセ→アロン→民」という伝達の構図を設けます。さらに、民の信頼を得るため、奇跡を起こすつえを与えます。これによって、民は、モーセが神によって遣わされたことを信じたと記されています。モーセが神の意志を受け取り、アロンが民やファラオに向けて語るという役割分担で、兄弟は共に使命を果たしていきます。
聖書において、神の言葉は特別な啓示を受けた預言者など、限られた者しか直接受け取ることができません。「出エジプト記」では、モーセが仲介者として神のメッセージを受け取り、さらにアロンというスポークスパーソンが、それを民にとって理解可能な言葉へと変換しました。つまり、聖書に登場する預言者たちは、神から受け取ったメッセージを人々が理解できる文脈に翻訳して伝え、民の態度変容を促していったのです。さらに、神はモーセに対し、視覚的・体験的な証拠となるつえを与えることで、民の信頼を得ながらその権威を補強したことが描かれています。これはまさに、エビデンスに基づく信頼を背景としたコミュニケーションの一例と見ることもでき、現代のPRの実務でも行われていることです。
新約聖書に見られる「ストーリーテリング」の技術

初期キリスト教会の発展において、コミュニケーションは中心的な役割を果たしました。使徒パウロは地中海各地を旅しながらキリストの教えを広め、新約聖書27巻のうち13巻を執筆したとされます。彼の書簡は、信徒の疑問に答えるために書かれ、礼拝の場で読み上げられることを前提としていました。歴史家の中には、こうした活動を「PRキャンペーン」と位置付ける見解もあります。実際、現在、全世界で約24億人、世界総人口の32%がキリスト教徒であることを考えれば、パウロの宣教活動は人類史上最も成功したPRキャンペーンの一つといっても過言ではありません。新約聖書には、また、「善きサマリア人 」や「放蕩(ほうとう)息子」など、さまざまなたとえ話が描かれています。神の教えやメッセージを人々が理解できるよう、親しみやすい物語を通して語られているものです。これは現代のPRにおいて重視される「ストーリーテリング」と本質的に同じ技法であり、新約聖書にはその原点ともいえるさまざまなストーリーテリングの実例が見られるのです。
PRの歴史は古代から始まり、AIの時代まで続きますが、その一部を電通PRコンサルティングのウェブサイトで公開しています。
https://www.dentsuprc.co.jp/pr/beginners/
世界のリーダーたちはPRの専門家に支えられてきた
PRミュージアムからはこの「PR Timeline」の他に、ハロルド・バーソンがレーガン元大統領と写る写真も提供していただきました。

大手PR会社の社長は、一国の大統領や首相のアドバイザーとして助言することがよくあります。イギリスのPR会社ベル・ポッティンガーの社長であったティモシー・ベルはマーガレット・サッチャー元首相のアドバイザーとして有名でした。アメリカではハロルド・バーソンが、歴代の大統領へ助言してきたことで知られています。中でもロナルド・レーガンとは友人関係にあり、レーガンがホワイトハウスを去った後も、月に1回は昼食を一緒に取っていました。PR展ではこういったPR業界のトリビアも展示しています。国家のリーダーが、PRの重要性を理解していたことがこれらの資料から分かります。
社会改革をもたらすPR
展示コンテンツはPRミュージアムから提供された歴史資料だけではありません。日本におけるPRの歴史では、60年前の電通報の記事の一部も紹介し、「パブリックリレーションズ」という言葉がどのようにして日本に入ってきたのかを紹介しています。
さらに、近年実施されたPRキャンペーンの成功事例なども動画とPOPで展示しました。その一つが、世界最大級のPR会社エデルマンがスウェーデンの家具ブランドであるIKEA(イケア)のためにカナダで実施したPRキャンペーン「SHT(シット)」です。このPRキャンペーンは「カンヌライオンズ2024」PR部門でゴールドを受賞しました。
社会を動かしたイケアのSHTキャンペーン
カナダでは、2022年ごろから全国的な物価高騰が続いており、イケアの調査によると、カナダ人の45%が自身の家計に不安を感じ、多くの人が限られた予算の中でより多くの価値を得るために、中古品市場に活路を見いだしていました。実際、月に1回以上中古品を購入している人は全体の31%に達していました。
一方、オンタリオ州では、全ての売買取引に13%のHST(ハーモナイズド・セールス・タックス/統一売上税)が課されます。この税は1997年から導入されており、もはや誰も疑問を持ちません。
ところが、イケアではある問題に気付きました。中古品を購入すると、税金が二重にかかってしまうことです。新しい持ち主は、最初の購入時にすでに支払われたHSTを、再び支払わされることになります。こうした二重課税によって、連邦政府にはなんと年間数百万ドルもの収益がもたらされていました。

イケアでは、環境保護のため、また、経済的な手頃さを提供するため、自社製品の中古品の売買を行っています。そのイケアが、この二重課税の問題と戦うため、「SHT(セカンドハンド・タックス)」を考案しました。これは、中古品に課される二重課税を事実上打ち消す“対抗税”です。仕組みはシンプルです。HSTが13%であるのに対し、SHTはマイナス13%。顧客がイケアで中古製品を購入する際、税金が相殺され、実質的に0%の税率となるのです。
イケアは、SHTの取り組みについて広くメディアに情報提供を行い、イケアの中古マーケットプレイスへのアクセスとHST廃止を訴える署名活動への参加を促しました。
このキャンペーンの結果、3万5000件以上の署名が集まり、イケアの中古品売り上げが192%の増加をしました。そしてカナダ政府は、二重課税を長期的に廃止するための政策変更についてイケアとの協議に応じることを決定したのです。
このようにPRには、社会課題を浮き彫りにし、その解決に向けたムーブメントをつくり上げるチカラがあるのです。われわれは、PR展で、こういったPRの可能性やチカラについても来場者に訴えていきました。
PRの歴史から未来を学ぶこと
過去を学ぶことは、単に知識を蓄積することではなく、未来のイノベーションを生み出すインサイトを得ることにつながります。洞窟壁画から、AIによる高度な対話が可能となった現代に至るまで、「パブリックリレーションズ」は、人や組織が社会に働きかけ、改革を生み出すチカラとして発展してきました。PR展「What’s PR?」は、小規模ながら、展示する歴史資料と、クリエイティブなケーススタディによって、その歩みと新たな可能性について考える機会の場となることをめざしています。
私たちPR展の運営チームは、「PRとは何か」「PRは人類社会にどのように関わってきたのか」を知っていただくことを出発点に、これからのPR、そして新たなイノベーションへとつながるインスピレーションを感じていただけることを願っています。
この記事は参考になりましたか?
著者

藤井 京子
株式会社 電通PRコンサルティング
エグゼクティブオフィス広報部/国際教養大学大学院客員准教授
国内外の企業、政府、自治体のパブリックリレーションズをサポート。現在は同社の広報を担当。2015年国際PR協会ゴールデンワールドアワードを受賞。編著書『成功17事例で学ぶ 自治体PR戦略』(時事通信社)、『Communicating: A Guide to PR in Japan』(Wiley)、「企業ミュージアムへようこそ 上下巻」(時事通信)など。日本PR協会認定PRプランナー。 2024年から国際教養大学大学院客員准教授(Graduate School of Global Communication and Language)。