醤油屋が、マーケティングを語ってもいいですか?
「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第3回は、岐阜県の醤油メーカー「山川醸造」です。
岐阜市長良葵町に「たまりや」というのれんを構える昭和18年創業の醤油メーカー、山川醸造。清流長良川の伏流水を使い、杉桶で美濃の伝統的な豆味噌とたまり醤油を醸造、販売している醤油蔵が、アイスクリーム専用醤油や、醤油ふりかけなどの加工品で次々とヒットを飛ばしている。「本物は、うまい」という信念の下、蔵人が手間を惜しまず、自然の気候と共に作り上げた味をぜひ、多くの方に味わっていただきたい、と3代目の晃生氏は胸を張る。

山川社長は、おそろしいほどフラットな人物だ。なじみの営業マンからご近所の主婦、そして心の師匠まで、人の意見に熱心に耳を傾ける。チャンスと感じたら、すぐやってみる。そこに頭でっかちな前例主義はない。
「もちろん、たまり醤油に対するこだわりはありますよ。でも、それってお客さんにとっては関係のないことですよね。うちが提供しているのは、醤油じゃなくて、幸せな食卓をつくることなんですから」。木桶仕込みの醤油のシェアは、全国で1%程度。そんなこだわりの醤油を作る会社の社長が、さらりとこんなことを言うのだ。その話だけで、僕はもうワクワクしてしまった。
あたりまえのことを、あたりまえにやることが一番むずかしい。山川社長は、伝統にも革新にもとらわれることなく、ただただおいしい食卓に向かって、まっすぐに進んでいる。そんな山川社長のお話は、学ぶべきことだらけだった。
文責:電通 第1統合ソリューション局 前田星平
なによりも大事なのは、商品開発力
「わが社は、実働9人くらいの、いわば『家族経営』の小さな会社です。主力商品は、たまりといわれる美濃伝統の、クセの強い、風味豊かな醤油です」と語る山川社長。でも、そのクセのある、というところが、いわゆるマーケティング的にはとても大きな壁だったのだそう。地方独特の風味が、東京のオシャレな店では受けない。甘口醤油が一般的な九州でも不評。もちろん、薄味が好まれる関西では論外の扱いだった。
醤油メーカーとしては後発で、しかも扱っているのが「たまり」という、当時、全国区では通用しない商品。「以前はBtoBの商売がほぼ100%を占めていたのですが、おやおや?この市場、どんどん先細っているぞ、ということにあるとき気づいたんです」。そのとき、愚直に「調味料」だけを作っていたのではいけないのだな。「売れる商品」をつくらなければ、と思ったのだと言う。

「私は元々、創造力に溢れたアイデアマンでもなんでもないし、経営学をマスターしているわけでもない。大学なんて、4年間、遊びに行っていたようなものですから(笑)」。作っているものの品質には、自信がある。でも、その作っているものは「豆味噌」と「たまり」だけ。さて、どうしようか、と考えたときに思いついたのが「手のひらに乗っけて、おいしく食べられる商品」を、たまり醤油で何か作れないか?ということだった。
一番の「弱み」こそが、一番の「強み」になる
山川社長がまず取り組んだのは、どうしたら「たまり醤油」が主役になれるのだろう?ということを徹底的に考えることだったのだという。最初に挑戦したのは、醤油ゴマ。この醤油ゴマ、一般的な醤油の賞味期限が2年ほどあるのに対して、わずか半年。なかなか勇気のいる挑戦だった。
ところが、この醤油ゴマが全国的なヒット商品となる。東海地方でしか消費されない、評価されない、いわば「弱み」と思っていた味が、全国で通用する「強み」になり得る、という手応えを感じた。「そこから、たまごかけごはんのたれ、アイスクリームにかける醤油、といった具合にラインナップを増やしていきました」
みたらし団子のように、甘いものとしょっぱいものって、意外と相性がいいもの。ああ、これはイケるぞ、と思ってメーカーに相談に行ったところ、かなりの数のロットがないと製品化は難しい、と言われたのだそう。「ああ、やっぱりダメだったか、とあきらめかけたのですが『じゃあ、アイスにかけるため専用のたまりをつくればいいじゃないか!』と発想を変えたんですね」
山川社長によると、アイスに限らず、料理とは「完成されたものがうまいかどうか」で価値が決まるものであって、たまりそのもので勝負していても意味がない。とにかく、アイスに合うたまりをつくってやろうと、水飴を加えたり、みりんとか、だしとか、あらゆるものを調合してみた。「若い女性に受け入れてもらえるほんのりとした、でも濃厚でクセになる甘さをどう演出するかなど、必死で考えました」
生醤油ではハードルになっていた「たまりのクセの強さ」が、加工品に形を変えた途端、唯一無二のおいしさの秘密として武器になる。その経験から山川醸造では、本当に醤油屋さんですか?と驚かれるほどの多彩な商品をラインアップするようになっていく。

とはいえ、「主役」を張れなければ、生き残れない
山川社長が面白い、と指摘するのは「文句を言う人がお客さんになるとは限らない」ということ。長年付き合いのある取引先やベテランの社員は、大切なパートナーであるものの、新規の顧客にはならない。なので、新しい味に敏感な若い世代、特に女性の意見に積極的に耳を傾けた。その結果、ジャムやシロップのように、アイスクリームにどばっとかけておいしい「たまり」を、1年ほどの試行錯誤の末、作り上げた。
とはいうものの、「主役」を張れるような商品を生み出せなければ、しょせん下請けのメーカーにすぎない。「日本酒で言うなら『あのブランドの、純米大吟醸』みたいな商品が世の中に認められない限り、岐阜の名もなき醤油メーカーです。『ふりかける醤油』というヒット商品も、そうした発想から生まれました」。
これまで家畜の飼料にするしかなかった醤油のカスを、山形に送って「醤油味の塩」にしてもらうという発想。なんだか、本末転倒のような気もするものの、これが受けた。それまでにもあった粉末の醤油ではなく、「醤油味の塩」。それも、たまり醤油味の。まさに、コロンブスの卵のような発想だ。

良いものが売れる、とは限らない
山川社長が心の師匠と仰ぐ人の言葉を、二つ、紹介してくれた。
「伝統や文化を振りかざしてモノを売ろうとするのは、メーカーのおごりでしかない」
「キミは、まんじゅうを食べたことはあるの?」
まんじゅうの話はどういうことなのですか?と尋ねると、要するに、子どもの頃に食べたまんじゅうと、今売られているまんじゅう、何か違うと思わない?ということなのだそう。そういえば、昔のまんじゅうは砂糖コテコテだったけど、今のまんじゅうはクリーミーな気がします。と答えたところ「それが、消費者ニーズというものじゃないの?」と、ズバリと刺され、心に響く言葉となった。
「学ぶとは、まねることなんだということも、同時に気づかされました」。いきなり「我流」を突っ走っても、迷走するだけ。とりあえず、100%徹底的に真似してみる。これが、山川社長流の極意だ。今は山川醸造の名物となっている「蔵開放イベント」も、元々はとある酒蔵の取り組みにヒントをもらったものだと言う。「まねているうちに、だんだん『自分流』が見えてくる。まねたものを、アレンジしていくこと。それが、クリエイティブなことだと思いますね」

伝統は守り抜く。でも、固執はしない
山川社長の娘で4代目となる華奈子さんは、こう言う。「伝統に固執せずに、なにか新しいことができないかというチャレンジを常にしているところが、山川醸造の強みなのかもしれません」と。それは、ネットを使った「蔵見学」の企画はもちろん、商品のパッケージひとつにも表れている。「食卓に置かれた時に、ごちゃごちゃした印象にならず、でも、どこかウキウキする」そんなデザインを追求しているのだそう。
「その意味では、父も母も、そして私も、伝統を守りつつも、これまでにない楽しいこと提供できないか、ということを諦めていないんだと思います」。お客さまとの距離がまた一つ縮まったな、と感じられた瞬間が、ものすごくうれしい。そう語る華奈子さんの表情は、とても無邪気で、優しいものだった。
山川醸造が営む「たまりや」のホームページは、こちら。
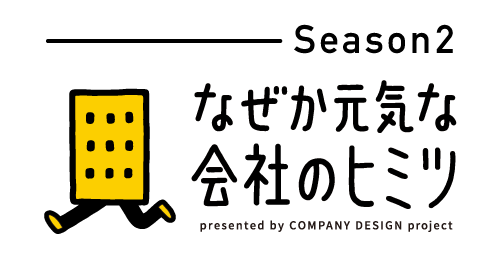
「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第3回は、醤油メーカー「山川醸造」をご紹介しました。
Season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
(編集後記)
山川社長の表情は、どこまでも穏やかだ。「もうけてやろう」「成功してやろう」といったものが、どこにも感じられない。社員やお客さま、そして家族に「楽しいね」と言ってもらうために、自分にはいったい何ができるんだろう?そんなことを、毎日考えている人なんだろうな、という印象だった。
そのためには「接点を持つこと」が大切なのだ、と山川社長は言う。広告業界のワードで言えば「コンタクトポイント」ということだ。接点を持つためには、ネットでも、SNSでも積極的に利用する。クラウドファンディングも、ブログも、一から勉強した。もうけるためではない。つながりたい一心で、おいしいものをより多くの人に知ってもらいたいというその思いで、マウスを握り、キーボードを叩くのだ。
リモート取材の日、期せずして「白い衣装」で画面に現れた山川親子に、どうして今日はお二人とも白いお召し物なのですか?と尋ねてみた。さあ、どうしてなのでしょう?と、照れながら顔を見合わせるお二人に、とてつもない絆の強さのようなものを感じた。
この記事は参考になりましたか?
著者

前田 星平
株式会社 電通
ビジネストランスフォーメーションクリエーティブセンター
コミュニケーションデザイナー
クリエーティブ、PR、マーケティング、プロモーション、イベント、ウェブ制作など、複数の部署での経験値を生かして、現在はコミュニケーションデザイナー。6歳児のパパ。



