「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第14回は、岩手に本社を構え、アートビジネスを手掛ける福祉実験ユニット「ヘラルボニー」。その挑戦の核心に迫ります。
双子の兄弟で、アートビジネスを手掛ける松田社長。4つ上のお兄様が、先天性の知的障害を伴う症状なのだという。その兄の存在こそが、障害のあるアーティストによるブランド化という発想につながった。
作品の持つ力こそが全てであるアートの世界に、あらゆる差別や偏見はない、はずだ。ところが、現実は違う。性別や年齢、国籍、学歴、賞歴、障害があることなど、あらゆるフィルターを通して作品が評価される。そこに多くの過小評価が生まれてしまう。松田社長へのインタビューで印象的だったのは「フェア」という言葉。単純に社会的な弱者を救ってあげたい、ということではない。美しいな、かわいいな、素敵だなと思うものが正しく評価されて、そこに社会的な価値が生まれる。そんな世の中に転換するきっかけづくりがしたい、と松田社長は言う。
この会社が持つインクルージョン性は、社長の出身が岩手であり、現在も本社を岩手に構えていることとも無関係ではなさそうだ。そして、この普遍的な理念の先に、どのような未来を描いているのか。そのあたりも、今回のインタビューではぜひ探ってみたい。
文責:後藤一臣(電通BXCC局)

フェアじゃない社会を、どうにかしたかった
「僕自身、母親が社会福祉士をしていたこともあって、ヘラルボニーさんの事業には注目していたんです」という後藤からの投げかけに、松田社長は穏やかな表情で応えた。「ありがとうございます。僕も、新卒の2年目に岩手の福祉施設を訪ねる機会があって、そこで知的障害のあるアーティストの才能を目の当たりにしたことが創業のきっかけでした」
松田社長のすごいところは、福祉=思いやりや介護、という連想ではなく「この才能をブランドという傘の中で、社会に価値として提案できるのではないか」と、発想したところだ。「障害のある人を救いたい、とか、そういうことではなく、そこにある美しいものを価値として社会とコネクトするにはどうしたらいいんだろう?ということを、まず考えたんです。素晴らしいアーティストが生み出した作品が目の前にある。それらをデータ化して、美しい形で世の中に送り出すことができれば、これは誰にとってもWin-Winのビジネスになるんじゃないか、と」
幼い頃から、4つ上のお兄さまのことを間近で見ていて、とにかく世の中フェアじゃない!と憤りを感じていた、と松田社長は言う。「家の中では、兄の突飛な行動や発想力みたいなものを、日常として当たり前に素敵だな、と思っていたのですが、一歩外に出ると、兄は『障害者』という枠の中で生きている、偏見や差別が待っている。そこに違和感を抱いていました」

松田崇弥氏:株式会社ヘラルボニー代表取締役・CEO。小山薫堂が率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズ、プランナーを経て独立。「異彩を、放て。」をミッションに掲げる福祉実験ユニットを双子の兄・文登と共に設立。岩手と東京の2拠点を軸に福祉領域のアップデートに挑む。ヘラルボニーのクリエイティブを統括。日本を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」受賞。日本オープンイノベーション大賞「環境大臣賞」受賞。
「大学で企画構想を学んでいたこともあり、ある時、世の中フェアじゃない!という憤りが、ひょっとしたらこれはチャンスなのではないか、と思えてきたんです。アートって、その人の個性から生まれるものですよね。あるいは、普通の人にはまねのできない、とてつもない時間と集中力を必要とされる作業に没頭できる能力によるもの。知的障害のあるアーティストの才能は、もっと評価されてしかるべきなのでは?ということなんです」
そして松田社長の発想がユニークなのは、アートをデザインライセンスの文脈で捉えた、ということだ。「有名ブランドのデザイン、と言われてアタマに浮かぶものがありますよね。あのようなデザインパターンについて特筆すべき才能のあるアーティストを世の中に送り出すことができれば、ビジネスとして成立するのではないか、ということなんです」
松田社長いわく、パターンのデザインは知的障害のある人にとって「日常のルーティン」と密接に関係している傾向があるのだという。例えば、延々と水玉模様だけを描き続けることができてしまう才能。繰り返しの表現によって生み出されるアート作品を、「知的障害があるからこそ描ける世界である」と捉え、着目したのだ。
デザインの文脈で、アートを捉える
「アート、と言われると、一点物の絵画とか彫刻を思い浮かべますよね。もちろん、それにも価値はあるんですが、デザインのパターンなのだ、と考えれば、途端に応用範囲は広がる。バッグにしてもいいし、Tシャツにしてもいい。工事の仮囲いのデザインにも展開できる。商品パッケージにもなる。これはいいなと思う作品を起用して、デザインとして世の中に広めればいいんだ、ということに気付いたんです」
ピュアアートとビジネスは、ある意味、対極のものとされる。広告の世界でも、そうだ。「あのねえ、キミ。僕らはアート作品をつくってるんじゃない。商品を売るための広告をつくってるんだよ!」とどこからか声が聞こえてきそうである。でも、松田社長の発言には、ハッとさせられた。「芸術には、力がある。人の心を動かし、お金の循環を生み出すような力が」

イノベーションは、辺境の地から生まれる
イノベーションは、辺境の地から生まれる、と松田社長は言う。「岩手には、上場企業も少なく、ビジネス的には不毛な地かもしれません。でも、だからこそ何かを生み出そうというエネルギーが湧いてくる。そこで生まれたものを、東京に持っていく。世界に発信していく。それが、僕が担っている仕事であり、責任だと思っています」
松田社長のこの言葉には、地域にひもづいた「足腰の強さ」のようなものを感じた。ヘラルボニーのビジネスは、障害のある作家のアート作品をプラットフォームとして組織化していくものであり、そのためには、本人の意思と家族の協力、そして、その才能を認めていく文化が重要である。その文化を創造するには、トレンドの移り変わりが早い都市圏よりも、地方の方がマッチしている。今、ヘラルボニーが元気なのは、岩手という地盤で、文化を創造できたからなのだと確信した。生まれた文化をブランド化し、それをマネタイズする。マネタイズするにはマス化が必要だから、そこで初めて都市部に進出するのだ。とても真っ当な考え方である。
しかし、ビジネスの世界では、しばしば発想の順番が逆転する。まずは、いかに稼ぐか。そのために、いかにブランドをつくるか。結果として、文化的なものがつくれればいい、といったように。でも、それでは長く愛されるブランドはつくれないのではないか。大切にすべきは、文化だ。ヘラルボニーのそれを支えているのは、地域の風土であり、人と人のつながりであり、誰かが誰かを想う気持ちであり、個々人の輝く個性だ。そんな、基本的なことに改めて気付かされた。

大事なことは、作家ファーストであること
「電通では、クリエイターでもプロデュースの能力が必要な時代になっていると感じていますが、基本的には、アーティストにとってはプロデューサーという存在が重要ですよね。江戸時代の浮世絵師も、天才的な才能があったとしても、それをプロデュースする版元がいなかったら、単に絵を描いてるだけ、になってしまいます」そんな問いかけに、松田社長はこう答えた。
「会社のスタンスとして、常に作家ファーストを重視しています。作家のことを第一に、大事に、考えています」。松田社長によると、何かトラブルが起きた時に、頭を下げる順番も決めているのだという。「例えば納期に作品が間に合わないという可能性があった場合、施設や作家さんを急かすことはせず、私たちがクライアントに謝りに行くようになっています。万が一何か起きた時の細かい対応を決めておくことで、作家さんと施設を常に最優先で対応することを目指しています」
福祉施設、作家に対する還元率の割合も公開している。「還元率は、原画が40〜50%、ワンショットライセンスが30%、仮囲いアートが10%、プロダクトライセンスが8%(内5%が弊社、3%が福祉施設、作家)、自社物販が5%になります。公平性や透明性は何より大事にしています」

優しい世界とは、フェアな世界
ヘラルボニーの広報を担当している浅川里菜氏は、こう言う。「作家さんや社会に対する貢献や支援としてではなく、自分自身の好奇心こそ、作品やアーティストに対するリスペクトこそがこの仕事に夢中になっている最大の理由です」。松田社長も、うなずいてこう続けた。
「そうですね。自分たちは知的障害のある方たちに食べさせてもらっている、言わば支援されている立場だと思っているので、支援やサポートという言葉はあまり使わないです。『障害者支援』という部分がフィーチャーされるよりも、作家によるアートやデザインのビジネスでありたい」この発言は、アーティストの才能をビジネスの真ん中においていることがうかがえる発言であった。
最後に、松田社長がよく口にする「優しい世界」とはどういうものなのかを尋ねてみた。「フェアな世界、ということだと思いますね。障害のある人が『できない』のではなくて、できるのに、あまりにも社会に障壁があるため『できない』というのは、アンフェアでしょう。その障壁を取り除く手段として、アートは有効だと思うんです」。ヘラルボニーが掲げている「異彩を、放て。」というスローガンの真意が、とてもよく理解できた。

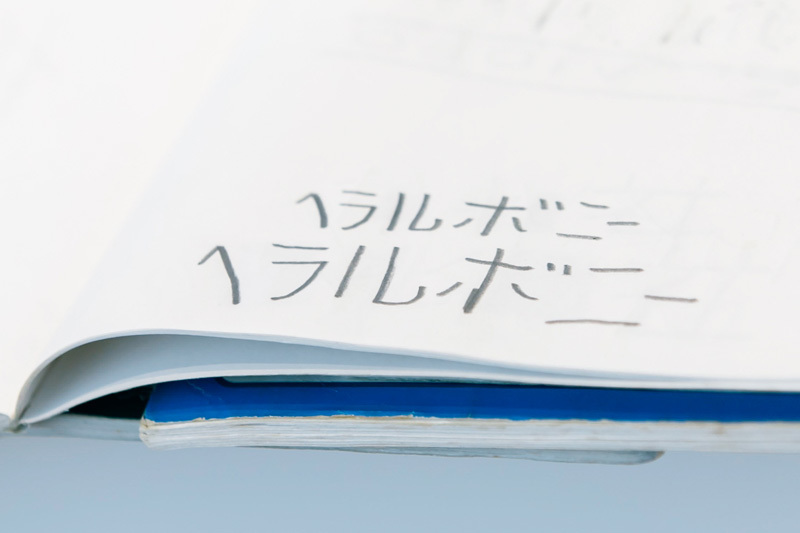
ヘラルボニーのホームページは、こちら。
コーポレートサイトは、こちら。
ブランドサイトは、こちら。
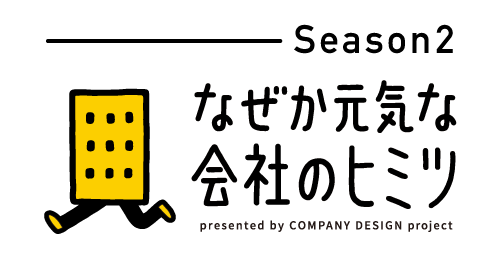
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第14回は、岩手に本社を構え、アートビジネスを手がける「ヘラルボニー」をご紹介しました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
松田社長の言葉で印象的だったのは、「僕自身、別に、アートにこだわっているわけではないんです」というもの。えっ、と耳を疑った。が、話を伺うにつれ、その真意が分かってきた。知的障害のある人に限らず、「できないことをできるようにする」ことは難しい。
例えば、松田社長の4つ上のお兄様は、他人に対して普通に挨拶をすることが、とてつもなく苦手だったりする。「でも、そのありのままの姿に社会の方が付加価値をつけることができたら、とっても優しい世界が生まれると思うんです。挨拶のできないホテルとか飲食店とかが、あってもいいじゃないですか。うわさでは聞いていたけど、本当に無愛想なんだ。でも、サービスは心地いいし、料理もうまい!みたいな。そういうその人のありのままを肯定するものを、世の中に提供していけたらな、と」
インタビューを通じて、松田社長が繰り返し口にした「フェア」の意味がちょっと分かった気がする。弱者に手を差し伸べてあげましょう、みたいなことではない。価値あるものを生み出せる人間を、正当に評価して、きちんとリスペクトし合える世の中にしたい、ということだ。
「優しい世界」を、精神論や道徳で語るのは簡単だ。それを、社会の仕組みとして成立させることに、松田社長は取り組んでいる。アートそのものが、目的なのではない。もちろん、金もうけのためでもない。あくまで、知的障害のある人が自分らしく生きられる「優しい世界」を実現するための手段なのだ。
この記事は参考になりましたか?
著者

後藤 一臣
株式会社 電通
BXクリエーティブ・センター
局長 エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
課題に対する最適解をニュートラルに発想。ストプラ+CR+メディアをワンストップで。Creativity×経営で事業成長にコミット。カンヌ金、アドフェストグランプリなど受賞。



