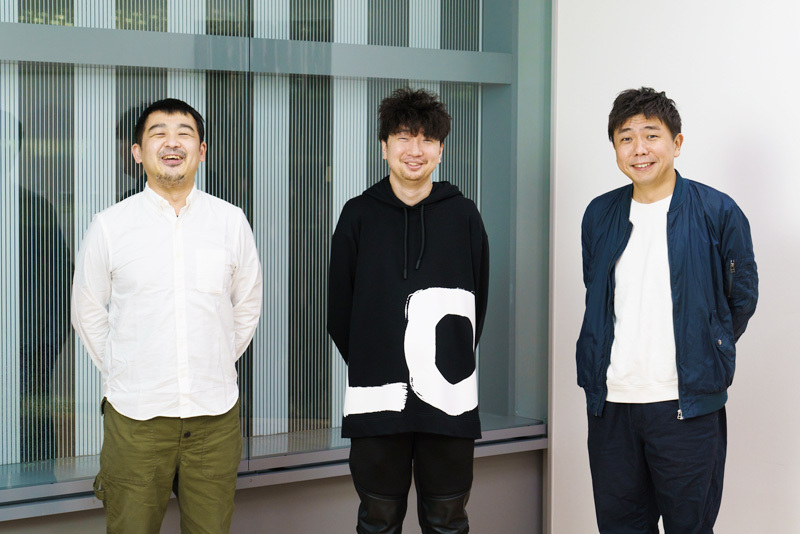©原作:モンキー・パンチ ©TMS・NTV ©横関大/講談社 ©2021「劇場版 ルパンの娘」製作委員会
2021年にアニメ化50周年記念企画としてスタートしたテレビアニメ「ルパン三世 PART6」(日本テレビ系)と、同年に公開された映画「劇場版 ルパンの娘」(フジテレビ系)。
アニメと実写、日本テレビとフジテレビ。
全く異なるコンテンツであるにもかかわらず、両者の垣根を越えた異例のコラボプロモーションが大きな反響を呼びました。
この驚愕のコラボは、なぜ実現したのか?日本テレビのプロデューサー 塩出正樹氏と、フジテレビのプロデューサー 稲葉直人氏をゲストに迎え、電通コンテンツビジネス・デザイン・センターの小杉純善氏が話を聞きました。
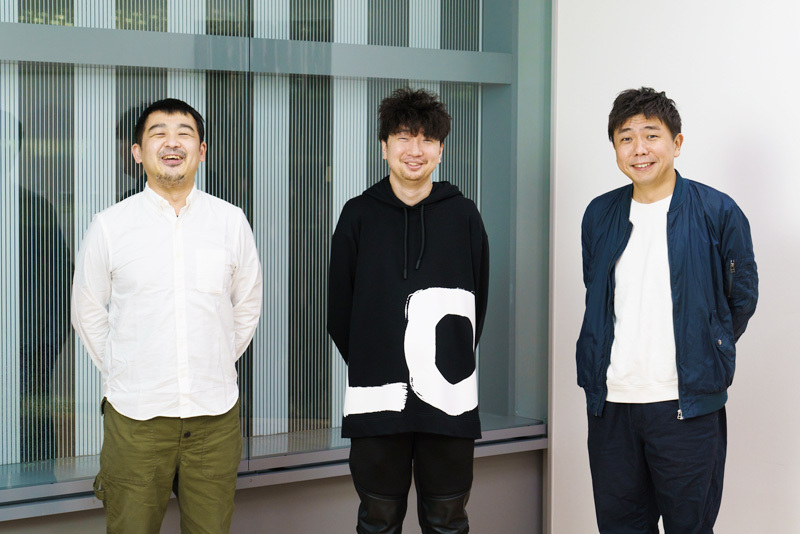
左から日本テレビ塩出正樹氏、電通小杉純善氏、フジテレビ稲葉直人氏。対談時はマスクをし、新型コロナ感染症対策をした上で行われました。
「ルパン三世」と「ルパンの娘」が、お互いの広告を盗み合う衝撃展開
小杉:まず私から今回のコラボについて簡単に説明します。全ての始まりは、「ルパン三世 PART6」と「劇場版 ルパンの娘」、各公式Twitterアカウント。ヘッダーに、突如として謎の「犯行声明文」が現れました。特に告知はしていなかったのですが、SNS上では気がついたユーザーたちのあいだで“ザワつき”が巻き起こりましたね。


お互いの公式Twitterアカウントに、謎の予告状!ネットをざわつかせたコラボの予兆。
小杉:その後、それぞれの公式YouTubeチャンネルで公開した予告映像のラストで、「この広告はいただいた」という犯行メッセージと共に互いの作品を告知。
これを皮切りに、OOH広告やクリアファイルのプレゼントキャンペーンなど、コラボプロモーションが次々と展開されました。
小杉:以上がコラボの全体像です。このコラボの背景について、日本テレビとフジテレビ、両者の立場から詳しくお聞かせいただければと思います。
塩出:日本テレビの「ルパン三世」シリーズは、もともと原作コミックの作者であるモンキー・パンチ先生がクリエイターに対してとても寛容な方で、コンテンツ自体がとても“柔軟”だったんです。おかげでこれまでもトップクリエイターの個性やアイデアが発揮された、多彩な作品が生み出されてきました。多くのファンに支えられて、2021年でアニメ化50周年を迎えたのですが、一方で新規ファンの獲得や、ライトユーザーの方々に深く楽しんでいただく機会をもっと増やしたいと考えていました。
電通さんから今回のコラボをご提案いただいた時は、本当に実現できたら、今までリーチできていなかった層にもアプローチできるのではないかとワクワクしたことを覚えています。「ルパンの娘」もまた、モンキー・パンチ先生の姿勢にも通じる“柔軟さ”を体現している作品ですし、二つの“ルパン”コンテンツがコラボするのはとても面白いなと。乗り越えなければならない壁はたくさんありましたが、皆さんのご協力のおかげで実現できました。
稲葉:「ルパンの娘」は横関大さんの小説が原作なのですが、深田恭子さん主演の実写ドラマ版ではあえて特撮風のレトロな雰囲気を全面に押し出して、最近のドラマっぽくないものを目指しました。40~50代のおじさんが集まって自分たちが面白いと思うものを作ったつもりが、いざフタを開けてみると、なぜか小中学生とそのお母さんたちに好評でして(笑)。決して万人受けする作品じゃなくても、熱量を込めれば届く人には届くのだと実感しました。
ドラマがファミリー層にも好評だったおかげもあり、映画の企画も順調に進んでいたのですが、コロナ禍で映画館に行くファミリーが激減してしまい、もっと幅広い層に届ける手段が必要になりました。コロナ禍を抜きにしても、近年はインターネットのコンテンツが急速に台頭する中、テレビ局も既存の考え方にとらわれすぎてはいけないという危機感もありました。そんな時、日テレさんが「ルパン三世」の新シリーズを始めると知り、「ルパン同士で一緒に面白いことはできないかな?」と同期の電通テレビ局社員とルパンの娘の映画プロモーションを手伝ってくれたメンバーと盛り上がっていたんです。
さすがに実際にコラボするのは難しいと思っていたのですが、その同期がよく動いてくれたこと、そして何よりも塩出さんの人柄のおかげで実現できたと思っています。
「タブーを破った」ことが業界内だけでなく視聴者にもインパクトを与えた
小杉:お二人ともありがとうございます。日本テレビとフジテレビ、それぞれの関係者の尽力なしでは成立し得なかった企画だと思っています。視聴者やファンの反応はいかがでしたか?
塩出:「ルパン三世」は歴史のあるコンテンツだからこそ、新規層やライト層には敬遠されがちな面もありました。アニメファンでも、“シリーズもの”は古いものから順を追って見たい人が多いので、いきなりPART6と言われても、とっつきにくいんですよね。今回、攻めたコラボがSNSを中心に話題になることで、「ルパンがなんか変なことやっているな」と、今まで接点がなかった層からもリアクションを頂けました。
稲葉:「ルパンの娘」は逆に歴史が浅いコンテンツなので、当たり前ですけれど「ルパン三世」と比較されて厳しい意見を頂くこともありました。それが今回のコラボによって、ある意味“公認”をもらえたと言いますか、「ルパン三世」ファンからも肯定的な意見を頂けたことが、とてもうれしかったです。あと、最近は視聴者の方々も“業界ルール”的なことに詳しいので、そのタブーを破ったインパクトは伝わったように感じます。
塩出:最近は特定コンテンツのスピンオフを展開するパターンも増えているので、どっちが本物、どっちが偽物という見方だけでなく、いろんな形のコンテンツを許容する雰囲気も醸成されているような気がしますね。私たちも新しい“ルパン”コンテンツとコラボできることは本当に光栄なことでした。
小杉:先ほどタブーとおっしゃっていました。やはり日本テレビとフジテレビというライバル企業がコラボすることのハードルは、僕らが思っている以上に高かったと思いますが、その辺りはいかがですか。
塩出:「他局と一緒に盛り上げよう」なんて、ひと昔前は絶対に認められなかったことですからね。大変なことはいっぱいありました。ただ、今回はコラボにおけるクリエイティブそのものが好評だったこともあり、時間がない中でもうまく調整できたと思っています。「あのルパンが、新しいことにチャレンジしている」と業界内外で話題になったことで、今後もテレビ局の垣根を越えた面白いコラボが生まれるのではないでしょうか。
稲葉:いろんなコンテンツがありますからね、一緒にドラマとか映画、作りたいですよね(笑)。
IPビジネスの原石だらけ!テレビの鍵は「コンテンツありき」の発想にある

小杉:近年、放送局の事業領域は変化し続けており、“放送外”のビジネスも重要なファクターになっています。特にIPビジネスについて、両社はどのような取り組みをされていますか?
塩出:IPビジネスに関しては、「ルパン三世」のようなアニメはもちろん、最近だとNizi ProjectやTHE FIRSTなど、アーティストのオーディション過程を見せるコンテンツが大きな反響を頂けています。これをさらに盛り上げて広げていく方法を模索しています。
稲葉:今はまず、過去にヒットしたドラマやバラエティーなど、「今眠っているコンテンツ」を掘り起こして世の中に届けることが、会社として注力していることの一つです。その上で、やはりオリジナルコンテンツをヒットさせたほうがIPビジネスとしてのインパクトも大きくなるので、新しく面白いオリジナルコンテンツを生み出していけるといいですね。
小杉:ありがとうございます。今の稲葉さんのお話にありましたが、私が電通でIPビジネスに携わる中で感じるのは、放送されているコンテンツの中に原石がたくさんあるということ。決してファンの規模が大きくないコンテンツでも、コアファンには深く刺さる魅力があり、そこには大きな可能性がある。今回のコラボも「ルパン三世」と「ルパンの娘」、双方のコアファンが盛り上がる相乗効果で、お互いのコンテンツがより幅広い層に広がっていきました。原石の状態であるコンテンツを磨いて輝かせていく段階からご一緒することで、より多くの人たちに面白いコンテンツを届け、テレビ局の放送外ビジネスを盛り上げていけると考えています。
塩出:それと個人的な考えですが、“放送外ビジネス”という捉え方自体も変えたほうが良いと思っているんです。私自身もそのような束縛から抜け出す努力をしているところですが、放送“外”という言葉の奥底には、「放送がメインでIPは端っこのビジネス」という意識が感じられます。でも本来って、まずはコンテンツがあり、放送も放送以外の手段も使ってコンテンツを広げていくことが、テレビ局の役割だと思うんです。それこそ、今回のコラボのように、競合関係を越えてテレビ業界全体でコンテンツを盛り上げることが、巡り巡ってテレビの魅力を高めることにつながるのではないでしょうか。
稲葉:同感です!コンテンツを中心に考えると、テレビのライバルとなるコンテンツって、インターネット配信だけでなく、SNSなどのコミュニケーションツールも含めて山のようにありますよね。そうなると、もはや民放5局の中だけで競い合っている時代ではないのかなと。あらゆる選択肢の中から自分たちの番組を選んでもらうために欠かせないのは、やっぱりコンテンツの力です。今後、いかに強いコンテンツを作り続けられるかが放送局には求められるし、強いコンテンツさえ生まれれば、自ずとマネタイズもうまくいくと思います。
小杉:今回はライバルである2社が、お互いに削り合うのではなく、高め合うことにベクトルを向けてくださったことが大きいと思っています。この事例をきっかけに、放送局の垣根を越えた新しいチャレンジが次々と生まれることを願っています。本日はありがとうございました!