「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第32回は、震災から間もない2012年に宮城県気仙沼市に創業した、ニット製品の製造・販売を手掛けるKESENNUMA KNITTING(気仙沼ニッティング)を紹介します。
東北の港町、気仙沼の地で一流のニットが生まれている。オーダーメードで、全て手編みでつくられ、その編み手は地域の女性たち。価格的にも地理的にも気軽に手が出せるものではないそのニットには、全国にファンがたくさんいて、1年半待ちの製品もあるという。
そんな気仙沼ニッティングの代表を務めるのは、気仙沼とは縁もゆかりもなかった御手洗瑞子社長。マッキンゼー・アンド・カンパニーでコンサルタントとして勤務後、ブータン王国政府の首相フェローとして同国の観光業活性化に取り組んだ、ユニークな経歴の持ち主だ。
一体、どうしたらこんなことが実現できるのか。そのヒミツを探っていくと、豊かな仕事とは何か、成長する企業に必要なものとは何かが、自然と見えてきた。
文責:天内駿士(あまないはやと)(電通東日本)
「始められる仕事」であり、「続けられる仕事」であること
「会社設立の経緯や背景について、お話しください」という型どおりの質問からインタビューは始まった。東日本大震災直後の、2012年のことだ。誰がどう考えても、相当の覚悟であったろうと思う。それに対する御手洗社長の答えは、こうだ。
「仕事をつくりたい、ということでした。一時的な復興支援ではなく、この地に根づいて続いていく仕事をつくりたいと思いました。気仙沼ニッティングを始めたのは、震災の翌年、2012年です。当時は、まだ復旧や生活支援が中心の時期でした。被災した人たちのための仮設住宅ができ、雨風はしのげる。支援物資もくる。最低限の生活はできるようになっていました。でも、日々の仕事がないんです。家だけでなく、職場も被災してしまっていますから。
家を失ったということは、大変なことです。同時に、仕事がなくなってしまったという現実もまた、耐えがたいことだと思いました。もらうばかりの生活というのは、常に『すみません、ありがとうございます』と頭を下げていなければならず、精神的にきついものです。それに仕事の機会がないと、がんばりどころがない。打ち込めるものがないでしょう。当時、一番混んでいたのは、パチンコ店でした。それが、私が見た気仙沼でした」
のっけから、すごい話だ。報道やSNSだけでは伝わらない、被災地への支援というものが、いかに難しいかがよく分かる。衣食住だけでは、人間は生きていけない。日々のやりがいが必要なのだ。
「それで、仕事をつくりたい、と思いました。地域に根づき、続いていく仕事。いずれこの地の産業となりうる仕事。そんなときに糸井重里さんとの出会いもあり、気仙沼で編み物の事業を始めました。編み物なら、毛糸と編み針があればすぐにできます。被災している気仙沼でも、地盤整備などを待たず、まずは始めることができる仕事でした。なぜ編み物の事業にしたのか、とよく聞かれます。気仙沼には編み物の文化があったということが背景にありますが、それだけでなく、フィージビリティ(編集部注:実現可能性)が決め手であったと思います」
なるほど、始めやすさが重要か、と早合点した筆者に、「でも、そういう計画だけで事業がうまくいくものではないのです。実際に気仙沼の人たちに、編み物の仕事をやりたいか、どういう形だったらできるか、たくさん聞いて、仕事の形をつくっていきました」と、御手洗社長の話は続く。

気仙沼ニッティングができるまでの物語はこちら
https://www.knitting.co.jp/story/
「編み手の○○さん」と呼ばれることへの誇り
「働く人にとって、働きやすいかということはとても大切です。当時気仙沼でいろいろな人の話を聞くと、育児や介護、家事などがあってフルタイムで外出するのが難しいけれど、できることなら仕事がしたい、という人が多くいました。そうであれば、そういう人たちが取り組める仕事をつくろうと思ったんです。編み手の仕事は、家で、好きな時間に取り組めますから、仕事以外にもやらなくてはいけないことが多い人にとっては取り組みやすい仕事です。でも、だからといって簡単な仕事ではないのですよ。職人仕事ですから」
気仙沼ニッティングでは、「編み手さんのニーズから仕事をつくる」という御手洗社長の言葉が印象的だった。こうした“インクルーシブな働きやすさ”は、今の時代、事業が続いていくために必要なことの一つだろう。多様な人材が共存することは、事業や組織に刺激を与え、しなやかな強さをもたらす。世の中的にはコロナ禍で進んだこの視点を、御手洗社長はかなり早くに取り入れていたのだ。
御手洗社長はさらに、働きやすさだけでなく、編み手さんのモチベーションが大切であると続ける。
「自分の仕事が、誰かの喜びにつながっていると実感できるということは、心からうれしいことだと思います。もちろん、生きていくためにお金が必要であり、そのために仕事をします。でも、仕事は、自分の時間を捧げるものだからこそ、対価のために我慢する苦役、ではさみしいですよね。仕事を通じて、自分が生活の糧を得るばかりでなく、その仕事を人が喜んでくれている、社会のためになっている、という実感があることは、人生を豊かにします」
「〇〇さんの仕事」として認められ、褒めてもらったとき、ひとは無上の喜びを感じる。おカネも大事だが、「さすが、天内さんの仕事だね」と言ってもらえると、ああ、この仕事をしていて本当によかった、と思う。それはどんな仕事でも同じかもしれない。「編み手の〇〇さんのニットが欲しい。何年待ちでも構わない」というお客さまからの声は、格別なものだろう。
「お客さまと、働く人。その双方に、うれしさを生む方法を考えることが、経営者である自分の仕事だと思います」。
あまりにも本質的で、まっすぐな御手洗社長の言葉に不意を突かれた気がして、用意していた「ブランディングとは、どういうことなのか?」という紋切り型の質問を、思わず飲み込んだ。

「クオリティ」が、「ブランド」をつくる
しかし、インタビュアーとして、その質問は避けては通れない。「あのう……御手洗社長にとってのブランディングとは、どういうものなのでしょうか?」と恐る恐る、尋ねてみた。マッキンゼー出身で、これほどのブランドに携わっている人だ、きっと戦略的な答えが返ってくるだろうと思いきや、御手洗社長のコメントは至ってシンプルだった。
「ブランディングのためになにかをしなければ、と思ったことあまりはないです。わくわくできるものをつくるのは大事だな、とは思いますけど。着る人にとっても、つくる人にとっても。もちろん、商品のクオリティを高く維持することは大前提です。商品のクオリティが、お客さんと会社の間の信頼になり、その信頼関係が結果的にブランドをつくるのかなと思います」
では、ブランドの源泉となる製品のクオリティはどうつくられているのか。今回取材して、驚いたのは、ニットづくりはとても「理数系なもの」ということだ。手編みのニットと聞くと、職人それぞれの個性が出た、一つ一つ違う製品を想像してしまう。そんな先入観から、「手編みならではのバラバラさが、人の温かみを感じさせる」という話になることを想像していた。
けれど実際は、仕上がりのシルエットや寸法を定め、そこから図面をおこし、細部まで破綻しないよう編み方を決め、編み手はその図面にもとづき編んでいく。図面を忠実に再現しつつ、いかに着心地のよく美しいニットに仕上げるかが、編み手の技術力だ。その技術力により、クオリティの高い製品になる。
気仙沼ニッティングのニットは、編み手の「お客さまがよろこぶニットを届ける」という思いが、製品のクオリティに表れているように思う。検品時の仕上がりによっては、毛糸をほどいて編みなおすこともあるが、むしろ編み手が自分のつくったものに納得いかず、自らつくり直すことが多いそうだ。
そうしてつくられたニットが、お客さまのもとに届く。その喜びの声が編み手に届く。手紙や、時には会いに来てくれることもある。その声は編み手の喜びになり、ニットのメンテナンス時はまたお客さまを思って編み、それを受け取ったお客さまはまた喜び、ニットを長く愛用することができる……そうやって、ニットを通じた「楽しい・うれしい」が循環して、長く長くつながっていく。
ロジカルだけど、確かに「手」を感じる。温かみがある。ここに気仙沼ニッティングのクオリティの心髄があると感じた。

ストーリーを編む、という仕事
インタビューの中で、御手洗社長は、気仙沼に根付く編み物文化の背景を教えてくれた。
気仙沼は遠洋漁業が盛んで、気仙沼の船は、遠く大西洋まで行って漁をする。船上での漁師の仕事は、魚をとることばかりでない。魚をとるための網を繕い、からまった釣り糸をほぐし、漁に備えることも彼らの仕事だ。そのため漁師は手先が器用で、針と糸になじみが深い。彼らは、船上で時間があるときに、よくセーターを編んだ。
そのセーターが、父の帰りを待つ家族への最高のプレゼントになった。気仙沼ニッティングの編み手にも、子ども時代、漁師だった父に編んでもらったセーターが宝物だったという人が多くいる。

それだけではない。羊が身近にいたということも、気仙沼の編み物文化を下支えした。「60代の編み手に話を聞くと、子どものころ、家に1〜2匹羊がいたという人が、けっこういます。毎年、毛刈り職人が地域をまわり、各家庭の羊の毛を刈った。その羊毛を業者に糸にしてもらい、毎年、家族のセーターを編んだり、コートを作ったりしたのだそうです」
気仙沼になぜ羊がいたのか?それは、かつて戦時下の日本では、北方に行く兵士の防寒着をつくることを目的に羊毛の内製化が目指され、政府によって東北地域で牧羊が奨励されたことが背景にある。
「岩手県の遠野などは、いまも羊料理で有名ですね。羊が多くいたのでしょう。気仙沼で編み物をする人が多かったことも、同じルーツなんです」
土地の持つ記憶と、先人から受け継いだ確かな技術が、編み手のお客さまとの物語と一緒に編みこまれて、世界でただひとつのニットが生まれているのだ。

最後に、本連載のテーマである「元気な会社」についても聞いてみた。御手洗社長は、しばらく考えたのち、こう言った。
「だれに言われるわけでもなく、あれをやってみたい、これをすればもっとよくなる、そんな気持ちでどんどん自ら仕事をしたくなる。そういう人や仕事が多い会社は、元気なんじゃないでしょうか」
いまの自分にできることを、ワクワクしながらやってみる。失敗したら、編み物をほどくように最初からやり直せばいい。御手洗社長が実践するPDCAは、いたってシンプルかつ誠実だ。だからこそ、その仕事は多くの人の心に響く。最後に聞かせてもらった言葉が、これまた深い。
「商品を買ってくださるお客さまと、働く人たち、その両方を幸せにすることが創業当初からの私の思いであり、これからも変わることのない事業目標です。それって、世界の幸せの総量を増やすってことですから。そう、思われませんか?」
 KESENNUMA KNITTING(気仙沼ニッティング)のHPは、こちら。
KESENNUMA KNITTING(気仙沼ニッティング)のHPは、こちら。
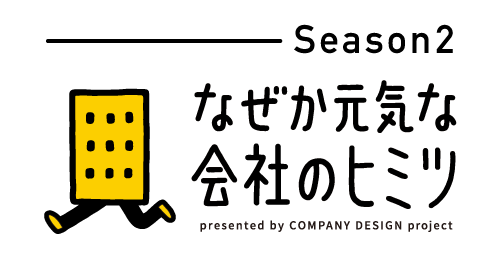 「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第32回は、宮城県気仙沼市を拠点に、ニット製品の製造・販売を手掛けるKESENNUMA KNITTING(気仙沼ニッティング)を紹介しました。
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第32回は、宮城県気仙沼市を拠点に、ニット製品の製造・販売を手掛けるKESENNUMA KNITTING(気仙沼ニッティング)を紹介しました。【編集後記】
御手洗社長のコメントは、理路整然としているが、決して冷たいものではない。むしろ、温かい。温かくて、深い。
自らの信念は、揺らがない。決してブレない。でも、相手の立場や思いには、とことん寄り添って理解しようとする。その相手は、お客さまであり、会社や事業を共に進めていく仲間であり、地域や社会そのものだ。起業する、あるいは経営を続けていくというのは、そういうことなのだ、と改めて思った。
「御手洗社長とその仲間たち」が編むニットも、ロジカルで、温かい。そこには、確かな技術と相手への思いが込められている。
そこに、ファンがつく。当たり前といえばそうかもしれないが、その当たり前を貫くことは、なかなかできないことではないだろうか。
この記事は参考になりましたか?
著者

天内 駿士
電通東日本
第1ビジネスプロデュース局
ビジネスプロデューサー
入社以来一貫してビジネスプロデュース職に従事。クライアントの課題発見、その解決策となるソリューションの提案・実現に注力し、継続的な事業成長支援を行う。




