「させない」医療から、「ささえる」医療へ
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第33回は、医師という肩書きを持ちながら、「トラベルドクター」という旅行会社を立ち上げた伊藤玲哉社長に、その思いを語っていただいた。
伊藤社長との出会いは2021年。がんサバイバーをサポートするプロジェクトLAVENDER RINGの活動の一環で、LAVENDER RING DESIGN AWARDSを開催した時のこと。「がん患者や広く疾病経験者の生活の体験自体を向上するプロダクトや空間、体験をデザインしたもの」から選ぶアワードで、トラベルドクターはグランプリを獲得した。どこか人懐っこそうな印象なのだが、「社会を変えたい」という強い意志が言葉の端々から感じられた記憶がある。
トラベルドクターの設立は、2020年。スタートから3年余りが経過した。医師、看護師、介護士などで構成されるチームで、病気を抱えている方の「旅への願い」をかなえるという事業だ。「医療×旅」と言われると、なんだかコロンブスの卵のような感じがする。メス!鉗子(かんし)!汗!みたいな、ドラマで見たことのあるような緊迫した場面と、旅先でいい湯だな、はなかなか結びつかない。でも、人の幸せってなんでしょう?と言われると、なるほど、つながった!という気持ちになる。
広告会社に身を置いていると、「発想をジャンプさせろ」ということがよく言われる。クライアントの期待に応えられるかも、そのジャンプの加減にかかっているといっていい。が、これがなかなか難しい。ジャンプが足りないと、そんなことくらいこちらでも思いつきますよ、となってしまうし、すっとんきょうな方角へ大ジャンプをしても、よく分かりませんね、となる。
トラベルドクター、という社名がすでにキャッチーだ。キャッチーでありながら、なんとなく想像ができる。どんなことなの?どんなジャンプを見せてくれるの?と、その先が知りたくなる。そんな思いから、今回の取材を伊藤社長にお願いした。ドクター視点で見る「旅の価値」というものに、ぜひ、迫ってみたい。
文責:中川真仁(電通BXCC)
夢をあきらめていたのは、むしろ医療従事者ではないか?
患者さんという呼び方が僕はあまり好きでないのですが、と前置きした上で伊藤社長はこんな話を聞かせてくれた。「患者さんは、旅に出かけたい、という気持ちを隠しているんですよね。病を患っている私には、そんなことは到底、かなうはずがないものだ、願ってはいけないものなのだ、というように。その思いに気付いたときに、ああ、僕がお役に立てることはそういうことなのではないか、と思ったんです」

東京都出身昭和大学医学部卒業。洛和会音羽病院 初期/後期臨床研修総合診療科・在宅診療・ER救急・麻酔科に従事。介護士初任者研修 ・ 介護タクシー運転手。グロービス経営大学院 2019期生
TOKYO STARTUP GATEWAY 2019 最優秀賞
経済産業省 始動Next Innovator 2019 シリコンバレー派遣選抜
当初の周りの反応は、トラベルドクター?また伊藤が、変なことを言い出したぞ、というものだったのだそうだ。起業から3年、コロナも収まりつつある中で、問い合わせも増えてきているという。伊藤社長いわく、「お一人お一人の中で、人生を後悔したくない、という思いが高まっているのだと思います。旅行に出かけたい、という思いは決してあきらめなければならないものではないはずですから。もちろん、まだ道は半ばですが、最近になってようやく『トラベルドクターの伊藤です』と名乗ってもいいのかな、という気持ちになってきています」
旅行に行きたい、という夢をあきらめていたのは、そこにストップをかけていたのは、むしろ医療従事者のほうではないか、と伊藤社長は指摘する。あなたは「患者さん」なのだから、無理せず寝ていてください、というような。「もちろん、なにか事故があってはいけない。そこへの配慮や備えは大切ですよ。でも、その人の夢と真剣に向き合って、その夢をかなえてあげたいと願うのは、医師というよりは人として当たり前のことですよね。ご家族のお立場でも、それは同じだと思います」

誰だって「自由人」でいたい。僕自身もそうだから
人は、半分くらいの親孝行くらいしか、できていないのではないでしょうか?と伊藤社長は言う。「お父さんか、お母さん、どちらかを亡くされたときに、はたと気づくのだと思います。ああ、私は親孝行を十分にしてあげられなかった、と」。「孝行したいときに親はなし」と言われるが、わが身を振り返っても同じ気持ちだ。「人間、生きているかぎり、自由でいたいと思うんですよ。とんでもないぜいたくがしたい、とかそういうことではなく、ご自身の力で、あるいは周りの力を借りて思い出の場所を訪ねてみたいとか、温泉につかってみたいとか。そういう自由を、生きる喜びを、奪ってはいけないと思うんです」
伊藤社長のご実家は、羽田空港にほど近い場所。少年時代は、飛行機を見上げながら過ごしていたという。そんな少年が、トラベルドクターになっているとは、なんだかドラマのような筋書きですね、と話を向けると「そうですね、親父は町医者の三代目で、僕は四代目になるんですが、親父から医者になれ、と言われたことは一度もありません。もし、そう言われていたら、医者にはならなかったでしょう。いわゆる医師を経てトラベルドクターという道を決めたのは、自分が自由でいたいから、ではなく、患者さんの自由のため。患者さんの自由に生きる権利を奪いたくなかったからなんです」

事業はまだまだ、始まったばかり
伊藤社長が思い描くビジネスの展望は、7つのステップでできているのだという。「まずは、旅行することをあきらめなくていいんですよ、ということを知っていただくこと。次に、それが事業として存続可能なものであることを示すこと。現時点では、やっとそこまでたどり着けたのかな、という思いです」
そこから先の構想が、すごい。「次にやりたいことは、現時点では私を含めた1チームで行動していますが、その1チームで47都道府県からのオファーに対応することはできません。現地対応できる体制を整えることが大事です。4つ目は、重度の患者さんを特別に連れ出すのでなく、軽度な患者さんが、自由に旅ができるようにすること。5つ目は、インバウンド対応。6つ目はその逆で、日本から海外へ連れていってあげられるようにすること。ハワイにでも、北極にでも、です。7つ目は、そんなばかなこと、と思われるかもしれませんが、月とか宇宙への旅を提供することなんです」
人生の最後のページに風景を届けたい、と伊藤社長は言う。「病室の、殺風景な天井を眺めながら人生を終える、というのはあまりにも切ないじゃないですか。自由を提供するということから言えば、医療はまだまだ無力なのではないか、と思います。医療に全力を尽くすことは医師の責務ですが、それで全てが解決できるとは僕は思っていません」

白衣を脱ぐことが、大事。
そのためには、医師として「白衣を脱ぐこと」が大事だと伊藤社長は言う。「私は白衣を着た医師である、あなたはパジャマを着た患者である、というところから本物のコミュニケーションは生まれないと思うんです。トラベルドクターというのもそんな思いからつけたネーミングであって、もちろん医師ではあるのですが、旅仲間でありたい、ということなんです」
「トラベルwithドクター」ということではないのだ、と思った。「そのためには、まずは思いを伺う。ご本人はもちろん、ご家族の思いも。思いというか、願いですね。その上で、その願いをかなえるために不安に思っていることを伺う。で、四方八方、手を尽くして背中を押してあげる。背中を押すのは、旅をサポートしてくれる人たちに対しても同様で、丁寧に説明する。ああ、こんなに笑顔になってもらえるんだ、ということが分かると、それまで反対していた人たちも協力してくれるようになるんです。お客さま本来の表情が見えると、ああ、このプロジェクトに参加して良かった、という気持ちになってもらえる。医療従事者の間でも、応援してくれる人が増えてきました」
既製服ではなく、その人に合わせたオーダーメードの服を、チーム一丸となって作るというようなことだ。命を扱う、命を預かる、ということがいかに大事なことなのか、サービスというものがいかに深く、尊いものであるのか、を思い知らされる。

人生という物語の「選択肢」を増やしたい。
自由であるためには、選択肢がたくさんあることが大切だ、と伊藤社長は言う。「海でも山でも温泉でも、どこへでもお連れしますよ、と伝えるだけで喜んでもらえる。もちろん、そう約束してしまった以上、こちらは可能なかぎり手を尽くします。どうしてなのか分かりませんが、自分は逆境に追い込まれるほど燃えるタイプなんです(笑)」
旅行はあくまで、幸せになるための手段であって目的ではない。「それでいうと、若いころに担当した患者さんに、早く死にたい、早く死なせてほしい、と言われ続けていたのですが、あるとき『先生、実は旅行に行きたいんです』と打ち明けられて、ハッとしたんです。僕には『行きたい』ではなく『先生、私、生きたいんです』と聞こえたんですよ」
そのために、人生の4大イベントとしての冠婚葬祭に加えて、5つ目のイベントを作りたいというのが伊藤社長の思いなのだという。人生100年と言われる時代だが、節目節目のイベントのようなものは、案外、多くない。「生きていくための、生きていることの喜びを感じられるセレモニーが、人生には必要なのだと思います。ご自身の物語を編む、というのはそういうことですから。そのお手伝いができたとしたら、医師として、人として、こんなにうれしいことはありません」


トラベルドクターのHPは、こちら。
トラベルドクターに関する動画は、こちら。
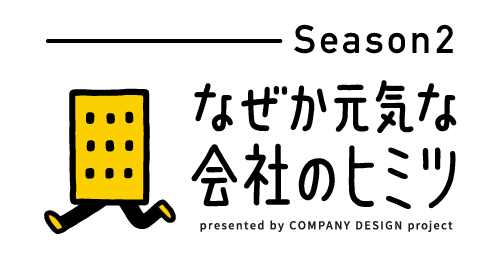
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第33回は、医師という肩書きを持ちながら、「トラベルドクター」という旅行会社を立ち上げた伊藤玲哉社長に、その思いを語っていただきました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
伊藤社長のお話を伺っていて、かつての上司に「余計なことをしよう」と言われたことを思い出した。いい言葉だな、とその時も思った。「余計なこと」をするには、勇気がいる。なによりまず、相手やチームメートとの信頼関係がなければ成立しない。それは、ビジネスとして成立しているのか?リスクはどのように回避するのか?そんな余計なことはどうでもいいから、確実にもうかることを考えろ、というのがオトナの理屈というものだ。
でも、人が思わず涙ぐんでしまうような、心が震えるような出来事というのは、他人から「余計なこと」をしてもらったときではないだろうか?サービス業に携わる者として(あらゆる職業はサービス業だと思うが)、心しておかなければならないことだと思う。
旅とは、ぜいたくなものだ。単純な話、おカネがかかる。いろいろな人の助けなしには成立しない。ましてや、体が不自由となれば、そんなぜいたくは許されるものではない、と自制してしまう。その夢、あきらめてしまうのはもったいないですよ、と伊藤社長はやさしく手を差し伸べる。「娘さんの結婚披露宴に出かけたいのでしょう?ならば、なにがなんでもお連れしますよ」と。えっ、そんなことができるんですか?と驚く相手に、伊藤社長は、おそらくはこう返すはずだ。「私を、誰だとお思いですか?トラベルドクターですよ。あなたの人生に寄り添うパートナーなんです」と。プロとしてのプライドと、相手へのリスペクト、その両方がなければ出てこない言葉だ。
この記事は参考になりましたか?
著者

中川 真仁
株式会社 電通
BXCC
クリエーティブディレクター
広告会社、スタートアップなどを経て2016年電通入社。コピーライター/CMプランナーが出自ですが、映像、PR、webプロモーション、イベントや出版、事業開発サポートなど担当領域は様々。受賞歴はいろいろ。また漫才コンビ「ハコグミ」として活動中。




