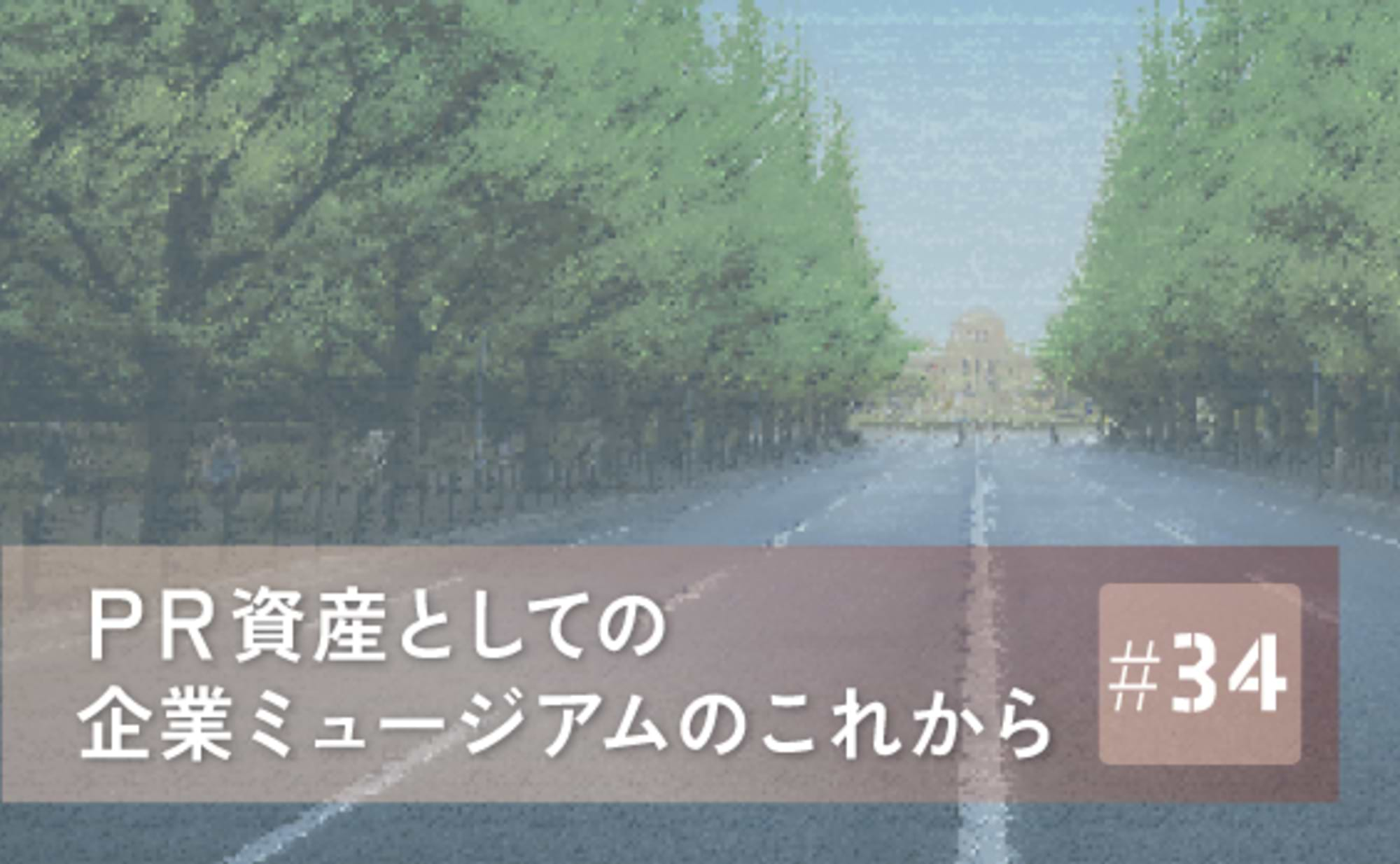「社会課題を、超えていく。」を伝えるURの企業ミュージアム

企業ミュージアムは、「ミュージアム」というアカデミックな領域と「企業」というビジネス領域の両方にまたがるバッファーゾーンにある。そして運営を担う企業の広報、ブランディング、宣伝、人事などと多様に連携する組織である。本連載では、企業が手掛けるさまざまなミュージアムをPRのプロフェッショナルが紹介し、その役割や機能、可能性について考察したい。
これまで35回の連載で、合計33の民間企業の企業ミュージアムを取り上げ、企業のオウンドメディアとしての機能や役割、PR資産としての可能性について論じてきた。本稿では、連載の「番外編」として、独立行政法人が運営するミュージアムを紹介し、民間企業とは異なる成り立ちを持つ組織が、どのような目的でミュージアムを運営し、その機能を有効活用しているのか、PRの側面から考察する。
独立行政法人都市再生機構が運営するURまちとくらしのミュージアムは、2023年9月にオープンして間もないが、週末は予約でいっぱいという人気ミュージアムである。また、すでに海外メディアや、外国政府・自治体関係者が訪れるほど海外からも注目を集めている。
取材と文:井上 大輔(電通PRコンサルティング)

メディア報道を追い風に週末の予約はいつも満員
「団地の聖地」と呼ばれる場所が、東京にあるのをご存じだろうか。それは北区赤羽台。高度経済成長期真っただ中の1962(昭和37)年、当時の日本住宅公団が3373戸もの大団地を建設した場所だ。この地で生まれた「名作団地」は、集合住宅の未来モデルを数々提案し、日本型集合住宅の進歩に特異点(シンギュラリティ)をもたらした。
そんな赤羽台にオープンしたのが、URまちとくらしのミュージアム。2023年9月15日に開館したばかりの、独立行政法人都市再生機構(UR:Urban Renaissance Agency、以下UR)の企業ミュージアムだ。URがこれまで取り組んできた街づくり(都市再生・震災復興・ニュータウン開発など)と暮らし(団地)の歴史、そして未来を一望できる施設なのだが、最大の特徴は展示の多くが体験型であるということ。これにより来場者は見る・読むだけでなく、五感の全てを使ってURという企業を知ることになる。「えっ?」「うわぁ~!」と声を上げてしまうような、イマーシブな面白さがあるのだ。
実際、開館直後から週末の予約はいつも満員。想定以上のペースで来館者が訪れているという。客層も、都市設計を学ぶ学生や研究者はもちろん、ご年配の夫婦や若いカップル、子ども連れのファミリーまで幅広い。メディアの取材が多いことも人気の追い風になっており、広報が集客に結びついている好例と言える。
さらに海外からの注目度も高く、イタリアの建築専門メディアをはじめ外国メディアからの取材も複数受けている。広報担当は「海外の大学の研究のための来訪や、世界銀行等からも視察を受けており、日本の高度経済成長期の建築や人々の暮らしを伝える施設としての関心は、海外の人から見ても高いのでは、と考えている」と語る。
幅広い事業、長い歴史─URを知ってもらうことの難しさ
URという企業を説明するのは、難しい。国に代わって公共性の高い事業を執行する公企業としての独立行政法人であり、母体は1955年に戦後の住宅不足を解消するため設立された日本住宅公団だ。企業ミッション一つとっても、営利企業とは趣が異なる。
事業内容も、全国約70万戸もの団地を管理・経営する賃貸住宅事業だけでなく、都市再生事業、震災復興支援事業など幅広い。半世紀以上にわたり、時代時代で社会の要請に応じてきた歴史があるのだが、企業としての理解や共感を得やすいかどうかは疑問が残る。団地や都市は私たちの生活に密接しており、本当は、URは誰にとっても身近な存在であるはずなのだが、企業広報が一筋縄ではいかないことは容易に想像できる。しかしURまちとくらしのミュージアムは、その課題をクリアしている。数々の体験型展示がURという企業にリアリティを与え、本質的な企業理解を促しているからだ。

街や暮らしの歴史と未来に、触れる、飛び込む、参加する
URは、どのようにしてこの企業ミュージアムで生活者との密なコミュニケーションを実現しているのだろうか。まずは展示物や手法について紹介していく。URまちとくらしのミュージアムのキャッチフレーズは、「過去・現在・未来を一望。新たなくらし方を探求し続ける」だ。ここでは時代ごとに街をつくり、新しいライフスタイルを探求してきたURの、これまでと今、そしてこれからが紹介されている。従ってその展示手法も実にさまざま、時に規格外だ。

例えば、復元住戸。館内には各時代を象徴する4つの団地の住戸が、当時そのままに展示されている。ポイントは再現ではなく、あくまで復元であるということ。当時の部材などがそのまま使われており、触ることはもちろん、入室することもできる。

一方ではデジタル技術も効果的に活用。壁と床の4面にプロジェクションマッピングが投影され、浮遊感を感じながら都市開発の歴史を鳥瞰(ちょうかん)したり、約21メートルの巨大スクリーンで都市再生や震災復興などの大規模事業を目の当たりにできる。まさにその時代、その空間に飛び込む体験だ。

さらにミュージアム棟を出ると、目の前には登録有形文化財(建造物)である4つの住棟がそびえ立つ。その迫力は、もはや展示という枠を超えている。敷地の中心となる中庭「ワークショップひろば」は2024年7月から本格的に始動し、地域交流・活性化の場として住民参加型のイベントやマルシェの開催などが予定されている。
約100年前の団地を“内見”するタイムスリップ体験
ここからは、PRコンテンツとして特にインパクトを感じる展示をピックアップして紹介していく。

まずは、なんといっても復元住戸だろう。4つの団地の住戸が時代を追いながら、当時使用していた建材や建具、サッシなどをそのまま使って復元されている。つまりセットではなく本物、ということだ。例えば1920年代、今から約100年前に建てられた同潤会代官山アパートメントに入ると、かすかに畳が香る。そして居間の広さは約13平方メートル、天井高は約2.3メートルというコンパクトな造りに驚かされる。まさに当時の人々のお宅を訪問しているような、生活感をじかに感じるタイムスリップ体験と言える。

続く蓮根団地では生活様式の洋風化が感じられ、晴海高層アパートに至ってはデザイン性の追求が見て取れる。ガチャリとドアを開け、次の部屋へ移るたび、それらが現代を生きる私たちの住まいとつながっていることを実感するのだ。住宅やライフスタイルは、誰かのたゆまぬ工夫と努力の積み重ねで洗練されていく。その発見こそが、URの事業を知ることにつながっている。
4つの団地の復元住居、詳しくはこちら。
ちなみに、間取り図でよく見る「DK」。いわゆるダイニングキッチンだが、あの「DK」という表現はURが先駆けだ。さらに、キッチンの流し台と言えばステンレスが主流だが、日本で一般に普及したのもURの団地からだという。他にも、私たちの生活で当たり前になっていることのトリビアがあちこちに潜んでおり、知的好奇心が刺激される。

こちらは「団地はじめてモノ語り」という展示。時代ごとの住宅部品が壁一面、天井までレイアウトされている。知っている世代には懐かしく、知らない世代にはモダンアートのように見えるかもしれない。なかでもインターホンチャイムはどれも現役で、実際に押すことができる。「ピンポ~ン」や「ブー」といい音が鳴ると、ほとんどの来館者がビクッ!とするという。こんな遊び心のある展示も、このミュージアムの魅力の一つだ。

こうした集合住宅の住宅部品たちは常に改良され、一定の期間がたてば廃棄される運命にあるが、同時に人々の生活を支えてきた大切なパーツであり、都市の生活史を後世に残す貴重な資料となり得る。それらを遺産として保存しキュレーションすることも、企業ミュージアムの重要な役割と言えよう。
ユニークな「スターハウス」を丸ごと展示
敷地内には4棟の団地の住棟が並び、4棟全てが団地初の登録有形文化財(建造物)に登録されている。そのうち3棟がポイント型という形式の住棟、通称「スターハウス」だ。1フロアに3つの部屋を配置し、全ての部屋で3方向から外気と光が入るよう設計されている。上空から見下ろすとY字型の形状になっており、星を連想させるためにその名がついた。その斬新なデザインに来館者は目を見張ることになるのだが、これが60年前に建てられていたという事実にも驚かされる。思わず一言添えて、ソーシャルメディアでシェアしたくなる展示となっている。

一方で、街でよく目にする団地も展示されている。それが「ラボ41」、板状階段室型といわれる住棟だ。

全ての部屋が南向き、さらにバルコニーも設置され、採光・通気が最大になるよう設計されている。これがなぜ、登録有形文化財(建造物)として保存され、展示されているのか。それは、高度経済成長期の標準的な住棟形式で、今の団地に直接つながる貴重な資料だからだ。目を引くものだけに価値があるわけではない。“日常”にも始まりがあり、私たちの暮らしと地続きの歴史がある。「ラボ41」はそれを教えてくれる。現在は内部が一部改装され、改修技術等の実証フィールドとしても活用されている。
団地は大量生産される住宅だ。老朽化すれば解体され、新しい住まいに建て替えられていく。しかしその新陳代謝の裏には、時代ごとのライフスタイルへの提案があり、挑戦がある。スライス・オブ・ライフを残しておくことは一企業の歴史を超えて、日本の住宅史を残すことにつながると言えよう。なお、4棟はいずれも、歴史的資料性を守るため、普段は内部公開をしていないとのことだ。
地域活性や被災地とのつながりもミュージアムの一部
地元住民との交流や周辺地域の活性化にも重きを置いているのも、このミュージアムの特徴だ。多様なステークホルダーとのダイレクトな関係づくりを重視しているのだ。
例えば、2023年11月からエントリーを開始した「まちとくらしのトライアルコンペ」がその一つ。広く一般の人からアイデアを募り、新たな風景をつくり出す活動やデザイン、ビジネスの実験場として、ミュージアムのパブリックスペースを活用していくという試みだ。2024年3月には最優秀賞が決定し、その受賞作を基に赤羽台に農耕地をつくる計画が始まる。さらに7月以降は、本格的に地域イベントなども予定されている。

「地域の皆さんあっての街づくり。イベント風景もまた、ミュージアムの一部として捉えている」施設の担当者はそう語る。参加することを通して、現在進行形のURを知ってもらい、良好な関係を築いていく。それもまた、このミュージアムのミッションだ。
ミュージアムは地元以外とのつながりも重視している。主要事業である震災復興支援の一環として、ここでは被災地の関係人口の増加や風化の防止にも取り組んでいる。2024年2月には、東日本大震災で津波を逃れた桜の苗木を3本、岩手県と宮城県から譲り受け植樹した。ミュージアムを訪れた人に、満開の桜をめでながら、被災地を思い出してもらうという趣向だ。早ければ翌年の春には花を咲かせ、10年単位の年月をかけて震災の記憶をとどめ続けていく。これもまた、街と暮らしの時代をつくってきたURならではの、長い視野を持った取り組みだろう。

「社会課題を、超えていく。」を貫く
URの広報担当者は語る。「一般の皆様には、URと言えば賃貸住宅といった印象が強いが、その時代その地域に合った街づくりを追い求めてきたことを、ぜひ多くの方に知ってもらいたい。ニュータウン開発や都市再生事業、震災復興支援事業等、街づくりには欠かせない事業にURは取り組んできた。今後も未来に向けて暮らしをより豊かにするために、新しい取り組みを実施していきたい。その発信をこのミュージアムから行っていけたらと思っている」
街をつくる。暮らしを豊かにする。URの事業とはつまるところ、地域の問題や時代が生んだ弊害を解決していくことに他ならない。いわば社会課題への挑戦だ。それを追体験できるこのミュージアムは、誰もが社会課題と無縁ではない現代において、事業への理解と共感の獲得に大きな効果を発揮しているといえよう。
URは「社会課題を、超えていく。」という広報メッセージを掲げており、その意志はミュージアムにも貫かれている。この揺るぎない姿勢もまた、URを雄弁に物語っていると感じた。
【編集後記】(ウェブ電通報編集部より)
編者の母(84)などは折に触れ、こんなことを編者に言う。「あなたには、あなたが3歳になるまでに、もうすでに一生分の親孝行をしてもらったわ」と。おそらくは、その頃の暮らしも今と違わず忙しく、ヘトヘトだったに違いない。でも、人生振り返ってみれば、あの時代、あの街での、あの暮らしはかけがえのない宝物だ、という気持ちになるのだろう。
暮らしとは、住まいとは、そういうものだと思う。URまちとくらしのミュージアムは、当時は気づかなかった幸せのカタチ、あるいは、この時代に生まれて初めて目にする幸せのカタチを実体験することで、今、この瞬間の暮らしや、やがて来る未来の暮らしへ思いを馳せることのできる数少ないミュージアムだ。まさに、看板に偽りなし。この体験もまた、訪れた人の生涯の宝物になるにちがいない。
この記事は参考になりましたか?
著者

井上 大輔
株式会社 電通PRコンサルティング
メディア事業会社等を経て現職。官公庁を中心にパブリック領域や社会課題解決型のプロジェクトに従事。パラスポーツの普及発展プロジェクトで、「PRアワードグランプリ2021」「PR Awards Asia 2022」などを受賞。日本PR協会認定PRプランナー。