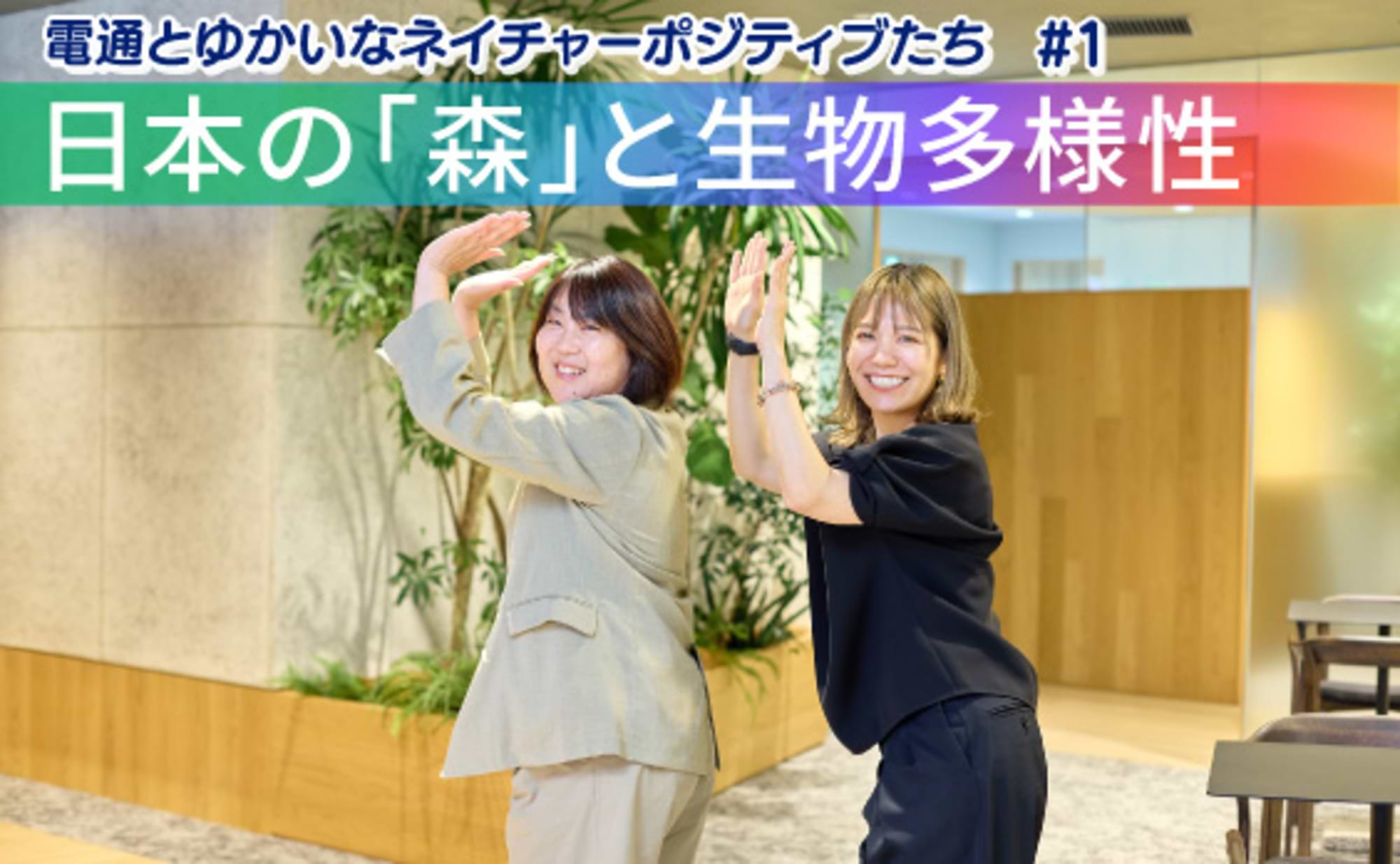※この記事は、2024年4月24日「Business Insider Japan」で公開された記事を一部編集し、掲載しています。
あらゆる社会活動の基盤となる自然資源。従来から環境保護は重要なテーマだったが、近年は単に自然を守るだけでなく、それを社会経済の持続的な発展につなげる“ネイチャーポジティブ”が広がりつつある。
この新潮流を社会実装するため、電通がスタートアップのシンク・ネイチャーと共同で開発したのが、生物多様性とビジネスを可視化する「バタフライチェック」だ。開発に携わった3人に、生物多様性をめぐるパラダイムシフトについて話を聞いた。
広がりつつある“ネイチャーポジティブ”という概念
生物多様性が注目を集めている。人間の社会生活は自然に少なからず負荷を与えてしまう。その影響で、現在100万種以上の野生生物が絶滅の危機に。生物多様性の問題は2022年にモントリオールで開かれたCOP15でも取り上げられて、その再生は世界的な課題になっている。
自然の保全や再生は、以前から国や自治体、市民団体が中心になって取り組んできた。ただ、近年はこの領域にパラダイムシフトが起きている。“ネイチャーポジティブ”というコンセプトが広がってきたのだ。生物多様性の研究者であり、大学発スタートアップのシンク・ネイチャー創業者である久保田康裕氏はこう解説する。

久保田康裕氏/琉球大学 理学部 海洋自然科学科 教授、統計数理研究所 客員教授、シンク・ネイチャー 代表取締役。北海道大学農学部卒業、帯広畜産大学大学院修士課程修了、東京都立大学理学部大学院博士課程修了 博士(理学)。専門は生態学。世界中の森をめぐるフィールドワークと、ビッグデータやAIを活用したデータサイエンスによって、生物多様性の保全科学を推進する。研究チームでスタートアップ「シンク・ネイチャー」を起業し、生物多様性市場を創出することに挑戦している。
「これまで自然保護と経済成長は、どちらかを選ぶという二項対立で語られてきました。しかしSDGsのウエディングケーキモデルで、生物多様性のパイの上に、社会のパイ、さらにその上に経済のパイがあるという考え方が示されました。すべての土台となる生物多様性のパイを大きくしてこそ、社会や経済は持続的に成長できます。これがネイチャーポジティブの考え方の基盤であり、だからこそ、ビジネスセクターも含めてみんなで取り組もうという機運が高まっています」(久保田氏)
実際、企業はこの流れと無縁ではいられない。2023年にTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワークが決定。生物多様性が経営にもたらすリスクや機会、それに向けた対応といった情報の開示を企業に求める動きが本格化している。気候変動問題で日本企業は後れを取ったが、その反省からか、今回は日本企業の動きが速い。TNFDアーリーアダプター(早期採択者)に登録した企業を国別で見ると、2024年1月の時点で日本が最多の80社だった。
ただ、企業の取り組みには温度差がある。電通サステナビリティコンサルティング室 生物多様性チームリーダーの澤井有香氏は、クライアントと接する中で企業側の戸惑いを感じ取っていた。

澤井有香氏/電通 サステナビリティコンサルティング室 事業推進コンサルティング部 シニアコンサルタント。生物多様性チームリーダー。HR系のクリエイティブ会社を経て、電通へ入社。ビジネスプロデューサーとして飲料/食品/AI/化粧品業界を担当し、ブランド業務を中心に、広告制作・新商品開発・事業立ち上げ等、幅広く活動。保護猫を家族に迎え入れたことをきっかけに、社会課題への意識が高まり、サステナビリティコンサルティング室へ。現室では、生物多様性を中心にさまざまなサステナビリティ領域で活動中。猫とビールとキャンプを愛する。
「まずTNFDに対応して、その他は以前からやっていたCSRとしての自然関連活動を継続するという企業がほとんど。事業と生物多様性を結びつけたアクションは、ほぼ手つかずです。理由の一つは、効果が可視化されていないこと。何をすれば生物多様性にどれだけポジティブな影響があり、それがビジネスにどれだけインパクトを与えるのかがわからないので、企業も踏み込みづらいのです」(澤井氏)
ネイチャーポジティブ施策の自然とビジネスへの成果を可視化
この壁を乗り越えてネイチャーポジティブ経営を浸透させるには、生物多様性とビジネスを可視化するツールが欠かせない——。そうした問題意識から電通とシンク・ネイチャーが共同開発したのが「バタフライチェック」である。バタフライチェックは、アクションによって増減する生物多様性を測定し、その変化が自然環境に与えるインパクトと、ビジネスに与えるインパクトをそれぞれ定量・定性で可視化する。両方を統合することで、より効果的なネイチャーポジティブ施策を打てるようになる。
高度な分析が可能なのは、今回タッグを組んだ両社がそれぞれの得意領域で知見を発揮したからだ。シンク・ネイチャーは、生態系や生態系サービス(生態系から社会が得られる恵み)の分析を担当。久保田氏は自社の強みについて次のよう語る。
「世界中の陸と海の生物多様性情報をビッグデータ化。情報が少ないエリアはAIを活用して補い、30万種の生物の時空間分布を高解像度で把握しています。それをベースに、さまざまな産業セクターの企業の事業活動と自然の接点や依存の関係、事業活動が生物多様性や生態系サービスに与える影響を数値化。どのようなアクションをすればネガティブな影響を減らせるのか、あるいは自然にポジティブなのかというシナリオ分析も提供しています」(久保田氏)
一方、ビジネスに与える影響の可視化は、電通が以前から取り組んできた領域だ。バタフライチェックでは、顧客をはじめ従業員や投資家、取引先といったステークホルダーからの評価を調査とヒアリングで可視化。そこにはマーケティングやパブリックリレーションで長年培ってきた手法が用いられている。
さらに今回は、クリエイティブの力が発揮されていることも見逃せない。バタフライチェックは、その名前からもわかるようにチョウをモチーフにしたデザインが特徴。

提供:電通/シンク・ネイチャー
左羽に自然への効果、右羽にビジネスへの効果をまとめて、ネイチャーポジティブなアクションのインパクトが直感的に理解できるようにした。クリエイティブを担当した電通サステナビリティコンサルティング室の森由里佳氏は次のように明かす。

森由里佳氏/電通 サステナビリティコンサルティング室 クリエーティブライター/プランナー。広告コピーライターを経て、BX領域へ。ブランドコミュニケーションの他、経営ビジョン開発、事業開発、ナラティブ開発、表現コンサルティング、インナーアクティベーションの設計等、言語化を軸に幅広い分野に取り組む。出産を機にサステナビリティへの課題意識が高まり、SX関連プロジェクトを多く受け持つ。「バタフライチェック」のクリエイティブを担当。ウイスキーと舞台を愛する。
「生態系サービスは4つに整理されるのが一般的ですが、膨大な情報量を正しく整理するだけではアクションの価値が理解されづらい面があります。もっと直感的で魅力的なものにする必要がありますし、事業との結びつきが示せれば、ステークホルダーも巻き込みやすくなります。
そうすればアクションの主体となる方々や組織もエンパワーメントできますし、何よりその先に、ネイチャーポジティブを実現する社会が見えてくる、と考えました。そこでたどり着いたのが、チョウの羽ばたきがめぐりめぐって遠く離れた土地で竜巻を起こすという“バタフライエフェクト”というワード。小さなアクションが世界を変えるという希望を込めて、花粉媒介者でもあるチョウをモチーフにしたバタフライチェックをデザインしました」(森氏)
完成したビジュアルを見たとき、久保田氏は大きな可能性を感じたという。
「TNFDへの対応は、サステナビリティやESGの観点から、金融・機関投資家と企業の間のB to B関係で求められるものなので、それに関連した専門的な情報を開示すればいい。しかし、ビジネスの多くはB to CやB to B to Cで最後に消費者、つまり一般の市民がいます。企業の生物多様性対応は、消費者を巻き込まなければ、ビジネスとして大きな動きにはなりづらい。バタフライチェックは、その壁を乗り越える機会をつくるツールだと確信しました」(久保田氏)
生物多様性でバタフライエフェクトを起こす
バタフライチェックの活用で何ができるのか。COEDOビールを展開する埼玉県川越市の協同商事のケースを紹介しよう。

提供:協同商事・電通
同社は醸造所横の人工芝グラウンドを有機農法の麦畑に変え、そこでつくったクラフトビールをイベントで販売するなど、ネイチャーポジティブな活動に以前から取り組んできた。ただ、その効果を定量化しておらず、シンボル的な活動にとどまっていた。そこでバタフライチェックの実証実験に参加。麦畑化したのはサッカーコートほどの大きさだったが、分析の結果、植物類は0から72種、チョウ類は1から17種、鳥類は13から49種に増えるなど、生物多様性が回復した。

提供:電通/シンク・ネイチャー
「自然に対しては、農地の保水力で水量調整機能が増加する等、主に水関連の生態系サービスでポジティブな効果があることが可視化されました。さらにビジネス面でも、ブランドイメージやリクルーティングに効果があることがわかりました。一方、アクションへの参加意向は高いにもかかわらず、アクションの認知は低く、機会ロスを生んでいることが明らかに。社長は『課題が見えたので次の改善につなげられる』とおっしゃっていました」(澤井氏)
バタフライチェックは今年2月にリリースされた。今後の展開について、澤井氏は期待を込めて最後にこう語ってくれた。
「“生物多様性”と聞くと自分とは遠い話だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、世界のGDPの約半分は自然に依存している中(※)で、生物多様性の未来はわれわれ人間の未来といっても過言ではありません。再生への第一歩として可視化をきっかけに、各企業で生物多様性がプロジェクトになっていくとうれしいですね。投資家に対応するだけでなく、生活者や従業員、さらに地域住民やサプライチェーンを巻き込んで、いかに大きな動きへとつなげていけるか。バタフライチェックをまさにバタフライエフェクトを起こす最初の羽ばたきにすることで、私たちも社会や経済のサステナブルな発展に貢献してきたいと思います」(澤井氏)
※世界経済フォーラム「自然関連リスクの増大:自然を取り巻く危機がビジネスや経済にとって重要である理由」より
バタフライチェックの詳細についてはこちら
(Business Insider Japan Brand Studio)